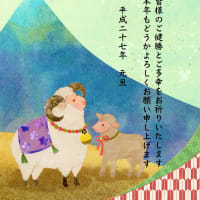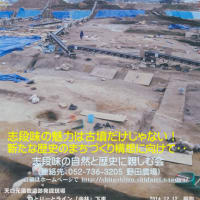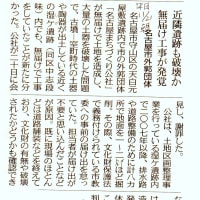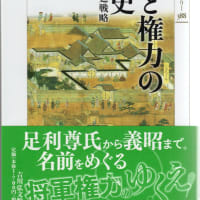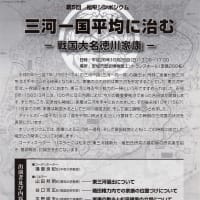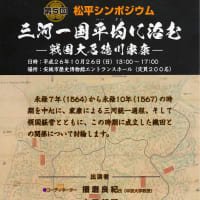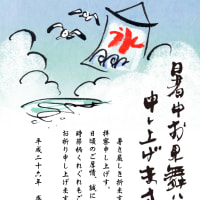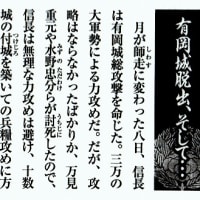●水野筑後守忠徳 参考資料1/2
=====================================================================
【主な参考文献】(順不同)
東京大學史料編纂所『水野忠徳事蹟』(東京大學史料編纂所所蔵データベース)
東京大學史料編纂所『大日本古文書幕末外国関係文書之十五』
東京大學史料編纂所『大日本古文書幕末外国関係文書附録之一、二、三、四、六』
石井良助『編年江戸武鑑・文化武鑑4』
福地源一郎『幕末政治家』
福地源一郎『懐往事談』―― 「水野忠徳の朝廷批判」
尾佐竹猛『幕末遣外使節物語』
綱淵謙錠『幕臣列伝』
綱淵謙錠『幕末に生きる』
土居良三『幕末五人の外国奉行』
大久保利謙『江戸 第一巻 幕政編(一)』
大久保利謙『江戸 第二巻 幕政編(二)』
大久保利謙『江戸 第三巻 渉外編』
日本史籍協會『幕末外交談』續日本史籍協會叢書
日本史籍協會『昨夢紀事 二 三 四巻』續日本史籍協會叢書
日本史籍協會『長崎警衛記録』續日本史籍協會叢書153
加藤英明『徳川幕府外国方:近代的対外事務担当の先駆―その機構と人―』
幕末維新論集7『幕末維新と外交』に収録
横浜市役所『横濱市史稿』政治編二
日本歴史学会編『明治維新人名辞典』
小川恭一『江戸幕府旗本人名辞典 第三巻』
笹間良彦『江戸幕府役職集成(増補版)』
竹内誠・深井雅海『日本近世人名辞典』
田中弘之『幕末の小笠原』
佐藤雅美『大君の通貨』
====================================================================
[史料TN1-1]
▼『水野忠徳事蹟』著者不詳の小伝(東京大學史料編纂所所蔵データベース)を翻刻
水野癡雲(ちうん)
名ハ忠徳[、]通称ハ甲子(カシ)次郎[。]後ニ従五位下ニ叙シ筑後守又下總守ニ任ス[。]致仕(退官)シテ癡雲ト号ス[。]諏訪庄右衛門頼篤ノ次男[。]文化十二年(1815)四月九日江戸愛宕下ノ邸ニ生ス[。]文政五年(1822)十月十三日水野弥三郎忠長ノ義子ト為ル[。]明治元年(1868)七月九日雑司ヶ谷村ノ別墅(別宅)ニ卒ス[。]年五十四[。]牛込早稲田浄泉寺(*1)ニ葬ル[。]長男晋[、]三男透[、]共ニ平民(*2)トナル[。]今其居所ヲ詳ニセス[。]」
天保七年(1836)九月廿日小性組番拝命
同十三年(1842)十二月三日徳川家系調
同十四年(1843)九月廿四日西丸ノ目付
弘化二年(1845)四月十五日使番
嘉永二年(1849)七月廿八日先手銕砲頭
同年 (1849)十月九日火附盗賊改
同五年(1852)四月十五日浦賀奉行(千石高、御役料千石)
同六年(1853)四月廿六日長崎奉行(千石高、御役料四千四百表)
安政元年(1854)十二月廿四日勘定奉行勝手掛
同四年(1857)四月十五日長崎奉行兼帯
同年 (1857)十二月三日田安館家老
同五年(1858)六月八日外国奉行
同年(1858)八月 日亜国行内命
同六年(1859)四月八日勘定奉行勝手掛兼帯
同年(1859)八月廿八日軍艦奉行兼勤如故
同年(1859)十月廿七日西丸留守居外国事務如故
文久元年(1861)十二月十三日小笠原島行
同二年(1862)箱館奉行
同年(1862)八月八日謝病隠遁
水野筑後守 若年ノ時甲子(カシ)次郎
父高三百俵 甲子次郎ハ部屋住ニテ両番ヘ被召出
コレハ學問出精(励む)ニ付(両番ノ部屋住ニ数多アリ)[、]
父[は]放蕩人ニテ極[めて]困窮(貧乏)[、]公事(役職)[で]出入多シ[。]
甲子次郎[は、]強情モノニテ相番中ノコマリモノナレども[、]
親ノ借金取ヨクシノキ居[り、]
學問ヨロシキ故ヲ以[って]御目付ニナル[。]
此頃ノ評判[では、]學問ニテ御目付御用ニ立[つ]モノハ水野計リ[、]
稀ナルコトナリト[。]然ルニ性質強情且堅タ過テ同勤ノコマリモノ[、]
又御用便ニ相成無[、]御目付御免御使番トナル[。]
久シク勤メテ居ル内[、]修行セシヤ[、]更ニ人物変リ[、]
元来才気モアル故ニ御先手ニ傳ス(此頃ワル口ニ[、]
御先手ハ[、]イキタ親父ノ捨所抔(等)イフ頃ナレハ 火付盗賊改加役ト云)
此加役ヲ勤メ[、]夫ヨリ終ニ御勘定奉行トナル[。]
西洋ヘ初メテ使節ノ砌[、]水野ヘ被仰付[、]彼國ニテモメツラシキ事ナレハ
彼各國新聞紙ヲ始[、]種々ノ書物ヲナス故ニ名高シ[。]
御勘定奉行ヲ勤メル頃ハ[、]若年ノ頃トハ大ニカワリ[、]
水野ノ手紙ハ皆ヒラカナニテ[、]口ニテ物イフコトクニ認ム[、]
故ニ用向ノ足リヌトイフコトナシ[。]元来文才アリテ漢書ハ博覧(多識)[、]
性質ハ大膽(大胆)[、]モノガフト何ト悟リテ[、]此ヒラカナ文章ト
變シタルナレハ[、]言行トモニカワリ[、]政府ノ御用便ヲナスコト
衆人ニ勝レ[。]後年役ヲ辭シテモ[、]此人ヲシタヒ
水野ヘ行テ相談ヲナス役人アマタアリシナリ[。]
[註釈]
*1=牛込早稲田浄泉寺とは、東京都新宿区喜久井町に所在した寺であったが、明治四十年(1907)五月二十三日付で、同区牛込原町(原町)の松雲寺と合併し、松雲寺と号し芝松坂町へ移転。さらに大正二年(1913)、松雲寺は宗清寺と合併し、松雲山宗清寺と号し、東京都中野区上高田1-27-6へ再移転し現在に至る。当寺には水野筑後守忠徳の墓があり、水野定勝の子孫の菩提寺となっている。
*2=「長男晋[、]三男透[、]共ニ平民(*2)トナル」とあることから、二男某氏が継嗣となったものか。また忠徳の孫に克譲が居るが、この三名の何れの子息なのかは不明。
[2009.4.7追記]忠徳領地菩提寺の大儀寺御住持から資料を恵贈いただき、二男忠敬が当家五代当主となり、その息子が克譲と判明した。
[史料TN1-2]
▼『幕末政治家』福地源一郎/著
[福地源一郎は、幕末期の幕臣で水野筑後守忠徳の配下にあった。明治時代はジャーナリスト、作家。幼名は八十吉。号は桜痴、櫻癡。天保十二年(1841)生まれ。
本書は、幕末の政治について主に証言を元にまとめたものである。]
水野筑後守忠徳
余(福地源一郎)が、此政治家(水野筑後守忠徳)を見知りたるは、此人が嘉永六年(1853)、長崎奉行にて、魯国(ロシア)全権と会見したる時に在り、此頃は余はいまだ幼年(忠徳より26歳下)にして、何の弁別(識別)も無かりしが、余が父は医師にて水野の知遇を得て、時々国事など論談したる事ありけるに、「水野は当時魯国使節と談判の為に西下せる筒井川路の諸人に対して、常に強硬説を持したり」と云へり(是は慈父の直話)。
其後、余は東上して水野の食客(居候)と成り、尋(つい)で訳官となりて水野の配下に列し、始終此人に左右したる(そば近く仕える)を以て、水野を知るや最詳なり。水野は外交に関しては、鎖国の不可なるを覚りて、開国議を採り、内治に関しては、幕政の弛廃(しはい。すたれて行われなくなること)を憂いて、改革議を唱へたれども、其性質は、急速を嫌ひて斬新を喜び、秩序を重んじて軽挙を忌める人なれば、寧ろ保守の気象(気性)に富めるが如くなりき。されば外交内治に関し、岩瀬、永井等と往々意見の衝突せる所ありしと雖も、閣議已(すで)に定まりたれば、意を枉(ま)げて是に従ひ、幕府の全権となりて英仏諸国条約に調印したりと云へり。是に由て外国条約の諸項に就て、水野は其後とても、常に慨嘆せられたる事ありけり。若それ其智略才幹(才知に富んだ謀をする手腕)より言えば、水野は遙かに岩瀬小栗の下に在りと雖も、其強硬剛直(頑固に信念を曲げない)は優に其上に位して、以て陰然(隠然)その観望を恕リぎたる政治家なりとす(余が亡友杉浦謙氏は、「水野は大久保に似たり。小栗は井上公に似たり」と評せる事あり。蓋し適評なり)。
[中略]
条約に拠り「金銀貨同種同量交換」の太だ我に不利なるを覚知して、水野は、外国金銀の均合を調査し我往時の南鐐銀(二朱銀)を再興して、新たに是を鋳造し以て、墨銀(メキシコドルラル)一円の半に同量ならしめ、即ち当時の金小判一両と洋銀四円(南鐐八個)との均合に成さしめんと謀りたるるも、水野の計画なりしが、惜しいかな、幕府の財政は多数の南鐐を鋳造して一般の通用に充てること能はざりしが為に、折角の計画も中途にして徒為(無駄)に属したりき。
水野が事を議し政を論ずるや、己が進ずる所は固く執りて動かず、敢えて交譲するを肯ぜざりければ、外人にも悦ばれず、幕閣にも容れられずして、常に不遇の地位に立てり。水野は常に嘆息して曰く、「今日外交の困難なるは、当初岩瀬永井等が、内国の事情を察知せずして、米国条約草案於いて、多くハルリスの要求を容れたるが故なり。凡そ外交の事たり、漫りに外国の要求を承諾す可らず。それと同時に承諾したる以上は、必ず之を実行して、彼を甘心(同意)せしめざる可らず。余(水野筑後守忠徳)は此事を前知して、頻りに論じたれども、用ひられざりしが、果たして今の情勢に至り、日本の国威を損じたるは残念なり」云々(余は屡々(しばしば)此嘆息しての述懐を聞きたり)。
[中略]
水野は退隠と後と雖も、陰然政治に容喙(差し出口)したり。既に文久三年(1863)、将軍家御上洛の時に当り、閣老小笠原図書頭が、大兵を率いて突然大阪に至り、入京せんと迫りたるは、其実水野が其謀に与りて、是を行はしめたるなり(其時余は水野に随行したり)。是に由て水野は蟄居を命ぜられ、其より全く志を政界に絶ちたるなり。
[中略]
又水野は、小笠原の外国に侵略されん事を憂ひ、幕閣に建議して自ら彼島に渡航し、日本の版図(領土)たる事を分明に定めたり(此事は我友田辺太一氏その随行と成りて赴きれば、、是を知る尤も詳なり)。其余、琉球の取締向、および蝦夷地の経界等に関し、「幕府は多年困難の際と雖も、之を忽(ゆるが)せに附し去る可らず」と切論し「外国の為に我国の版図を侵略せらるゝの恐れあり」と痛議したるは、数回にして止らざりけり(退隠の後にも猶屡々建議したる事ありき)。
[後略]
[史料TN1-3]
▼『懐往事談』―― 「水野忠徳の朝廷批判」福地源一郎/著
「然れ共、夫にても御聴納これ無くば、日本全国を挙て焦土にせざるが御天職にてましますなり。其の御天職を尽させ玉ふ御為には如何なる思召も枉させ玉ふべきに、焦土となるも攘夷を行はんとは、恐れながら御一己の御好を以て天下に易させ玉ふと申すものにて候ふ、然る上は恐惶の至なれども、御譲位を促し奉るか否らずば都の外へ行幸なし奉るの外は候はず」
[史料TN1-4]
▼『江戸』第三巻 渉外編――水野筑後守忠徳手記
「阿蘭陀國へ軍艦注文の事」
嘉永六(1853)癸丑六月十九日[、]阿蘭陀國へ軍艦并蒸気船共七艇購入方の議を定め[、]其都合を甲比丹へ可相尋旨[、]當時の閣老安部伊勢守より長崎奉行水野筑後守(長崎奉行に任せられしは同年四月廿八日(ママ)にて當時赴任の準備中なり)へ直達せらる[。]因って當時長崎表に在勤せる奉行大澤豊後守へ早速申遣の處[、]松平河内守の意見により筑後守か赴任の上[、]之か用務を辨すへきことに決定し[、]筑後守は其赴任に先たち豫め其購入に関する用件を具申協定せり[。]
一 甲比丹へ蒸気船軍艦とも献納か又は交易品に替[えて]持越(船で持帰る)すへきかを 談判(話し合い)する事
一 蘭船持越方交易並献上にては不都合なれは別段(特別)六七艘は御買入可相成に付早 々相廻はし候事に談判する事
一 軍艦及蒸気船の雛形製造を甲比丹へ申付け出来次第直に送付すへき事
筑後守か長崎奉行赴任は[、]此等の特別用務あるか為め[、]恒例供連れの外[、]手附萩原又作を差加へられ[、]筑後守は同年七月廿一日江戸を出立し[、]八月廿六日長崎に着任せり[。]斯して直[ぐ]に大澤豊後守と共に甲比丹に對し右注文の意を通し[、]一應の取調を了したる後[、]豫め左記の如き見込を立て[、]以て之か談判をなすへき旨を江戸に具状して其決定を仰けり[。]
一 蘭船取寄に付いては砲具類も組込の方に取計ふへき事
一 船取寄は外國戦争等の為には無之[、]全く運送の利便の為めたる主意を申諭す事
一 取寄すへき船の價格は[、]豫め難相分但リニイ船は壹艘百万「キュルデン」なる事
一キュルテンは[銀]六匁貮分五厘なり
一 御買入船へ[、]乗込人数[、]帰國之乗船并船代渡の御品積[、]帰りの船は別段持渡 可差許事
一 交換品は禁物さりとも[、]米を初め人作の分を可相渡[、]数品取極め置く事
但正金は甲比丹所望あるも[、]銅とても渡し不申方に可致事
一 軍艦は砲具組込の方[、]蒸気船は石炭類組入れて取寄する事
一 人数乗戻船も持越土俵積込可申難きの儀様子に寄積荷別商売にて持越可差許事
一 船運用傳授の蘭人は留置き[、]出島建足し(建増)又は昆布蔵等へ為住[、]滞在中は
唐蘭同断の見込にて少々充損益を見斗可扱遣積
一 右傳受候者は[、]水主大工共野母小瀬戸御番所附等の御手當に准し[、]土地の者を 撰み人物相定め申付執行為到見込
一 一時に数十艘の持渡は無覚束儀
一 蒸気船雛形一艘は[、]脇荷蘭人所持分来夏別商売に致し取寄候見込[、]右横文字和 解造之尤價千両の儀
一 船御取寄の数[、]来年は可成丈ケ多く[、]其上は追々数十艘と無際限申渡置候見込
一 蒸気雛形等は可申付大工[、]當時連渡無之に付[、]来夏持来るへき旨[、]甲比丹申 出の儀
右の如く之か注文に関する取扱の要領を定めたる上[、]其趣旨により甲比丹と商議し[、]之か談判を取極め[、]其次第を江戸に報告せり[。]其進達書類は左の如し[。]
[其進達書類内容以降は後略する]
[史料TN1-5]
▼『江戸』第三巻 渉外編――水野筑後守忠徳手記
「嘉永六年(1853)十二月於長崎表露西亜使節應接の時水野筑後守の記事」
長崎奉行水野筑後守日記抄
嘉永六年(1853)十二月十四日の一節
一 魯人に肥前守(筒井)[が]初對話[の]為[、]案内家老廣川忠左衛門(長崎奉行水野筑後守の家来なり[、]旗本の家なるも長崎奉行は一萬石大名の格式にて在勤するゆゑ其家来を家老といふ也)支配[の]勘定松本金六郎[は]羽織袴ニ而(て)五時比ヨリ使節船に相越[、]玄関迄御儒者古賀謹一郎[が]出迎え[、]直に書院へ通す[。]肥州左衛門(筒井肥前守 川路左衛門尉)者(ハ)裏附狩衣[、]荒尾(御目付荒尾土佐守)并奉行両人者(ハ)大紋ニ而(テ)何連(いずれ)も鞘巻太刀(腰刀)[を]用[い]之[、]古賀者(ハ)布衣也[、]御勘定組頭中村為彌[、]同留役(御勘定評定所留役)菊地大助者(ハ)假布衣[、]支配勘定某御徒目付永持亭次郎者(ハ)假素袍[を]用[い]之[、]双方乍[ら]立會而(て)[、]釋(説明する)自分共者(ハ)床之方江(ヱ)[、]豐州(大澤豊後守)と両人[は]脇に立並[、]其外此度御用ニ而(テ)罷越候[、]中村初[め]永持ハ附ケ入丈「(入側=いりかわ。座敷と濡れ縁との間の細長い通路。畳を敷いたものを縁座敷という)之方敷居内[、]其[を]餘[く]同断(同様)のし免(熨斗目=のしめ、腰替わりの小袖)[を]着候[、]御普請役以下は入丈「[、]御代官高橋作右衛門は長上下(長裃)[、]其外地役に相越居候支配勘定等はのし免麻之[、]家老用人給人は豐州方一同會所調役年寄共迄床之方末[、]家老部ヤ(部屋)入口外に敷居内高木外に家老以下着座す[。]相揃一同目禮双方會釋(会釈)畢(終)て[、筒井]肥前守左衛門其外銘々より初見之口上一ト通り済[、]豐州自分ヨリも申聞る畢(終)て[、]肥州左衛門尚又追々談判[に]可致旨の挨拶有之[、]會釋双方引ク[。]此時中村為彌控所迄案内す[。]控所へ菓子茶出し右相済[、]同人又書院へ案内[、]此時此方者(ハ)上ケ畳高サ八寸(24cm)[、]先方者(ハ)イス(船より持来る)用之[、]但最初は肥州[・]左衛門両人被出[、]三十七採之料理出し對食被到候
此料理向(料理をするにあたり)松平主殿頭[が]出崎(出掛)中故[、]同方[は]料理番へ 申付之昨朝ヨリ夜通しにて出来す
双方食事畢(終)て菊地[が]案内[を]申来[た]る[。]豐州[と]自分者(ハ)床之方[、]御目付荒尾土州[・]古賀謹一郎者(ハ)肥州と同列[、]左衛門尉上ノ畳之上ニ着座[。]肥州左衛門ヨリ渡来の挨拶且書翰之儀[、]追々可談旨被申諭畢(終)て右ニ付両條(両條とは蝦夷地境界決定の事及通商相叶ふ哉の二件ならん)當席ニ而(て)直に承知致度旨申出る[。]何れ後日と挨拶之處[、]然らは明朝四人之内壹人船へ可越對談可致[、]尤軽事之旨申聞る[。]兼而(て)明日明後日者(ハ)賀日之旨[、]昨日断[わり]置く故其旨相達[、]然らは付属之者壹人可差越書面可相渡明夕迄否可申答旨聞る[。]尚又軽事必即時可決事の旨申立る[。]
承引(承諾してひきうけること)之旨申達[、]其後先方ヨリ改而(て)奉行両人江(ヱ)上陸之儀[、]明日ヨリ可致旨申聞る[。]未た修理不相整出来次第可及沙汰旨相達[、]猶又十七日役々一同船江(ヱ)可相越旨申聞る[。]鎮臺(地方の軍団や役所)之儀故従是可及挨拶旨申聞る[。]承伏畢(終)て尚又今日馳走之禮申聞双方會釋対座[。]使節直ニ退散[、]中村[が]玄関迄案内[。]九半過来着其比帰る[。]
但上陸往返剱附筒持之音楽奏之
 >
>
[史料TN1-6]
▼『大日本古文書幕末外国関係文書附録之三』
三 水野忠徳雑録之一
(安政二年(1855)正月より九月に至る)
〇水野筑後守忠徳ハ、安政元年(1854)十二月、長崎奉行ヨリ勘定奉行ニ轉ジ、同四年(1857)十二月、田安家家老ニ轉ジ、同五年(1858)七月、外國奉行ニ轉ジ、勘定奉行ヲ兼ネ、同年十月、西丸留守居ニ轉ジ、文久元年(1861)五月、再ビ外國奉行に任ジ、同二年(1862)七月、箱舘奉行ニ轉ジ、同年九月、職を辞セリ、此雑録ハ、忠徳ガ安政二年(1855)、勘定奉行ノ職ニ在リシ時ヨリ、文久二年(1862)、外國奉行ノ職ニ在リシ間、外國ニ関する公文私記ヲ集メタルモノニシテ、東京水野克讓氏ノ所蔵ニ係ル、
(表紙)
「 水野忠徳
安政二(1855)乙卯年雑録 」
[抜粋]
安政二(1855)乙卯年雑録
正月小
「日米條約批准書ヲ下田ニ送ス」
一 二日、下田ニ、去寅(1854)十二月九日ヨリ、渡来滞船之アメリカ蒸気船使節アーダムス應接とし[、]相越居ル町奉行井戸對馬守江(ヱ)約條本書(日米條約批准書)為持可遣旨ニ而(テ)、阿部伊勢守殿、(奥祐筆)早川庄次郎ニ而(テ)松平河内守江(ヱ)御渡、即日夕七時頃、宿継(*1-6-1)ニ而(テ)差立(1-6-2)候、尤昨日ヨリ御沙汰ニ而(テ)、大急キニ付、御普請役 (四文字空白マゝ)昨日ヨリ出立、下田迄之宿駅江(ヱ)、大切之御品、急[ギ]継立(宿継)之儀申達ニ相成、(〇頭注ニ「船名ホウハタン三百人余乗此船唐國ニ相越居處、アータムス三个月巳前、本國ヨリ唐ヘ越、乗組渡来之由」トアリ、)
「條約批准書ノ躰裁」
右約條書(條約批准書)[の体裁]者(ハ)、大奉書ニ而(テ)、上表紙大和錦紫綴糸、本篇附録と貮冊ニナリ、毎冊奥書有之、御老中方御連名御花押計(バカリ)ナリ、安政元甲寅年(1854)十二月ノ月附(作成月)ナリ、上ハ箱桐正目、糸附可奈物(金物)、物(衍カ(*1-6-3))銀ニ而(テ)菱ナリ、紅丸打紐(*1-6-4)ニ而(テ)結[ブ]、上箱同断(同様)、紫平打紐ナリ、可奈物(金物)ハ、煮グルミ奈り(ナリ)、其上を上ハ箱へ入仕立、差立ニナル、品川迄ハ湯呑所ノ同心附添たり、右者(ハ)加奈川ニ而(テ)定り之条約奈リ、別に扣(控)有之、
「亜米利加條約批准書ノ交換」
一 下田亜墨船使節江(ヱ)、正月五日、約條書附録とも本書貮冊相渡、先方ヨリも受取、尤附録者(ハ)重[ね]而(テ)可持渡、夫迄相違無之段、アータムス書面差出、翌六日、井戸初[め]彼船(アメリカ船)江(ヱ)相越、饗応受、六日辰上刻(午前八時から九時頃)無滞出帆、被下物も全権ニ而(テ)取計相渡、且井戸對州江(ヱ)此度為取替御委任之書面、伊勢守殿御一名之御花押御渡ニ付、元日ニ差遣候、先方ニ而(テ)不承引ニ有之旨ヲ以、約條書同様御連名御花押とも、下田ニ而(テ)取計相認、アータムス江(ヱ)渡候由、
[註]
*1-6-1=しゅくつぎ。人馬を入れ替えながら、宿場から宿場へ荷物などを順に送ること。
*1-6-2=さしたて。(1)人を差し向けること。(2)郵便物などを発送すること。
*1-6-3=衍字(えんじ)。《「衍」は余りの意》。語句の中に間違って入った不必要な文字。
*1-6-4=うちひも。糸の組み目を篦(へら)で打ち込んで固く仕上げた紐。組紐。打ち緒。
R-4>水野筑後守忠徳 参考資料2/2
=====================================================================
【主な参考文献】(順不同)
東京大學史料編纂所『水野忠徳事蹟』(東京大學史料編纂所所蔵データベース)
東京大學史料編纂所『大日本古文書幕末外国関係文書之十五』
東京大學史料編纂所『大日本古文書幕末外国関係文書附録之一、二、三、四、六』
石井良助『編年江戸武鑑・文化武鑑4』
福地源一郎『幕末政治家』
福地源一郎『懐往事談』―― 「水野忠徳の朝廷批判」
尾佐竹猛『幕末遣外使節物語』
綱淵謙錠『幕臣列伝』
綱淵謙錠『幕末に生きる』
土居良三『幕末五人の外国奉行』
大久保利謙『江戸 第一巻 幕政編(一)』
大久保利謙『江戸 第二巻 幕政編(二)』
大久保利謙『江戸 第三巻 渉外編』
日本史籍協會『幕末外交談』續日本史籍協會叢書
日本史籍協會『昨夢紀事 二 三 四巻』續日本史籍協會叢書
日本史籍協會『長崎警衛記録』續日本史籍協會叢書153
加藤英明『徳川幕府外国方:近代的対外事務担当の先駆―その機構と人―』
幕末維新論集7『幕末維新と外交』に収録
横浜市役所『横濱市史稿』政治編二
日本歴史学会編『明治維新人名辞典』
小川恭一『江戸幕府旗本人名辞典 第三巻』
笹間良彦『江戸幕府役職集成(増補版)』
竹内誠・深井雅海『日本近世人名辞典』
田中弘之『幕末の小笠原』
佐藤雅美『大君の通貨』
====================================================================
[史料TN1-1]
▼『水野忠徳事蹟』著者不詳の小伝(東京大學史料編纂所所蔵データベース)を翻刻
水野癡雲(ちうん)
名ハ忠徳[、]通称ハ甲子(カシ)次郎[。]後ニ従五位下ニ叙シ筑後守又下總守ニ任ス[。]致仕(退官)シテ癡雲ト号ス[。]諏訪庄右衛門頼篤ノ次男[。]文化十二年(1815)四月九日江戸愛宕下ノ邸ニ生ス[。]文政五年(1822)十月十三日水野弥三郎忠長ノ義子ト為ル[。]明治元年(1868)七月九日雑司ヶ谷村ノ別墅(別宅)ニ卒ス[。]年五十四[。]牛込早稲田浄泉寺(*1)ニ葬ル[。]長男晋[、]三男透[、]共ニ平民(*2)トナル[。]今其居所ヲ詳ニセス[。]」
天保七年(1836)九月廿日小性組番拝命
同十三年(1842)十二月三日徳川家系調
同十四年(1843)九月廿四日西丸ノ目付
弘化二年(1845)四月十五日使番
嘉永二年(1849)七月廿八日先手銕砲頭
同年 (1849)十月九日火附盗賊改
同五年(1852)四月十五日浦賀奉行(千石高、御役料千石)
同六年(1853)四月廿六日長崎奉行(千石高、御役料四千四百表)
安政元年(1854)十二月廿四日勘定奉行勝手掛
同四年(1857)四月十五日長崎奉行兼帯
同年 (1857)十二月三日田安館家老
同五年(1858)六月八日外国奉行
同年(1858)八月 日亜国行内命
同六年(1859)四月八日勘定奉行勝手掛兼帯
同年(1859)八月廿八日軍艦奉行兼勤如故
同年(1859)十月廿七日西丸留守居外国事務如故
文久元年(1861)十二月十三日小笠原島行
同二年(1862)箱館奉行
同年(1862)八月八日謝病隠遁
水野筑後守 若年ノ時甲子(カシ)次郎
父高三百俵 甲子次郎ハ部屋住ニテ両番ヘ被召出
コレハ學問出精(励む)ニ付(両番ノ部屋住ニ数多アリ)[、]
父[は]放蕩人ニテ極[めて]困窮(貧乏)[、]公事(役職)[で]出入多シ[。]
甲子次郎[は、]強情モノニテ相番中ノコマリモノナレども[、]
親ノ借金取ヨクシノキ居[り、]
學問ヨロシキ故ヲ以[って]御目付ニナル[。]
此頃ノ評判[では、]學問ニテ御目付御用ニ立[つ]モノハ水野計リ[、]
稀ナルコトナリト[。]然ルニ性質強情且堅タ過テ同勤ノコマリモノ[、]
又御用便ニ相成無[、]御目付御免御使番トナル[。]
久シク勤メテ居ル内[、]修行セシヤ[、]更ニ人物変リ[、]
元来才気モアル故ニ御先手ニ傳ス(此頃ワル口ニ[、]
御先手ハ[、]イキタ親父ノ捨所抔(等)イフ頃ナレハ 火付盗賊改加役ト云)
此加役ヲ勤メ[、]夫ヨリ終ニ御勘定奉行トナル[。]
西洋ヘ初メテ使節ノ砌[、]水野ヘ被仰付[、]彼國ニテモメツラシキ事ナレハ
彼各國新聞紙ヲ始[、]種々ノ書物ヲナス故ニ名高シ[。]
御勘定奉行ヲ勤メル頃ハ[、]若年ノ頃トハ大ニカワリ[、]
水野ノ手紙ハ皆ヒラカナニテ[、]口ニテ物イフコトクニ認ム[、]
故ニ用向ノ足リヌトイフコトナシ[。]元来文才アリテ漢書ハ博覧(多識)[、]
性質ハ大膽(大胆)[、]モノガフト何ト悟リテ[、]此ヒラカナ文章ト
變シタルナレハ[、]言行トモニカワリ[、]政府ノ御用便ヲナスコト
衆人ニ勝レ[。]後年役ヲ辭シテモ[、]此人ヲシタヒ
水野ヘ行テ相談ヲナス役人アマタアリシナリ[。]
[註釈]
*1=牛込早稲田浄泉寺とは、東京都新宿区喜久井町に所在した寺であったが、明治四十年(1907)五月二十三日付で、同区牛込原町(原町)の松雲寺と合併し、松雲寺と号し芝松坂町へ移転。さらに大正二年(1913)、松雲寺は宗清寺と合併し、松雲山宗清寺と号し、東京都中野区上高田1-27-6へ再移転し現在に至る。当寺には水野筑後守忠徳の墓があり、水野定勝の子孫の菩提寺となっている。
*2=「長男晋[、]三男透[、]共ニ平民(*2)トナル」とあることから、二男某氏が継嗣となったものか。また忠徳の孫に克譲が居るが、この三名の何れの子息なのかは不明。
[2009.4.7追記]忠徳領地菩提寺の大儀寺御住持から資料を恵贈いただき、二男忠敬が当家五代当主となり、その息子が克譲と判明した。
[史料TN1-2]
▼『幕末政治家』福地源一郎/著
[福地源一郎は、幕末期の幕臣で水野筑後守忠徳の配下にあった。明治時代はジャーナリスト、作家。幼名は八十吉。号は桜痴、櫻癡。天保十二年(1841)生まれ。
本書は、幕末の政治について主に証言を元にまとめたものである。]
水野筑後守忠徳
余(福地源一郎)が、此政治家(水野筑後守忠徳)を見知りたるは、此人が嘉永六年(1853)、長崎奉行にて、魯国(ロシア)全権と会見したる時に在り、此頃は余はいまだ幼年(忠徳より26歳下)にして、何の弁別(識別)も無かりしが、余が父は医師にて水野の知遇を得て、時々国事など論談したる事ありけるに、「水野は当時魯国使節と談判の為に西下せる筒井川路の諸人に対して、常に強硬説を持したり」と云へり(是は慈父の直話)。
其後、余は東上して水野の食客(居候)と成り、尋(つい)で訳官となりて水野の配下に列し、始終此人に左右したる(そば近く仕える)を以て、水野を知るや最詳なり。水野は外交に関しては、鎖国の不可なるを覚りて、開国議を採り、内治に関しては、幕政の弛廃(しはい。すたれて行われなくなること)を憂いて、改革議を唱へたれども、其性質は、急速を嫌ひて斬新を喜び、秩序を重んじて軽挙を忌める人なれば、寧ろ保守の気象(気性)に富めるが如くなりき。されば外交内治に関し、岩瀬、永井等と往々意見の衝突せる所ありしと雖も、閣議已(すで)に定まりたれば、意を枉(ま)げて是に従ひ、幕府の全権となりて英仏諸国条約に調印したりと云へり。是に由て外国条約の諸項に就て、水野は其後とても、常に慨嘆せられたる事ありけり。若それ其智略才幹(才知に富んだ謀をする手腕)より言えば、水野は遙かに岩瀬小栗の下に在りと雖も、其強硬剛直(頑固に信念を曲げない)は優に其上に位して、以て陰然(隠然)その観望を恕リぎたる政治家なりとす(余が亡友杉浦謙氏は、「水野は大久保に似たり。小栗は井上公に似たり」と評せる事あり。蓋し適評なり)。
[中略]
条約に拠り「金銀貨同種同量交換」の太だ我に不利なるを覚知して、水野は、外国金銀の均合を調査し我往時の南鐐銀(二朱銀)を再興して、新たに是を鋳造し以て、墨銀(メキシコドルラル)一円の半に同量ならしめ、即ち当時の金小判一両と洋銀四円(南鐐八個)との均合に成さしめんと謀りたるるも、水野の計画なりしが、惜しいかな、幕府の財政は多数の南鐐を鋳造して一般の通用に充てること能はざりしが為に、折角の計画も中途にして徒為(無駄)に属したりき。
水野が事を議し政を論ずるや、己が進ずる所は固く執りて動かず、敢えて交譲するを肯ぜざりければ、外人にも悦ばれず、幕閣にも容れられずして、常に不遇の地位に立てり。水野は常に嘆息して曰く、「今日外交の困難なるは、当初岩瀬永井等が、内国の事情を察知せずして、米国条約草案於いて、多くハルリスの要求を容れたるが故なり。凡そ外交の事たり、漫りに外国の要求を承諾す可らず。それと同時に承諾したる以上は、必ず之を実行して、彼を甘心(同意)せしめざる可らず。余(水野筑後守忠徳)は此事を前知して、頻りに論じたれども、用ひられざりしが、果たして今の情勢に至り、日本の国威を損じたるは残念なり」云々(余は屡々(しばしば)此嘆息しての述懐を聞きたり)。
[中略]
水野は退隠と後と雖も、陰然政治に容喙(差し出口)したり。既に文久三年(1863)、将軍家御上洛の時に当り、閣老小笠原図書頭が、大兵を率いて突然大阪に至り、入京せんと迫りたるは、其実水野が其謀に与りて、是を行はしめたるなり(其時余は水野に随行したり)。是に由て水野は蟄居を命ぜられ、其より全く志を政界に絶ちたるなり。
[中略]
又水野は、小笠原の外国に侵略されん事を憂ひ、幕閣に建議して自ら彼島に渡航し、日本の版図(領土)たる事を分明に定めたり(此事は我友田辺太一氏その随行と成りて赴きれば、、是を知る尤も詳なり)。其余、琉球の取締向、および蝦夷地の経界等に関し、「幕府は多年困難の際と雖も、之を忽(ゆるが)せに附し去る可らず」と切論し「外国の為に我国の版図を侵略せらるゝの恐れあり」と痛議したるは、数回にして止らざりけり(退隠の後にも猶屡々建議したる事ありき)。
[後略]
[史料TN1-3]
▼『懐往事談』―― 「水野忠徳の朝廷批判」福地源一郎/著
「然れ共、夫にても御聴納これ無くば、日本全国を挙て焦土にせざるが御天職にてましますなり。其の御天職を尽させ玉ふ御為には如何なる思召も枉させ玉ふべきに、焦土となるも攘夷を行はんとは、恐れながら御一己の御好を以て天下に易させ玉ふと申すものにて候ふ、然る上は恐惶の至なれども、御譲位を促し奉るか否らずば都の外へ行幸なし奉るの外は候はず」
[史料TN1-4]
▼『江戸』第三巻 渉外編――水野筑後守忠徳手記
「阿蘭陀國へ軍艦注文の事」
嘉永六(1853)癸丑六月十九日[、]阿蘭陀國へ軍艦并蒸気船共七艇購入方の議を定め[、]其都合を甲比丹へ可相尋旨[、]當時の閣老安部伊勢守より長崎奉行水野筑後守(長崎奉行に任せられしは同年四月廿八日(ママ)にて當時赴任の準備中なり)へ直達せらる[。]因って當時長崎表に在勤せる奉行大澤豊後守へ早速申遣の處[、]松平河内守の意見により筑後守か赴任の上[、]之か用務を辨すへきことに決定し[、]筑後守は其赴任に先たち豫め其購入に関する用件を具申協定せり[。]
一 甲比丹へ蒸気船軍艦とも献納か又は交易品に替[えて]持越(船で持帰る)すへきかを 談判(話し合い)する事
一 蘭船持越方交易並献上にては不都合なれは別段(特別)六七艘は御買入可相成に付早 々相廻はし候事に談判する事
一 軍艦及蒸気船の雛形製造を甲比丹へ申付け出来次第直に送付すへき事
筑後守か長崎奉行赴任は[、]此等の特別用務あるか為め[、]恒例供連れの外[、]手附萩原又作を差加へられ[、]筑後守は同年七月廿一日江戸を出立し[、]八月廿六日長崎に着任せり[。]斯して直[ぐ]に大澤豊後守と共に甲比丹に對し右注文の意を通し[、]一應の取調を了したる後[、]豫め左記の如き見込を立て[、]以て之か談判をなすへき旨を江戸に具状して其決定を仰けり[。]
一 蘭船取寄に付いては砲具類も組込の方に取計ふへき事
一 船取寄は外國戦争等の為には無之[、]全く運送の利便の為めたる主意を申諭す事
一 取寄すへき船の價格は[、]豫め難相分但リニイ船は壹艘百万「キュルデン」なる事
一キュルテンは[銀]六匁貮分五厘なり
一 御買入船へ[、]乗込人数[、]帰國之乗船并船代渡の御品積[、]帰りの船は別段持渡 可差許事
一 交換品は禁物さりとも[、]米を初め人作の分を可相渡[、]数品取極め置く事
但正金は甲比丹所望あるも[、]銅とても渡し不申方に可致事
一 軍艦は砲具組込の方[、]蒸気船は石炭類組入れて取寄する事
一 人数乗戻船も持越土俵積込可申難きの儀様子に寄積荷別商売にて持越可差許事
一 船運用傳授の蘭人は留置き[、]出島建足し(建増)又は昆布蔵等へ為住[、]滞在中は
唐蘭同断の見込にて少々充損益を見斗可扱遣積
一 右傳受候者は[、]水主大工共野母小瀬戸御番所附等の御手當に准し[、]土地の者を 撰み人物相定め申付執行為到見込
一 一時に数十艘の持渡は無覚束儀
一 蒸気船雛形一艘は[、]脇荷蘭人所持分来夏別商売に致し取寄候見込[、]右横文字和 解造之尤價千両の儀
一 船御取寄の数[、]来年は可成丈ケ多く[、]其上は追々数十艘と無際限申渡置候見込
一 蒸気雛形等は可申付大工[、]當時連渡無之に付[、]来夏持来るへき旨[、]甲比丹申 出の儀
右の如く之か注文に関する取扱の要領を定めたる上[、]其趣旨により甲比丹と商議し[、]之か談判を取極め[、]其次第を江戸に報告せり[。]其進達書類は左の如し[。]
[其進達書類内容以降は後略する]
[史料TN1-5]
▼『江戸』第三巻 渉外編――水野筑後守忠徳手記
「嘉永六年(1853)十二月於長崎表露西亜使節應接の時水野筑後守の記事」
長崎奉行水野筑後守日記抄
嘉永六年(1853)十二月十四日の一節
一 魯人に肥前守(筒井)[が]初對話[の]為[、]案内家老廣川忠左衛門(長崎奉行水野筑後守の家来なり[、]旗本の家なるも長崎奉行は一萬石大名の格式にて在勤するゆゑ其家来を家老といふ也)支配[の]勘定松本金六郎[は]羽織袴ニ而(て)五時比ヨリ使節船に相越[、]玄関迄御儒者古賀謹一郎[が]出迎え[、]直に書院へ通す[。]肥州左衛門(筒井肥前守 川路左衛門尉)者(ハ)裏附狩衣[、]荒尾(御目付荒尾土佐守)并奉行両人者(ハ)大紋ニ而(テ)何連(いずれ)も鞘巻太刀(腰刀)[を]用[い]之[、]古賀者(ハ)布衣也[、]御勘定組頭中村為彌[、]同留役(御勘定評定所留役)菊地大助者(ハ)假布衣[、]支配勘定某御徒目付永持亭次郎者(ハ)假素袍[を]用[い]之[、]双方乍[ら]立會而(て)[、]釋(説明する)自分共者(ハ)床之方江(ヱ)[、]豐州(大澤豊後守)と両人[は]脇に立並[、]其外此度御用ニ而(テ)罷越候[、]中村初[め]永持ハ附ケ入丈「(入側=いりかわ。座敷と濡れ縁との間の細長い通路。畳を敷いたものを縁座敷という)之方敷居内[、]其[を]餘[く]同断(同様)のし免(熨斗目=のしめ、腰替わりの小袖)[を]着候[、]御普請役以下は入丈「[、]御代官高橋作右衛門は長上下(長裃)[、]其外地役に相越居候支配勘定等はのし免麻之[、]家老用人給人は豐州方一同會所調役年寄共迄床之方末[、]家老部ヤ(部屋)入口外に敷居内高木外に家老以下着座す[。]相揃一同目禮双方會釋(会釈)畢(終)て[、筒井]肥前守左衛門其外銘々より初見之口上一ト通り済[、]豐州自分ヨリも申聞る畢(終)て[、]肥州左衛門尚又追々談判[に]可致旨の挨拶有之[、]會釋双方引ク[。]此時中村為彌控所迄案内す[。]控所へ菓子茶出し右相済[、]同人又書院へ案内[、]此時此方者(ハ)上ケ畳高サ八寸(24cm)[、]先方者(ハ)イス(船より持来る)用之[、]但最初は肥州[・]左衛門両人被出[、]三十七採之料理出し對食被到候
此料理向(料理をするにあたり)松平主殿頭[が]出崎(出掛)中故[、]同方[は]料理番へ 申付之昨朝ヨリ夜通しにて出来す
双方食事畢(終)て菊地[が]案内[を]申来[た]る[。]豐州[と]自分者(ハ)床之方[、]御目付荒尾土州[・]古賀謹一郎者(ハ)肥州と同列[、]左衛門尉上ノ畳之上ニ着座[。]肥州左衛門ヨリ渡来の挨拶且書翰之儀[、]追々可談旨被申諭畢(終)て右ニ付両條(両條とは蝦夷地境界決定の事及通商相叶ふ哉の二件ならん)當席ニ而(て)直に承知致度旨申出る[。]何れ後日と挨拶之處[、]然らは明朝四人之内壹人船へ可越對談可致[、]尤軽事之旨申聞る[。]兼而(て)明日明後日者(ハ)賀日之旨[、]昨日断[わり]置く故其旨相達[、]然らは付属之者壹人可差越書面可相渡明夕迄否可申答旨聞る[。]尚又軽事必即時可決事の旨申立る[。]
承引(承諾してひきうけること)之旨申達[、]其後先方ヨリ改而(て)奉行両人江(ヱ)上陸之儀[、]明日ヨリ可致旨申聞る[。]未た修理不相整出来次第可及沙汰旨相達[、]猶又十七日役々一同船江(ヱ)可相越旨申聞る[。]鎮臺(地方の軍団や役所)之儀故従是可及挨拶旨申聞る[。]承伏畢(終)て尚又今日馳走之禮申聞双方會釋対座[。]使節直ニ退散[、]中村[が]玄関迄案内[。]九半過来着其比帰る[。]
但上陸往返剱附筒持之音楽奏之
 >
>[史料TN1-6]
▼『大日本古文書幕末外国関係文書附録之三』
三 水野忠徳雑録之一
(安政二年(1855)正月より九月に至る)
〇水野筑後守忠徳ハ、安政元年(1854)十二月、長崎奉行ヨリ勘定奉行ニ轉ジ、同四年(1857)十二月、田安家家老ニ轉ジ、同五年(1858)七月、外國奉行ニ轉ジ、勘定奉行ヲ兼ネ、同年十月、西丸留守居ニ轉ジ、文久元年(1861)五月、再ビ外國奉行に任ジ、同二年(1862)七月、箱舘奉行ニ轉ジ、同年九月、職を辞セリ、此雑録ハ、忠徳ガ安政二年(1855)、勘定奉行ノ職ニ在リシ時ヨリ、文久二年(1862)、外國奉行ノ職ニ在リシ間、外國ニ関する公文私記ヲ集メタルモノニシテ、東京水野克讓氏ノ所蔵ニ係ル、
(表紙)
「 水野忠徳
安政二(1855)乙卯年雑録 」
[抜粋]
安政二(1855)乙卯年雑録
正月小
「日米條約批准書ヲ下田ニ送ス」
一 二日、下田ニ、去寅(1854)十二月九日ヨリ、渡来滞船之アメリカ蒸気船使節アーダムス應接とし[、]相越居ル町奉行井戸對馬守江(ヱ)約條本書(日米條約批准書)為持可遣旨ニ而(テ)、阿部伊勢守殿、(奥祐筆)早川庄次郎ニ而(テ)松平河内守江(ヱ)御渡、即日夕七時頃、宿継(*1-6-1)ニ而(テ)差立(1-6-2)候、尤昨日ヨリ御沙汰ニ而(テ)、大急キニ付、御普請役 (四文字空白マゝ)昨日ヨリ出立、下田迄之宿駅江(ヱ)、大切之御品、急[ギ]継立(宿継)之儀申達ニ相成、(〇頭注ニ「船名ホウハタン三百人余乗此船唐國ニ相越居處、アータムス三个月巳前、本國ヨリ唐ヘ越、乗組渡来之由」トアリ、)
「條約批准書ノ躰裁」
右約條書(條約批准書)[の体裁]者(ハ)、大奉書ニ而(テ)、上表紙大和錦紫綴糸、本篇附録と貮冊ニナリ、毎冊奥書有之、御老中方御連名御花押計(バカリ)ナリ、安政元甲寅年(1854)十二月ノ月附(作成月)ナリ、上ハ箱桐正目、糸附可奈物(金物)、物(衍カ(*1-6-3))銀ニ而(テ)菱ナリ、紅丸打紐(*1-6-4)ニ而(テ)結[ブ]、上箱同断(同様)、紫平打紐ナリ、可奈物(金物)ハ、煮グルミ奈り(ナリ)、其上を上ハ箱へ入仕立、差立ニナル、品川迄ハ湯呑所ノ同心附添たり、右者(ハ)加奈川ニ而(テ)定り之条約奈リ、別に扣(控)有之、
「亜米利加條約批准書ノ交換」
一 下田亜墨船使節江(ヱ)、正月五日、約條書附録とも本書貮冊相渡、先方ヨリも受取、尤附録者(ハ)重[ね]而(テ)可持渡、夫迄相違無之段、アータムス書面差出、翌六日、井戸初[め]彼船(アメリカ船)江(ヱ)相越、饗応受、六日辰上刻(午前八時から九時頃)無滞出帆、被下物も全権ニ而(テ)取計相渡、且井戸對州江(ヱ)此度為取替御委任之書面、伊勢守殿御一名之御花押御渡ニ付、元日ニ差遣候、先方ニ而(テ)不承引ニ有之旨ヲ以、約條書同様御連名御花押とも、下田ニ而(テ)取計相認、アータムス江(ヱ)渡候由、
[註]
*1-6-1=しゅくつぎ。人馬を入れ替えながら、宿場から宿場へ荷物などを順に送ること。
*1-6-2=さしたて。(1)人を差し向けること。(2)郵便物などを発送すること。
*1-6-3=衍字(えんじ)。《「衍」は余りの意》。語句の中に間違って入った不必要な文字。
*1-6-4=うちひも。糸の組み目を篦(へら)で打ち込んで固く仕上げた紐。組紐。打ち緒。
R-4>水野筑後守忠徳 参考資料2/2