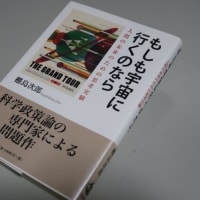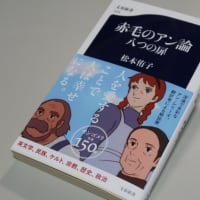☆《美術にぶるっ! ベストセレクション 日本近代美術の100年》(東京国立近代美術館)☆
曇天ベースでときおり小雨も降るなか、「美術にぶるっ!」としたくて竹橋にある東京国立近代美術館へ行ってきた。東京国立近代美術館は一昨年秋に《上村松園展》を見に行って以来2度目。《上村松園展》のときはものすごい人出だったので、それを見越して開館30分前に行ったのだが、チケット売り場にはまだだれもおらず、今日は閉館日だったのではないかと確認したくらいだった。2番目に来た女性も驚いたらしく「チケット売り場はここだけですよね」と尋ねられてしまった。上村松園だの東山魁夷だのといっただれでも知っている画家を除けば、日本の画家の展覧会は西洋の画家ほどには人を集められないのかもしれない。土曜日の午前中とはいえ、中年以降の年配者が多かったことから見ても、若い人の目には日本画や日本の画家の作品は、あまり魅力的に映っていないということもあるのかもしれない。
とはいえ、観客が少なかったので、自分のペースでゆっくりと鑑賞できたのは幸いだった。最初にエレベーターで4階まで上がり下へと降りてくる順路になっている。4階で最初に目を射たのは萬鉄五郎の「裸体美人」(重要文化財)だ。何かの画集で初めて見たときも衝撃的だったが、実物の色使いや構図には圧倒的な迫力があって「ぶるっ!」というよりは「どきっ!」とさせられる。数十メートルにも及ぶ水墨画の絵巻物である横山大観の「生々流転」(重要文化財)には、思わず「ほおっ~!」と唸らされてしまう。深山幽谷の雲の中で生じた水滴が落ちて川となり、やがて大河となって海へと注ぎ、再び空へと昇っていくさまを描いたものだ。いまの時代ならばエコロジー的な視点で眺める人も少なくないだろう。もちろん自然の「生々流転」は人の「生々流転」とも重ね合わされて描かれているにちがいない。
和田三蔵の「南風」は美術のテキストなどでもよく見かける作品である。小さな木造船に乗る4人の男。赤い腰布だけを身につけ、上半身の逞しい裸体をさらした男にまず目がいく。横にいる白いシャツの男も海の男らしい精悍な表情をしている。対照的に前にいる左右の二人の男は力なく座り込んでいる。これから先の運命を赤い腰布の男と白シャツの男に委ねているようにも見える。そして、紺青色の海と白波、船上に落ちる濃い影。絵の前に立つと、やがて画面に引き込まれ、南からの熱風が顔にあたるような気がしてくる。船乗りの仕事を「板一枚下は地獄」などというが、生死の狭間にいる海の男ならではの力強さが伝わってくる。精悍な男たちを見ていると、ささいなことは忘れて生きる勇気が湧いてくるかのようだ。思わず、初めて「ぶるっ!」とした。
藤田嗣治の「五人の裸婦」は、その美しい裸婦像に「おおっ!」と小さく叫びそうになる作品だ。白磁のような美しさだけでなく、どこか不思議な雰囲気もたたえている。五人はそれぞれ五感を表しているという解説を読むと、不思議さの一端がわかったような気がした。高村光太郎の彫刻「手」も著名な作品だが、見れば見るほど奇妙な指の配置をしている。間近に見ることで、その奇妙さにあらためて納得し、さらに不思議さも以前より倍加した。「ん!?」という感じだろうか。彫刻では新海竹太郎の「ゆあみ」(重要文化財)も興味深かった。日本人をモデルにしていながらも西洋的なプロポーションの裸婦像であり、和洋混交の先駆的な作品であるという。薄布をまとっているところも日本的であるという解説に「なっとく!」した。
3階に下りると、まず藤田嗣治の「アッツ島玉砕」と「サイパン島同胞臣節を全うす」に目を奪われた。「五人の裸婦」からは想像できない藤田嗣治の別の一面を見ることができる。とくに「アッツ島玉砕」はリアルさを超えた玉砕の描画に言葉を失ってしまう! 藤田はのちに戦争協力の批判を浴びるのだが、画家も生きるためには当時の政治情勢に逆らえなかったということなのだろう。日本画では上村松園の「母子」(重要文化財)、小倉遊亀の「浴女 その一」、福田平八郎の「雨」、東山魁夷の「秋翳」など、「日本画っていいな!」と思わせる作品が続く。
しかし、いちばん心ひかれたのは高山辰雄の「いだく」だった。高山辰雄の名前も知らず、もちろん初めて見る絵である。二人の女性が赤ん坊を抱いているだけというシンプルな構図である。背景はぼやけていて幻想的なイメージでもある。赤子を抱く二人の手はつながっており、新たな命がかけがえのないものとして守られている印象を強くする。女性の表情もやさしさに満ちている。赤ん坊から見れば、二人の女性に抱かれて、深い安らぎのなかに佇んでいるかのようだ。胎内回帰の郷愁を描いているようにも思える。だからなのか、この絵には「ほっ!」とさせられた。
2階は主に、いわゆる前衛的な作品や東京国立近代美術館が所蔵する海外の作品が並ぶ。ここまでが「第Ⅰ部 MOMAT コレクションスペシャル」であり、1階が「第Ⅱ部 実験場1950s」となっている。2階と1階はかけあしで見ただけだが、1階の土門拳と川田喜久治による原爆関連の写真は決して忘れてはならない記録である!(なお、「MOMAT」は「The National Museum of Modern Art, Tokyo」の略である)
この美術展は東京国立近代美術館開館60周年記念であり、美術にふるえるという美術鑑賞の原点を「ぶるっ!」という言葉で表している。「ぶるっ!」という言葉が適切かどうかは少し疑問に思うが、「!」をつけたくなる作品にはいくつも出会った。最後にショップで絵葉書を数枚買って帰路に着いた。(その前に、NHKも主催者の一つであり、そのアンケートに答えてきた) 入館からここまで約2時間半。4階と3階で多くの時間を費やしたが、満足のいく時間を過ごしたように思う。
藤田嗣治を持ち出すまでもなく、美術もまた時代を写し、画家もまた時代に翻弄される。再び政権交代が行われるのは確実な情勢だ。政権交代の是非はともかくとしても、政治家が安心、安定、強靭などと口にすればするほど、世の中は不安や不安定さが増し、弱者が置き去りにされていくような気がしてならない。ともあれ、少々貧しくても、ある程度の不便さはがまんしても、ゆっくりと絵が鑑賞できて、どんな本でも読めて、画家や作家が―あえて付け加えるが、科学者も―時代を鼓舞することを要請されないように、こころから願わずにはいられない。
下の写真は4階にある「眺めのよい部屋」で、皇居が眺望できる。


曇天ベースでときおり小雨も降るなか、「美術にぶるっ!」としたくて竹橋にある東京国立近代美術館へ行ってきた。東京国立近代美術館は一昨年秋に《上村松園展》を見に行って以来2度目。《上村松園展》のときはものすごい人出だったので、それを見越して開館30分前に行ったのだが、チケット売り場にはまだだれもおらず、今日は閉館日だったのではないかと確認したくらいだった。2番目に来た女性も驚いたらしく「チケット売り場はここだけですよね」と尋ねられてしまった。上村松園だの東山魁夷だのといっただれでも知っている画家を除けば、日本の画家の展覧会は西洋の画家ほどには人を集められないのかもしれない。土曜日の午前中とはいえ、中年以降の年配者が多かったことから見ても、若い人の目には日本画や日本の画家の作品は、あまり魅力的に映っていないということもあるのかもしれない。
とはいえ、観客が少なかったので、自分のペースでゆっくりと鑑賞できたのは幸いだった。最初にエレベーターで4階まで上がり下へと降りてくる順路になっている。4階で最初に目を射たのは萬鉄五郎の「裸体美人」(重要文化財)だ。何かの画集で初めて見たときも衝撃的だったが、実物の色使いや構図には圧倒的な迫力があって「ぶるっ!」というよりは「どきっ!」とさせられる。数十メートルにも及ぶ水墨画の絵巻物である横山大観の「生々流転」(重要文化財)には、思わず「ほおっ~!」と唸らされてしまう。深山幽谷の雲の中で生じた水滴が落ちて川となり、やがて大河となって海へと注ぎ、再び空へと昇っていくさまを描いたものだ。いまの時代ならばエコロジー的な視点で眺める人も少なくないだろう。もちろん自然の「生々流転」は人の「生々流転」とも重ね合わされて描かれているにちがいない。
和田三蔵の「南風」は美術のテキストなどでもよく見かける作品である。小さな木造船に乗る4人の男。赤い腰布だけを身につけ、上半身の逞しい裸体をさらした男にまず目がいく。横にいる白いシャツの男も海の男らしい精悍な表情をしている。対照的に前にいる左右の二人の男は力なく座り込んでいる。これから先の運命を赤い腰布の男と白シャツの男に委ねているようにも見える。そして、紺青色の海と白波、船上に落ちる濃い影。絵の前に立つと、やがて画面に引き込まれ、南からの熱風が顔にあたるような気がしてくる。船乗りの仕事を「板一枚下は地獄」などというが、生死の狭間にいる海の男ならではの力強さが伝わってくる。精悍な男たちを見ていると、ささいなことは忘れて生きる勇気が湧いてくるかのようだ。思わず、初めて「ぶるっ!」とした。
藤田嗣治の「五人の裸婦」は、その美しい裸婦像に「おおっ!」と小さく叫びそうになる作品だ。白磁のような美しさだけでなく、どこか不思議な雰囲気もたたえている。五人はそれぞれ五感を表しているという解説を読むと、不思議さの一端がわかったような気がした。高村光太郎の彫刻「手」も著名な作品だが、見れば見るほど奇妙な指の配置をしている。間近に見ることで、その奇妙さにあらためて納得し、さらに不思議さも以前より倍加した。「ん!?」という感じだろうか。彫刻では新海竹太郎の「ゆあみ」(重要文化財)も興味深かった。日本人をモデルにしていながらも西洋的なプロポーションの裸婦像であり、和洋混交の先駆的な作品であるという。薄布をまとっているところも日本的であるという解説に「なっとく!」した。
3階に下りると、まず藤田嗣治の「アッツ島玉砕」と「サイパン島同胞臣節を全うす」に目を奪われた。「五人の裸婦」からは想像できない藤田嗣治の別の一面を見ることができる。とくに「アッツ島玉砕」はリアルさを超えた玉砕の描画に言葉を失ってしまう! 藤田はのちに戦争協力の批判を浴びるのだが、画家も生きるためには当時の政治情勢に逆らえなかったということなのだろう。日本画では上村松園の「母子」(重要文化財)、小倉遊亀の「浴女 その一」、福田平八郎の「雨」、東山魁夷の「秋翳」など、「日本画っていいな!」と思わせる作品が続く。
しかし、いちばん心ひかれたのは高山辰雄の「いだく」だった。高山辰雄の名前も知らず、もちろん初めて見る絵である。二人の女性が赤ん坊を抱いているだけというシンプルな構図である。背景はぼやけていて幻想的なイメージでもある。赤子を抱く二人の手はつながっており、新たな命がかけがえのないものとして守られている印象を強くする。女性の表情もやさしさに満ちている。赤ん坊から見れば、二人の女性に抱かれて、深い安らぎのなかに佇んでいるかのようだ。胎内回帰の郷愁を描いているようにも思える。だからなのか、この絵には「ほっ!」とさせられた。
2階は主に、いわゆる前衛的な作品や東京国立近代美術館が所蔵する海外の作品が並ぶ。ここまでが「第Ⅰ部 MOMAT コレクションスペシャル」であり、1階が「第Ⅱ部 実験場1950s」となっている。2階と1階はかけあしで見ただけだが、1階の土門拳と川田喜久治による原爆関連の写真は決して忘れてはならない記録である!(なお、「MOMAT」は「The National Museum of Modern Art, Tokyo」の略である)
この美術展は東京国立近代美術館開館60周年記念であり、美術にふるえるという美術鑑賞の原点を「ぶるっ!」という言葉で表している。「ぶるっ!」という言葉が適切かどうかは少し疑問に思うが、「!」をつけたくなる作品にはいくつも出会った。最後にショップで絵葉書を数枚買って帰路に着いた。(その前に、NHKも主催者の一つであり、そのアンケートに答えてきた) 入館からここまで約2時間半。4階と3階で多くの時間を費やしたが、満足のいく時間を過ごしたように思う。
藤田嗣治を持ち出すまでもなく、美術もまた時代を写し、画家もまた時代に翻弄される。再び政権交代が行われるのは確実な情勢だ。政権交代の是非はともかくとしても、政治家が安心、安定、強靭などと口にすればするほど、世の中は不安や不安定さが増し、弱者が置き去りにされていくような気がしてならない。ともあれ、少々貧しくても、ある程度の不便さはがまんしても、ゆっくりと絵が鑑賞できて、どんな本でも読めて、画家や作家が―あえて付け加えるが、科学者も―時代を鼓舞することを要請されないように、こころから願わずにはいられない。
下の写真は4階にある「眺めのよい部屋」で、皇居が眺望できる。