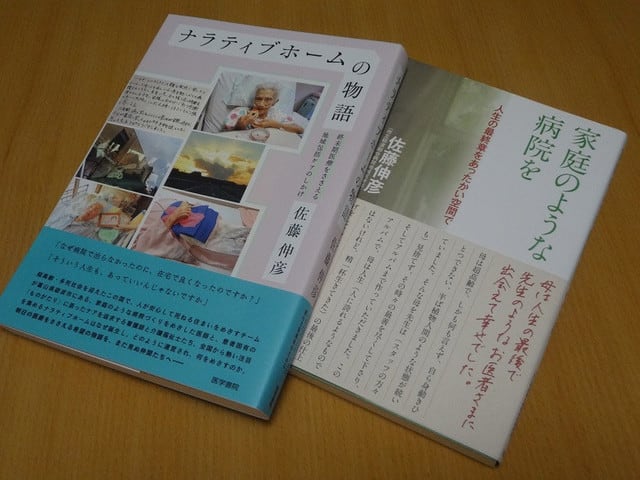
☆『家庭のような病院を』(佐藤伸彦・著、文藝春秋)、『ナラティブホームの物語』(佐藤伸彦・著、医学書院)☆
『家庭のような病院を』を知ったときのことはよく覚えている。当時ある私立大学の学生用PCルームでアルバイトをしていた。学生が不正なアクセスをしていないか監視し、ワードやエクセルなどの基本的ソフトの使い方やトラブルについての相談を受け、解決するのが主な仕事だった。学生から相談が来ない限り非常にヒマな仕事で、アルバイトとは無関係な自分の仕事をしたりネットを見て遊んでいることが多かった。そんなある日、いつも見ていた森岡正博さんのブログで『家庭のような病院を』の書評を読んだ。遠距離介護をはじめたばかりの頃で、まだまだ深刻な状況ではなかったが、この本の内容に興味をもった。
数日後、池袋のジュンク堂で本書を見つけ、著者の略歴を見て驚いた。著者の佐藤伸彦先生は、実家周辺にある最も大きな総合病院の勤務医だった。自分を含め家族の誰もが何度もお世話になったことのある地域の中核病院で、母はその数年前に大腸ガンの手術を受けていたし、父もさまざまな病気で定期的に通院していた。それからしばらくして、母のめまいの症状がよくならないため(その総合病院の耳鼻科や脳神経外科、実家近くの中規模病院の心療内科でも診てもらったが、あまり相手にされず)最後の頼みの綱のような気持で、その総合病院の神経内科へ行った。
そこの「担当医」表でまさしく「佐藤伸彦」の名前に出会った。初めてお会いしたとき、ちょっと怖そうな感じがしたが、実に丁寧にこちらの話を聴いてくださった。すぐに薬を処方するようなこともなく、「どうすればいいですかね~」と一緒になって悩んでくださったのが、とても印象に残った。あまりに長く話していたため、「次の患者さんも待っているので、あとでまたゆっくり話しましょうか」ということで一度診察室を出て、すべての患者さんの診察が終わった後、あらためて話を聴いてくださった。
結局、どこかに病変があるわけではなく、すぐに治る症状でもないだろうから、訪問看護を受けながら様子を見ることになった。たしかこのとき初めて「訪問看護指示書」を書いてもらい、すでに週何回かのサービスを受けていた在宅介護に加えて、訪問看護(看護師さんが月1回、理学療法師さんが月2回、わが家を訪問すること)がスタートした。佐藤先生が「ものがたり診療所」を開設され独立された後も、母は佐藤先生の許へ通院していた。その後、足腰が弱るなどして通院がむずかしくなったとき、看護や介護の手続きなどを実家近くの「かかりつけ医」に移してもらったが、介護と看護のスタート前後に佐藤先生と出会ったことは本当に幸運だったと、いまでも思っている。母も「(失礼ながら)怖そうな顔しといでるけど、いい先生や」といつも言っていた。父の終末期には「ナラティブホーム」への入居を考えて相談に伺ったこともあったが、そのときも時間を割いて丁寧に説明してくださったことを覚えている(こちらの事情で入居は実現しなかったが)。
佐藤先生とのきっかけを作ってくれた『家庭のような病院を』だが、当時もちろん一読したはずなのに、いまあらためて読み直してみて、あまり内容を覚えていないことに驚かされた。当時も考えさせられることが多々あったはずなのに、そのことよりも本の著者である「佐藤伸彦」先生に母が診てもらっているという、言い方は悪いが一種の“権威”のようなものに関心が傾いてしまっていたのかもしれない。
『家庭のような病院を』が2013年に絶版となったため、新たに出版されたのが『ナラティブホームの物語』である。『ナラティブホームの物語』は『家庭のような病院を』を再構成し、さらに当時はまだ構想段階だった「ものがたり診療所」を含む「ナラティブホーム」の実現へ向けての経緯や、開設後の問題点や「ナラティブホーム」で出会った方々の「ものがたり」についてもふれられており、多くのページが付け加えられている。前者が理論編ならば、後者は実践編といった趣も感じられる。
後者には前者になかった外山義氏が指摘した「五つの落差」についての記述があり、そこに「ナラティブホーム」の理念が集約されているように思われて、とても興味深く読んだ。地域で生活してきた高齢者が生活の場を施設に移したとき、「空間」・「時間」・「規則」・「言葉」・「役割」の落差が生じるという。自分の住みなれた家(「空間」)ならば、自分の好きなとき(「時間」)に好きなように(「規則」)誰からも指示されること(「言葉」)なく地域や家族の一員として(「役割」)過ごすことができるのに、施設に入ればそのすべてに落差が生まれてくる。「家庭のような病院」とは「自宅ではない在宅」を施設や病院の枠を超えて実現しようとする挑戦である。佐藤先生はそれを「ナラティブホーム」と名付けた。
「ナラティブ」は「物語」や「語り」と訳されるが、余談ながら個人的には「ものがたり」とひらがなで書いた方がしっくりとくる。最近は「心」や「命」も個人的に「こころ」や「いのち」と書くことが多いのだが、これも「心」・「命」と書くと抽象的・客観的な感じがするのに対して、「こころ」・「いのち」には暖かみが感じられ、自分を捨象しない表現に思えるからかもしれない。自分としては「こころ」・「いのち」は「心」・「命」の「ものがたり」的表現のつもりでいる、といっても良いだろう。
佐藤先生は人間の存在や医療を考えるとき、「科学性」(「科学的理解」)と「小説性」(「物語的理解」)との狭間にある灰色の部分に注目する。これは「客観性」と「主観性」の問題といっても良いだろうし、「専門性」や「当事者性」の問題と言い換えることもできるだろう。いまやわれわれの日々の生活は科学や科学技術を抜きにして語ることはできないが、その一方で科学や科学技術では決して語り得ないことがあることにも、多くの人々は気づきはじめている。「ナラティブホーム」は、現代医療における臨床の場が両者の葛藤とバランスの上に成り立っていることを理解した上で、終末期医療に関わっていこうとする試みである。
思うに自分が学問を志したのも、科学と科学では語り得ぬことの狭間を見究めようとする道程だった。生来の障害による身体の不確実性を補うかのように、確実性を標榜する科学にひかれたのは当然のなりゆきだったかもしれない。しかし、こころの奥底に生起するさまざまな葛藤に科学はこたえてくれなかった。ときあたかも公害問題が社会を席巻していた。やがて進むべき道を探しあぐね、いろいろな試みに時を費やしていった。そんなとき(三十代も半ばに達していただろうか)森岡正博さんの『生命学への招待』に出会った。科学だけでもない、哲学や倫理学だけでもない、そのスケールの大きさに圧倒され、心底こんな研究がしてみたいと思った。『生命学への招待』は自分の道標となり、バイブルのような存在となった。「生命倫理」という学問分野があることも、このころ初めて知った。その後も森岡さんの著書を読み漁り、自分自身を捨象しない研究姿勢に大きな共感を抱いた。
四十路に足を踏み入れてまもなく、当時は少々の蓄えもあったため、あらためて学問の道を志すべく社会人入試に挑んだ。志望は現役受験生時代と同じ物理だったが、今度は物理の可能性を拓くためではなく、科学の限界を知るために科学の頂点たる物理(「物理帝国主義」という言葉もあった)を学ぼうと思った。在学中は物理を専門にする気持ちも少し芽生えたが、結局ある教員(WHOから委託された高齢者のQOL研究が専門で、少しばかり研究の手伝いもさせてもらっていた)の助言で、生命倫理の専門家をめざしてある大学院の門をたたいた。
志望研究室の教員にコンタクトをとったところ、その大学の大学院志望学生のための無料勉強会をやっているので出てくださいと言われ、数ヶ月のあいだ看護学や保健学(本来の専攻は看護学や保健学であって、生命倫理の研究はその一部として存在していた)の受験勉強をした。同時に教員公認のもぐりの学生として「精神医学」と「生命倫理」の講義も聴講した。「生命倫理」の講義は参加型の授業で、もぐりなのに討論にも参加させてもらい楽しかったが、「精神医学」は病名と病態の羅列でついていくのが大変だった。
受験勉強の甲斐あって専門科目はよくできたと思ったが、残念ながら(というべきか迷うところだが)不合格の通知をもらった。教員によると、やはり専門科目よりも英語の成績が少したりなかったということだった。この結果を受けて、来年再び受験すれば合格する可能性は高いように思われたが、生命倫理に対する熱意が中折れ状態になってしまった。そもそも森岡さんの著書に導かれるかたちで生命倫理を志したが、生命倫理についての自分なりの問題意識は不明確なままだった。脳死だの、出生前診断だの、終末期医療におけるインフォームドコンセントだのといった重い問題に果たして自分が耐えられるのか、自信もなくなっていった。
思い返してみれば、生命倫理は「科学性」と「小説性」との狭間で揺れ動く、自らのこころの葛藤を回避する手段だったのかもしれない。同時に、いつもこころを癒してくれたのは自然の存在だったことに、あらためて気がついた。自然は科学的理解の興味対象だけではなく、情緒的安定の源泉でもあった。人はなぜ自然に癒されるのか、人はなぜ自然を美しいと思うのか。本書にも、最後に何を見て死にたいかという問いに「自然」という答えが圧倒的に多かったというアンケート結果が紹介されているが、それはなぜなのだろうか。科学(たとえば進化論など)もそれなりに答えを用意しているようだが、それだけで納得ができるようには思われない。自然を探求していた科学がいつのまにか自然を破壊する元凶へと変貌する不思議さも、大いに知的好奇心がそそられた。森岡さんの著書は生命倫理のすすめであると同時に環境倫理のすすめでもあったのだが、そのことにもあらためて気づかされた。こうして、生命倫理から環境倫理へと舵を切ることになった。
環境倫理(公には自分の専門を「環境倫理」としていないが、専門的には重要なことであったとしても一般的には些末なことに思われるので、ここではこのままにしておく)の分野においても、先に佐藤先生が指摘していた「科学性」と「小説性」との狭間の問題は重要なことである。いや、むしろ生命倫理と環境倫理とを別のものと捉えることに無理があるのかもしれない。われわれの「いのち」は環境によって生かされているが、同時にわれわれの「いのち」は環境をかたちづくり、あるいは改変していくものでもある。生命と環境とは地続きのものであり、やはり「ナラティブ」につながっていると見るのが自然であろう。
誤解を恐れずにいえば、「ナラティブ」や「ものがたり」は自分を棚上げにせず、自分自身も巻き込んで他者(人間であろうと自然であろうと)と共にあろうとする姿勢の表明ではないだろうか。学術論文ならば、自らを外におき客観的な記述が求められるのはやむを得ないことだろうが、それで終わりとしてはならないのではないか。機会を見つけて、その問題についての当事者性も語るべきだろう。佐藤先生の言葉を借りれば「専門性を捨てる専門性」と言い換えても良いだろう。「専門性を捨てた部分で初めて、患者さんと向かい合う関係性が出来上がってくる」ため「医療に携わるものに必須と言っても過言ではない」というが、この能力は科学者などの専門家にとっても非常に重要であろう。専門家による上から目線の難解な説明は、非専門家の自己決定権の放棄(専門家へのおまかせの姿勢)にもつながりかねない。「専門性を捨てる専門性」によって専門家と非専門家とが向き合う関係性こそが、「ナラティブ」の実態ではないだろうか。
「ナラティブ」な視点から語られる話は聞く者をわくわくさせる。佐藤先生の著書が興味深く読めるのも、森岡さんの著書に魅せられたのも、このわくわく感によるものだ。本書にカントを手がかりにして介護の義務を説いた大学教員の話がでてくるが、これなどはまったく逆のパターンである。学会などへ行けば、この手の発表ばかりで辟易とさせられることが少なくない。枝葉末節にこだわるいわゆる学会的質問によって、むしろ研究意欲がそがれ、悪しき感情や不信を助長されることもある。
「ナラティブ」は人と人との共感の輪を広げ、人と人とをつなぐ役割も果たしていく。『ナラティブホームの物語』は、ネルソン・マンデラの「成し遂げたことで私を判断するのではなく、失敗して再び立ち上がってきた回数で判断してほしい」という言葉を受けて、佐藤先生の「成し遂げたことで私を判断するのではなく、そのつどつながった仲間の広がりで判断してほしい」の言葉で終わっている。この本によって新たな関係性が築かれたし、さまざまな関係性の結節点にこの本があったことを思うと、本書は自分の人生にとって重要な一冊として存在し続けるだろう。
(文章は2016年12月末頃に執筆)

『家庭のような病院を』を知ったときのことはよく覚えている。当時ある私立大学の学生用PCルームでアルバイトをしていた。学生が不正なアクセスをしていないか監視し、ワードやエクセルなどの基本的ソフトの使い方やトラブルについての相談を受け、解決するのが主な仕事だった。学生から相談が来ない限り非常にヒマな仕事で、アルバイトとは無関係な自分の仕事をしたりネットを見て遊んでいることが多かった。そんなある日、いつも見ていた森岡正博さんのブログで『家庭のような病院を』の書評を読んだ。遠距離介護をはじめたばかりの頃で、まだまだ深刻な状況ではなかったが、この本の内容に興味をもった。
数日後、池袋のジュンク堂で本書を見つけ、著者の略歴を見て驚いた。著者の佐藤伸彦先生は、実家周辺にある最も大きな総合病院の勤務医だった。自分を含め家族の誰もが何度もお世話になったことのある地域の中核病院で、母はその数年前に大腸ガンの手術を受けていたし、父もさまざまな病気で定期的に通院していた。それからしばらくして、母のめまいの症状がよくならないため(その総合病院の耳鼻科や脳神経外科、実家近くの中規模病院の心療内科でも診てもらったが、あまり相手にされず)最後の頼みの綱のような気持で、その総合病院の神経内科へ行った。
そこの「担当医」表でまさしく「佐藤伸彦」の名前に出会った。初めてお会いしたとき、ちょっと怖そうな感じがしたが、実に丁寧にこちらの話を聴いてくださった。すぐに薬を処方するようなこともなく、「どうすればいいですかね~」と一緒になって悩んでくださったのが、とても印象に残った。あまりに長く話していたため、「次の患者さんも待っているので、あとでまたゆっくり話しましょうか」ということで一度診察室を出て、すべての患者さんの診察が終わった後、あらためて話を聴いてくださった。
結局、どこかに病変があるわけではなく、すぐに治る症状でもないだろうから、訪問看護を受けながら様子を見ることになった。たしかこのとき初めて「訪問看護指示書」を書いてもらい、すでに週何回かのサービスを受けていた在宅介護に加えて、訪問看護(看護師さんが月1回、理学療法師さんが月2回、わが家を訪問すること)がスタートした。佐藤先生が「ものがたり診療所」を開設され独立された後も、母は佐藤先生の許へ通院していた。その後、足腰が弱るなどして通院がむずかしくなったとき、看護や介護の手続きなどを実家近くの「かかりつけ医」に移してもらったが、介護と看護のスタート前後に佐藤先生と出会ったことは本当に幸運だったと、いまでも思っている。母も「(失礼ながら)怖そうな顔しといでるけど、いい先生や」といつも言っていた。父の終末期には「ナラティブホーム」への入居を考えて相談に伺ったこともあったが、そのときも時間を割いて丁寧に説明してくださったことを覚えている(こちらの事情で入居は実現しなかったが)。
佐藤先生とのきっかけを作ってくれた『家庭のような病院を』だが、当時もちろん一読したはずなのに、いまあらためて読み直してみて、あまり内容を覚えていないことに驚かされた。当時も考えさせられることが多々あったはずなのに、そのことよりも本の著者である「佐藤伸彦」先生に母が診てもらっているという、言い方は悪いが一種の“権威”のようなものに関心が傾いてしまっていたのかもしれない。
『家庭のような病院を』が2013年に絶版となったため、新たに出版されたのが『ナラティブホームの物語』である。『ナラティブホームの物語』は『家庭のような病院を』を再構成し、さらに当時はまだ構想段階だった「ものがたり診療所」を含む「ナラティブホーム」の実現へ向けての経緯や、開設後の問題点や「ナラティブホーム」で出会った方々の「ものがたり」についてもふれられており、多くのページが付け加えられている。前者が理論編ならば、後者は実践編といった趣も感じられる。
後者には前者になかった外山義氏が指摘した「五つの落差」についての記述があり、そこに「ナラティブホーム」の理念が集約されているように思われて、とても興味深く読んだ。地域で生活してきた高齢者が生活の場を施設に移したとき、「空間」・「時間」・「規則」・「言葉」・「役割」の落差が生じるという。自分の住みなれた家(「空間」)ならば、自分の好きなとき(「時間」)に好きなように(「規則」)誰からも指示されること(「言葉」)なく地域や家族の一員として(「役割」)過ごすことができるのに、施設に入ればそのすべてに落差が生まれてくる。「家庭のような病院」とは「自宅ではない在宅」を施設や病院の枠を超えて実現しようとする挑戦である。佐藤先生はそれを「ナラティブホーム」と名付けた。
「ナラティブ」は「物語」や「語り」と訳されるが、余談ながら個人的には「ものがたり」とひらがなで書いた方がしっくりとくる。最近は「心」や「命」も個人的に「こころ」や「いのち」と書くことが多いのだが、これも「心」・「命」と書くと抽象的・客観的な感じがするのに対して、「こころ」・「いのち」には暖かみが感じられ、自分を捨象しない表現に思えるからかもしれない。自分としては「こころ」・「いのち」は「心」・「命」の「ものがたり」的表現のつもりでいる、といっても良いだろう。
佐藤先生は人間の存在や医療を考えるとき、「科学性」(「科学的理解」)と「小説性」(「物語的理解」)との狭間にある灰色の部分に注目する。これは「客観性」と「主観性」の問題といっても良いだろうし、「専門性」や「当事者性」の問題と言い換えることもできるだろう。いまやわれわれの日々の生活は科学や科学技術を抜きにして語ることはできないが、その一方で科学や科学技術では決して語り得ないことがあることにも、多くの人々は気づきはじめている。「ナラティブホーム」は、現代医療における臨床の場が両者の葛藤とバランスの上に成り立っていることを理解した上で、終末期医療に関わっていこうとする試みである。
思うに自分が学問を志したのも、科学と科学では語り得ぬことの狭間を見究めようとする道程だった。生来の障害による身体の不確実性を補うかのように、確実性を標榜する科学にひかれたのは当然のなりゆきだったかもしれない。しかし、こころの奥底に生起するさまざまな葛藤に科学はこたえてくれなかった。ときあたかも公害問題が社会を席巻していた。やがて進むべき道を探しあぐね、いろいろな試みに時を費やしていった。そんなとき(三十代も半ばに達していただろうか)森岡正博さんの『生命学への招待』に出会った。科学だけでもない、哲学や倫理学だけでもない、そのスケールの大きさに圧倒され、心底こんな研究がしてみたいと思った。『生命学への招待』は自分の道標となり、バイブルのような存在となった。「生命倫理」という学問分野があることも、このころ初めて知った。その後も森岡さんの著書を読み漁り、自分自身を捨象しない研究姿勢に大きな共感を抱いた。
四十路に足を踏み入れてまもなく、当時は少々の蓄えもあったため、あらためて学問の道を志すべく社会人入試に挑んだ。志望は現役受験生時代と同じ物理だったが、今度は物理の可能性を拓くためではなく、科学の限界を知るために科学の頂点たる物理(「物理帝国主義」という言葉もあった)を学ぼうと思った。在学中は物理を専門にする気持ちも少し芽生えたが、結局ある教員(WHOから委託された高齢者のQOL研究が専門で、少しばかり研究の手伝いもさせてもらっていた)の助言で、生命倫理の専門家をめざしてある大学院の門をたたいた。
志望研究室の教員にコンタクトをとったところ、その大学の大学院志望学生のための無料勉強会をやっているので出てくださいと言われ、数ヶ月のあいだ看護学や保健学(本来の専攻は看護学や保健学であって、生命倫理の研究はその一部として存在していた)の受験勉強をした。同時に教員公認のもぐりの学生として「精神医学」と「生命倫理」の講義も聴講した。「生命倫理」の講義は参加型の授業で、もぐりなのに討論にも参加させてもらい楽しかったが、「精神医学」は病名と病態の羅列でついていくのが大変だった。
受験勉強の甲斐あって専門科目はよくできたと思ったが、残念ながら(というべきか迷うところだが)不合格の通知をもらった。教員によると、やはり専門科目よりも英語の成績が少したりなかったということだった。この結果を受けて、来年再び受験すれば合格する可能性は高いように思われたが、生命倫理に対する熱意が中折れ状態になってしまった。そもそも森岡さんの著書に導かれるかたちで生命倫理を志したが、生命倫理についての自分なりの問題意識は不明確なままだった。脳死だの、出生前診断だの、終末期医療におけるインフォームドコンセントだのといった重い問題に果たして自分が耐えられるのか、自信もなくなっていった。
思い返してみれば、生命倫理は「科学性」と「小説性」との狭間で揺れ動く、自らのこころの葛藤を回避する手段だったのかもしれない。同時に、いつもこころを癒してくれたのは自然の存在だったことに、あらためて気がついた。自然は科学的理解の興味対象だけではなく、情緒的安定の源泉でもあった。人はなぜ自然に癒されるのか、人はなぜ自然を美しいと思うのか。本書にも、最後に何を見て死にたいかという問いに「自然」という答えが圧倒的に多かったというアンケート結果が紹介されているが、それはなぜなのだろうか。科学(たとえば進化論など)もそれなりに答えを用意しているようだが、それだけで納得ができるようには思われない。自然を探求していた科学がいつのまにか自然を破壊する元凶へと変貌する不思議さも、大いに知的好奇心がそそられた。森岡さんの著書は生命倫理のすすめであると同時に環境倫理のすすめでもあったのだが、そのことにもあらためて気づかされた。こうして、生命倫理から環境倫理へと舵を切ることになった。
環境倫理(公には自分の専門を「環境倫理」としていないが、専門的には重要なことであったとしても一般的には些末なことに思われるので、ここではこのままにしておく)の分野においても、先に佐藤先生が指摘していた「科学性」と「小説性」との狭間の問題は重要なことである。いや、むしろ生命倫理と環境倫理とを別のものと捉えることに無理があるのかもしれない。われわれの「いのち」は環境によって生かされているが、同時にわれわれの「いのち」は環境をかたちづくり、あるいは改変していくものでもある。生命と環境とは地続きのものであり、やはり「ナラティブ」につながっていると見るのが自然であろう。
誤解を恐れずにいえば、「ナラティブ」や「ものがたり」は自分を棚上げにせず、自分自身も巻き込んで他者(人間であろうと自然であろうと)と共にあろうとする姿勢の表明ではないだろうか。学術論文ならば、自らを外におき客観的な記述が求められるのはやむを得ないことだろうが、それで終わりとしてはならないのではないか。機会を見つけて、その問題についての当事者性も語るべきだろう。佐藤先生の言葉を借りれば「専門性を捨てる専門性」と言い換えても良いだろう。「専門性を捨てた部分で初めて、患者さんと向かい合う関係性が出来上がってくる」ため「医療に携わるものに必須と言っても過言ではない」というが、この能力は科学者などの専門家にとっても非常に重要であろう。専門家による上から目線の難解な説明は、非専門家の自己決定権の放棄(専門家へのおまかせの姿勢)にもつながりかねない。「専門性を捨てる専門性」によって専門家と非専門家とが向き合う関係性こそが、「ナラティブ」の実態ではないだろうか。
「ナラティブ」な視点から語られる話は聞く者をわくわくさせる。佐藤先生の著書が興味深く読めるのも、森岡さんの著書に魅せられたのも、このわくわく感によるものだ。本書にカントを手がかりにして介護の義務を説いた大学教員の話がでてくるが、これなどはまったく逆のパターンである。学会などへ行けば、この手の発表ばかりで辟易とさせられることが少なくない。枝葉末節にこだわるいわゆる学会的質問によって、むしろ研究意欲がそがれ、悪しき感情や不信を助長されることもある。
「ナラティブ」は人と人との共感の輪を広げ、人と人とをつなぐ役割も果たしていく。『ナラティブホームの物語』は、ネルソン・マンデラの「成し遂げたことで私を判断するのではなく、失敗して再び立ち上がってきた回数で判断してほしい」という言葉を受けて、佐藤先生の「成し遂げたことで私を判断するのではなく、そのつどつながった仲間の広がりで判断してほしい」の言葉で終わっている。この本によって新たな関係性が築かれたし、さまざまな関係性の結節点にこの本があったことを思うと、本書は自分の人生にとって重要な一冊として存在し続けるだろう。
(文章は2016年12月末頃に執筆)

























