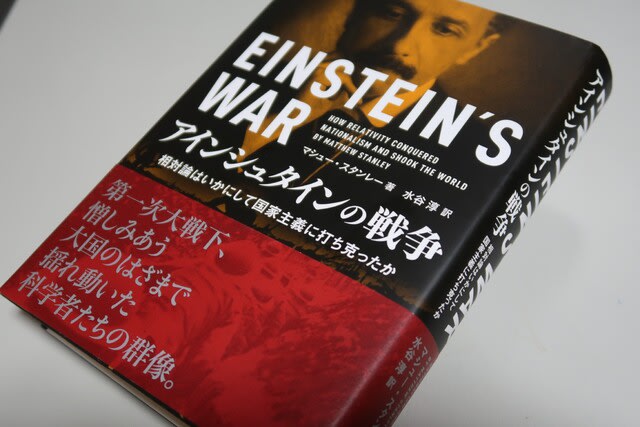
☆『アインシュタインの戦争』(マシュー・スタンレー・著、水谷淳・訳、新潮社)☆
本書に登場するアインシュタインは、われわれがよく知っている功成り名を上げたアインシュタインではなく、そこに至るまでの無名の(少なくとも世間一般に名前が知れ渡る前の)アインシュタインである。
本書は物理学の本としてよりも歴史の書として読むべきだろう。たしかに相対性理論(ここではとくに一般相対性理論のことを指すが、以後「相対性理論」としておく)成立前後の物理学について、かなり専門的な議論、いきさつも描かれている。数式は使われていないものの、正確に理解しようとすると容易ではないだろう。わたし自身、大学で物理を専攻したとはいえ、正確に理解できたとはとても言いがたい。
しかし、それを理解できなくても、いっこうに差し支えない。むしろ本書の主眼の一つは、アインシュタインが自ら発想した相対性理論をいかにして発展させ、世に問うたのか、彼の苦悩する姿を描くところにあるように思う。
時あたかも世界で初めての世界大戦、つまり第一次世界大戦前後の時代である。世界は、とくにヨーロッパは大きく揺らぎ、国と国は分断され憎しみあう。なかでも当時アインシュタインが住んでいたドイツとイギリスは海を挟んで政治的・軍事的に対峙し、お互いを非難しあっていた。
そのイギリスに住んでいたのが、本書のもう一人のキーパーソンであるエディントンである。エディントンはアインシュタインのことをほとんど知ることもなく、ある経緯から相対性理論のことを知り興味を持った。相対性理論が事実であれば革命的な科学理論である。
エディントンは相対性理論を検証すべく日食の観測を計画する。日食の時には月により太陽の光が遮断される。相対性理論は太陽の重力により太陽近傍の星の位置にズレが生じること(いわゆる重力レンズ効果)を予言していた。そのことを観測により実証しようとしたのである。
しかし、ことは容易に進まない。現在のようにインターネットが世界に張り巡らされた時代ではなく、通信もほとんど手紙に頼るしかない。しかし世界は戦争へと歩み始めていて、それさえも容易ではなくなりつつあった。
アインシュタインもエディントンも、母国は敵国どうしであったが、何よりも平和を望んでいた。しかし、二人の周囲の科学者たちの多くは愛国者としてナショナリズムに染まっていった。科学の営みは社会から距離をおいていて、「価値中立」的と考えられている。もちろん「価値中立」性自体にも多くの議論はあるのだが、ひとまずそのことはおいておく。両国の科学者たちは「価値中立」であるはずの科学を、敵国の科学というだけで誹謗中傷を繰り返していた。
しかし、アインシュタインとエディントンは冷静な判断の上に立っていた。科学の発展には平和が何よりも重要であることを、本書は読者に強く印象づける。
世界政府を構想し平和を望んでいたアインシュタインではあるが、けっして聖人君子のように道徳を金科玉条のごとく守るような人物として描かれてはいない。その私生活はほめられたようなものではないし、多くの市井の人々とそれほど変わりはない。エディントンもまた同様である。ただ、彼はクエーカー教徒だったからか、アインシュタインに比べればストイックであったように見える。
第一次世界大戦が終了した翌年1919年、イギリスからアフリカ西海岸沖のプリンシペ島と南米ブラジルのソブレルに向けて二つの観測隊が出発し日食の観測を行った。観測隊が帰国後、エディントンは撮影した写真を精査し、相対性理論は正しいとした。
しかし、この革命的な科学理論が(科学者を含めた)万人に受け入れられないことを懸念し、エディントンは発表の舞台作りにもこころを砕いた。いまわれわれは当然のように相対性理論を、ニュートン力学を超えるものとして受け入れているが、ニュートン力学はイギリス人のニュートンによって築かれたのであり、相対性理論はドイツ出身のユダヤ人科学者によって発想され、結果的にニュートン力学の権威を貶めることになり、その時期がまさに両国が敵対していた時代であったことに思いを馳せてみるべきである。
1919年11月7日付けの『ロンドンタイムズ』に「科学の革命」の見出しが躍り、ついに相対性理論は世に出たのである。本書は、その後のアインシュタインや相対性理論の経緯についても紙幅を割き、日食観測自体についての検証も忘れていない。本書の筆致は最後まで冷静であり好感が持てる。
本書で語られた事実は100年ほど前のことだが、その主題は色褪せるどころか極めて今日的である。科学者も人間である以上、感情を持ち、異なる政治的立場に立つこともある。しかしだからといって、科学は信頼の置けない代物ではないし、科学を真っ向から否定することもまちがっている。
科学は人間である科学者によってなされるが、その営みは社会と無関係ではありえない。そのことをこころに刻み、科学の営みを常に冷静に見守っていくことこそ、いまわれわれに必要なことである。
アインシュタインや相対性理論に関する本はいまでも書店に山積みされ、屋上屋を架すようにも見える。しかし、本書は明らかに一線を画し、近年希に見るアインシュタイン・相対性理論関連の良書である。
ただ一つ残念なのは、本文中の注釈がウェブ上でしか見られないことである。それも(PDFにはなっているものの)英語のままである。もっとも、本書を読むにあたってそれほど注釈の必要性は感じなかったが、注釈について知りたいと思う読者にとっては不便だろう。

本書に登場するアインシュタインは、われわれがよく知っている功成り名を上げたアインシュタインではなく、そこに至るまでの無名の(少なくとも世間一般に名前が知れ渡る前の)アインシュタインである。
本書は物理学の本としてよりも歴史の書として読むべきだろう。たしかに相対性理論(ここではとくに一般相対性理論のことを指すが、以後「相対性理論」としておく)成立前後の物理学について、かなり専門的な議論、いきさつも描かれている。数式は使われていないものの、正確に理解しようとすると容易ではないだろう。わたし自身、大学で物理を専攻したとはいえ、正確に理解できたとはとても言いがたい。
しかし、それを理解できなくても、いっこうに差し支えない。むしろ本書の主眼の一つは、アインシュタインが自ら発想した相対性理論をいかにして発展させ、世に問うたのか、彼の苦悩する姿を描くところにあるように思う。
時あたかも世界で初めての世界大戦、つまり第一次世界大戦前後の時代である。世界は、とくにヨーロッパは大きく揺らぎ、国と国は分断され憎しみあう。なかでも当時アインシュタインが住んでいたドイツとイギリスは海を挟んで政治的・軍事的に対峙し、お互いを非難しあっていた。
そのイギリスに住んでいたのが、本書のもう一人のキーパーソンであるエディントンである。エディントンはアインシュタインのことをほとんど知ることもなく、ある経緯から相対性理論のことを知り興味を持った。相対性理論が事実であれば革命的な科学理論である。
エディントンは相対性理論を検証すべく日食の観測を計画する。日食の時には月により太陽の光が遮断される。相対性理論は太陽の重力により太陽近傍の星の位置にズレが生じること(いわゆる重力レンズ効果)を予言していた。そのことを観測により実証しようとしたのである。
しかし、ことは容易に進まない。現在のようにインターネットが世界に張り巡らされた時代ではなく、通信もほとんど手紙に頼るしかない。しかし世界は戦争へと歩み始めていて、それさえも容易ではなくなりつつあった。
アインシュタインもエディントンも、母国は敵国どうしであったが、何よりも平和を望んでいた。しかし、二人の周囲の科学者たちの多くは愛国者としてナショナリズムに染まっていった。科学の営みは社会から距離をおいていて、「価値中立」的と考えられている。もちろん「価値中立」性自体にも多くの議論はあるのだが、ひとまずそのことはおいておく。両国の科学者たちは「価値中立」であるはずの科学を、敵国の科学というだけで誹謗中傷を繰り返していた。
しかし、アインシュタインとエディントンは冷静な判断の上に立っていた。科学の発展には平和が何よりも重要であることを、本書は読者に強く印象づける。
世界政府を構想し平和を望んでいたアインシュタインではあるが、けっして聖人君子のように道徳を金科玉条のごとく守るような人物として描かれてはいない。その私生活はほめられたようなものではないし、多くの市井の人々とそれほど変わりはない。エディントンもまた同様である。ただ、彼はクエーカー教徒だったからか、アインシュタインに比べればストイックであったように見える。
第一次世界大戦が終了した翌年1919年、イギリスからアフリカ西海岸沖のプリンシペ島と南米ブラジルのソブレルに向けて二つの観測隊が出発し日食の観測を行った。観測隊が帰国後、エディントンは撮影した写真を精査し、相対性理論は正しいとした。
しかし、この革命的な科学理論が(科学者を含めた)万人に受け入れられないことを懸念し、エディントンは発表の舞台作りにもこころを砕いた。いまわれわれは当然のように相対性理論を、ニュートン力学を超えるものとして受け入れているが、ニュートン力学はイギリス人のニュートンによって築かれたのであり、相対性理論はドイツ出身のユダヤ人科学者によって発想され、結果的にニュートン力学の権威を貶めることになり、その時期がまさに両国が敵対していた時代であったことに思いを馳せてみるべきである。
1919年11月7日付けの『ロンドンタイムズ』に「科学の革命」の見出しが躍り、ついに相対性理論は世に出たのである。本書は、その後のアインシュタインや相対性理論の経緯についても紙幅を割き、日食観測自体についての検証も忘れていない。本書の筆致は最後まで冷静であり好感が持てる。
本書で語られた事実は100年ほど前のことだが、その主題は色褪せるどころか極めて今日的である。科学者も人間である以上、感情を持ち、異なる政治的立場に立つこともある。しかしだからといって、科学は信頼の置けない代物ではないし、科学を真っ向から否定することもまちがっている。
科学は人間である科学者によってなされるが、その営みは社会と無関係ではありえない。そのことをこころに刻み、科学の営みを常に冷静に見守っていくことこそ、いまわれわれに必要なことである。
アインシュタインや相対性理論に関する本はいまでも書店に山積みされ、屋上屋を架すようにも見える。しかし、本書は明らかに一線を画し、近年希に見るアインシュタイン・相対性理論関連の良書である。
ただ一つ残念なのは、本文中の注釈がウェブ上でしか見られないことである。それも(PDFにはなっているものの)英語のままである。もっとも、本書を読むにあたってそれほど注釈の必要性は感じなかったが、注釈について知りたいと思う読者にとっては不便だろう。

























