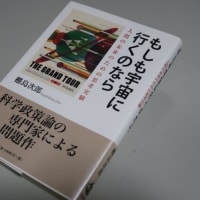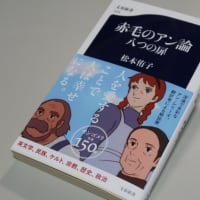『モネ 大回顧展』(国立新美術館)
国立新美術館へは初めて行った。六本木ヒルズや東京ミッドタウンとならんで、最近の六本木を代表する建築物の一つである。地下鉄千代田線乃木坂駅からは専用通路を通って、雨天でも傘のお世話になることなく館内へ入ることができる。建築デザインを批評する能力はないが、巨大な吹き抜けのロビーは、お台場にある日本科学未来館のロビーとどこか似た感じがした。設計はあの黒川紀章さん。黒川さんの最近の本気なのか遊び心なのかわからないパフォーマンスを見ていると、彼が世界的な建築家であることを忘れてしまうが、この巨大な建築物を見ると―そのデザインの評価はともあれ―黒川さん本来の才能にあらためて気づかされる。
目的は国立新美術館の見学ではなく『モネ 大回顧展』の鑑賞である。モネは以前から鑑賞してみたいと思っていた画家の一人だったので、この機会を逃すことはできなかった。何といってもモネの作品を一挙に100点ちかくも見られるのである。自分の予定や込み具合も算段して平日である木曜日の夕方に行ったのだが、会場は相当な人出だった。明らかに男性よりも女性のほうが多かったが、老若は問わずという感じだった。もちろん全員がモネのファンというわけではないだろうが、日本人にとってモネがよく知られた画家であることが、来場者の数からわかるような気がした。
一般的に日本人にとっては睡蓮を描いた作品がよく知られているように思う。しかし、自分としては『迷宮美術館』(NHK総合テレビ)で取り上げていた『かささぎ』をまず見たかった。降り積もった雪景色のなかに一羽のかささぎが小さく描かれている作品である。モネといえば色鮮やかな風景画を描いたという印象が強いのかもしれないが、むしろ光と影が織りなす風景を表現しようとしていたというべきだろう。『アトリエから戸外へ 印象派の時代』によれば、モネは光の効果を表現するために、同じ題材を扱う連作を描いたのだという。有名な『積みわら』も1891年には同時に15点が展覧会でならべられたという。今回も4点の『積みわら』が展示されていた。たとえば「夏の終わりの朝」の積みわらと「雪の朝」の積みわらとが、まさしく印象的に描き分けられている。
この『かささぎ』もまた、透明な大気につつまれた雪の降り積もった日の風景を印象的に描いている。感触まで伝わってくるような雪面や、そこに落ちる影を見ていると、雪がたんなる白で、そして影がたんなる黒で表されるものではないことがよくわかる。われわれが住んでいる世界や見ている風景は、たんに色彩の足し算や引き算で構成されているのではなく、光と影の作用によって色彩が活性化されたり、微妙な色彩を生み出すことで作られているように思われる。『かささぎ』をはじめ『テムズ川のチャリング・クロス橋』や『シヴェルニーのセーヌ川支流』など、とくに印象に残った作品にはそのような効果が強く表れているように思う。自分が写真を撮るときも、光の効果や光と影のコントラストを気にすることがよくある。モネの作品と比較の対象にはもちろんならないが、知らず知らずのうちにモネの絵画を見ることで受けた印象を自分の内に取り込んで、そのフレームワークで撮ろうとしているのかもしれない。
やや忙しい日程をぬって足を運んだ「モネ」展だったが、それだけの価値は十分にあった。芸術にふれるというよりは、自分の好きなものを見られるのはやはり幸せなことである。芸術の価値などと小難しいことをいわなくても、自分の好きなものを見たり聴いたりして幸せになることこそが最高の「芸術の価値」だと思う。
国立新美術館へは初めて行った。六本木ヒルズや東京ミッドタウンとならんで、最近の六本木を代表する建築物の一つである。地下鉄千代田線乃木坂駅からは専用通路を通って、雨天でも傘のお世話になることなく館内へ入ることができる。建築デザインを批評する能力はないが、巨大な吹き抜けのロビーは、お台場にある日本科学未来館のロビーとどこか似た感じがした。設計はあの黒川紀章さん。黒川さんの最近の本気なのか遊び心なのかわからないパフォーマンスを見ていると、彼が世界的な建築家であることを忘れてしまうが、この巨大な建築物を見ると―そのデザインの評価はともあれ―黒川さん本来の才能にあらためて気づかされる。
目的は国立新美術館の見学ではなく『モネ 大回顧展』の鑑賞である。モネは以前から鑑賞してみたいと思っていた画家の一人だったので、この機会を逃すことはできなかった。何といってもモネの作品を一挙に100点ちかくも見られるのである。自分の予定や込み具合も算段して平日である木曜日の夕方に行ったのだが、会場は相当な人出だった。明らかに男性よりも女性のほうが多かったが、老若は問わずという感じだった。もちろん全員がモネのファンというわけではないだろうが、日本人にとってモネがよく知られた画家であることが、来場者の数からわかるような気がした。
一般的に日本人にとっては睡蓮を描いた作品がよく知られているように思う。しかし、自分としては『迷宮美術館』(NHK総合テレビ)で取り上げていた『かささぎ』をまず見たかった。降り積もった雪景色のなかに一羽のかささぎが小さく描かれている作品である。モネといえば色鮮やかな風景画を描いたという印象が強いのかもしれないが、むしろ光と影が織りなす風景を表現しようとしていたというべきだろう。『アトリエから戸外へ 印象派の時代』によれば、モネは光の効果を表現するために、同じ題材を扱う連作を描いたのだという。有名な『積みわら』も1891年には同時に15点が展覧会でならべられたという。今回も4点の『積みわら』が展示されていた。たとえば「夏の終わりの朝」の積みわらと「雪の朝」の積みわらとが、まさしく印象的に描き分けられている。
この『かささぎ』もまた、透明な大気につつまれた雪の降り積もった日の風景を印象的に描いている。感触まで伝わってくるような雪面や、そこに落ちる影を見ていると、雪がたんなる白で、そして影がたんなる黒で表されるものではないことがよくわかる。われわれが住んでいる世界や見ている風景は、たんに色彩の足し算や引き算で構成されているのではなく、光と影の作用によって色彩が活性化されたり、微妙な色彩を生み出すことで作られているように思われる。『かささぎ』をはじめ『テムズ川のチャリング・クロス橋』や『シヴェルニーのセーヌ川支流』など、とくに印象に残った作品にはそのような効果が強く表れているように思う。自分が写真を撮るときも、光の効果や光と影のコントラストを気にすることがよくある。モネの作品と比較の対象にはもちろんならないが、知らず知らずのうちにモネの絵画を見ることで受けた印象を自分の内に取り込んで、そのフレームワークで撮ろうとしているのかもしれない。
やや忙しい日程をぬって足を運んだ「モネ」展だったが、それだけの価値は十分にあった。芸術にふれるというよりは、自分の好きなものを見られるのはやはり幸せなことである。芸術の価値などと小難しいことをいわなくても、自分の好きなものを見たり聴いたりして幸せになることこそが最高の「芸術の価値」だと思う。