ついでに観劇記録。
まず、アメリカものは人種や宗教やセクシュアリティにかかわる話が多い中、
ご当地歴史子ども物?ということで、NEWSIESにトライ。
1899年NYの新聞配達少年newsiesのストライキを題材とした話で、
孤児や家計補助としての児童労働と搾取、感化院の問題等にも触れ、
最後は少年たちが自分たちで印刷機をのっとって
新聞を出してストに勝利するという話。
92年に、時のディズニーミュージカルアニメを手掛けた
アラン・メンケン作曲で映画化したら大こけした作品が、
2012年にミュージカルにしたら大ヒットしたというものらしいです。
振り付けがショーアップされていて話題を呼びやすいのに加えて、
さすがアラン・メンケンというか、曲が耳に残る残る。
92年はミュージカル映画というジャンルが微妙だった時代なのと、
動画で見る限りオールドファッションなつくりだったのでこけたけれども、
今回の舞台の振付は、21世紀対応舞台ミュージカルとしての勘所は
きちんと押さえているという感じです。
女性が数名しか出てこない、「かわいい」男の子の元気あふれるステージ
という需要がアメリカにあったことが驚きだったのと、
子どもの力を児童労働という文脈で話題にするのは、
イギリス児童文学系とはちょっと違う流れだなあ
というまとまらない感想をもったのでした。
http://www.newsiesthemusical.com/
もう1つ、サウスパークのクリエーターがお送りする「問題作」としてヒット中の
The Book of Mormon(2011年トニー賞受賞策)へ。
モルモン教(「異端」とされてきたアメリカ発のキリスト教の流派)の布教に
ウガンダに飛ばされた若い宣教師が、現実におののき、適当な布教をし、
教会に怒られるが、それでハッピーならいいじゃんと新しい宗教ができた、
みたいな、とことんバカバカしい話。
どこかで聞いたことがあるような音楽を引用しまくりながら、
名曲に載せて、ゲイレズビアン、宗教、アメリカ、ヒトラー、人種…と
タブーというタブーをあえて侵しまくるきわどいストーリーライン…。
キャストの層の厚さを感じさせる、すばらしいショーでした。
すばらしいショーだったのですが…。
同じ系統でもAvenue Qは、きれいごとどおりにいかない大人の人生を
パペットを使って反省するというところに留まっていたので、
すごく好きだったのですが、これはあきらかに一線超えていて、
露骨すぎて途中で周りのように笑えなくなりました。
(私の英語力とキリスト教の知識が微妙なため、
単純に話についていけなかったところもありましたが。)
10年くらい前に話題になった「プロデューサーズ」もナチスだしてきたり
際どかったけど、アメリカって、際どい一線を越えて笑わせないと、
自己反省できないのでしょうか??
考えてみれば、2000年代に入ってからのトニー賞の傾向をみるに、
ブロードウェーは、人種や性、セクシュアリティ、宗教などの
タブーに挑んだ「問題作」がもてはやされる傾向にあるようです。
そういう方向に再帰性を昂進させたショーしか流行らないのだとしたら、
それもちょっとむなしい気もします。
ウェストエンドのほうが、Singin' in the RainとかTop Hatとか、
ハリウッドの往年のミュージカル映画の舞台化に挑んでいるのが不思議です。
(児童文学は、英国の推しコンテンツなので、
ミュージカル化の動きがでるのはわからなくないですが。)
http://www.bookofmormonbroadway.com/


まず、アメリカものは人種や宗教やセクシュアリティにかかわる話が多い中、
ご当地歴史子ども物?ということで、NEWSIESにトライ。
1899年NYの新聞配達少年newsiesのストライキを題材とした話で、
孤児や家計補助としての児童労働と搾取、感化院の問題等にも触れ、
最後は少年たちが自分たちで印刷機をのっとって
新聞を出してストに勝利するという話。
92年に、時のディズニーミュージカルアニメを手掛けた
アラン・メンケン作曲で映画化したら大こけした作品が、
2012年にミュージカルにしたら大ヒットしたというものらしいです。
振り付けがショーアップされていて話題を呼びやすいのに加えて、
さすがアラン・メンケンというか、曲が耳に残る残る。
92年はミュージカル映画というジャンルが微妙だった時代なのと、
動画で見る限りオールドファッションなつくりだったのでこけたけれども、
今回の舞台の振付は、21世紀対応舞台ミュージカルとしての勘所は
きちんと押さえているという感じです。
女性が数名しか出てこない、「かわいい」男の子の元気あふれるステージ
という需要がアメリカにあったことが驚きだったのと、
子どもの力を児童労働という文脈で話題にするのは、
イギリス児童文学系とはちょっと違う流れだなあ
というまとまらない感想をもったのでした。
http://www.newsiesthemusical.com/
もう1つ、サウスパークのクリエーターがお送りする「問題作」としてヒット中の
The Book of Mormon(2011年トニー賞受賞策)へ。
モルモン教(「異端」とされてきたアメリカ発のキリスト教の流派)の布教に
ウガンダに飛ばされた若い宣教師が、現実におののき、適当な布教をし、
教会に怒られるが、それでハッピーならいいじゃんと新しい宗教ができた、
みたいな、とことんバカバカしい話。
どこかで聞いたことがあるような音楽を引用しまくりながら、
名曲に載せて、ゲイレズビアン、宗教、アメリカ、ヒトラー、人種…と
タブーというタブーをあえて侵しまくるきわどいストーリーライン…。
キャストの層の厚さを感じさせる、すばらしいショーでした。
すばらしいショーだったのですが…。
同じ系統でもAvenue Qは、きれいごとどおりにいかない大人の人生を
パペットを使って反省するというところに留まっていたので、
すごく好きだったのですが、これはあきらかに一線超えていて、
露骨すぎて途中で周りのように笑えなくなりました。
(私の英語力とキリスト教の知識が微妙なため、
単純に話についていけなかったところもありましたが。)
10年くらい前に話題になった「プロデューサーズ」もナチスだしてきたり
際どかったけど、アメリカって、際どい一線を越えて笑わせないと、
自己反省できないのでしょうか??
考えてみれば、2000年代に入ってからのトニー賞の傾向をみるに、
ブロードウェーは、人種や性、セクシュアリティ、宗教などの
タブーに挑んだ「問題作」がもてはやされる傾向にあるようです。
そういう方向に再帰性を昂進させたショーしか流行らないのだとしたら、
それもちょっとむなしい気もします。
ウェストエンドのほうが、Singin' in the RainとかTop Hatとか、
ハリウッドの往年のミュージカル映画の舞台化に挑んでいるのが不思議です。
(児童文学は、英国の推しコンテンツなので、
ミュージカル化の動きがでるのはわからなくないですが。)
http://www.bookofmormonbroadway.com/














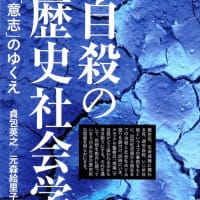






※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます