完全に当初目的も執筆熱意も失っているブログでありましたが、教育とは学校とは何かをしゃべりながら、新しいオンライン授業で自分と学生の皆さんに何が起きるかを考えるという不思議な体験が始まり2か月経過するなかで、気になっていることをまとめました。
課題=チェックされる、成績に関わると思い込む学生
オンライン講義が始まって2か月。多くの大学が、「学生の通信環境その他に配慮して、オンデマンド講義で課題を回収する形を基本にお願いしたい」(大意)となった結果、学生・教師双方が膨大な課業管理地獄になるディストピアが出現している。
教員側の窓から見てまず目立つのは、あきらかに教員側が期待している以上に、課題に必死に取り組む学生の姿だ。出したか出さないか、取り組んだか取り組まないかのみチェックするなどとしている授業でも、何百字もやたら書き込んだコメントが返ってくる。さらに、ちょっとの誤字で自動採点で×がついた学生が、どうにかにならないでしょうかと問い合わせてくる。(どうにかも何も・・・。)
みんな、先生への提出物は細かくチェックされて採点されているという思い込みを内面化しすぎているのだろうか。そうだとしたら、どれだけ学校化されているのか。高校までの学びの態度が抜けないという意味では「生徒化」と呼ぼうか。(しかも「生きる力」云々以降のがんばっている感を見せる必要のある学校の。)社会学では過剰に社会化されたことを、「過剰社会化」と言ったりする人もいる。ちなみに、「過剰社会化」は行き過ぎという点でどちらかというとよろしくないニュアンスで使われる。
オンライン講義はどこまで学校的なのか
学校外の通信教育では、かなりの数の脱落者がいるはずだと思う。(ちなみに私は高校時代、Z会に1-2回しか返送しないでお金をドブに捨てた。)だから、この過剰な頑張り、過剰に学校化・生徒化された振る舞いは、オンライン講義という形が必然的にもたらすものではないと思う。これまでの学校経験が、学校で提出物を課されたら先生に見られているに違いない、成績に、卒業に関わるものだ、という態度に結びついている気がする。(『学校って何だろう』の苅谷先生のいじわるな「実験」を思い出す。)
一方、オンラインでの受講では、他の学生の雰囲気が見えない。ほかにどんな人たちがどんな態度で座っているのか、どの程度の手抜きでやっているのか、そもそも教室に現れてすらいないのかの空気感がわからないのがいけないのかもしれない。
私たちが巻き込まれたオンライン講義とは何なのか。大学の学びを変えるのか。大学教員関係のSNSでは、そんな言葉が2か月前から飛び交っていた。(私は「苦肉の策なんだから、そんなに今から息巻かないでも…」というタイプであったが。)
ところが、すでにとても学校化した身体の人たちが、対面の学校のインフォーマルなガス抜き機能を欠落させた場で、どこまで看守に見られていると思ってふるまっていいのか決めかねて自らハードルを上げているというのが、今の私から(中央棟の看守室から)見える景色の1つなのだ。(もう一方で、いつもより脱落していく人も多く二極化しているという話はまた今度。)












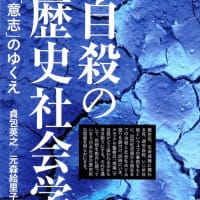






※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます