※ドネーションシップわかちあい、会員ページの日記より転載します
◆「外国人の貧困問題について」の学習会
先日、大阪・釜ヶ崎にある「ふるさとの家」で開かれた
「外国人の貧困問題について」の学習会に行ってきました。
在特会が外国人排除の活動を展開し、橋下知事が朝鮮学校の授業料無償化を否定するなど、
在日外国人への排外主義が露わになる中、
外国人のおかれている貧困の問題を学んでいこうという趣旨です。
講師は金光敏さん (コリアNGOセンター事務局長)
学習会での金光敏さんのお話の要旨を以下に簡単にまとめてみました。
*******************
■OECD加盟国(主に先進国)の中でも、
日本は少子高齢化が特に進んでいる(65歳以上が人口の22%)。
40年後には人口の2000万人が減ることになる。
そのことから、移民の受け入れが議論されている。
2007年に経団連が打ち出した案では、
高度人材確保のために1000万人の移民の受け入れを掲げている。
移民国家への転換が必要な時代を迎えている。
■日本の出生率は1.28であり、韓国(南朝鮮)は1.2以下。
日本・韓国・中国ともに、移民の受け入れを検討している。
その国にとって「国益」となる人材(高度人材)の移民を受け入れることになると、
入国管理が一層厳しくなるという問題が指摘されている。
加えて、移民を受け入れる前に、移民の生活の安定を保証する制度の確立が求められている。
今までの日本の施策を見ると、一旦受け入れるとその後はほったらかしで、
生活の安定・福祉・教育といった面での制度の不備から、不幸な状況が生み出され続けている。
「日本は単一民族国家である」という意識が強いことから、マイノリティー差別がまかり通っている。
一方、韓国では移民に対して、法の下の平等を適用している。
韓国では来年から、二重国籍を認める方針を打ち出している。
(日本では、二重国籍は認められず、22歳になると、どちらの国籍にするかを迫られる)
韓国は人口の分母を増やして、有能な人材を受け入れるために、
移民を支援する制度が整備されつつある。
そのために、国によって「多文化家族支援センター」が各地に整備され、
言語・就労・心理カウンセリングなどの公的支援を一括して行う体制を整えている。
日本では、例えば名古屋や大阪豊中などにある
「国際交流協会」などが一部そうした役割を担っているが、
いずれも地方自治体の持ち出し状態で、国家としての施策には至っていない。
日本はかつて、ブラジルなどへ移民を排出する国だったが、
今や移民の受け入れ国となりつつある。
「移民が行き先の国を選ぶ方向」へと向かっているなかで、
移民を公的に支援する仕組みがほとんど無い日本は、
移民受け入れ各国の中では不利な状況を自ら作り出している。
■2007年から、日本在住のブラジル人と関わっているが、
彼らの生活や子どもの教育がおかれている状況は、大変厳しくなってきている。
日本は1990年頃(バブル期)に労働力不足から、
ブラジル日系人3世までに定住資格を与えるようになった。
それを受けて32万人がブラジルから日本に来たが、その8割強が派遣労働に就いた。
ブローカーがブラジルで日系人を集めて、日本の派遣会社へ斡旋したからだった。
そして1997年頃から、日本各地で「ブラジル学校」ができはじめた。
それは社内の託児所や保育所が始まりだった。
日本語ができない →孤立 →イジメ →不登校 →
ブラジル人託児施設が必要になる――という構図。
日本では、外国人は「義務教育」の対象外であり、
日本の学校では彼らの受け入れ態勢が全くなかったためだ。
ブラジルからの移民は、
日本にとっては「労働力ロボットが来た」という感覚だったからだろう。
こうしてブラジル人だけでなく、フィリピン人やペルー人などの移民もふくめて、
不安定就労と不登校の吹きだまりとなった。
リーマンショック以降、彼らのほとんどが真っ先に解雇され、失業した。
浜松の駅前の公園には、ホームレス状態のブラジル人がたくさん現れた。
日本人でも派遣切りでホームレスになる人がいる中、
日本語のできないブラジル人がホームレスになると、再就職などできない。
ブラジル人学校へ通う子どもたちは、親の失業で授業料が払えなくなって不就学になり、
またブラジルへ帰る家族もいて、ブラジル人学校の多くが運営できなくなってしまった。
(13~14歳の中学生がダンボール工場で低賃金の児童労働させられる―そんな例も珍しくない)
■こうした日本における「外国人の貧困問題」の出発点は、
在日朝鮮韓国人の歩まされてきた歴史にある。
「ダンボール工場で低賃金の児童労働」は
40~50年前の在日の子どもたちの姿とそのまま重なる。
私の親たちの世代は、
最低賃金以下で寝る間を惜しんで長時間働いても日当が¥2000程度だった。
高度経済成長のなかでも、ダンピングにあい最底辺にいたのだ。
今日本では「ワーキングプア」「格差社会」などと言われるが、
在日の人たちは今までほとんどそうだった。
日本在住のブラジル人・ペルー人・フィリピン人も、
そして日本の庶民さえも、在日朝鮮韓国人化している――とも言える。
日本在住の外国人がどうしてこんなに生きにくいのか?
その原因の一つに、制度の不備、つまりセーフティーネットの脆弱さが指摘されている。
日本では、外国人が失業すると即、「生活保護」しかないのだ。
それまでにあるはずの「失業補償」をはじめとする
様々なセーフティーネットが無いか、あるいは機能していない。
ブラジル人がハローワークに行ってもポルトガル語では対応してもらえないし、行く気にもならない。
役所へ行くこと自体に、大きなハードルが存在する。
国が家賃の補助をする制度もない。
(公営住宅の応募は9倍なのに対して、民間の賃貸物件は20%が空家なのに、、、)
最後の頼みの「生活保護」ですら、
それを申請するのに(言語の問題などで)第三者の手助けが必要になる。
「生活保護の切り下げ反対」も必要だが、
それ以上に日本在住の外国人も視野に入れた、新しい社会保障制度のボトムアップが求められる。
*******************
このあと質疑応答の時間ももたれました。
私は今まで講演会などの「質疑応答」で手を挙げたことはなかったのですが、
今回はちょっと質問させていただきました。(緊張ぎみ)
「日本在住の外国人も視野に入れた、
新しい社会保障制度のボトムアップが求められる」というお話を聞いて、
私はベーシックインカムを思ったので、そのことを聞いてみたくなったのでした。
金光敏さんは、どちらかというとベーシックインカムよりも、
北欧型の社会保障制度を思い描いておられるようでした。
金光敏さんの講演会を聞いて考えさせられました。
今は庶民のほとんどが中流かそれ以下の暮らしに追いやられて、
自分の暮らしを維持するのにいっぱいで、もっと立場の弱い人たちのことを思う余裕すらない、
そうした想像力すら奪われているんじゃないのかなぁと。
自分がしんどいときに、それらを受け入れながらも、そこで踏ん張って、
自分と同じかそれ以上に大変な思いをしている人たちのことを思う―――
自分自身がそんなふうにはしてこれなかったし、今もどうなのかあやしいばかりです。
「困ったときは、お互いさま」 「困ったときこそ、お互いさま」
そんなドネーションシップの思いって、シンプルでありながら実はすごく深い!と。
自分もそこに沿っていきたいし、そんな世の中になったら、今回の学習会のようなことも必要なくなる。
自分にできることは小さいけれど、足元から一歩踏み出したいなぁ。
◆「外国人の貧困問題について」の学習会
先日、大阪・釜ヶ崎にある「ふるさとの家」で開かれた
「外国人の貧困問題について」の学習会に行ってきました。
在特会が外国人排除の活動を展開し、橋下知事が朝鮮学校の授業料無償化を否定するなど、
在日外国人への排外主義が露わになる中、
外国人のおかれている貧困の問題を学んでいこうという趣旨です。
講師は金光敏さん (コリアNGOセンター事務局長)
学習会での金光敏さんのお話の要旨を以下に簡単にまとめてみました。
*******************
■OECD加盟国(主に先進国)の中でも、
日本は少子高齢化が特に進んでいる(65歳以上が人口の22%)。
40年後には人口の2000万人が減ることになる。
そのことから、移民の受け入れが議論されている。
2007年に経団連が打ち出した案では、
高度人材確保のために1000万人の移民の受け入れを掲げている。
移民国家への転換が必要な時代を迎えている。
■日本の出生率は1.28であり、韓国(南朝鮮)は1.2以下。
日本・韓国・中国ともに、移民の受け入れを検討している。
その国にとって「国益」となる人材(高度人材)の移民を受け入れることになると、
入国管理が一層厳しくなるという問題が指摘されている。
加えて、移民を受け入れる前に、移民の生活の安定を保証する制度の確立が求められている。
今までの日本の施策を見ると、一旦受け入れるとその後はほったらかしで、
生活の安定・福祉・教育といった面での制度の不備から、不幸な状況が生み出され続けている。
「日本は単一民族国家である」という意識が強いことから、マイノリティー差別がまかり通っている。
一方、韓国では移民に対して、法の下の平等を適用している。
韓国では来年から、二重国籍を認める方針を打ち出している。
(日本では、二重国籍は認められず、22歳になると、どちらの国籍にするかを迫られる)
韓国は人口の分母を増やして、有能な人材を受け入れるために、
移民を支援する制度が整備されつつある。
そのために、国によって「多文化家族支援センター」が各地に整備され、
言語・就労・心理カウンセリングなどの公的支援を一括して行う体制を整えている。
日本では、例えば名古屋や大阪豊中などにある
「国際交流協会」などが一部そうした役割を担っているが、
いずれも地方自治体の持ち出し状態で、国家としての施策には至っていない。
日本はかつて、ブラジルなどへ移民を排出する国だったが、
今や移民の受け入れ国となりつつある。
「移民が行き先の国を選ぶ方向」へと向かっているなかで、
移民を公的に支援する仕組みがほとんど無い日本は、
移民受け入れ各国の中では不利な状況を自ら作り出している。
■2007年から、日本在住のブラジル人と関わっているが、
彼らの生活や子どもの教育がおかれている状況は、大変厳しくなってきている。
日本は1990年頃(バブル期)に労働力不足から、
ブラジル日系人3世までに定住資格を与えるようになった。
それを受けて32万人がブラジルから日本に来たが、その8割強が派遣労働に就いた。
ブローカーがブラジルで日系人を集めて、日本の派遣会社へ斡旋したからだった。
そして1997年頃から、日本各地で「ブラジル学校」ができはじめた。
それは社内の託児所や保育所が始まりだった。
日本語ができない →孤立 →イジメ →不登校 →
ブラジル人託児施設が必要になる――という構図。
日本では、外国人は「義務教育」の対象外であり、
日本の学校では彼らの受け入れ態勢が全くなかったためだ。
ブラジルからの移民は、
日本にとっては「労働力ロボットが来た」という感覚だったからだろう。
こうしてブラジル人だけでなく、フィリピン人やペルー人などの移民もふくめて、
不安定就労と不登校の吹きだまりとなった。
リーマンショック以降、彼らのほとんどが真っ先に解雇され、失業した。
浜松の駅前の公園には、ホームレス状態のブラジル人がたくさん現れた。
日本人でも派遣切りでホームレスになる人がいる中、
日本語のできないブラジル人がホームレスになると、再就職などできない。
ブラジル人学校へ通う子どもたちは、親の失業で授業料が払えなくなって不就学になり、
またブラジルへ帰る家族もいて、ブラジル人学校の多くが運営できなくなってしまった。
(13~14歳の中学生がダンボール工場で低賃金の児童労働させられる―そんな例も珍しくない)
■こうした日本における「外国人の貧困問題」の出発点は、
在日朝鮮韓国人の歩まされてきた歴史にある。
「ダンボール工場で低賃金の児童労働」は
40~50年前の在日の子どもたちの姿とそのまま重なる。
私の親たちの世代は、
最低賃金以下で寝る間を惜しんで長時間働いても日当が¥2000程度だった。
高度経済成長のなかでも、ダンピングにあい最底辺にいたのだ。
今日本では「ワーキングプア」「格差社会」などと言われるが、
在日の人たちは今までほとんどそうだった。
日本在住のブラジル人・ペルー人・フィリピン人も、
そして日本の庶民さえも、在日朝鮮韓国人化している――とも言える。
日本在住の外国人がどうしてこんなに生きにくいのか?
その原因の一つに、制度の不備、つまりセーフティーネットの脆弱さが指摘されている。
日本では、外国人が失業すると即、「生活保護」しかないのだ。
それまでにあるはずの「失業補償」をはじめとする
様々なセーフティーネットが無いか、あるいは機能していない。
ブラジル人がハローワークに行ってもポルトガル語では対応してもらえないし、行く気にもならない。
役所へ行くこと自体に、大きなハードルが存在する。
国が家賃の補助をする制度もない。
(公営住宅の応募は9倍なのに対して、民間の賃貸物件は20%が空家なのに、、、)
最後の頼みの「生活保護」ですら、
それを申請するのに(言語の問題などで)第三者の手助けが必要になる。
「生活保護の切り下げ反対」も必要だが、
それ以上に日本在住の外国人も視野に入れた、新しい社会保障制度のボトムアップが求められる。
*******************
このあと質疑応答の時間ももたれました。
私は今まで講演会などの「質疑応答」で手を挙げたことはなかったのですが、
今回はちょっと質問させていただきました。(緊張ぎみ)
「日本在住の外国人も視野に入れた、
新しい社会保障制度のボトムアップが求められる」というお話を聞いて、
私はベーシックインカムを思ったので、そのことを聞いてみたくなったのでした。
金光敏さんは、どちらかというとベーシックインカムよりも、
北欧型の社会保障制度を思い描いておられるようでした。
金光敏さんの講演会を聞いて考えさせられました。
今は庶民のほとんどが中流かそれ以下の暮らしに追いやられて、
自分の暮らしを維持するのにいっぱいで、もっと立場の弱い人たちのことを思う余裕すらない、
そうした想像力すら奪われているんじゃないのかなぁと。
自分がしんどいときに、それらを受け入れながらも、そこで踏ん張って、
自分と同じかそれ以上に大変な思いをしている人たちのことを思う―――
自分自身がそんなふうにはしてこれなかったし、今もどうなのかあやしいばかりです。
「困ったときは、お互いさま」 「困ったときこそ、お互いさま」
そんなドネーションシップの思いって、シンプルでありながら実はすごく深い!と。
自分もそこに沿っていきたいし、そんな世の中になったら、今回の学習会のようなことも必要なくなる。
自分にできることは小さいけれど、足元から一歩踏み出したいなぁ。



















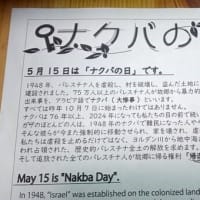







※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます