※ドネ会員ページに紹介してもらった情報から
2014年3月20日、梅田野宿者襲撃殺人事件の判決がありました。
以下、生田さんのブログよりご紹介します。
◆◆◆ 梅田野宿者襲撃殺人事件の判決、そして襲撃の詳細について ◆◆◆(2014.3.20)
(30日書き足し・書き換え)
2012年10月に大阪駅で起こった野宿襲撃事件の判決が今日、20日に下りた。
この事件を報道で知り、直後に現場で被害者、目撃者から聞き取りを行なった。
そして、襲撃事件を考える実行委員会を作り、事件を考えるシンポジウムを2回行ない、大阪府教育委員会、市教委と意見交換を行なうなどの活動を続けてきた(現在も活動中)。
事件後1年以上たち、2014年2月から裁判員裁判として公判が始まった。
この裁判のしばらく前、少年たちの弁護団から、襲撃する少年たちの問題や襲撃の社会的背景について話をしてほしいと言われ、野宿者襲撃の実態、襲撃する少年たちの背景(いじめや自傷行為との関連)、学校での授業の意義などについて話した。
また、少年たちにぼくの書いた『おっちゃん、なんで外で寝なあかんの?―こども夜回りと「ホームレス」の人たち』が差し入れられ、彼らがそれを読んだということも聞いた。
その後、弁護側から裁判での出廷を求められた。
弁護団に話したような、野宿者襲撃事件の背景について証言してほしい、という内容だ。
野宿者支援をしている立場なので、加害者の弁護側の証人として出廷・証言することはどうなんだろうと考えた。
そんなことをしたら、「加害者の立場に立って応援するのか」という批判もされそうだ。
しかし、「襲撃を止めるためには襲撃のメカニズムを理解しなければならない、戦争を止めるためには戦争が起こるメカニズムを理解しなければならないように。
そして、『理解』することは『共感』することではない。」「加害者を擁護するのではなく、野宿者襲撃を社会が止めるための理解に寄与するためなら意味がある」と判断して承諾した。
だが、ぼくの証人申請は裁判長から却下になったため、裁判への出廷はなくなった。
しかし、裁判が終わった今から振り返って、裁判官のこの判断は誤りだったと思う。(なお、この裁判の裁判長は、大阪地検特捜部の捜査資料改ざん・隠蔽事件やペルー人男性の7才の少女への殺人・強制わいせつ致死事件などを担当している)。
また、何人かの母親は、弁護人とぼくを通して「こども夜まわり」に参加したいと申し入れ、山王こどもセンターの夜回りに参加してこどもたちと夜まわりをした。
その経験を、1人の母親は鑑別所の少年に伝えたという。
裁判が始まると、可能な限り傍聴を続けてきた。
裁判は4人の少年を同時に扱うために長時間になり、日によっては朝10時から夕方6時前までということもあった。
あとで触れるように、内容が非常に重く深刻なため、連日出ていた裁判員の負担は大変なものだっただろう。
傍聴しているぼくたちも内容の深刻さにショックを受け、疲労困憊させられた。
裁判の内容は、「家族、本人などによる少年たちの生育歴」「検察による事件の詳細」「冨松さんを解剖した医師の証言」「本人、家族と面会した鑑定人の証言」が主なものだ。
公判で検察は全員に求刑・懲役5年以上10年以下を求め、4人は暴行の事実を認めたが、「殺すつもりはなかった」と殺意を否認し、弁護側も「保護処分が相当」と主張した。
今日の判決は、傷害致死罪を適用し、2人に懲役5年以上8年以下、1人に懲役5年以上7年以下、残りの1人に懲役3年6月以上5年以下の不定期刑となった。
公判終了後、MBSテレビ『VOICE』のインタビューを受け、裁判の問題点いくつかについて話した(その番組は見てない)。あらためて、ここで裁判の問題についていくつか触れる。
★ この裁判の意義
まず、野宿者襲撃について、これほど多くの情報が裁判で明らかにされたのは非常に珍しい。
野宿者襲撃の多くは10代の少年グループによって起こされるが、従来の少年法では、こうした事件が傍聴人のいる法廷で裁かれることは、ほとんどありえなかった。
だが、少年法改正によって、14才、15才でも家庭裁判所が刑事裁判にまわすことが可能になり、16才以上では重大事件をおこした場合、刑事裁判にまわすのが原則になった。
この結果、襲撃事件当時全員16才だった少年たちが裁判員裁判で裁かれるという結果になった。ぼくは少年法「改正」に反対だが、襲撃の詳細や少年たちの情報を知り得たこと自体は有益だ(ありがたい)と感じている。
今までは、深刻な襲撃事件が起こっても、ホントに「何もわからない」ままだったからだ。
なお、事件の詳細でわかるように、この裁判の4人の少年は野宿者襲撃について当初必ずしも積極的なメンバーではなかった。
もともと12人のグループがいて、一部の少年たちが野宿者襲撃を主導していた。
それがしだいに過激化し、最終的に14日に冨松さん殺害に至ったが、たまたま14日にいたのがこの4人だったということだ。
その意味で、事件の全貌はまだまだ明らかになっていない。
なお、この裁判はマスコミによってほとんど報道されなかった。
裁判初日と判決日にある程度の記者が来た程度で、ほとんどの日程については記者による傍聴がなかった。
事件内容を報道する気が最初からない、という印象だ。
事件の深刻さと、後で触れる社会的に解決すべき差別事件としての意味を考えると、このメディアの無関心は異様ではないかと思う。
★ 襲撃はなぜ起こったのか―「仲間と一緒にいたかった」から?
裁判によって最も明らかにして欲しいのは、「なぜこのような残虐な連続襲撃が16才の少年たちによって野宿者に対して行なわれたのか」「このような事件を繰り返さないために何が必要なのか」ということだ。
この裁判では、それについて、検察・弁護人・裁判官の誰からもほとんど解答が示されなかった。
たとえば、判決では「仲間と遊びたい」「面白半分」に襲撃したとしたが、これはほとんど何も言っていない。
「仲間と遊びたい」と「面白半分」にふざけあったりゲームをしたりする少年は大勢いるだろう。
だが、それがなぜ野宿者への襲撃につながるのか、まったく理解できないからだ。
裁判のかなりの時間は、少年本人、家族への証人尋問によって少年たちの生育歴の詳細を明らかにすることに使われた。
これを詳しく書くと、小さい本一冊くらいになってしまうし、そもそも、あまりに個人的な内容なので、ここでは触れない(府教委との意見交換や集会の報告などではある程度話しているが)。
4人の環境はそれぞれ違うが、多くは虐待、いじめ、貧困、育児放棄など、非常に深刻なものだった。
弁護人や鑑定人が強調したように、こうした生育歴が少年たちに深い傷を残し、人との関係で常に不安や不信を持ち、信頼感を持って本音を話し合う人間関係を持つことができなくなったということは疑えないと思う。
少年たちは4人とも公立高校を退学し、2人は仕事をしていない状態だった。
グループはもともと同じ中学だった12人ほどがいたが、その多くが「仕事がなく、学校に行っていない」状態だった。
グループは、彼らが言っていたように「本音では話せない、表面的なつきあい」「仲間の顔色や空気を読みすぎていた」状態だった。
家にも学校にも職場にも居場所がなかった少年たちが集まり唯一の居場所を作ったが、それも「仮の居場所」でしかなかったのだ。
鑑定人は4人の少年や両親と面接し、少年たちの生育歴や心理的な問題について詳しく述べた。これについては、直接少年たちと面談した結果のものとして非常に参考になったが、襲撃の要因について、鑑定人は「仲間と一緒にいたかった」という要因を繰り返した他、「普通ではない強い刺激を必要とした」という点を一回だけ述べていた。
確かに、この少年たちに限らず、野宿者襲撃を行なった少年たちには、自分の存在に自信がなく不安なまま、過度に仲間に同調し、絶対に仲間はずれにされないよう衝突しないように友だちの顔色をうかがい続けていることが多い。
誰からも相手にされず、世の中全体から孤立してしまうことは、彼らには絶対に避けたいことだからだ。
普通の友だち関係なら、悪いこと、したくないことをみんながしそうになったら、「そんなこと止めよう」と言うだろう。
しかし、裁判で少年の一人が言っていたように、「『ノリ悪い』と言われるのはムチャいやだった。顔が腫れるぐらいの暴力なら、ノリ悪いと言われるぐらいなら、行ったほうがいいと思った」。彼らにとって、「仲間はずれ」はどれほど恐ろしいかということを、この発言はよく示している。
その意味で、鑑定人が「仲間と一緒にいたかった」ことを挙げるのは妥当だろう。
しかし、裁判でも質問があったように、「仲間と一緒にいたかった」のなら、カラオケに行ったりサッカーをしたりすればよかったのではないかという疑問は当然出る。
ぼくの「野宿問題の授業」での感想文で、私は野宿者を襲ったりしないけどそうする人の気持ちはわかる、私もその子たちと同じで「人を傷つけなければ、自分の生き場所がない」からだ、と書いた中学2年生がいた。
おそらく、野宿者襲撃の要因には、何らかの暴力によってしか解消できないと本人に思わせるような「息苦しさ」「生き場所のなさ」がある。
そうした状態にいる場合、こどもたちは常識では考えられない他傷や自傷の暴力を行なうことがある。
例えば、自傷行為を繰り返す人は、「心の傷みを体の傷みに置き換えることで少しだけホッとする」「自分につけた傷によってはじめて自分の存在を実感できる」と言うことがある。
それと同じように、野宿者を襲撃する少年たちは、集団による血を見るような暴力、「人間を襲撃する」という常識では考えられない行為によって自分の存在を肯定し実感しようとしているのかもしれない。
自傷する人に対して「自分を傷つけてはいけない」といくら言っても意味があまりない。
それと同じように、襲撃する少年たちに「人を傷つけてはいけない」といくら説教しても、それだけではあまり意味はない。
自傷、他傷をせざるをえないと本人が感じるような切迫した「生き苦しさ」=「息苦しさ」を解決する必要があるからだ。
しかし、「生き苦しさ」を持つ人が多い中、そうした人がみんな野宿者を襲撃するはずはない。当然、そこには別の要因がある。
★ 野宿者襲撃は差別襲撃だが、裁判はその問題を回避した
裁判で、少年の一人が弁護人から「事件当時、路上生活者についてどう思ってた?」と聞かれ、「公園など、人の遊ぶ所に寝ていて、邪魔な人と思ってた。見下していた」「ホームレスはきたない。殴っていいと思った」と答えている。
「ジャマというのは聞いたことある?」と聞かれ、「聞いたこともあるし、汚いものを見る態度が大人にもあった。母に『仕事をしなかったらあんな人になるんやで』と言われた」と言っている。
そう言った母も、その親からそう言われていたという。
つまり、長年にわたる野宿者への差別・偏見が社会にあったということだ。
明らかに、こうした野宿者への差別意識が少年たちの襲撃の背景にあった。
また、「路上生活者に対してなぜタマゴを投げた?」と聞かれ、彼らは「警察に言われないと思って」「中学生のとき、石を投げたけど、問題にならなかったので」と答えている。
彼らが中学生のときに行なった野宿者襲撃を社会が問題にできなかったことが、襲撃のエスカレートを招いたことも明らかだ。
この野宿者襲撃事件は、言うまでもないが野宿者に対する差別襲撃・ヘイトクライムだった(ヘイトクライム(Hate crime)とは、人種、民族、宗教、性的指向などに係る特定の属性を有する個人や集団に対する偏見や憎悪が元で引き起こされる犯罪行為を指す。ウィキペディア)。
例えば、在日朝鮮・韓国人に対する襲撃や、障害者や女性に対する襲撃暴行があった場合、事件そのものが差別であり、事件の背景にある差別を究明しなければならないことは明白だろう。
たとえば、京都朝鮮第一初級学校に対する在特会の街宣活動に関する裁判で、京都地裁は「在特会の街宣は人種差別に当たる」として禁止や賠償の司法判断をした。
だが、野宿者襲撃に関するこの裁判は、一貫して「差別」にほとんど言及しなかった。
最初に言ったように、判決は「仲間と遊びたい」「面白半分」に襲撃したとした。
また、検察は「日ごろの欲求不満を解消するため」「ストレス解消のため」とした。
これは、事件の内容を考えると非常に奇妙なことだった。
一方、弁護人は少年に対し「本(野宿者についての本)を読んだよね、被害者の調書を聞きましたよね? 今はどう思う?」と聞き、「自分と一緒で家族もいて仕事もしていたんだとわかりました」「当時は?」「わかりませんでした」というやりとりをしている。
つまり、弁護人たちは少年たちに対する尋問で、野宿者に対する偏見について当時の彼らの考え方を聞き、それがどのように変わったかを明らかにした。
彼らが「反省している」ことを示すためにも、それは必要だったろう。
ただ、弁護人も、野宿者への差別を特に事件の焦点として問題にすることは控え続けたと思われる。
そこには、「野宿者への差別があるのなら、殺意もあったのではないか」と追究されることを懸念した、という面があったかもしれない。
「殺意」の有無が、「殺人」か「傷害致傷」を決める上で決定的なポイントになるからだ。
また、少年たちの証言を聞いていると、1人1人で考え方や深まり方はちがうが、反省は多くの場合は表面的で、自分の身をもって考えることはできていないようだった。
それは、少年の1人が「路上生活者には関心がない」「見下していなかった」と言っていたことからも感じられた(「襲撃する対象」としてしか考えない相手を「見下していない」などありえない)。
弁護人の基本的な方針は、少年たちが、たとえば虐待の影響などから精神的に未熟であり、今後の成長に更生を期待すべきだ、というものだったと思う。
少年犯罪である限り、それは一面では正しいのだろう。
だが、「野宿者への差別は、われわれも含め社会全体として解決しなければならない問題としてある。
野宿者へのバッシングや排除などの差別は、主に「成熟」しているはずの大人が意図的に行なっているからだ。
人種差別や女性差別と同様、襲撃は社会全体で行なわれている差別の突出した一部としてある。
差別を解消するためには、何が必要だったのだろうか。
たとえば、学校などで「野宿問題の授業」が取り組まれたり、本を読む機会があったり、彼らの野宿者に対する偏見を変える機会があれば、こうした事件は起こらなかったかもしれない。
神奈川県川崎市で「野宿問題の授業」が全公立校で行なわれた結果、それまで多発していた野宿者襲撃が3分の1程度まで激減したという例はそれを証明している。
しかし、大阪ではそうした機会を作ることはできなかった。
ぼくたちは繰り返し大阪市、大阪負教育委員会に「年に一度は野宿問題の授業をしてください」と訴えているが、それは依然として実現していない。
その意味で、われわれの社会は野宿者差別や襲撃を解決しようとせず放置し続けている。
「未熟」な少年たちを断罪すればそれでおしまい、という話ではないのだ。
検察、弁護人の法廷でのエネルギーのかなりは「殺意の有無」の検証に使われた。
これによって「傷害致死」か「殺人」かが問われるのだから、そこに焦点が行くのは無理はないかもしれない。
だが、「殺意」の定義をめぐり、われわれから見てあまり意味のない神学的論争が行なわれたという気がする。
問題は、なぜ特に野宿者についてあれほど暴力がエスカレートし、常識的に見れば「死ぬに決まってるだろ」としか思えない激しく執拗な暴力を行なったのか、ということにある。
それに較べて、「殺意」の定義の問題はほとんど意味のないものだった。
これが判決の無内容につながっている。
この裁判は、少年たちの生育歴と襲撃の詳細、特に後で引用するように、被害者の証言など、多くの情報を与えてくれたが、「なぜこのような残虐な連続襲撃が16才の少年たちによって野宿者に対して行なわれたのか」「このような事件を繰り返さないために何が必要なのか」については何も示さなかった。
これは、裁判が事件を通して社会に事件の問題と解決の方向を示すという社会的役割を果たせなかったということだ。
裁判ができないなら、それはわれわれ自身が行なわなければならないだろう。
(現在、この事件と裁判の問題を問う集会を実行委として企画している)。
(後略)
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞
★全文はこちら (生田さんのサイト)
→ http://www1.odn.ne.jp/~cex38710/thesedays20.htm
★ブログランキングに参加しています★
クリックいただけると嬉しいです♪(右上のバナー)
2014年3月20日、梅田野宿者襲撃殺人事件の判決がありました。
以下、生田さんのブログよりご紹介します。
◆◆◆ 梅田野宿者襲撃殺人事件の判決、そして襲撃の詳細について ◆◆◆(2014.3.20)
(30日書き足し・書き換え)
2012年10月に大阪駅で起こった野宿襲撃事件の判決が今日、20日に下りた。
この事件を報道で知り、直後に現場で被害者、目撃者から聞き取りを行なった。
そして、襲撃事件を考える実行委員会を作り、事件を考えるシンポジウムを2回行ない、大阪府教育委員会、市教委と意見交換を行なうなどの活動を続けてきた(現在も活動中)。
事件後1年以上たち、2014年2月から裁判員裁判として公判が始まった。
この裁判のしばらく前、少年たちの弁護団から、襲撃する少年たちの問題や襲撃の社会的背景について話をしてほしいと言われ、野宿者襲撃の実態、襲撃する少年たちの背景(いじめや自傷行為との関連)、学校での授業の意義などについて話した。
また、少年たちにぼくの書いた『おっちゃん、なんで外で寝なあかんの?―こども夜回りと「ホームレス」の人たち』が差し入れられ、彼らがそれを読んだということも聞いた。
その後、弁護側から裁判での出廷を求められた。
弁護団に話したような、野宿者襲撃事件の背景について証言してほしい、という内容だ。
野宿者支援をしている立場なので、加害者の弁護側の証人として出廷・証言することはどうなんだろうと考えた。
そんなことをしたら、「加害者の立場に立って応援するのか」という批判もされそうだ。
しかし、「襲撃を止めるためには襲撃のメカニズムを理解しなければならない、戦争を止めるためには戦争が起こるメカニズムを理解しなければならないように。
そして、『理解』することは『共感』することではない。」「加害者を擁護するのではなく、野宿者襲撃を社会が止めるための理解に寄与するためなら意味がある」と判断して承諾した。
だが、ぼくの証人申請は裁判長から却下になったため、裁判への出廷はなくなった。
しかし、裁判が終わった今から振り返って、裁判官のこの判断は誤りだったと思う。(なお、この裁判の裁判長は、大阪地検特捜部の捜査資料改ざん・隠蔽事件やペルー人男性の7才の少女への殺人・強制わいせつ致死事件などを担当している)。
また、何人かの母親は、弁護人とぼくを通して「こども夜まわり」に参加したいと申し入れ、山王こどもセンターの夜回りに参加してこどもたちと夜まわりをした。
その経験を、1人の母親は鑑別所の少年に伝えたという。
裁判が始まると、可能な限り傍聴を続けてきた。
裁判は4人の少年を同時に扱うために長時間になり、日によっては朝10時から夕方6時前までということもあった。
あとで触れるように、内容が非常に重く深刻なため、連日出ていた裁判員の負担は大変なものだっただろう。
傍聴しているぼくたちも内容の深刻さにショックを受け、疲労困憊させられた。
裁判の内容は、「家族、本人などによる少年たちの生育歴」「検察による事件の詳細」「冨松さんを解剖した医師の証言」「本人、家族と面会した鑑定人の証言」が主なものだ。
公判で検察は全員に求刑・懲役5年以上10年以下を求め、4人は暴行の事実を認めたが、「殺すつもりはなかった」と殺意を否認し、弁護側も「保護処分が相当」と主張した。
今日の判決は、傷害致死罪を適用し、2人に懲役5年以上8年以下、1人に懲役5年以上7年以下、残りの1人に懲役3年6月以上5年以下の不定期刑となった。
公判終了後、MBSテレビ『VOICE』のインタビューを受け、裁判の問題点いくつかについて話した(その番組は見てない)。あらためて、ここで裁判の問題についていくつか触れる。
★ この裁判の意義
まず、野宿者襲撃について、これほど多くの情報が裁判で明らかにされたのは非常に珍しい。
野宿者襲撃の多くは10代の少年グループによって起こされるが、従来の少年法では、こうした事件が傍聴人のいる法廷で裁かれることは、ほとんどありえなかった。
だが、少年法改正によって、14才、15才でも家庭裁判所が刑事裁判にまわすことが可能になり、16才以上では重大事件をおこした場合、刑事裁判にまわすのが原則になった。
この結果、襲撃事件当時全員16才だった少年たちが裁判員裁判で裁かれるという結果になった。ぼくは少年法「改正」に反対だが、襲撃の詳細や少年たちの情報を知り得たこと自体は有益だ(ありがたい)と感じている。
今までは、深刻な襲撃事件が起こっても、ホントに「何もわからない」ままだったからだ。
なお、事件の詳細でわかるように、この裁判の4人の少年は野宿者襲撃について当初必ずしも積極的なメンバーではなかった。
もともと12人のグループがいて、一部の少年たちが野宿者襲撃を主導していた。
それがしだいに過激化し、最終的に14日に冨松さん殺害に至ったが、たまたま14日にいたのがこの4人だったということだ。
その意味で、事件の全貌はまだまだ明らかになっていない。
なお、この裁判はマスコミによってほとんど報道されなかった。
裁判初日と判決日にある程度の記者が来た程度で、ほとんどの日程については記者による傍聴がなかった。
事件内容を報道する気が最初からない、という印象だ。
事件の深刻さと、後で触れる社会的に解決すべき差別事件としての意味を考えると、このメディアの無関心は異様ではないかと思う。
★ 襲撃はなぜ起こったのか―「仲間と一緒にいたかった」から?
裁判によって最も明らかにして欲しいのは、「なぜこのような残虐な連続襲撃が16才の少年たちによって野宿者に対して行なわれたのか」「このような事件を繰り返さないために何が必要なのか」ということだ。
この裁判では、それについて、検察・弁護人・裁判官の誰からもほとんど解答が示されなかった。
たとえば、判決では「仲間と遊びたい」「面白半分」に襲撃したとしたが、これはほとんど何も言っていない。
「仲間と遊びたい」と「面白半分」にふざけあったりゲームをしたりする少年は大勢いるだろう。
だが、それがなぜ野宿者への襲撃につながるのか、まったく理解できないからだ。
裁判のかなりの時間は、少年本人、家族への証人尋問によって少年たちの生育歴の詳細を明らかにすることに使われた。
これを詳しく書くと、小さい本一冊くらいになってしまうし、そもそも、あまりに個人的な内容なので、ここでは触れない(府教委との意見交換や集会の報告などではある程度話しているが)。
4人の環境はそれぞれ違うが、多くは虐待、いじめ、貧困、育児放棄など、非常に深刻なものだった。
弁護人や鑑定人が強調したように、こうした生育歴が少年たちに深い傷を残し、人との関係で常に不安や不信を持ち、信頼感を持って本音を話し合う人間関係を持つことができなくなったということは疑えないと思う。
少年たちは4人とも公立高校を退学し、2人は仕事をしていない状態だった。
グループはもともと同じ中学だった12人ほどがいたが、その多くが「仕事がなく、学校に行っていない」状態だった。
グループは、彼らが言っていたように「本音では話せない、表面的なつきあい」「仲間の顔色や空気を読みすぎていた」状態だった。
家にも学校にも職場にも居場所がなかった少年たちが集まり唯一の居場所を作ったが、それも「仮の居場所」でしかなかったのだ。
鑑定人は4人の少年や両親と面接し、少年たちの生育歴や心理的な問題について詳しく述べた。これについては、直接少年たちと面談した結果のものとして非常に参考になったが、襲撃の要因について、鑑定人は「仲間と一緒にいたかった」という要因を繰り返した他、「普通ではない強い刺激を必要とした」という点を一回だけ述べていた。
確かに、この少年たちに限らず、野宿者襲撃を行なった少年たちには、自分の存在に自信がなく不安なまま、過度に仲間に同調し、絶対に仲間はずれにされないよう衝突しないように友だちの顔色をうかがい続けていることが多い。
誰からも相手にされず、世の中全体から孤立してしまうことは、彼らには絶対に避けたいことだからだ。
普通の友だち関係なら、悪いこと、したくないことをみんながしそうになったら、「そんなこと止めよう」と言うだろう。
しかし、裁判で少年の一人が言っていたように、「『ノリ悪い』と言われるのはムチャいやだった。顔が腫れるぐらいの暴力なら、ノリ悪いと言われるぐらいなら、行ったほうがいいと思った」。彼らにとって、「仲間はずれ」はどれほど恐ろしいかということを、この発言はよく示している。
その意味で、鑑定人が「仲間と一緒にいたかった」ことを挙げるのは妥当だろう。
しかし、裁判でも質問があったように、「仲間と一緒にいたかった」のなら、カラオケに行ったりサッカーをしたりすればよかったのではないかという疑問は当然出る。
ぼくの「野宿問題の授業」での感想文で、私は野宿者を襲ったりしないけどそうする人の気持ちはわかる、私もその子たちと同じで「人を傷つけなければ、自分の生き場所がない」からだ、と書いた中学2年生がいた。
おそらく、野宿者襲撃の要因には、何らかの暴力によってしか解消できないと本人に思わせるような「息苦しさ」「生き場所のなさ」がある。
そうした状態にいる場合、こどもたちは常識では考えられない他傷や自傷の暴力を行なうことがある。
例えば、自傷行為を繰り返す人は、「心の傷みを体の傷みに置き換えることで少しだけホッとする」「自分につけた傷によってはじめて自分の存在を実感できる」と言うことがある。
それと同じように、野宿者を襲撃する少年たちは、集団による血を見るような暴力、「人間を襲撃する」という常識では考えられない行為によって自分の存在を肯定し実感しようとしているのかもしれない。
自傷する人に対して「自分を傷つけてはいけない」といくら言っても意味があまりない。
それと同じように、襲撃する少年たちに「人を傷つけてはいけない」といくら説教しても、それだけではあまり意味はない。
自傷、他傷をせざるをえないと本人が感じるような切迫した「生き苦しさ」=「息苦しさ」を解決する必要があるからだ。
しかし、「生き苦しさ」を持つ人が多い中、そうした人がみんな野宿者を襲撃するはずはない。当然、そこには別の要因がある。
★ 野宿者襲撃は差別襲撃だが、裁判はその問題を回避した
裁判で、少年の一人が弁護人から「事件当時、路上生活者についてどう思ってた?」と聞かれ、「公園など、人の遊ぶ所に寝ていて、邪魔な人と思ってた。見下していた」「ホームレスはきたない。殴っていいと思った」と答えている。
「ジャマというのは聞いたことある?」と聞かれ、「聞いたこともあるし、汚いものを見る態度が大人にもあった。母に『仕事をしなかったらあんな人になるんやで』と言われた」と言っている。
そう言った母も、その親からそう言われていたという。
つまり、長年にわたる野宿者への差別・偏見が社会にあったということだ。
明らかに、こうした野宿者への差別意識が少年たちの襲撃の背景にあった。
また、「路上生活者に対してなぜタマゴを投げた?」と聞かれ、彼らは「警察に言われないと思って」「中学生のとき、石を投げたけど、問題にならなかったので」と答えている。
彼らが中学生のときに行なった野宿者襲撃を社会が問題にできなかったことが、襲撃のエスカレートを招いたことも明らかだ。
この野宿者襲撃事件は、言うまでもないが野宿者に対する差別襲撃・ヘイトクライムだった(ヘイトクライム(Hate crime)とは、人種、民族、宗教、性的指向などに係る特定の属性を有する個人や集団に対する偏見や憎悪が元で引き起こされる犯罪行為を指す。ウィキペディア)。
例えば、在日朝鮮・韓国人に対する襲撃や、障害者や女性に対する襲撃暴行があった場合、事件そのものが差別であり、事件の背景にある差別を究明しなければならないことは明白だろう。
たとえば、京都朝鮮第一初級学校に対する在特会の街宣活動に関する裁判で、京都地裁は「在特会の街宣は人種差別に当たる」として禁止や賠償の司法判断をした。
だが、野宿者襲撃に関するこの裁判は、一貫して「差別」にほとんど言及しなかった。
最初に言ったように、判決は「仲間と遊びたい」「面白半分」に襲撃したとした。
また、検察は「日ごろの欲求不満を解消するため」「ストレス解消のため」とした。
これは、事件の内容を考えると非常に奇妙なことだった。
一方、弁護人は少年に対し「本(野宿者についての本)を読んだよね、被害者の調書を聞きましたよね? 今はどう思う?」と聞き、「自分と一緒で家族もいて仕事もしていたんだとわかりました」「当時は?」「わかりませんでした」というやりとりをしている。
つまり、弁護人たちは少年たちに対する尋問で、野宿者に対する偏見について当時の彼らの考え方を聞き、それがどのように変わったかを明らかにした。
彼らが「反省している」ことを示すためにも、それは必要だったろう。
ただ、弁護人も、野宿者への差別を特に事件の焦点として問題にすることは控え続けたと思われる。
そこには、「野宿者への差別があるのなら、殺意もあったのではないか」と追究されることを懸念した、という面があったかもしれない。
「殺意」の有無が、「殺人」か「傷害致傷」を決める上で決定的なポイントになるからだ。
また、少年たちの証言を聞いていると、1人1人で考え方や深まり方はちがうが、反省は多くの場合は表面的で、自分の身をもって考えることはできていないようだった。
それは、少年の1人が「路上生活者には関心がない」「見下していなかった」と言っていたことからも感じられた(「襲撃する対象」としてしか考えない相手を「見下していない」などありえない)。
弁護人の基本的な方針は、少年たちが、たとえば虐待の影響などから精神的に未熟であり、今後の成長に更生を期待すべきだ、というものだったと思う。
少年犯罪である限り、それは一面では正しいのだろう。
だが、「野宿者への差別は、われわれも含め社会全体として解決しなければならない問題としてある。
野宿者へのバッシングや排除などの差別は、主に「成熟」しているはずの大人が意図的に行なっているからだ。
人種差別や女性差別と同様、襲撃は社会全体で行なわれている差別の突出した一部としてある。
差別を解消するためには、何が必要だったのだろうか。
たとえば、学校などで「野宿問題の授業」が取り組まれたり、本を読む機会があったり、彼らの野宿者に対する偏見を変える機会があれば、こうした事件は起こらなかったかもしれない。
神奈川県川崎市で「野宿問題の授業」が全公立校で行なわれた結果、それまで多発していた野宿者襲撃が3分の1程度まで激減したという例はそれを証明している。
しかし、大阪ではそうした機会を作ることはできなかった。
ぼくたちは繰り返し大阪市、大阪負教育委員会に「年に一度は野宿問題の授業をしてください」と訴えているが、それは依然として実現していない。
その意味で、われわれの社会は野宿者差別や襲撃を解決しようとせず放置し続けている。
「未熟」な少年たちを断罪すればそれでおしまい、という話ではないのだ。
検察、弁護人の法廷でのエネルギーのかなりは「殺意の有無」の検証に使われた。
これによって「傷害致死」か「殺人」かが問われるのだから、そこに焦点が行くのは無理はないかもしれない。
だが、「殺意」の定義をめぐり、われわれから見てあまり意味のない神学的論争が行なわれたという気がする。
問題は、なぜ特に野宿者についてあれほど暴力がエスカレートし、常識的に見れば「死ぬに決まってるだろ」としか思えない激しく執拗な暴力を行なったのか、ということにある。
それに較べて、「殺意」の定義の問題はほとんど意味のないものだった。
これが判決の無内容につながっている。
この裁判は、少年たちの生育歴と襲撃の詳細、特に後で引用するように、被害者の証言など、多くの情報を与えてくれたが、「なぜこのような残虐な連続襲撃が16才の少年たちによって野宿者に対して行なわれたのか」「このような事件を繰り返さないために何が必要なのか」については何も示さなかった。
これは、裁判が事件を通して社会に事件の問題と解決の方向を示すという社会的役割を果たせなかったということだ。
裁判ができないなら、それはわれわれ自身が行なわなければならないだろう。
(現在、この事件と裁判の問題を問う集会を実行委として企画している)。
(後略)
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞
★全文はこちら (生田さんのサイト)
→ http://www1.odn.ne.jp/~cex38710/thesedays20.htm
★ブログランキングに参加しています★
クリックいただけると嬉しいです♪(右上のバナー)














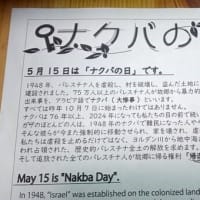

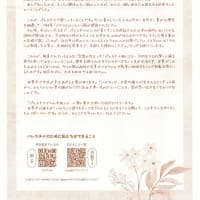
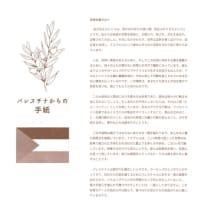









※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます