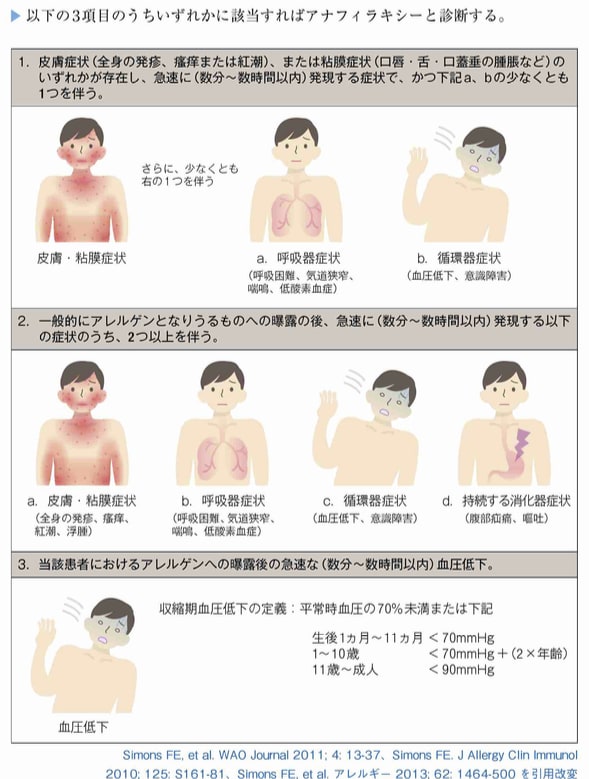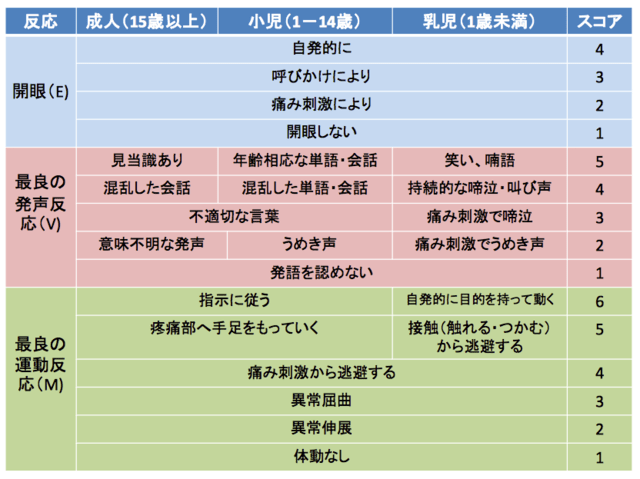「小児科は儲からない」で有名です。
知り合いのお子さんが医学部を卒業して小児科医になりました。
その親は「形成外科のような儲かる科を勧めたのに、よりによって小児科を選ぶなんて・・・」と小児科医の私を前にして宣う・・・。
小児科は子どもの風邪診療が中心で、検査もあまり必要なく、さらに近年の少子化がそれに拍車をかけて収入が減り続けているのは事実。
おそらく今後は小児科単科の開業は難しくなるのではないか、と懸念する声さえあります。
さて、2018年春に行われる診療報酬改定の概要が見えてきました。
小児科に縁があるのは「小児抗菌薬適正使用加算」くらいでしょうか。
■ シリーズ◎2018診療・介護報酬同時改定【感染症】抗菌薬の適正使用への取り組みを新たに評価
「小児抗菌薬適正使用支援加算」80点が新設
(2018/2/9 :日経メディカル)
う〜ん、この記事を読んでも、当院で算定できるのかどうか、よくわかりません。
私はもう20年も前から、
「風邪の9割はウイルス感染症だから抗生物質は効かない、だから処方しません」
「風邪症状の患者さんに抗生物質が必要な場合は溶連菌感染症と中耳炎くらい」
と説明してきました。
だから、かかりつけ患者さんにたまに抗生物質を処方すると、
「先生、抗生物質がホントに必要なんでしょうか?」
なんて逆に聞かれたりします。
もう一つ、この件を扱った記事を見つけました。
■ 「小児抗菌薬適正使用支援加算」、80点の高評価 〜「抗微生物薬適正使用の手引き」に則した治療が原則
(2018年2月7日:m3.com)
「感染症の研修会等に定期的に参加していること」ってアバウトな基準ですねえ。
この時代、ネット配信の「e-ラーニング」で研修するシステムを作って欲しいものです。
歳を取って持病を抱えると、なかなか遠くの研究会・研修会に参加できなくなりますので。
知り合いのお子さんが医学部を卒業して小児科医になりました。
その親は「形成外科のような儲かる科を勧めたのに、よりによって小児科を選ぶなんて・・・」と小児科医の私を前にして宣う・・・。
小児科は子どもの風邪診療が中心で、検査もあまり必要なく、さらに近年の少子化がそれに拍車をかけて収入が減り続けているのは事実。
おそらく今後は小児科単科の開業は難しくなるのではないか、と懸念する声さえあります。
さて、2018年春に行われる診療報酬改定の概要が見えてきました。
小児科に縁があるのは「小児抗菌薬適正使用加算」くらいでしょうか。
■ シリーズ◎2018診療・介護報酬同時改定【感染症】抗菌薬の適正使用への取り組みを新たに評価
「小児抗菌薬適正使用支援加算」80点が新設
(2018/2/9 :日経メディカル)
う〜ん、この記事を読んでも、当院で算定できるのかどうか、よくわかりません。
私はもう20年も前から、
「風邪の9割はウイルス感染症だから抗生物質は効かない、だから処方しません」
「風邪症状の患者さんに抗生物質が必要な場合は溶連菌感染症と中耳炎くらい」
と説明してきました。
だから、かかりつけ患者さんにたまに抗生物質を処方すると、
「先生、抗生物質がホントに必要なんでしょうか?」
なんて逆に聞かれたりします。
もう一つ、この件を扱った記事を見つけました。
■ 「小児抗菌薬適正使用支援加算」、80点の高評価 〜「抗微生物薬適正使用の手引き」に則した治療が原則
(2018年2月7日:m3.com)
「感染症の研修会等に定期的に参加していること」ってアバウトな基準ですねえ。
この時代、ネット配信の「e-ラーニング」で研修するシステムを作って欲しいものです。
歳を取って持病を抱えると、なかなか遠くの研究会・研修会に参加できなくなりますので。