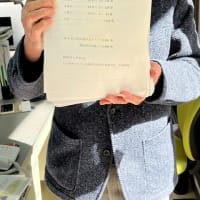第25回(2014年)なくせじん肺全国キャラバン行動が始まる!
<連合長崎佐世保地協と佐世保地区労に要請>
10月1日午前、キャラバン長崎実行委員会は連合長崎佐世保地域協議会と佐世保地区労に、キャラバン成功のために協力を依頼し懇談を深めました。連合地協では、鴨川博明事務局長が応対しました。鴨川氏は「今日は、SSK(佐世保重工業㈱)で、労災被災者の合同慰霊祭が行われている。じん肺やアスベスト問題は、佐世保でも重要な問題」「根絶に向けて協力できることがあれば協力したい」と語りました。
佐世保地区労は、書記の方が歓迎してくれました。佐世保地区労は、長崎北松じん肺訴訟を支えた屋台骨でもあり、根絶署名も頑張って取り組んでいます。第1回全国キャラバンの前年に地区労の古い宣伝カーで、四国、関西まで行った、じん肺根絶北松の灯の河西龍太郎弁護士と篠崎正人さんは、懐かしげに当時の思い出を語りました。要請には、河西、篠崎氏と長崎実行委員会の村里正昭事務局長、中里研哉事務局次長、伊王島じん肺根絶の会佐藤郁雄会長、じん肺根絶北松の灯の石丸吉一さんが参加しました。
<北松じん肺根絶祈念碑「慰霊祭」>
10月1日午後2時から長崎県佐々町にある「北松じん肺根絶の碑」前で「慰霊祭」が開催され、全国の代表や九州各地からの代表70人が参加しました。根絶の碑は、長崎北松じん肺訴訟の勝利解決を記念して2002年5月に建立されました。キャラバン全国実行委員会を代表して岩城邦治全国じん肺弁連代表委員があいさつし、東光寺住職の読経が流れる中、参加者は焼香をおこないました。
堤勇孝じん肺患者同盟長崎県会長が、碑の建立に至った経過や長崎北松じん肺訴訟の闘いについて熱く語りました。最後に同訴訟原告団遺族の一人である石丸吉一さんが、全国のみなさんにお礼を述べ終了しました。
<第25回全国出陣集会>
1日午後3時15分から佐々町文化会館で、「2014年(第25回)なくせじん肺全国キャラバン全国出陣集会」が開催され250人が参加しました。建交労長崎県本部の飯田彰吾書記長と藤田久美子長崎民医労書記長の司会で始まり、まず、ながせん合唱団(三菱重工長崎造船所で働いた労働者を中心に作っている男性合唱団)が「林道人夫」「勝利の日まで」を力強く歌い上げました。「林道人夫」は、道やトンネルをつくった労働者をうたったもので、「勝利の日までは」じん肺の仲間たちのことをうたった歌です。
山下登司夫全国実行委員会代表委員が、主催者あいさつをおこないました。山下氏は「25回目になるキャラバンと北松じん肺提訴35年の節目に全国出陣式をこの地で行うことは大きな意義がある」と述べました。
引き続き山本一行西日本石炭弁護団事務局長が「じん肺運動、日鉄闘争の到達点と課題と題して」基調報告。佐世保地区労議長の豊里敬治氏、長崎県労連副議長の溝口一彦氏、じん肺闘争支援東京連絡会の柴田和啓東京地評幹事が連帯あいさつを行いました。
河西龍太郎弁護士は「キャラバン行動の思い出」について、岩城邦治弁護士は「日鉄闘争35年をまとめたブックレット」の紹介を行いました。
そして、じん肺、アスベスト裁判を闘っている各訴訟団が決意表明を行いました。三井神岡鉱山、三菱下関造船、トンネルじん肺根絶、首都圏建設アスベスト、九州建設アスベスト、築炉じん肺、新北海道石炭、西日本石炭じん肺訴訟 と続きました。大阪泉南アスベストからは、メッセージが寄せられました。
最後は横山巖弁護士(長崎実行委員会代表世話人)が閉会あいさつを行いました。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
10月2日の要請行動
<長崎労働局要請>
午前9時から長崎労働局に要請をおこない、監督課、健康課、労災課の課長らが応対しました。要請側は、中里事務局長を責任者に東京支援連の宮崎法正さん、俵倍作さんら13人が参加しました。
監督課長は「提言をすべて読んだ。提言については本省に伝える」「粉じん対策は、第7次が終わり第8次の長崎版を出し、事業場への指導を行っている」と回答しました。健康課長は「健康管理手帳の3年要件は、法令の改正を伴うので本省に伝える」「健康管理手帳の交付は、申請書を管理区分決定書と同時に送付している」「石綿手帳は、診断書に胸膜プラークの記載があれば申請書を送付している」と述べました。インフルエンザの接種費用については、長崎労働局での判断では無理なので、皆さんからの世論を盛り上げてほしい」と逆提案がありました。
その他にはトンネル現場の労働時間について監督課長は「4か所の現場調査も行い10時間労働実態はつかんでいるが8時間を超えていても現法律では違法といえない」と述べました。間質性肺炎問題では「合併症とはなっていないので認められない」という回答をしたので、「合併症ではない。じん肺そのものなのだ。長崎ではじん肺認定者が今年になって、4人も間質性肺炎で亡くなっている」と反論しました。
労働局の行事の関係で、時間が30分しか取れないというタイトなスケジュールでしたので、十分な意見交換ができませんでした。建交労九州キャラバンなどともかぶる内容なので、今後引き続き要請を強めます。
<長崎県知事要請>
長崎県知事要請は10時から行い、長崎実行委員会加盟の各団体から16人と、全国じん肺弁連事務局の長岡良春さんが参加しました。
県のじん肺根絶に向けた取り組みとしては、雇用労政課発行の情報誌にじん肺防止対策のページを増量したり、雇用労政課のホームページに労働局のページをリンクしてじん肺に対する情報にアクセスしやすいようにしたりといったものにとどまりました。新規のじん肺防止において重要な、トンネル建設工事における労働時間規制については、受注者の判断に任せており、じん肺患者を多く抱える長崎県としてどういった対策を講じ改善するのかという主体性も意気込みも感じられるものではありませんでした。
<長崎市長要請>
2日午後2時から東京支援連3人を含む計9団体18名が参加し長崎市長要請をおこないました。市側は、県産業労働部雇用労働政策課労政福祉班 参事 櫻木祐宏氏はじめ、商工部産業雇用政策課、環境部廃棄物対策課、市民健康部地域保健課地域医療室、など12名。要請団は、全国じん肺弁護団連絡会の長岡氏、じん肺闘争支援東京連絡会の俵氏、宮崎氏が参加。
長崎市とは、30分という時間制限を設けるなら、要請団が事前に文書で要請内容を届け事前に市が文書で回答をという要望をし、昨年から実現しました。
第1項、三菱長崎造船所に対して、じん肺根絶のためにどう対処したか?
市回答:長崎市の経済発展を支え続けてきた造船業において、その経済発展の陰の部分としてじん肺患者が生まれ苦しまれていることを心痛に堪えない。市としては、直接的な指導監督を行う立場はないが引き続き企業に対し、一層の配慮をお願いしていく。
要請団:陰の部分という表現は不適切。対策にお金をかければ防げる職業病だ。
指導・監督の直接的権限はないと言うが、考え違いだ。規制権限は国だけではない。一企業である三菱にはもっと規制すべき。日本一の患者発生企業の三菱は規制権限行使が問われている。国の権限と言うのは考え違いだ。筑豊判決(2004年)を引いて反論。
市回答:市労政便り10月号で、本日の内容を踏まえ、注意を喚起していきたい。
市政便り6月、9月発行・ホームページでも。商工業者の目に触れるように。
要請団:トンネル、造船など、じん肺防止策のポイントは、労働時間を減らし粉じん暴露を減らすことが根本問題だ。労働時間に焦点を当てた対策に知恵を絞ってほしい。
アスベスト含有建物の所での効果的暴露防止策を行政として作るべきだ。
市回答:アスベスト患者の病理解剖事例は市立病院機構においてH25年度は0件である。
最後に要請団は、30分の要請時間はあまりにも短い。せめて1時間の時間をと要望しました。
<長崎県医師会要請>
長崎県医師会には①「会で取り組んでいるじん肺・石綿患者対策の概要について」②「じん肺患者へのインフルエンザの優先的接種に協力を」③「間質性肺炎などのじん肺関連死が疑われる場合は、遺族に対し積極的に病理解剖を勧めて欲しい」④「会として長崎労働局に対し疫学調査を行うよう要請して欲しい」の4点を要請しました。要請団は、中里研哉キャラバン実行委員会事務局次長を責任者に長崎民医連の山口喜久雄氏ら6人が参加しました。
応対した長谷川宏常任理事(開業医)と瀬戸牧子常任理事(長崎北病院神経内科医)は、①については、「長崎大学の芦沢和人教授の映像診断の講演」「行政機関からの通達があれば会員に通知している」と回答がありました。②については、「胸部の基礎疾患のある人には優先的にしている」「(じん肺患者だけでなく)家族にも勧めて欲しい」と逆提案もありました。③については「『間質性肺炎』と確定診断があれば、病院側は(解剖)しないので、費用は患者側負担となるので勧めるのは厳しい。20数万円かかるし、解剖医が不足していて要望に応じるのは厳しいのが実態」と貴重な回答がありました。そして、厚労省の労働政策審議会安全衛生分科会じん肺部会の「じん肺画像診断」の研究を芦沢教授が中心になって進める背景に、解剖医の不足問題などもあるのではないかということも明らかになりました。
中里事務局次長は、「剖検を積み重ねている医師や研究者からは、画像とのかい離が指摘されている」と述べました。