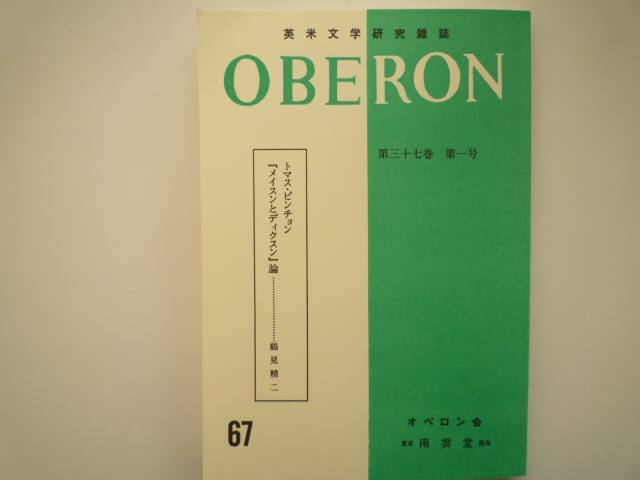オベロン会の刊行物、
『オベロン』の第 67 号が刊行されました。
今号は4本の論文掲載です。
羽矢謙一 「孤独な音色――アイリッシュロイヤリストの悲劇」
川井万里子 「『リア王』の時代背景」
鶴見精二 「パララクス、線、鎖――『メイスンとディクスン』をめぐって」
千葉康樹 「脚注偏愛の編集者――ジョン・ニコルズと『十八世紀文学逸話』」
定価 2,000 円にて、南雲堂から販売しています。
お求めの方は、南雲堂までお願いします。
<編集担当者のつぶやき>
「いやー。今回は、図版が多くて、とにかく大変でした!
ページ数も多かったし!
Indesign も1年ぶりに使うものだから、いろいろ忘れてて、
すっごい手間取りました。
最後は、大あわての編集になりましたが、
編集上のミスが最小限であることを祈ります……。
来年は、余裕をもって編集したいので、その分、
原稿集めを早い時期からがんばります 」
」
では、みなさん、よいお年を!!
『オベロン』の第 67 号が刊行されました。
今号は4本の論文掲載です。
羽矢謙一 「孤独な音色――アイリッシュロイヤリストの悲劇」
川井万里子 「『リア王』の時代背景」
鶴見精二 「パララクス、線、鎖――『メイスンとディクスン』をめぐって」
千葉康樹 「脚注偏愛の編集者――ジョン・ニコルズと『十八世紀文学逸話』」
定価 2,000 円にて、南雲堂から販売しています。
お求めの方は、南雲堂までお願いします。
<編集担当者のつぶやき>
「いやー。今回は、図版が多くて、とにかく大変でした!
ページ数も多かったし!
Indesign も1年ぶりに使うものだから、いろいろ忘れてて、
すっごい手間取りました。
最後は、大あわての編集になりましたが、
編集上のミスが最小限であることを祈ります……。
来年は、余裕をもって編集したいので、その分、
原稿集めを早い時期からがんばります
 」
」では、みなさん、よいお年を!!