全然関係ないが他社比社レコードショップ?のフランクリンでザマキの「やりたいように」を聴かせてもらった。ヒップホップとラップに違いがあるのかなんなのかさえもまったくしらないけど、
スペースインベーダーズとオーディオスポーツしか聴いた事ないからまともな事が言えないけど
ザマキの「やりたいように」は俺達の山塚EYEがオーディオスポーツでラップしてる心地よいあの曲(タイトルわかりません)に言葉の流れる感じが似てて気持ち良かった。しかもタイトルの「やりたいように」が、スワンキーズの(後悔なんてしたくないから「やりたいように」生きるんだ)にあてはまる。この二つがなんだかスポッとはまった気がした。
さて本題。
電車男と最新号のブルータスこの二つのキーワードから本とネットの未来を僕の角度から書いてみようと思います。
生徒「俺じゃないっす」
生徒B「いや、俺もマジで知らないッスよ」
先生「じゃぁいったい「誰が本を殺すのか?』
佐野さんあんただよ。とブックオフでやたらと背表紙をみせつけられるたびに、読んだ事ないけどいつも思うんですよ。
でっ、電車男とブルータスですが、まずブルータスは何日か前にこの日記にも書いたようにたぶん
銀座のビックリしないハウスのマガジンハウスは意識して作ったわけではないと思うんだけど、本がめくれる感じの広告がちょうど本をめくった所に2回もくるグーゼンアートな部分(p16辺りのエルメス広告とその次の浜崎あゆみ広告)が本の一番おもしろい所だと思うんです。
「モノ感」であり「モノ間」であるといえばいいのかな?
恋人をさわるように本をさわるじゃないですか。
今まではコンピューターなんてなかったから「本」として強固だったんだけど、コンピューター登場インターネットで2ちゃんねる。このあたりまではまだ「本とコンピューター」という本を出して一部でコンピューターと本を考える人がいる位でよかったんだけど、ナンシー関が言ってたように(ウメミヤタツオからアンナパパに変わる速度)と同じで、もっと言えばケータイの登場で家電なんて言葉はなかったのに出来たとおもったらもう完全にケータイに支配されている。
自動車電話の頃は自宅の電話を家電とは呼ばなかった事を考えると、それに変わる新しいツール?が大衆性がありポップであればある程、既にあったものが塗り替えられやすい。
家電の立場から言えば今まではアピールする必要がなかった事をアピールしてどうにか食い付いてもらわないといけなくなった。電波が切れないとか、FAX送受信ができるとか、家電からかけたほうが安いとか。
では、僕が感じた電車男がどれだけ斬新であったか?ということを書いてみます。
1、誰も得をしない
2、パソコンと人の物理的な距離のリアルさとそれを見る人の距離がまったく同じである事。
書いててアホ臭くなってきたので、もっとわかりやすく書く。
例えば本は出来上がった後のものでいくら「今、原稿が書けず、原稿用紙とにらめっこをしている」とかいてあったとしてもそれが本になっていてそれを見ながら、作家が蕎麦やで悩む姿は想像できるけれど、本と自分の距離は同じだが、作家の書いた原稿から本になるまでには様々な距離がある。実際に電車男の本を買って読んでみたが、本(電車男)と自分の距離がおもしろくなく、まるで読まなかった。
誰も得をしない
というのは、実際に本になって売れているから誰か得をした人がいるんだろうけど、始まった時や終わった時にですら誰かが得をした感じがない事。
昔江角マキコが出てた「ショムニ」でやたらと綺麗な足ばっかりうつしててデへへとなってたらコマーシャルでフクスケのストキングを流したりする感じが一切無い事。
この誰も得をしないというのは凄く大きいキーワードになる気がする。
なんだか頭の中では上手くまとまってたと思ったけど、何も書けた気がしませんでした。
またいつか書きます。
スペースインベーダーズとオーディオスポーツしか聴いた事ないからまともな事が言えないけど
ザマキの「やりたいように」は俺達の山塚EYEがオーディオスポーツでラップしてる心地よいあの曲(タイトルわかりません)に言葉の流れる感じが似てて気持ち良かった。しかもタイトルの「やりたいように」が、スワンキーズの(後悔なんてしたくないから「やりたいように」生きるんだ)にあてはまる。この二つがなんだかスポッとはまった気がした。
さて本題。
電車男と最新号のブルータスこの二つのキーワードから本とネットの未来を僕の角度から書いてみようと思います。
生徒「俺じゃないっす」
生徒B「いや、俺もマジで知らないッスよ」
先生「じゃぁいったい「誰が本を殺すのか?』
佐野さんあんただよ。とブックオフでやたらと背表紙をみせつけられるたびに、読んだ事ないけどいつも思うんですよ。
でっ、電車男とブルータスですが、まずブルータスは何日か前にこの日記にも書いたようにたぶん
銀座のビックリしないハウスのマガジンハウスは意識して作ったわけではないと思うんだけど、本がめくれる感じの広告がちょうど本をめくった所に2回もくるグーゼンアートな部分(p16辺りのエルメス広告とその次の浜崎あゆみ広告)が本の一番おもしろい所だと思うんです。
「モノ感」であり「モノ間」であるといえばいいのかな?
恋人をさわるように本をさわるじゃないですか。
今まではコンピューターなんてなかったから「本」として強固だったんだけど、コンピューター登場インターネットで2ちゃんねる。このあたりまではまだ「本とコンピューター」という本を出して一部でコンピューターと本を考える人がいる位でよかったんだけど、ナンシー関が言ってたように(ウメミヤタツオからアンナパパに変わる速度)と同じで、もっと言えばケータイの登場で家電なんて言葉はなかったのに出来たとおもったらもう完全にケータイに支配されている。
自動車電話の頃は自宅の電話を家電とは呼ばなかった事を考えると、それに変わる新しいツール?が大衆性がありポップであればある程、既にあったものが塗り替えられやすい。
家電の立場から言えば今まではアピールする必要がなかった事をアピールしてどうにか食い付いてもらわないといけなくなった。電波が切れないとか、FAX送受信ができるとか、家電からかけたほうが安いとか。
では、僕が感じた電車男がどれだけ斬新であったか?ということを書いてみます。
1、誰も得をしない
2、パソコンと人の物理的な距離のリアルさとそれを見る人の距離がまったく同じである事。
書いててアホ臭くなってきたので、もっとわかりやすく書く。
例えば本は出来上がった後のものでいくら「今、原稿が書けず、原稿用紙とにらめっこをしている」とかいてあったとしてもそれが本になっていてそれを見ながら、作家が蕎麦やで悩む姿は想像できるけれど、本と自分の距離は同じだが、作家の書いた原稿から本になるまでには様々な距離がある。実際に電車男の本を買って読んでみたが、本(電車男)と自分の距離がおもしろくなく、まるで読まなかった。
誰も得をしない
というのは、実際に本になって売れているから誰か得をした人がいるんだろうけど、始まった時や終わった時にですら誰かが得をした感じがない事。
昔江角マキコが出てた「ショムニ」でやたらと綺麗な足ばっかりうつしててデへへとなってたらコマーシャルでフクスケのストキングを流したりする感じが一切無い事。
この誰も得をしないというのは凄く大きいキーワードになる気がする。
なんだか頭の中では上手くまとまってたと思ったけど、何も書けた気がしませんでした。
またいつか書きます。

















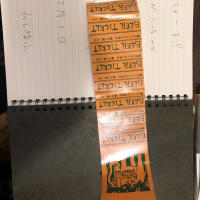


※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます