
本日日暮里行ってきました。
新作は発見できませんでしたが、
前回は写真を撮る事に夢中になりすぎて
細部を観てなかったので、じっくりと観る。
前回佐藤さんに逢った時に製作途中だった
「一旦停止」が出来上がっている。
昨日の予告通り、佐藤修悦と草間京平を
どうにか結びつけよと思い草間京平の
文献を読み漁る斜め読み。
何かが似てると思ったんだから仕方ない。
それで無理やり佐藤さんと草間京平を結び付けよう
としたんだけど、わからなくなってくる、。
でも何かあるはずだ。
草間京平はガリ版の神様と言われた人で、今生きていたら
100歳を超えている。
草間京平(くさま・きょうへい)
1902-1971(明治35年-昭和46年)、茨城県生まれ、
本名佐川義高。大正中期に上京、 郵便配達、人夫、
出版社の校正係などをしながら、文学を志す。
1920年(大正9年)に短歌の同人誌『孔雀草』を謄写印刷で創刊。
1923年、作家有島武郎から資金を得て、
芸術倶楽部アパートの一室で「黒船社」を設立、
謄写印刷技術の研究と出版に取り組む。
謄写印刷の技法開発、機材開発、研究誌の発行、教育・普及活動に尽くし、
謄写印刷技術の第一人者といわれた。
創作を多く残した若山八十氏と対比して、「複製派」と呼ばれることがある。
ガリ版http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%AC%84%E5%86%99%E7%89%88
でとんでもない程の綺麗な美術印刷をしていたのが
草間京平です。
地図とか浮世絵とか物凄く綺麗すぎてどこからみても
ガリ版で刷ったとは信じ難い作品ばかりで、最後の頃は
どうやって刷ったのかまったくわからないような
油絵のようなガリ版作品もあるんですが、本人は
単なる紙屑みたいなものだ。と言って何一つ保管していなかったようです。
なんとか拾い集めた草間京平と佐藤さんがつながるような文献
ガリ版は草間京平によって孔版(ガリ版のこと)に技術革命
された。それは人間技とは思えない精微な製版だった。
孔版につながる人で陰に陽に草間京平の影響をうけない人は
いないはず (昭和堂月報の時代より)
謄写文字についても草間京平が従来の楷書体の他、新しくゴシック体を考案しました。
草間は当時の無声映画の独得なタイトル文字からヒントを得て
これを謄写印刷のゴシック書体に取り入れた
と聞いております。彼は毎日この書体の研究に熱中して
1文字でも疑問があると直ぐに近くの映画館に行ってその文字
をタイトルの中にさがしてメモして来たというエピソードがあります。
(軽印刷のルーツ --- 東軽工千代田支部25周年史)
謄写印刷は磨かれざる宝石である。われわれはその研磨師である
(草間京平伝 --- 里美村教育委員会)
ガリ版は印象すらなくなるほど遠くのモノになってますが
でも、あえて無理やり知ってる事を言えば、
手描きの文字がそのまま印刷されたぶっきらぼうな
プリントごっこの兄貴みたいな存在でしかなかったんだけど
草間京平の浮世絵や地図の色の豊かさや
ソレを作る為に作った版が40版もあるという
気が遠くなっておそろしくなるような作業を思い浮かべると
本当にすごいなぁと思う。
おそらく草間京平の時代もとっくに浮世絵なんて言う文化は
なくて、ガリ版に対してそんなに高度な事はだれも求めて
なかったんだけど、やる
それ以外に答えがなかったんだと思う。
今も、佐藤さんの文字は凄いし、そこまでは誰も
求めてはいないんだけどやる。
文字の中味や意味ではなくカタチが大切だ
というような事を佐藤さんはインタビューの
中で答えている。
おそらく
今日僕がみた「一旦停止」も「一時停止」
では伝わらない何かがあるのだろうなぁと思う。
最後にちょっとした朗報です。
今週末に日暮里駅構内の改装工事が
あるらしく、1つか2つくらい何か新しい文字を
切る予定とのことです。
それでは、また明日
新作は発見できませんでしたが、
前回は写真を撮る事に夢中になりすぎて
細部を観てなかったので、じっくりと観る。
前回佐藤さんに逢った時に製作途中だった
「一旦停止」が出来上がっている。
昨日の予告通り、佐藤修悦と草間京平を
どうにか結びつけよと思い草間京平の
文献を読み漁る斜め読み。
何かが似てると思ったんだから仕方ない。
それで無理やり佐藤さんと草間京平を結び付けよう
としたんだけど、わからなくなってくる、。
でも何かあるはずだ。
草間京平はガリ版の神様と言われた人で、今生きていたら
100歳を超えている。
草間京平(くさま・きょうへい)
1902-1971(明治35年-昭和46年)、茨城県生まれ、
本名佐川義高。大正中期に上京、 郵便配達、人夫、
出版社の校正係などをしながら、文学を志す。
1920年(大正9年)に短歌の同人誌『孔雀草』を謄写印刷で創刊。
1923年、作家有島武郎から資金を得て、
芸術倶楽部アパートの一室で「黒船社」を設立、
謄写印刷技術の研究と出版に取り組む。
謄写印刷の技法開発、機材開発、研究誌の発行、教育・普及活動に尽くし、
謄写印刷技術の第一人者といわれた。
創作を多く残した若山八十氏と対比して、「複製派」と呼ばれることがある。
ガリ版http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%AC%84%E5%86%99%E7%89%88
でとんでもない程の綺麗な美術印刷をしていたのが
草間京平です。
地図とか浮世絵とか物凄く綺麗すぎてどこからみても
ガリ版で刷ったとは信じ難い作品ばかりで、最後の頃は
どうやって刷ったのかまったくわからないような
油絵のようなガリ版作品もあるんですが、本人は
単なる紙屑みたいなものだ。と言って何一つ保管していなかったようです。
なんとか拾い集めた草間京平と佐藤さんがつながるような文献
ガリ版は草間京平によって孔版(ガリ版のこと)に技術革命
された。それは人間技とは思えない精微な製版だった。
孔版につながる人で陰に陽に草間京平の影響をうけない人は
いないはず (昭和堂月報の時代より)
謄写文字についても草間京平が従来の楷書体の他、新しくゴシック体を考案しました。
草間は当時の無声映画の独得なタイトル文字からヒントを得て
これを謄写印刷のゴシック書体に取り入れた
と聞いております。彼は毎日この書体の研究に熱中して
1文字でも疑問があると直ぐに近くの映画館に行ってその文字
をタイトルの中にさがしてメモして来たというエピソードがあります。
(軽印刷のルーツ --- 東軽工千代田支部25周年史)
謄写印刷は磨かれざる宝石である。われわれはその研磨師である
(草間京平伝 --- 里美村教育委員会)
ガリ版は印象すらなくなるほど遠くのモノになってますが
でも、あえて無理やり知ってる事を言えば、
手描きの文字がそのまま印刷されたぶっきらぼうな
プリントごっこの兄貴みたいな存在でしかなかったんだけど
草間京平の浮世絵や地図の色の豊かさや
ソレを作る為に作った版が40版もあるという
気が遠くなっておそろしくなるような作業を思い浮かべると
本当にすごいなぁと思う。
おそらく草間京平の時代もとっくに浮世絵なんて言う文化は
なくて、ガリ版に対してそんなに高度な事はだれも求めて
なかったんだけど、やる
それ以外に答えがなかったんだと思う。
今も、佐藤さんの文字は凄いし、そこまでは誰も
求めてはいないんだけどやる。
文字の中味や意味ではなくカタチが大切だ
というような事を佐藤さんはインタビューの
中で答えている。
おそらく
今日僕がみた「一旦停止」も「一時停止」
では伝わらない何かがあるのだろうなぁと思う。
最後にちょっとした朗報です。
今週末に日暮里駅構内の改装工事が
あるらしく、1つか2つくらい何か新しい文字を
切る予定とのことです。
それでは、また明日

















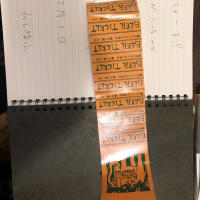


※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます