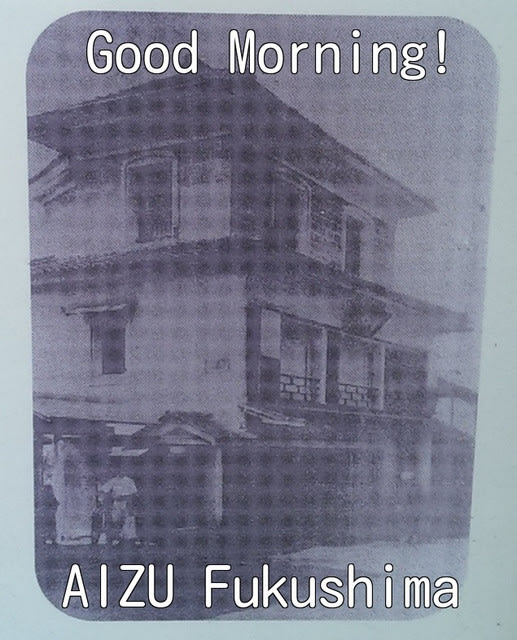おはようございます。旅人宿 会津野 宿主の長谷川洋一です。
今日は、カルテルのことを考えてみます。
車を運転していると、ガソリンの値段はいつも気になるものです。
市況が上昇すると、一斉に各ガソリンスタンドの価格が値上がりし、まるで申し合わせたように同じ価格になることが多々あります。
もしここに、競争制限的行為を行う合意があればカルテルとなります。たいていの場合は、他の店の価格を調べたうえで、ガソリンスタンドが自己判断し値上げをします。この場合は、カルテルになりません。
つまり、複数の業者間での合意があるかないかが問題となります。
さて、表題に掲げたデジタルカルテル。
いま、インターネットのマッチングモデルによるシェアリングエコノミーの分野で問題となっています。
それでは民泊の例をみてみましょう。
民泊アプリのairbnbでは、宿泊をしたい人と受け入れたい人のマッチングを行います。ここでは、民泊の受け入れ側がいわゆる業者の立場になります。
受け入れ側は、立地や設備などを考慮して1泊の値段をつけます。airbnbには、この値段を需給に応じて変動させるスマートプライシングという機能があります。この機能を使う場合、受け入れ側は、最低価格と最高価格を設定し、airbnbはアクセスや予約の状況を考慮しながら、設定の範囲内でどんどん値段を変更していきます。
airbnbは、販売額に相当する一定の率で報酬を受け取るビジネスモデルのため、販売額が大きい方が手数料収入が増えます。
受け入れ側も、同じ部屋が高い値段で売れた方が嬉しいことなので、この機能を使います。
ここに、競争制限的行為の合意があるかないかは微妙ですが、"値段の明確な合意"はありません。
割を喰うのはだれかと言えば、需給がひっ迫したときに泊まる宿泊者ということになります。
こういうことをデジタルカルテルと言います。
IoT(モノのインターネット)と呼ばれる家電などと、インターネットがつながる分野では、商品の発注が人工知能により行われようとしています。
たとえば、急速に気温が上がることを検知して、アイスクリームの発注を自動的に行う冷凍庫が開発されたら、その発注を受けるアイスクリーム屋さんは、急に忙しくなるので、そのアクセス増加により値段を変更するようなことが起きます。もし発注量が普段の100倍に達したら、値段も100倍にして自動的に受注すると言うことが起きるかも知れません。その場合、その冷凍庫を持つ人は、100倍の代金を払わなくてはなりません。
これもデジタルカルテルでしょう。
現行の法律では、競争制限的行為の合意があるかないかが、カルテルかそうでないかを分ける点です。なので、デジタルカルテルには対応できません。
経済学的には、需給により価格が変動するのは、至極当然のこと。
宿泊予約を考えると、あまりにも高い価格が提示されたときは、もっと安い日に宿泊するという働きが起きるでしょうから、いずれ平準化されるような気もします。しかし、例に出したアイスクリームなどは、平準化が難しい分野です。同じ商品が需給により大幅な価格変動が起きるでしょう。
リアルな分野では、アイスクリーム屋さんの店頭に、ガソリンスタンドのような電光掲示板で「ただいまのアイスクリームの値段」という表示が現れる世の中になるかも知れませんね。
社会においては、どんな価格設定が幸せなことなのか。考えさせられます。
今日も素敵な一日を過ごしましょう。
※コメントは、旅人宿会津野Facebookにて承ります。
※ご予約は、旅人宿会津野ホームページにて承ります。