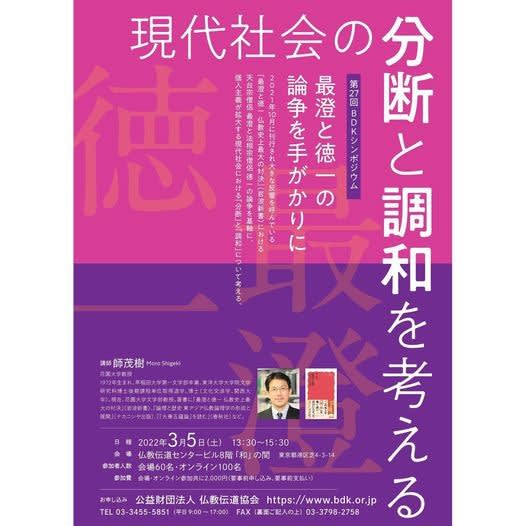滋賀教区東雲寺住職で、天台宗典編纂所編輯員の吉田慈順師が、令和4年5月8日号の比叡山時報に見開きで、伝教大師と宮沢賢治について「一乗の敷衍にささげたご生涯 宮沢賢治が成就を願ったみ教えとは」という題で書いています。
吉田師は、比叡山延暦寺の総本堂根本中堂の向かいに建っている宮沢賢治の下記の歌碑を取り上げ、
「根本中堂」
ねがはくは
妙法如来 正徧知
大師のみ旨
成らしめたまへ
その歌を踏まえて「最澄の御旨」を解明すべく筆を起こします。そして、最澄のキーワードが「一乗」であること。最澄が出家した近江国の大国師であった行表から「(行表)和上より心を一乗に帰すべきこと学んだ」という点を重視します。
また、当時の日本仏教界で法相宗と三論宗との間で論争が行われており、その段階で、すでに三乗か一乗かをめぐってであったために、その渦中にあった行表が、一乗の正しさを最澄に説いたというのです。
その使命を期待された最澄は「高雄講経」において、天台教学を講義することで、三論宗の側からは「長きに亘る論争が氷解した」と絶賛されたのです。
最澄はいつ最澄の法門を知ったのかと言うと、比叡山に入って間もない時期だといわれており、華厳宗の法蔵の著作を読むことで、天台大師の教えに心を寄せるようになったのでした。三論宗の一つの華厳宗を経て、天台宗の法門に入ったというのが、吉田師の見方です。
最澄の『願文』のなかの「伏して願わくは、解脱の味、独り飲まず。安楽の果、独り証せず。法界の衆生と同じく妙覚に登り、法界の衆生と同じく妙味を服せん」という言葉も、一乗の信仰の表れとみるのです。
私は旧約といわれる鳩摩羅什の妙法蓮華経は名文の誉れが高いものがありますが、そのお経を唱えておりますと、なぜか心まで洗われるような思いがしてなりません。また、宮沢賢治に関しては、田村芳朗の『法華経 真理・生命・実践』がその最期の様子を伝えています。「題目を唱え、父に次のごとく遺言した。国訳の『法華経』を一千部、知人に配ってほしい。その国訳の最後に『私の全生涯の仕事は、この経典をあなたにお届けし、その仏意にふれてあなたが無上道に入られることを』という意味の言葉を書き入れてほしい。こう遺言し、オキシフルで自分の体をふいて息をひきとっていった」
合掌