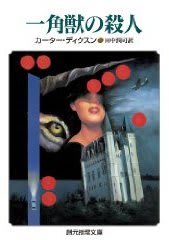
この作品でカーはなにをしたかったのでしょうか。
事件の世界を外界と隔絶させて、クローズドサークルの中での犯人探し、が一点。
それと、被害者の身元を曖昧にしておいて意外な犯人トリックをしかけることも一点。
被害者の身元を曖昧にするトリックは「盲目の理髪師」「九人と死で十人だ」で使われていますが、
この作品の被害者は「ドラモンド」として殺されたのか、「ガスケ」として殺されたのか、
最後まで判然としません。
被害者の身元が分からないという設定ならば、クイーンの「中途の家」のほうが鮮やかです。
クローズドサークルを作ってその中で犯人探しをさせるトリックは
「五つの箱の死」で大胆に使って失敗していましたが(^^)、
ここでも成功しているとは思えません。
やはりクイーンの「心地よく秘密めいた場所」のほうがうまく扱っていると思います。
それに「怪盗」「覆面探偵」という設定は、いくらカーがロマンの作家でも、
当時としても時代遅れではなかったでしょうか。
また被害者の扱われ方がぞんざいというか、いかにも殺されるだけに登場した、
というのもまるでゲーム的です。
著者が読者にしかけたトリックは『大きな「3人一役」の中に入った小さな2人一役』&脱力感あふれる犯人隠し、
というところでしょうか。
まあ、しかし、この入り組んだヘンテコな話を、傑作を書いた間にモノにしていたとは、こちらもさすが天才J・D・カー。
さて、この身代わり話のネタはどこからきたのか。なぜフランスが舞台なのか。
ここからは勝手な推測ですが、瓜二つの人間が入れ替わったコメディを書いていたフランス作家がいました。
その名はジョルジュ・フェドー。
フランス文学史には19世紀末の多くの象徴主義の詩人のなかに、
ヴォードヴィル作家としての名前があります。その喜劇は一世を風靡したそうです。
入れ替わりコメデイ作品は「耳に蚤」といい、
地主と下男が瓜二つで、交互に登場する(一人の役者が二役を演じる)地主と下男に周りが翻弄される喜劇です。
フェドーが亡くなったのは1921年、カーがパリに外遊するちょっと前あたりですね。
考えられるのは、カーはパリでフェドーの芝居を観ていたのではないか。
たぶんオペレッタとかコメデイには瓜二つをネタにしたものが「耳に蚤」以外にもあったでしょうから、
そのあたりをカーはふくらませて、瓜二つの男が入れ替わるボードヴィル調ミステリを書いてみた(あくまで書いてみた)のではないでしょうか。
1934年から1935年は、カーの代表作・傑作が発表された最初のピークだったのですが、
「一角獣の殺人」は手すさびとして書かれたのかもしれません。
とはいえ、冒頭のブロードウェイレヴューのジャズソングからの引用もあながち唐突ではない、
ボードヴィルを愛好したカーの姿が見えるようです。
事件の世界を外界と隔絶させて、クローズドサークルの中での犯人探し、が一点。
それと、被害者の身元を曖昧にしておいて意外な犯人トリックをしかけることも一点。
被害者の身元を曖昧にするトリックは「盲目の理髪師」「九人と死で十人だ」で使われていますが、
この作品の被害者は「ドラモンド」として殺されたのか、「ガスケ」として殺されたのか、
最後まで判然としません。
被害者の身元が分からないという設定ならば、クイーンの「中途の家」のほうが鮮やかです。
クローズドサークルを作ってその中で犯人探しをさせるトリックは
「五つの箱の死」で大胆に使って失敗していましたが(^^)、
ここでも成功しているとは思えません。
やはりクイーンの「心地よく秘密めいた場所」のほうがうまく扱っていると思います。
それに「怪盗」「覆面探偵」という設定は、いくらカーがロマンの作家でも、
当時としても時代遅れではなかったでしょうか。
また被害者の扱われ方がぞんざいというか、いかにも殺されるだけに登場した、
というのもまるでゲーム的です。
著者が読者にしかけたトリックは『大きな「3人一役」の中に入った小さな2人一役』&脱力感あふれる犯人隠し、
というところでしょうか。
まあ、しかし、この入り組んだヘンテコな話を、傑作を書いた間にモノにしていたとは、こちらもさすが天才J・D・カー。
さて、この身代わり話のネタはどこからきたのか。なぜフランスが舞台なのか。
ここからは勝手な推測ですが、瓜二つの人間が入れ替わったコメディを書いていたフランス作家がいました。
その名はジョルジュ・フェドー。
フランス文学史には19世紀末の多くの象徴主義の詩人のなかに、
ヴォードヴィル作家としての名前があります。その喜劇は一世を風靡したそうです。
入れ替わりコメデイ作品は「耳に蚤」といい、
地主と下男が瓜二つで、交互に登場する(一人の役者が二役を演じる)地主と下男に周りが翻弄される喜劇です。
フェドーが亡くなったのは1921年、カーがパリに外遊するちょっと前あたりですね。
考えられるのは、カーはパリでフェドーの芝居を観ていたのではないか。
たぶんオペレッタとかコメデイには瓜二つをネタにしたものが「耳に蚤」以外にもあったでしょうから、
そのあたりをカーはふくらませて、瓜二つの男が入れ替わるボードヴィル調ミステリを書いてみた(あくまで書いてみた)のではないでしょうか。
1934年から1935年は、カーの代表作・傑作が発表された最初のピークだったのですが、
「一角獣の殺人」は手すさびとして書かれたのかもしれません。
とはいえ、冒頭のブロードウェイレヴューのジャズソングからの引用もあながち唐突ではない、
ボードヴィルを愛好したカーの姿が見えるようです。














※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます