このブログでも時々出てくるカットバック。
元々はクロスカッティングと呼んでいたようですが、今はその一つのバリエーションであったカットバックの方が普及しているようです。
<クロスカッティング(cross-cutting)とは、異なる場面のシーンを交互に撮影(映写)する事により、臨場感や緊張感等の演出効果をもたらす映画の撮影技法。通常は、同時に複数の場所で進行している出来事を、交互に見せる事が多い。
映画史においては、1903年のエドウィン・ポーターによるアメリカ映画『大列車強盗』で、逃亡する強盗一味と、彼らを追いかける保安官の場面などで、初めて用いられた。 D・W・グリフィスが1915年の『國民の創生』における戦闘シーンで効果的に用いられた事により、さらに普及した。
カットバック(cutaway / cutback)もクロスカッティングと殆ど同意で、現在ではカットバックと呼ばれる事の方が多い。やはり異なる場面のシーンを交互に撮影する技法だが、通常、カットバックは場面Aから場面Bに短時間で戻る、一回の動きを指す。
フラッシュバックはクロスカッティング、カットバックのバリエーションの一つで、非常に短い間隔で異なる場面のシーンを切り返すこと。 フラッシュバックを多用(重用)し独自のスタイルを築き上げた作家としてサム・ペキンパーなどが有名である。(『ウィキペディア(Wikipedia)』より)>
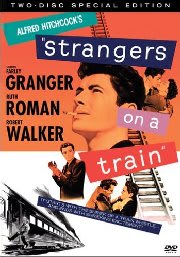 双葉先生の著書に出てくるカットバックの例で思い出されるのは、ヒッチコックの「見知らぬ乗客(1951)」。
双葉先生の著書に出てくるカットバックの例で思い出されるのは、ヒッチコックの「見知らぬ乗客(1951)」。
父親を殺して欲しいロバート・ウォーカーが、テニス選手のファーリー・グレンジャーに交換殺人を持ちかける。グレンジャーは相手にしないが、ウォーカーはさっさとグレンジャーの妻を殺害する。ウォーカーはグレンジャーに罪を被せようと、グレンジャーの試合中に彼のライターを殺害現場に置きに行く。
このシーンで、早く試合を終わらせようと焦るグレンジャーと、殺害現場に向かうウォーカーをカットバックで描き、サスペンスを盛り上げました。
「ダイ・ハード」シリーズでもクロスカッティングはよく使われました。ビルの中のマクレーン刑事と外の黒人警官や警察。ビルの中でもマクレーンと奥さん達捕虜がいるフロアとのカットバックもあったりして面白い映画でした。シリーズ2では空港ターミナルと飛行機内とのカットバックでした。
ジョージ・ロイ・ヒルの「明日に向って撃て!」は、『大列車強盗』と同じように追う者と追われる者が出てきますが、こちらは追われる側からだけの映像で緊迫感を盛り上げました。時々、追っ手の保安官達の映像がロングショットで挿入されましたがね。
「めぐりあう時間たち」は、三つの違う時間(時代)の話が平行して語られる作品でしたが、特にクロスさせた効果というものは感じませんでしたね。
「ペイ・フォワード」も違う時間軸の話がクロスして語られますが、コチラは終盤での交錯過程が面白い効果を生んでいました。
フラッシュ・バックも近年よく使われるようになりましたが、こちらはサスペンスより、ショッカー的な使い方が多いようです。
コレを場面展開に使って印象的だったのは「イージー・ライダー」。
<フラッシュバックを多用(重用)し独自のスタイルを築き上げた作家としてサム・ペキンパーなどが有名>とありますが、はて、そんなに使っていたかな?
余談ですが、ブログで使っているトラックバック。映画やテレビでは、カメラを後退移動させながら被写体を撮影することをそう言うようです。(豆知識だよ!)
元々はクロスカッティングと呼んでいたようですが、今はその一つのバリエーションであったカットバックの方が普及しているようです。
<クロスカッティング(cross-cutting)とは、異なる場面のシーンを交互に撮影(映写)する事により、臨場感や緊張感等の演出効果をもたらす映画の撮影技法。通常は、同時に複数の場所で進行している出来事を、交互に見せる事が多い。
映画史においては、1903年のエドウィン・ポーターによるアメリカ映画『大列車強盗』で、逃亡する強盗一味と、彼らを追いかける保安官の場面などで、初めて用いられた。 D・W・グリフィスが1915年の『國民の創生』における戦闘シーンで効果的に用いられた事により、さらに普及した。
カットバック(cutaway / cutback)もクロスカッティングと殆ど同意で、現在ではカットバックと呼ばれる事の方が多い。やはり異なる場面のシーンを交互に撮影する技法だが、通常、カットバックは場面Aから場面Bに短時間で戻る、一回の動きを指す。
フラッシュバックはクロスカッティング、カットバックのバリエーションの一つで、非常に短い間隔で異なる場面のシーンを切り返すこと。 フラッシュバックを多用(重用)し独自のスタイルを築き上げた作家としてサム・ペキンパーなどが有名である。(『ウィキペディア(Wikipedia)』より)>
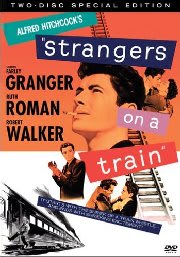 双葉先生の著書に出てくるカットバックの例で思い出されるのは、ヒッチコックの「見知らぬ乗客(1951)」。
双葉先生の著書に出てくるカットバックの例で思い出されるのは、ヒッチコックの「見知らぬ乗客(1951)」。父親を殺して欲しいロバート・ウォーカーが、テニス選手のファーリー・グレンジャーに交換殺人を持ちかける。グレンジャーは相手にしないが、ウォーカーはさっさとグレンジャーの妻を殺害する。ウォーカーはグレンジャーに罪を被せようと、グレンジャーの試合中に彼のライターを殺害現場に置きに行く。
このシーンで、早く試合を終わらせようと焦るグレンジャーと、殺害現場に向かうウォーカーをカットバックで描き、サスペンスを盛り上げました。
「ダイ・ハード」シリーズでもクロスカッティングはよく使われました。ビルの中のマクレーン刑事と外の黒人警官や警察。ビルの中でもマクレーンと奥さん達捕虜がいるフロアとのカットバックもあったりして面白い映画でした。シリーズ2では空港ターミナルと飛行機内とのカットバックでした。
ジョージ・ロイ・ヒルの「明日に向って撃て!」は、『大列車強盗』と同じように追う者と追われる者が出てきますが、こちらは追われる側からだけの映像で緊迫感を盛り上げました。時々、追っ手の保安官達の映像がロングショットで挿入されましたがね。
「めぐりあう時間たち」は、三つの違う時間(時代)の話が平行して語られる作品でしたが、特にクロスさせた効果というものは感じませんでしたね。
「ペイ・フォワード」も違う時間軸の話がクロスして語られますが、コチラは終盤での交錯過程が面白い効果を生んでいました。
フラッシュ・バックも近年よく使われるようになりましたが、こちらはサスペンスより、ショッカー的な使い方が多いようです。
コレを場面展開に使って印象的だったのは「イージー・ライダー」。
<フラッシュバックを多用(重用)し独自のスタイルを築き上げた作家としてサム・ペキンパーなどが有名>とありますが、はて、そんなに使っていたかな?
余談ですが、ブログで使っているトラックバック。映画やテレビでは、カメラを後退移動させながら被写体を撮影することをそう言うようです。(豆知識だよ!)



















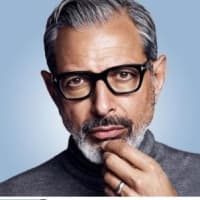



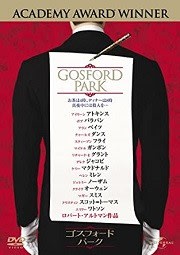









「見知らぬ乗客」は文字通りカットバックのお手本のような演出ですね。だてにサスペンスの神様と言われてはいないです。
数ヶ月前に「スター・ウォーズ/シスの復讐」というシリーズ最終作を観たのですが、二組の対決場面のカットバックがお粗末でした。ルーカスってこんなに下手だったかな。タイミングが悪いんですよ。
フラッシュバックと言えば、「真夜中のカーボーイ」が強烈な印象を残しています。恐らくこの作品の後からフラッシュバックが増えたんじゃないかと思っていますが、どうでしょうか?
ジョー・バックの過去のシーンですか?
観てないんですが、「質屋」にも使われていると聞いたことがあるし、60年代の末期辺りからと考えていいんでしょうね。
映画用語でいうフラッシュバックはワン・ショットかツー・ショッツの短いものと考えて良いでしょうね。演劇用語や文芸用語では、映画の回想シーンに相当する連続的なものにもこの語を当てはめます。映画のような短いものは不可能ですから。
尤も、英語では回想シーンをフラッシュバックと言っているかも。確認できていないです。
初回は中学生で物語ばかり追っていましたが、高校生になって観た時に強烈な印象を受けました。
買ったまま封を切らなかったDVDで前半だけ確認しましたが、ニューシネマの金字塔と思います。
ジョーのテキサス訛り、聞き取れないです。
「質屋」も素晴らしい作品です。必見だと思いますよ。
NYに向かう長距離バスの中で、子供の頃から寂しい境遇で育ったジョー・バックが、故郷での忌まわしい記憶を思い出すシーンでした。
>ジョーのテキサス訛り、聞き取れないです。
標準語も聞き取れない私です。(笑)
「質屋」。レンタルでも見かけませんね。そろそろBSでやってもいいはずなんですが。