
[東京 10日] - 日銀は4月26―27日の金融政策決定会合後に公表した「経済・物価情勢の展望(展望リポート)」で、物価目標2%達成時期の明記をやめた。従来は、6度の先送りを経て「2019年度ごろ」としていた。
黒田東彦総裁によると、展望リポートで物価見通しが2%を下回ると、達成が難しくなったから追加緩和に踏み切るという観測が生じるので、こうした誤解が生じないように達成時期に言及するのをやめたと説明している。
そして、緩和姿勢が後退したのかと問われると、「できるだけ早期に」と達成に向けた姿勢は以前と何も変わらないと語る。
ポイントは、1)黒田総裁が指摘する誤解に対して、正しい理解とは何か、2)本当に何も変わっていないと理解してよいのか、の2点だろう。
<追加緩和観測の封じ込め>
まず、誤解とは何か。展望リポートの年度見通しは、あくまで見通しであって、目標達成の時期を示したものではない。両者を混同するのが誤解だという。
従来の黒田総裁の説明では、いったん物価2%に達すると、その後はずっと2%以上の物価上昇率が継続するということだった。それを前提に、物価上昇率の実績値が安定的に2%の物価安定目標を超えることを目指すオーバーシュート型コミットメントがあったのではないか。
確かに、2019年10月の消費税増税での物価上昇率のアップダウンがあることは日銀も認めていた。そこでは、すう勢的に2%軌道を維持できるから、2019年度ごろの達成を可能と読み替えていた。
ところが、2020年度の見通しが4月27日の展望リポートで初めて発表されると、前年比1.8%だった(除く消費税要因)。しかも、大勢の見通しは1.5―1.8%のレンジだ。9人のうち最低8人は2020年度に平均2%は無理だとみている。これは、明らかに論理矛盾だ。2%の達成時期は、2019年度ごろではなく、2020年度以降になるはずだ。
誤解とは、見通しと目標達成の時期は違う言葉であり、同一視をしては困るということである。しかし、目標達成の時期を正しく理解したいと思うと、それはできない。「できるだけ早期に」と「2019年度ごろ」という説明は同じではないはずだ。実質的には、ほとんどの政策委員が少なくとも2019年度までに2%は達成困難であると認めていると読める。それを認めたとき、追加緩和は不要だから見守ってほしい、と言っているように聞こえる。
<論理のすり替え>
次に、できるだけ早期に達成すると言っているのだから、達成期限が示されなくても何も変わらない、と考えてよいのか。
今までは、2%の物価目標に、人々の予想物価をアンカーすると公言してきた。アンカーとは、くくり付けるという日銀の仲間内の用語だろう。日銀が必ず2%を達成すると公言するから、皆がそれを信じて行動するようになると、アンカーされる根拠を唱えてきた。しかし、2019年度も、2020年度も2%以上の物価予想になっていない。
以上、ロイターコラム
インフレターゲット2%だから、2%を超えたら、異次元の金融緩和をやめるのだから、私は全く問題ないと思っています。
まるでハイパーインフレになるかのようなことを言う学者には呆れます。
紫色のおばちゃん学者の言うことは全く当たっていません。
よく大学の教授が務まっていることに驚きです。


















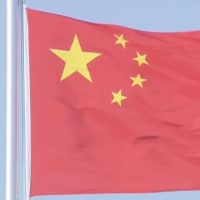


※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます