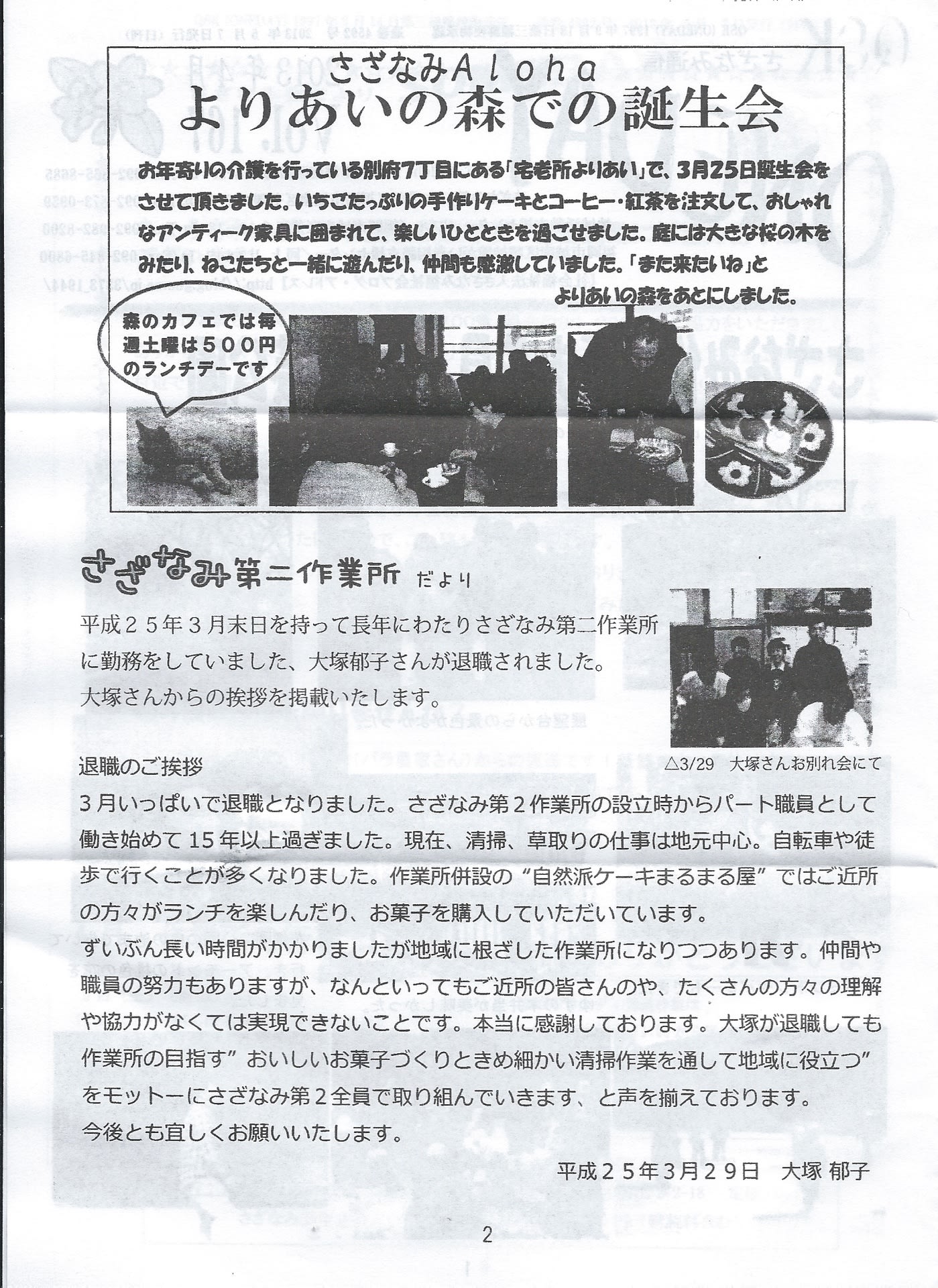保護者制度を廃止 雇用の障害者差別を禁止 福祉新聞2013年4月29日
政府は19日、保護者制度の廃止などを要点とする「精神保健福祉法改正案」と、雇用分野の差別禁止などを規定した「障害者雇用促進法改正案」を国会に提出した。
精神保健福祉法改正案は、かねて家族の負担感が問題視されていた保護者に関する規定を削除する。家庭裁判所などが選任した「保護者」には精神障害者に治療を受けさせることや退院時の引き取りが義務付けられているがこれを廃止する。
医療保護入院の見直しでは、保護者の同意要件を外す。配偶者、親権者、扶養義務者、後見人、保佐人いずれかの同意で良いとし、該当者がいなければ市町村長の判断とする。
ただ、精神障害の当事者などからは、「手続きが簡便になるだけで、家族間に軋轢が生じる問題は解決しない」という指摘もある。
精神科病院の管理者 には、退院後の生活環境に関する相談に乗る精神保健福祉士を置く
など、退院促進のための体制整備を義務付ける 。施行は2014年4 月を目指している。
一方、障害者雇用促進法は、障害者権利条約を批准するための大きな改正になる。雇用分野の障害者差別を禁止し、事業主には、障害者が職場で働く上で支障ないよう配慮する措置を講じるこ と〈合理的配慮の提供〉が義務付けられる。
措置が事業主の過重な負担になる場合は除くが、例えば、車いす利用者に合わせて作業台の高さを調整することや、知的障害のある従業員に口頭だけでなく分かりやすい文書や絵図で説明することなどが想定される。具体的な事例は、指針で示される。 事業主と障害者の間で紛争が起きること考えられ、基本は企業内の自主解決とするが、紛争調整委員会に よる調停や都道府県労働局長による勧告なども活用する。
施行は16年4月。法定雇用率の算定基礎に精神障害者を加えることも要点だが、これは企業の反発が強かったこともあり18年4月の施行とする。
悪質運転の厳罰化
持病申告で免許に罰則
政府は12日、悪質運転による事故の厳罰化を盛り込んだ「自動車の運転により人を死傷 させる行為等の処罰に関する法案」を国会に提出した。3月29日には、病気を申告せず運転免許を取得することに罰則を科す「道路交通法改正案」も提出。
今国会での成立を目指している。両法案は、てんかんの持病を隠して免許を取った運転手が起こした重大事故などを契機 に見直された経緯がある。遺族らが厳罰化を求めた一方、障害者団体などは「病気や障害のある人の排除につながる法律を作らないでほしい」との声も根強い。
厳罰化の新法は、現行の刑法から「危険運転致死傷罪」を移し、特定の病気の影響により
が想定されており、人を死亡させた場合は懲役15年以下となる。 このほか酒や薬物の影響で起こした事故現場から逃げるケース、一方通行の逆走など危険な運転による事故なども処罰対象になる。道路交通法の改正では、免許の取得・更新時に、発作や失神など運転に支障を及ぼすおそれがある病気を申告しなければ罰則を課す。これも、てんかんなどが想定されている。 該当患者の運転を知 っている医師が任意で公安委員会に届け出ても守秘義務に反しない とする規定も盛り込 む。 両法案については日本てんかん協会を中心に「一定の病気だけを取り上げた不当な処罰になる。社会環境整備がないまま罰則を制定すyるのも障害者らを排除する結果になる」ヘ規定の削除を求め署名を集めている。