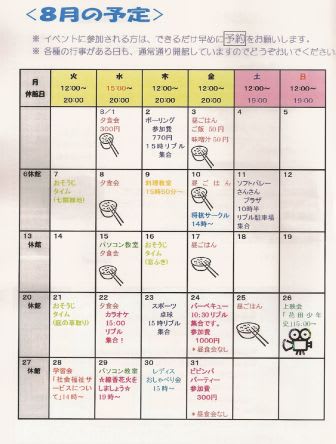2007年8月29日
「大分市で発生した水泳死亡事故」に関する声明
痛ましい事故をさけるため、てんかんのある人への水泳指導 がさらに適切な監視態勢のもとで行われること、
発作を恐れるあまり水泳を制限されないこと、を望みます。
社団法人 日本てんかん協会
会長 鶴井 啓司
8月27日(月)、大分市において授産施設が行うプール指導中に、通所利用者が死亡する事故が発生したことは、大変痛ましく、亡くなられた植木隆博さんのご冥福を衷心からお祈り申し上げ、御遺族の皆さまへも深甚なるお悔やみを申し上げる次第です。
今回の事故でお亡くなりになられたのは、てんかん発作に加えて重複障害のある方であり、当協会の会員でもありました。施設職員とヘルパーに引率されて遊泳されていました。ヘルパーが目を離した間に発作が起こったと報道は伝えています。
障害がある方の水泳で怖いのは障害があることではなく、障害を有するがゆえの安全サポートが万全でないということです。今回の悲劇のように、マンツーマンで付き添っていても、目を離した僅かな時間に発作が起きる可能性もあります。予知できない危険性を関係者全員が、改めて肝に銘じていただきたいと切に願います。サポート態勢が万全であったならば、たとえ発作に見舞われても適切な介助で彼を救うことが出来たのではないかと、無念の思いを禁じ得ません。
今回の事故の経緯についてはまだ分からない点もありますので、以下に一般的な問題について述べさせてもらいます。
■てんかんのある人だけに特別リスクが高いわけではない
てんかんのある人へのプール指導のあり方については、これまで学校教育の中などで毎夏話題となってきました。「てんかんはこわい病気」などと思われがちで、活動の制限が実施される例が少なくありませんでした。
しかし、たとえ水泳中に発作が起こったからといって、水面から顔を出して呼吸を確保し、発作が治まってから引き上げるという基本的介助を行えば大事にいたりません。重大な事故を招来するのは、「指導者がつい目を離した」「勝手に泳いでいた」などの管理上の問題がある場合です。
脳波の所見からは水泳中に発作が出現する可能性は少ないという結果も報告されています(「てんかん児と水泳」、松岡他、1983)。また、外国の研究などを見ても、子どもの水泳中の事故の統計を見ても、てんかんのある人に事故が多いという報告はありません。
(シリーズ・援助の実際Vol.9「てんかんと教育」、日本てんかん協会、1996)
■てんかんのある人のプール水泳は充分な安全サポート態勢で!
てんかんのある人へのプール指導では、十二分なサポート態勢で臨み、水泳中は指導員が目を離さないことが基本です。水泳中に絶対に発作が起こらないとは言えませんが、抱えるリスクは水泳を楽しむ人たち全てに共通しており、てんかんはそのうちの因子の一つに過ぎません。
今回の痛ましい事故を一面的に解釈して、てんかんのある人へのプール指導がやみくもに制限されることを、協会では危惧しています。この事故を教訓として、各学校や施設などでの指導体制を十分に見直してもらい、今年の残り少ないプール指導を引き続き安全に実施することこそが求められていると思います。
また、今回の事故は行政からの委託事業という積極的な取り組みの中で起きたことですが、てんかんのある人の社会参加を進めるためにも、この教訓を活かしてこの事業が継続されることを希望します。さらに、重度の障害者を受け入れる施設に対する人員配置の改善なども切望します。
「大分市で発生した水泳死亡事故」に関する声明
痛ましい事故をさけるため、てんかんのある人への水泳指導 がさらに適切な監視態勢のもとで行われること、
発作を恐れるあまり水泳を制限されないこと、を望みます。
社団法人 日本てんかん協会
会長 鶴井 啓司
8月27日(月)、大分市において授産施設が行うプール指導中に、通所利用者が死亡する事故が発生したことは、大変痛ましく、亡くなられた植木隆博さんのご冥福を衷心からお祈り申し上げ、御遺族の皆さまへも深甚なるお悔やみを申し上げる次第です。
今回の事故でお亡くなりになられたのは、てんかん発作に加えて重複障害のある方であり、当協会の会員でもありました。施設職員とヘルパーに引率されて遊泳されていました。ヘルパーが目を離した間に発作が起こったと報道は伝えています。
障害がある方の水泳で怖いのは障害があることではなく、障害を有するがゆえの安全サポートが万全でないということです。今回の悲劇のように、マンツーマンで付き添っていても、目を離した僅かな時間に発作が起きる可能性もあります。予知できない危険性を関係者全員が、改めて肝に銘じていただきたいと切に願います。サポート態勢が万全であったならば、たとえ発作に見舞われても適切な介助で彼を救うことが出来たのではないかと、無念の思いを禁じ得ません。
今回の事故の経緯についてはまだ分からない点もありますので、以下に一般的な問題について述べさせてもらいます。
■てんかんのある人だけに特別リスクが高いわけではない
てんかんのある人へのプール指導のあり方については、これまで学校教育の中などで毎夏話題となってきました。「てんかんはこわい病気」などと思われがちで、活動の制限が実施される例が少なくありませんでした。
しかし、たとえ水泳中に発作が起こったからといって、水面から顔を出して呼吸を確保し、発作が治まってから引き上げるという基本的介助を行えば大事にいたりません。重大な事故を招来するのは、「指導者がつい目を離した」「勝手に泳いでいた」などの管理上の問題がある場合です。
脳波の所見からは水泳中に発作が出現する可能性は少ないという結果も報告されています(「てんかん児と水泳」、松岡他、1983)。また、外国の研究などを見ても、子どもの水泳中の事故の統計を見ても、てんかんのある人に事故が多いという報告はありません。
(シリーズ・援助の実際Vol.9「てんかんと教育」、日本てんかん協会、1996)
■てんかんのある人のプール水泳は充分な安全サポート態勢で!
てんかんのある人へのプール指導では、十二分なサポート態勢で臨み、水泳中は指導員が目を離さないことが基本です。水泳中に絶対に発作が起こらないとは言えませんが、抱えるリスクは水泳を楽しむ人たち全てに共通しており、てんかんはそのうちの因子の一つに過ぎません。
今回の痛ましい事故を一面的に解釈して、てんかんのある人へのプール指導がやみくもに制限されることを、協会では危惧しています。この事故を教訓として、各学校や施設などでの指導体制を十分に見直してもらい、今年の残り少ないプール指導を引き続き安全に実施することこそが求められていると思います。
また、今回の事故は行政からの委託事業という積極的な取り組みの中で起きたことですが、てんかんのある人の社会参加を進めるためにも、この教訓を活かしてこの事業が継続されることを希望します。さらに、重度の障害者を受け入れる施設に対する人員配置の改善なども切望します。