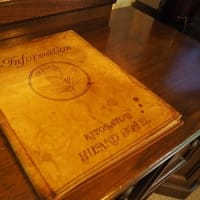温泉の紹介本や記事を読むと「温泉の定義」として1948年制定の温泉法の記載を良く見かける。ほんとによく見かける。
これは「温泉法」の目的を達成するための定義であって、温泉好きが温泉を語っているときに水戸黄門の印籠のように出されても困るし、ウザイ感じがします。。
温泉法では1%の源泉と99%の水を加熱した風呂も温泉となるのはよく知られていることだけれど「そんなものは温泉ではない」と思う人も多いはずで、そのように思う人に対し「イヤ、それはあなたの間違いで、これは温泉です」と言うことには意味があるのかということです。
なかには狭義の温泉と広義の温泉に分けて考える人もいるかもしれませんが、どーでも良いじゃないですか、定義なんて。そんなに必要ですか?
人それぞれの「温泉」があっていいし、それによって会話が成り立たなくなることはないと思いますね。むしろ人それぞれの温泉物語を聞きたいなぁ。
その前提で、私の場合は循環(つまり塩素入り)は温泉とは呼びたくないところです。だって、例えばコーヒー。
インスタントコーヒーはコーヒーではないという方もいると思いますが、私は好きですし、それもコーヒーと呼びます。
でも、このインスタントコーヒーですら濾過機で濾して塩素を入れたら、ま、塩素は入れないでしょうから字面が似ているということで塩でも入れますか。とてもコーヒーとは呼べないですよね。日本の濾過機は優秀ですからどんなになって出てくるんでしょうか。温泉もそうです。まったくの別物に仕上がっているはずです。
ちなみに宿の脱衣所あたりに温泉の分析表が掛けてあると思いますが、これは湯船のお湯を分析したわけではなく、源泉つまり地中から湧き出た直後のお湯の分析ですからお間違いなく。もともとはそういうお湯だったのか~と思いを馳せるのには役立ちます。
しかしそうは言っても、沸かし湯の日帰り温泉から帰ったお婆ちゃんが「いい温泉だったべし(なに弁?)」とかつぶやいていればそれは温泉ですし、子供が近所の銭湯を楽しい場所として温泉と呼べば「今日は温泉にいくか」ということにもなるかと思います。
そういうわけで、温泉法を引用するのであれば、それに対して自分はどういう考えを持っているかも説明しなければ、印籠の出しっぱなしみたいなものだと思います。だから、何?と言う感じですか。