1965年の映画。生まれた年だわ~。
毎月やってる映画の会の課題映画だったので、頑張ってみました3時間20分。
好きな小説のトップに入るのがトルストイの「戦争と平和」だし、
カラマーゾフなんかも好きなので、ロシア文学系は好きだと思います。
それで楽しく見ましたが、大河ドラマではあるけど、登場人物はさほど多くなく、
人間関係は少しだけややこしいけど、「戦争と平和」に比べたら
ものすごくシンプルなメロドラマストーリーです。
でも、原作を読んだ友達は、登場人物多すぎー!名前難しすぎー!と言ってたので
原作の方は映画よりたくさんの登場人物がいたのかな。
お話は長いので、ぶつっ、ぶつっ、と箇条書きでものすごく大雑把に書きます。
・両親を亡くしたジバゴは叔父に引き取られ医者で詩人になる。
・叔父のところの娘、優しく聡明なトーニャと結婚し幸せな家庭を築く。
・一方母娘で暮らすお針子の美しい娘ラーラは、母の愛人と関係を持つようになる。
・そのころジバゴはラーラと知り合い、彼女の美しさが気になる。
・ラーラには母の愛人だった弁護士と付き合う前から、革命に理想を燃やす恋人がいて、
結局その男と結婚するが、夫は革命に身を投じて行方不明に。
・ドイツとの戦争で従軍医として働くジバゴの元に、
偶然、看護師としてラーラが来て一緒に働くうちに気持ちが通うがそのまま別れる。
・革命のせいで、モスクワでの生活が大変になったジバゴ一家は妻の田舎の別荘へ。
・その近くの町でなんとラーラと偶然の再会アゲイン。とうとう愛し合うようになるが、
優しく明るく献身的な妻のことを考えて別れる決意をする。
・別れ話の後、ジバゴは革命軍に拉致され、医者として働かされる。
・その間にジバゴの家族はパリへ亡命を余儀なくされる。
・ジバゴ2年後に革命軍から逃げ出しラーラの元へ、つかの間の愛の時間。
・しかし、危険が迫り、ラーラの元愛人(その前は母親の愛人)だった弁護士が
助けに来て、一緒に逃げる。ジバゴはラーラだけ行かせて自分は別の道へ。
(・・・こんないい加減で大雑把な箇条書きでも長いな。笑)
・まあいろいろあって、ジバゴもラーラもいなくなり、
二人の娘だと思われる少女をジバゴの兄(党でそこそこ出世してる)が見つけ
これからは便宜を図ってやるよと言うところではじまり、終わる映画です。
映像が綺麗です。デジタルリマスターしてあるのかな。
雪のモスクワもきれいだし、列車のシーンもいいし、
田舎の家が冬に氷の宮殿みたいになっているのも面白いし素敵。寒そうだけど。
ラーラの青い瞳がものすごくきれいで、白目が透き通るように白いんだけど
暗い場所で、このラーラの目のところだけに光を当てて
そこからふっと浮かび上がって明るくなる、という演出を何度もしてて、
何度見ても美しい。
ラーラは悪徳弁護士と関係を持つんだけど、
相手が強引ではあったものの、自分でも惹かれるところがあったのか、
まだ18歳でお金を持った大人の魅力?に抗えなかったのか、結局受け入れて、
自分からも買ってもらった服を着ていそいそと出かけたりするわけで、
全く罪のない純真な少女というわけではありません。
ジバゴと愛し合うようになった後は、忌まわしい過去だわと後悔するけど、
過ちを犯さない清らかなトーニャに比べると矛盾のあるキャラクターながら、
何しろ美しいのでそれも魅力になるのかもしれませんね。
メロドラマ好きとしては、
このふたりは最後まで結ばれなかった方がロマンチックだったのにねぇと思う。
でもこれってメロドラマなのに、愛し合う二人がやっと会っても離れ離れになっても
全然見ている方にはキュンとくるものがないのです。
普通こういう映画だと、すれ違う二人が早く出会って結ばれてほしい!と思ったり
離れ離れになると切なくなったりするものですが、ここでは全然・・・。
これは→「サウルの息子」みたいに、物語はまあどうでもよくて、
結局その背景(見えるものも見えないものも)を見る映画なのだろうなと思いました。
でも、ロシアのこの時代を見るには、トルストイの方が断然上ではありますね。
桁違いと言っていいと思う。思想の深さの違いでしょう。
ジバゴと家族が田舎へ行って、門番小屋に落ち着くシーン。
寒いモスクワでの困窮生活と、窮屈でつらい列車の長旅の後、
緑の草木の合間に花まで咲き出している田舎の春の景色は
見ているこちらもほっとします。
そこで、昔の使用人だった爺やに、ストーブは使えます、薪は集めますと言われて
最初にジバゴが聞いたのが「馬鈴薯の種は?」
・・・やっぱ芋!芋なのか~!!
思い出したのは先月見た→「オデッセイ」でした。
火星で取り残され、お芋を育てて生き延びる話(だけではないけど)。
やっぱり、西欧の人は、芋なのね~!芋大事なのね~!とつっこんでしまった。
当時、この原作は革命に対して批判的であるとソ連では発禁になって
イタリアで出版されたということですが、
革命を批判する映画というわけではないけど、
革命側の人たちを冷たく書いている部分はあるし、
映画の中で何度も何度も「革命のためには個人の幸せや愛など排除していいのだ」
「そんなもの捨てろ」と言われるので、確かに革命に好意的には見えませんね。
全ての人の幸せを目指すという建前の理想ではなく、
すべての民は幸せを捨てて革命に命をかけろ!と繰り返す革命側を描いてるのだもの。
多くの労働者たちもそっぽ向くだろうと思うようなことを繰り替えされたら
まあ党的には、発禁にしておくか、と思ったのでしょう。
のちにフルシチョフだったか誰かが読んで(誰だっけうろ覚え)
特別に問題があると思えないと言ったそうではあるけど。
あと感じたのはロシアの広さ。大陸、ほんと広いなぁ。
前線ってどこ?と聞かれて、パルチザンたちは、自分たちのいるところが前線だ!
と答えるのですが、ロシアは人間に比べて土地が広すぎて、
ぽつんぽつんと、なんだか心もとない前線なんじゃないのそれ、とか思う。
いろいろと突っ込みどころの多い作品で
映画の会では、おしゃべりが物凄く盛り上がりましたが、
それでも文芸大作ですね。
昨年だったかに亡くなったオマー・シャリフ主演だったので、
「アラビアのロレンス」も見たくなったし、
「ラーラのテーマ」という主題歌も誰にでも聞き覚えのある美しいメロディだし。
(上の動画で流れています)
そういえば、
バラライカという三角形の胴を持つ弦楽器が重要なモチーフになってますが、
バラライカというカクテルがあって、それを飲もうと思ってたのに忘れてた。
今度いただきましょう。












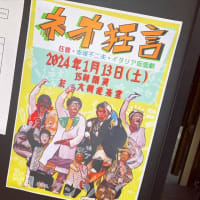





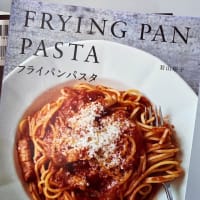

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます