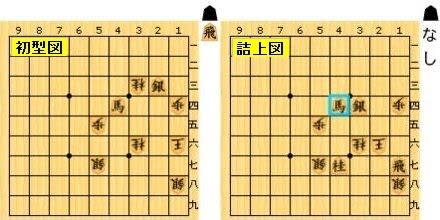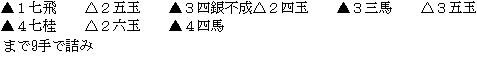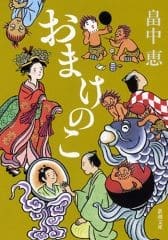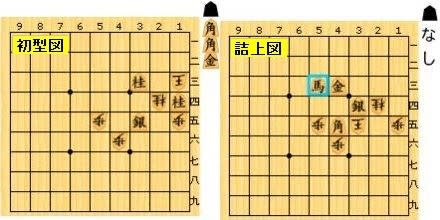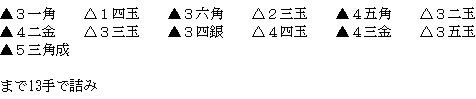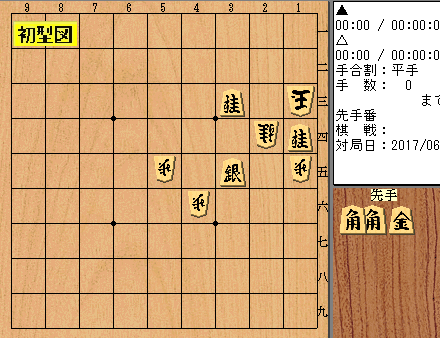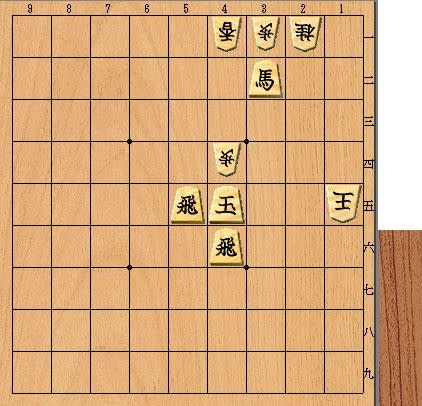「しゃばけ」シリーズ第5巻。全19巻もあるので、とりあえず5巻までと思っていたが、5巻目で大転換が。登場人物たちが江戸を離れ旅に出る。とりあえず近場の湯治地として箱根を目指す。海路、小田原まで進み、そこから山道を駕籠で登って箱根まで。途中の小田原と、箱根湯本で休みながら芦ノ湖の方まで行くのだろう。第一巻以来の長編である。

江戸時代の箱根は関所として有名で、なんらかの理由で関所破りをしようという人はかなりいたようで、山の中に入ると、天狗や追剥が待ち構えていることになっていた。
ところが、主人公の若だんなの行く先には、次々を命を狙う武士や雲助や妖怪たちがあらわれる。それは1000年昔の時代に遡って、山の神の娘を間違って生贄として芦ノ湖に放り込もうとした村人たちへの罪に原因があるのだが、自らの過ちを認めないのは世界的に人間の普遍性であるため、江戸から来る旅人のせいにして、殺してしまおうということになるわけだ(原書では、もっと複雑で魅力的に書かれている)。
ところで、『うそうそ』は第4巻『おまけのこ』同様に、死者は出ない。行方不明者もいない。シリーズの当初には、バッサバッサと様々な人間たちが多様な死に方をしていたのだが方向転換したのだろうか。次の死体は何巻目になるのだろうかとか、次の旅行先はどこになるのだろうか、といった興味で6巻目に進むのだろうか。
現在、個人的に一仕事中なので、手が空いたら、また5冊といった感じかな。

江戸時代の箱根は関所として有名で、なんらかの理由で関所破りをしようという人はかなりいたようで、山の中に入ると、天狗や追剥が待ち構えていることになっていた。
ところが、主人公の若だんなの行く先には、次々を命を狙う武士や雲助や妖怪たちがあらわれる。それは1000年昔の時代に遡って、山の神の娘を間違って生贄として芦ノ湖に放り込もうとした村人たちへの罪に原因があるのだが、自らの過ちを認めないのは世界的に人間の普遍性であるため、江戸から来る旅人のせいにして、殺してしまおうということになるわけだ(原書では、もっと複雑で魅力的に書かれている)。
ところで、『うそうそ』は第4巻『おまけのこ』同様に、死者は出ない。行方不明者もいない。シリーズの当初には、バッサバッサと様々な人間たちが多様な死に方をしていたのだが方向転換したのだろうか。次の死体は何巻目になるのだろうかとか、次の旅行先はどこになるのだろうか、といった興味で6巻目に進むのだろうか。
現在、個人的に一仕事中なので、手が空いたら、また5冊といった感じかな。