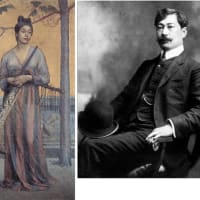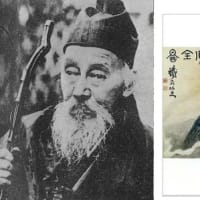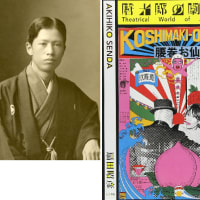A. だんだんよくなっていく、のか?だんだんわるくなっていくのか?
安倍政権は日本農政の基本政策として行われてきた「減反政策」をやめることにするらしい。かつて日本の農村を支えた米作り農家の保護のため、コメの価格を維持するように生産調整を国と農協が一体となってすすめた「減反」だった。しかし、地方農村地帯を地盤とした自民党農林族の有力議員は、民主党が圧勝した選挙で片っ端から落ち、もう今の与党にも野党にも古い農林族はいなくなった。TPP論議で日本農業が壊滅するといっても、もう別にいいじゃんとしか考えない人たちが政府や国会には溢れているわけだ。米作農業を保護する意味は、産業的にも政治的にも希薄化している。
ちなみにぼくも去年、山形県で学生を連れて米農家の調査をしたのだが、水田が広がる農村も、実は農業だけで生活している人は少ない。TPP反対を農協が唱えても、実は農業の衰退を危惧する声はそんなに聞かれない。すでに衰退は極まっているともいえるし、減反しなくても生産性の低い田はみな休耕田、非耕作地になっている。農村に生きる人々も、一部の販路をもった意欲的な農業者を別にすれば、もう農業は片手間で他に収入の道を確保しているのが、したたかな生き方である。
要するに今の政権の基本路線は、グローバル経済に適応し、旧来の規制を緩和し、非効率な組織や役に立たない人間は排除するか置いてけぼりにして、ひたすら国際競争を勝ち抜く力強い企業・起業によって、強力な経済成長を目指すことに集中している。「世界で一番、企業が活動しやすい国家」にしたい、という首相はさらに、それを軍事的にも支える強力な軍隊をもち、憲法の誓約(制約?)を無力化して自由に軍事力の行使ができる国家にしたいと意欲を燃やしている。世界中の機密情報をアメリカからもらうために、自分は平気でスパイ行為をしていても公務員・メディア・国民の情報漏えいはびしびし取り締まるという法案や、誰も知らないところで国家の重要な決定をしてしまえるような組織を作ろうとする。
かつて1980年代の中曽根政権('82~87)は、レーガン米政権の番犬となって「不沈戦艦」を称し、国鉄や電電公社・専売公社の民営化をすすめ、「スパイ防止法」を国会に出した。しかし、あの時代は一方で保守の側にも、過剰な対米追随、自衛隊の強化、公務員や組合などの弱体化政策には反対もあり、まして「減反政策」の廃止などとても言える雰囲気ではなかったと思う。中教審で日教組潰しに意欲を燃やした点でも、思想的に安倍晋三の師ともいえそうだが、中曽根の退陣は「売上税導入」が公約に反していたことへの批判の嵐だった。しかし、あれから20年以上経って、経済成長至上主義という点では池田隼人を装いながら、ある意味では中曽根康弘が用意していたことを安倍晋三はなぞっている。問題はそういう政権の意思に対して、国際情勢と国民の意識が1980年代とは大きく異なっていることだろう。
「日本を取り戻す」というスローガンは、かつて日本の歴史のどこかに取り戻すべき「栄光の時代があった」という認識がベースになっている。そういうことを言っている人たちのイメージはだいたい3つぐらいのパターンかと思う。それは、(1)戦後の1960~1980年代までの高度経済成長時代、ここが日本経済の絶頂期で、マンハッタンの一等地まで日本企業が買い占めるような「先進国成り上がり」の大勝利だという自慢。(2)明治維新1869年にはじまり日露戦争の勝利1905年までの「坂の上の雲」の上り坂への誇らしいアイデンティティ賛美。(3)さらに歴史を遡って、脅威としての西洋文明も中華文明も征服できなかった大八洲、天孫降臨・万世一系の神話的世界に「武士道」という人工的なあやしげなイメージを継ぎ合わせた「日本人」ユニーク論。このブログでぼくが考えてきたのは、この3つのような粗雑なイデオロギーは歴史というものをまともに知ろうとも見ようともしていない、ということだ。ただ、言えるのは彼らがバブル崩壊以降の失速の20年を、衰退の下り坂と見ており、安倍政権の政策が自民党を含め過去の失敗を克服し、だんだん良くなる進化だと信じていることだ。単純無垢な進化論信者。
さまざまな出来事自体も出来事の説明も、そこに現に生きていた人々にとっても、多様で複雑なものである。ぼくたちは無限に複雑な現実を生きている。それを正確に認識し適切な判断をするには、方法として「複雑性の縮減」をしない限り、人間には不可能である。宗教という社会システム(とくにユダヤ=キリスト教的一神教の場合だが)が提供してきたのは、「複雑性の縮減」を人間の能力を超えた神の意志として、人の行動のなかに埋め込むことだった。しかし、日本の場合は、宗教というのは文字も読めない大衆向けの教化言説以上のものであったのだろうか?それが権力をもたない素朴な庶民の信仰であるなら、ある意味で心配はない。だが、ありもしない栄光をまるで自分の能力の達成であるかに妄想した人々が、たかが短期的な経済システムの論理でしかないグローバル資本主義の一処方箋であるネオリベ政策に飛びつき、それとは縁も所縁もない「日の丸ナショナリズム」を、自分の政治的利権的野心を浄化するための道具にしている。日本は、だんだんよくなっているのか?それともだんだんわるくなっているのか?いや、歴史がある方向に向かって走り始めているとき、それがよい方向なのか、悪い方向なのかと問うこと自体、現実から目を離したイデオロギーだと思うべきだ。

B. 宗教現象の社会学
ニコラス・ルーマンはドイツの社会学者。社会学理論とくに独自の社会システム理論をうち立てた理論家として知られる(知られると言っても社会学という領域の、しかも小難しい理論社会学という世界だけの話だが・・)。ルーマンにも大きな著作として『宗教社会学』がある。ちょっと読んでみた。翻訳のせいか、著者の文章自体がこうなのか、とにかく非常にややこしく回りくどい文章である。マックス・ヴェーバーの文章も読みにくいといえば読みにくいけれども、あれは確実なことを正確に伝えようとする努力の結果で、我慢して読んでいくとなるほどこれは凄い、と思える。しかし、ルーマンの文章は、彼の理論の前提、社会システム論についてかなり頭に入っていないと、何が言いたいのか理解できない。
「宗教を機能的に定義しようとする試みは、従来たいして大きな成果を挙げてきたわけではないし、また今日広範な批判にさらされている。それに対する主要な批判は、宗教の機能のどんな特殊化も、宗教と同一の機能を果たすけれども、広義に解釈すれば、宗教とはみなされ得ない別種の諸制度、現象、あるいは機構をも包含してしまうというところにある。こういった余剰効果は機能的分析を行うと事実入手されてしまうものであるし、またそれどころかそれが意図されてもいる。機能的分析の原理はその分析対象を、ある問題に関し他の対象との比較を可能にするところにある。この分析技術は、方法論的には二行の関係を三行の関係に変換する。つまり、それはあるものを他のものと、ある問題に関して比較する。それ故この分析技術は題材に関するすべての情報を、題材が問題の解決に役立つその問題から見てとる、ということに依存しているのではまったくない。問題の関連は二重に情報を提供してくれるのである。まず、それ自身から、ついでまた、題材がそれと比較可能である他のものを選び出し、かつ限定する視点を提起するというところからである。したがって機能的分析を追求する認識形式は複合化している。つまり宗教は問題Xを解決する。しかしb、c、dなどが問題Xを解決するように解決するのではない。だから機能は題材を直接照明および側面照明のなかに置くことになる。機能は題材を二重に、つまり肯定的ならびに否定的に特殊化する。機能は、題材がどのように問題の解決に寄与するのかを示すと同時に、その題材が他の機能的に等価な形式のようには処理されないということも明らかにする。こうして機能はシステムの根本問題に繋がり、同時に、その解決方法は、複合化したシステムが構築されるにもかかわらず、長い進化の歴史の中で分化され、そのことで相互に差異化され、自己を特殊化するということを考慮に入れることも可能なのである。
定義化し‐カテゴリーに入れる方法とは異なり、機能的分析はまさに機能的等価物のすべてのクラスに向かう関連問題の徹底化を要請する。そのために引き受ける不明確さは、どっちみち回避することはできない。この不明確さは場合によっては口でうまくごまかすことができるかもしれない――宗教を神聖なもの、聖なるもの、強大なものとの関連で(あるいはそれらに関係するものとして)定義するときのように。だが、そのような定義では分析の進行はたちまち停滞してしまう。そうした方法では宗教体験自体に、つまりその対象にあまりにも急速に近づきすぎ、その結果短絡してしまうのだ。そうではなく、機能的分析は外部との繋がりに、概念の多面的応用性に、かつ他の対象領域における理論的諸経験の輸入に価値を置く、そういう距離を取った概念性を好む。それにより機能的分析はその題材との関連のなかで解体能力と再結合能力を高めていくのである。
このような方法は科学理論的に、また果たしてどのような条件下で正当化されうるものなのか、という問題についてはここでは触れない。我われはそれを実践してみて、そうすることでまず経験を積んでみよう。そしてそのような経験が集められた段階で、後から科学理論はそのための根拠を提示することができるかもしれない。
宗教という概念を機能的に規定する試みがいくつかあるが、それらのいくつかは前もって排除しておかねばならない。なぜならそれらはデータと矛盾していたり、あるいはあまりに無造作に、対象につかみかかろうとしているからだ。とくに宗教はシステムを統合化する機能を有しているという仮定は、データと矛盾する。なぜならば明らかにシステムを破壊する、あるいは解体をうながす宗教的運動もまた存在するからだ。宗教的諸経験は所与の社会的秩序を支持もするし、また問題にもする。各個人を肯定的態度へも導くし、また否定的態度へも導くことができる。また建設的に作用することも破壊的に作用することもある。あるいはまた宗教的諸経験は、あるものから別のものへと変化することもある。それにもかかわらず、宗教はとにかく統合化する機能をもっていると前提する者は、この事実状況を前にすると、宗教は現代社会においては全社会システムの領域での、あらゆる機能を喪失してしまったという確信を抱いてしまうことになるだろう。だが、それは上記概念の誤った構成の帰結、あまりに厳しく限定された機能理解の結果でしかないのではなかろうか。
宗教は解釈する機能を有しているとする理解はあまりにも単純すぎる。宗教が不明確で多義的な、また捉え難い事態の解釈並びにその明確化に係わっているということについては、異論のないところである。そこでは解釈に必要性が、つまり不明確な事態の出現ということが、素朴にかつ非分析的に前提されている。そうしたことは日常生活の地平ならびに解釈者の地平に対応している。しかし機能的分析はそのような解釈の貧困をたんに実存的に採用し、そのままにしておくことで満足することはできない。というのは多義性はシステム構造の相関概念として、あるいは、さらに戦略的に選ばれた操作の要件として、増大したり、もしくは減少せざるをえないからである。おそらくたんに論理的操作あるいは言語的操作の要件が問題なのかも知れない。あるいは十分に興味のある、精神的運動に発生した周囲世界への欲求がデザインの適当な設計技術によって満足させられ、または抑制されねばならないという、そうした欲求が問題なのかもしれない。それとも多義性という隠喩は、高位の公職において、その経歴上の成果がどのように使用されるのかを暗示するだけなのかもしれない。
このような観点が議論のなかに入ってくると、さらに解明し定義することもせず、最終の事物の捉え難さ、および不可知性に引きこもることは困難になる。確かに神学的にもつぎのことは容易に論証できるのではなかろうか。すなわち、成立したもの一切は、それ自体よりも複雑である原因を前提としており、したがって、成立したものはその成立を、創造されたものはその創造者を、十分には捉えることはできず、多義性という術語を捉え難いものの最高性のために用いるようになるということである。しかし知っておかなければならならいことは、進化論がこの間、この前提をまさに裏返しにしてしまい、条件づけられた選択制の過程を把握しようとしているということである。またこの過程は、複合的なシステムがそれ自身ほど複雑でない諸条件から、どのように発生するかを理解させてくれるのである。このような思考モデルが存在し、かつそのような前提を基礎にして科学的に成果をあげる研究がおこなわれるならば、古いモデルはその決定的な自明性を喪失するだろう。」ニコラス・ルーマン『宗教社会学』土方昭・三瓶憲彦訳、新泉社、1999.pp.10-12.(原著:Funktion der religion von Niklas Luhmann,1977. Suhrkamp Verlag, Frankfurt)
ウ~ん、やっぱり翻訳がゴツゴツの文章だな。素人の読者がこれを読んで理解できるとは思えない。こなしてルーマンが何を言いたいのか、書いてみたいがちょっと待ってね。
安倍政権は日本農政の基本政策として行われてきた「減反政策」をやめることにするらしい。かつて日本の農村を支えた米作り農家の保護のため、コメの価格を維持するように生産調整を国と農協が一体となってすすめた「減反」だった。しかし、地方農村地帯を地盤とした自民党農林族の有力議員は、民主党が圧勝した選挙で片っ端から落ち、もう今の与党にも野党にも古い農林族はいなくなった。TPP論議で日本農業が壊滅するといっても、もう別にいいじゃんとしか考えない人たちが政府や国会には溢れているわけだ。米作農業を保護する意味は、産業的にも政治的にも希薄化している。
ちなみにぼくも去年、山形県で学生を連れて米農家の調査をしたのだが、水田が広がる農村も、実は農業だけで生活している人は少ない。TPP反対を農協が唱えても、実は農業の衰退を危惧する声はそんなに聞かれない。すでに衰退は極まっているともいえるし、減反しなくても生産性の低い田はみな休耕田、非耕作地になっている。農村に生きる人々も、一部の販路をもった意欲的な農業者を別にすれば、もう農業は片手間で他に収入の道を確保しているのが、したたかな生き方である。
要するに今の政権の基本路線は、グローバル経済に適応し、旧来の規制を緩和し、非効率な組織や役に立たない人間は排除するか置いてけぼりにして、ひたすら国際競争を勝ち抜く力強い企業・起業によって、強力な経済成長を目指すことに集中している。「世界で一番、企業が活動しやすい国家」にしたい、という首相はさらに、それを軍事的にも支える強力な軍隊をもち、憲法の誓約(制約?)を無力化して自由に軍事力の行使ができる国家にしたいと意欲を燃やしている。世界中の機密情報をアメリカからもらうために、自分は平気でスパイ行為をしていても公務員・メディア・国民の情報漏えいはびしびし取り締まるという法案や、誰も知らないところで国家の重要な決定をしてしまえるような組織を作ろうとする。
かつて1980年代の中曽根政権('82~87)は、レーガン米政権の番犬となって「不沈戦艦」を称し、国鉄や電電公社・専売公社の民営化をすすめ、「スパイ防止法」を国会に出した。しかし、あの時代は一方で保守の側にも、過剰な対米追随、自衛隊の強化、公務員や組合などの弱体化政策には反対もあり、まして「減反政策」の廃止などとても言える雰囲気ではなかったと思う。中教審で日教組潰しに意欲を燃やした点でも、思想的に安倍晋三の師ともいえそうだが、中曽根の退陣は「売上税導入」が公約に反していたことへの批判の嵐だった。しかし、あれから20年以上経って、経済成長至上主義という点では池田隼人を装いながら、ある意味では中曽根康弘が用意していたことを安倍晋三はなぞっている。問題はそういう政権の意思に対して、国際情勢と国民の意識が1980年代とは大きく異なっていることだろう。
「日本を取り戻す」というスローガンは、かつて日本の歴史のどこかに取り戻すべき「栄光の時代があった」という認識がベースになっている。そういうことを言っている人たちのイメージはだいたい3つぐらいのパターンかと思う。それは、(1)戦後の1960~1980年代までの高度経済成長時代、ここが日本経済の絶頂期で、マンハッタンの一等地まで日本企業が買い占めるような「先進国成り上がり」の大勝利だという自慢。(2)明治維新1869年にはじまり日露戦争の勝利1905年までの「坂の上の雲」の上り坂への誇らしいアイデンティティ賛美。(3)さらに歴史を遡って、脅威としての西洋文明も中華文明も征服できなかった大八洲、天孫降臨・万世一系の神話的世界に「武士道」という人工的なあやしげなイメージを継ぎ合わせた「日本人」ユニーク論。このブログでぼくが考えてきたのは、この3つのような粗雑なイデオロギーは歴史というものをまともに知ろうとも見ようともしていない、ということだ。ただ、言えるのは彼らがバブル崩壊以降の失速の20年を、衰退の下り坂と見ており、安倍政権の政策が自民党を含め過去の失敗を克服し、だんだん良くなる進化だと信じていることだ。単純無垢な進化論信者。
さまざまな出来事自体も出来事の説明も、そこに現に生きていた人々にとっても、多様で複雑なものである。ぼくたちは無限に複雑な現実を生きている。それを正確に認識し適切な判断をするには、方法として「複雑性の縮減」をしない限り、人間には不可能である。宗教という社会システム(とくにユダヤ=キリスト教的一神教の場合だが)が提供してきたのは、「複雑性の縮減」を人間の能力を超えた神の意志として、人の行動のなかに埋め込むことだった。しかし、日本の場合は、宗教というのは文字も読めない大衆向けの教化言説以上のものであったのだろうか?それが権力をもたない素朴な庶民の信仰であるなら、ある意味で心配はない。だが、ありもしない栄光をまるで自分の能力の達成であるかに妄想した人々が、たかが短期的な経済システムの論理でしかないグローバル資本主義の一処方箋であるネオリベ政策に飛びつき、それとは縁も所縁もない「日の丸ナショナリズム」を、自分の政治的利権的野心を浄化するための道具にしている。日本は、だんだんよくなっているのか?それともだんだんわるくなっているのか?いや、歴史がある方向に向かって走り始めているとき、それがよい方向なのか、悪い方向なのかと問うこと自体、現実から目を離したイデオロギーだと思うべきだ。

B. 宗教現象の社会学
ニコラス・ルーマンはドイツの社会学者。社会学理論とくに独自の社会システム理論をうち立てた理論家として知られる(知られると言っても社会学という領域の、しかも小難しい理論社会学という世界だけの話だが・・)。ルーマンにも大きな著作として『宗教社会学』がある。ちょっと読んでみた。翻訳のせいか、著者の文章自体がこうなのか、とにかく非常にややこしく回りくどい文章である。マックス・ヴェーバーの文章も読みにくいといえば読みにくいけれども、あれは確実なことを正確に伝えようとする努力の結果で、我慢して読んでいくとなるほどこれは凄い、と思える。しかし、ルーマンの文章は、彼の理論の前提、社会システム論についてかなり頭に入っていないと、何が言いたいのか理解できない。
「宗教を機能的に定義しようとする試みは、従来たいして大きな成果を挙げてきたわけではないし、また今日広範な批判にさらされている。それに対する主要な批判は、宗教の機能のどんな特殊化も、宗教と同一の機能を果たすけれども、広義に解釈すれば、宗教とはみなされ得ない別種の諸制度、現象、あるいは機構をも包含してしまうというところにある。こういった余剰効果は機能的分析を行うと事実入手されてしまうものであるし、またそれどころかそれが意図されてもいる。機能的分析の原理はその分析対象を、ある問題に関し他の対象との比較を可能にするところにある。この分析技術は、方法論的には二行の関係を三行の関係に変換する。つまり、それはあるものを他のものと、ある問題に関して比較する。それ故この分析技術は題材に関するすべての情報を、題材が問題の解決に役立つその問題から見てとる、ということに依存しているのではまったくない。問題の関連は二重に情報を提供してくれるのである。まず、それ自身から、ついでまた、題材がそれと比較可能である他のものを選び出し、かつ限定する視点を提起するというところからである。したがって機能的分析を追求する認識形式は複合化している。つまり宗教は問題Xを解決する。しかしb、c、dなどが問題Xを解決するように解決するのではない。だから機能は題材を直接照明および側面照明のなかに置くことになる。機能は題材を二重に、つまり肯定的ならびに否定的に特殊化する。機能は、題材がどのように問題の解決に寄与するのかを示すと同時に、その題材が他の機能的に等価な形式のようには処理されないということも明らかにする。こうして機能はシステムの根本問題に繋がり、同時に、その解決方法は、複合化したシステムが構築されるにもかかわらず、長い進化の歴史の中で分化され、そのことで相互に差異化され、自己を特殊化するということを考慮に入れることも可能なのである。
定義化し‐カテゴリーに入れる方法とは異なり、機能的分析はまさに機能的等価物のすべてのクラスに向かう関連問題の徹底化を要請する。そのために引き受ける不明確さは、どっちみち回避することはできない。この不明確さは場合によっては口でうまくごまかすことができるかもしれない――宗教を神聖なもの、聖なるもの、強大なものとの関連で(あるいはそれらに関係するものとして)定義するときのように。だが、そのような定義では分析の進行はたちまち停滞してしまう。そうした方法では宗教体験自体に、つまりその対象にあまりにも急速に近づきすぎ、その結果短絡してしまうのだ。そうではなく、機能的分析は外部との繋がりに、概念の多面的応用性に、かつ他の対象領域における理論的諸経験の輸入に価値を置く、そういう距離を取った概念性を好む。それにより機能的分析はその題材との関連のなかで解体能力と再結合能力を高めていくのである。
このような方法は科学理論的に、また果たしてどのような条件下で正当化されうるものなのか、という問題についてはここでは触れない。我われはそれを実践してみて、そうすることでまず経験を積んでみよう。そしてそのような経験が集められた段階で、後から科学理論はそのための根拠を提示することができるかもしれない。
宗教という概念を機能的に規定する試みがいくつかあるが、それらのいくつかは前もって排除しておかねばならない。なぜならそれらはデータと矛盾していたり、あるいはあまりに無造作に、対象につかみかかろうとしているからだ。とくに宗教はシステムを統合化する機能を有しているという仮定は、データと矛盾する。なぜならば明らかにシステムを破壊する、あるいは解体をうながす宗教的運動もまた存在するからだ。宗教的諸経験は所与の社会的秩序を支持もするし、また問題にもする。各個人を肯定的態度へも導くし、また否定的態度へも導くことができる。また建設的に作用することも破壊的に作用することもある。あるいはまた宗教的諸経験は、あるものから別のものへと変化することもある。それにもかかわらず、宗教はとにかく統合化する機能をもっていると前提する者は、この事実状況を前にすると、宗教は現代社会においては全社会システムの領域での、あらゆる機能を喪失してしまったという確信を抱いてしまうことになるだろう。だが、それは上記概念の誤った構成の帰結、あまりに厳しく限定された機能理解の結果でしかないのではなかろうか。
宗教は解釈する機能を有しているとする理解はあまりにも単純すぎる。宗教が不明確で多義的な、また捉え難い事態の解釈並びにその明確化に係わっているということについては、異論のないところである。そこでは解釈に必要性が、つまり不明確な事態の出現ということが、素朴にかつ非分析的に前提されている。そうしたことは日常生活の地平ならびに解釈者の地平に対応している。しかし機能的分析はそのような解釈の貧困をたんに実存的に採用し、そのままにしておくことで満足することはできない。というのは多義性はシステム構造の相関概念として、あるいは、さらに戦略的に選ばれた操作の要件として、増大したり、もしくは減少せざるをえないからである。おそらくたんに論理的操作あるいは言語的操作の要件が問題なのかも知れない。あるいは十分に興味のある、精神的運動に発生した周囲世界への欲求がデザインの適当な設計技術によって満足させられ、または抑制されねばならないという、そうした欲求が問題なのかもしれない。それとも多義性という隠喩は、高位の公職において、その経歴上の成果がどのように使用されるのかを暗示するだけなのかもしれない。
このような観点が議論のなかに入ってくると、さらに解明し定義することもせず、最終の事物の捉え難さ、および不可知性に引きこもることは困難になる。確かに神学的にもつぎのことは容易に論証できるのではなかろうか。すなわち、成立したもの一切は、それ自体よりも複雑である原因を前提としており、したがって、成立したものはその成立を、創造されたものはその創造者を、十分には捉えることはできず、多義性という術語を捉え難いものの最高性のために用いるようになるということである。しかし知っておかなければならならいことは、進化論がこの間、この前提をまさに裏返しにしてしまい、条件づけられた選択制の過程を把握しようとしているということである。またこの過程は、複合的なシステムがそれ自身ほど複雑でない諸条件から、どのように発生するかを理解させてくれるのである。このような思考モデルが存在し、かつそのような前提を基礎にして科学的に成果をあげる研究がおこなわれるならば、古いモデルはその決定的な自明性を喪失するだろう。」ニコラス・ルーマン『宗教社会学』土方昭・三瓶憲彦訳、新泉社、1999.pp.10-12.(原著:Funktion der religion von Niklas Luhmann,1977. Suhrkamp Verlag, Frankfurt)
ウ~ん、やっぱり翻訳がゴツゴツの文章だな。素人の読者がこれを読んで理解できるとは思えない。こなしてルーマンが何を言いたいのか、書いてみたいがちょっと待ってね。