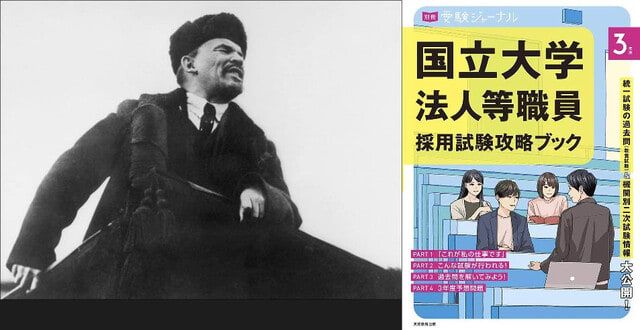A.母と娘の巡業旅
「ステージママ」なる言葉が、若い芸能人の卵を密着して売り出そうとする母親として知られるようになったのは、10歳の美空ひばりとその母・喜美枝さんのイメージが強く反映していた。なにしろ歌手はまだ小学生である。プロを目指すひばりは母親と一緒でなければなにもできない。戦後間もなくのまだテレビなどない時代、童謡歌手ではなく大人の歌を唄って巡業の旅をしなければ名も知られずお金も稼げない。加藤喜美枝さんは、東京山谷の育ちだが、夫の出征中も魚屋を支え子どもを育てるたくましさで、戦後すぐ娘が唄の才能をもつと信じて、この子を芸能界に売り出すことに情熱を燃やしたという。そういうことを考える親子は、たくさんいるだろうけれど、何もない焼け跡闇市の戦後に、本気で少女歌手でプロになれると思うのは、かなり現実離れしているだろう。第一、町の魚屋の子にはちゃんとした音楽教育を受けるチャンスなどない。
進駐軍の占領下にある横浜周辺は、米軍キャンプもあり歌手が唄う機会はあるが、アメリカ兵の求める音楽は当時のスウィング・ジャズである。やがてデビューしてからのひばりは、必要に迫られて英語でジャズも歌うようになるが、得意のレパートリーは日本の歌謡ヒット曲である。子どもが大人の歌を唄うのはまだ奇異の目で見られた。小学生にあんな歌を唄わせて、金を稼ごうなんてひどい親だと見る人もいたし、当の芸能界やレコード会社の幹部もそう考えた。
「そんなふうに、正規のルートで歌謡界に入ろうとしても、「いかがなものですかな?」と首を傾げられてしまうのだった。けっきょく、場末の劇場か田舎まわりの巡業で、職業歌手の前歌を歌うことだけしか、道はのこされていなかった。
〽星の流れに 身を占って
どこをねぐらの 今日の宿 (『星の流れに』清水みのる作詞 利根一郎作曲)
菊池章子の唄う『星の流れに』のデカダンスなメロディが、月収1800円ベースの生活苦の街に哀愁をかなでた1947(昭和22)年春、ひばりは、漫談の井口静波と俗曲の音丸夫妻の一座に加わって中国から四国への巡業に出発した。
そのころ、父親の増吉氏より母親の喜美枝さんのほうが、娘を歌手にすることに夢中になっていた。増吉氏にしてみれば、「美空楽団」の結成も一種の道楽だった。娘をプロの芸人にしようなどとは毛頭考えていなかった。だから、異常にハッスルしはじめた喜美枝さんと夫婦喧嘩になった。
「お前は和枝を河原コジキにするって、ずいぶん怒鳴られました。うちの人のガンコときたら、なみや、大ていじゃないんですからね。出てけバカヤローって、そのへんにあるものがとんでくる。ゲンコツが飛んでくる……」
だが喜美枝さんも負けず劣らず頑固だった。(この子は必ず日本一の歌手になる)という天の啓示のような想念に、母親はとり憑かれていた。それは信仰にも似た強さで喜美枝さんをとらえ、あの戦火の日々の闘魂をふるい立たせた。四国への旅と聞いて渋い顔をする増吉氏をやっとのことでくどき落として、喜美枝さんはひばりと母子二人、巡業に旅立っていった。
その巡業最中の四月二八日、四国の山の中で、ひばりにとって一生の運命を決定する事件がおこった。
……白い飛沫をあげて岩をかむ川の流れを、ひばりはバスの窓に頭をおしつけて、ぼんやり眺めていた。四国山脈をぬって走る山道だった。雨もよいの空は澱んでいた。さみしい風景だった。
ずっと立ちどおしで、足が痛くて、窓の外をみつめているうちに涙がこぼれてきた。子供心を、見知らぬ土地の孤独がしめつけた。そのとたんだった。からだが宙にさらわれ、天と地がぐるりと逆さになって、そのまま真っ暗な奈落に落ちていった。旧坂を下っていたバスがトラックと衝突したのである。
音丸の話――
「大杉という駅の近くにさしかかったとき、トンネルを出て、坂道を下っていったのですが、左手が崖になっていてその向こうに、駅が見えました。運転手がそちらの方をちょっとわき見したらしいのですね。目の前にいきなりトラックがあらわれて、あわててハンドルを切ったのですが、間に合わなくて、ぶつかってしまったのです。私たちのバスは、左手の崖に、横倒しになって落ちました」
「私は座席から床に投げ出されたのですが、不思議とケガをしませんでした。窓から外にはい出しました。見ると、和枝ちゃんが、血だらけになって倒れていました。バスの中から引き出して、近くの民家に運びこみました。息をしているかいないかという仮死状態でした。もう1人重傷だったのが女の車掌さんで、この人はバスの中から救い出した時は死んでいました。この車掌さんと和枝ちゃんと、二人を土間に寝かせて、むしろをかけようとしたのです。あ、ひどいことをするなと思ったとき、お母さんが、まだ死んでいない!と叫んで、和枝ちゃんのむしろをはねのけたのです。
お医者さんが来て人工呼吸をして、やがて息をふきかえしました。右手首のところを切り、胸や、頭を強くうっているようでした。押すとゴボッゴボッと音がしました。和枝ちゃんは、文字通り九死に一生を得て、二週間くらい高知の病院で治療してから横浜に帰っていきました」
「自己の起こる前、和枝ちゃんは一番うしろの座席に座っていて、窓に顔をおしつけて外の景色を眺めていました。そのうちに、涙をポロポロ流していたのです。どうしたのときいても、ウウンというだけで、黙ってまたポロポロ涙を流していました。どうしたのかわかりませんでしたが、和枝ちゃんて、そんな子供だったのです。おとなしくじっとしているのです。まるで、何かに耐えているような大人っぽい表情でいつも黙っているのです。あの時も何かを感じて涙を流していたのでしょうね」
横浜の家に帰って敷居をまたぐと、増吉氏が鬼のような顔をして待っていた。いきなり、喜美枝さんの横面をなぐりつけて、「もう金輪際、和枝には歌をうたわせないぞ」と怒鳴りつけた。
「ええ、そのときは私もあきらめてましたね。これ以上、うちの人に無理はいえないって。でもこういってみたんです。じゃあ、和枝の気持ちをきいてちょうだい。この子が納得したら、もうぷっつり芸事はやめさせます」
増吉氏が、歌手なんかやめて学校に行きなというと、ひばりは大声をあげて泣きだした。「いやだい、いやだい」いつまでも泣きやまない。とうとう根負けをした父親は「じゃ、勝手にしな」とさじを投げた。
ひばりの話――
「私の人生のテーマはそのとき決りました。歌手になれないなら、自殺しちゃおうって思ったんです。10歳でした。そんな小さな子供のくせに、そう思いました。神さまってものがあるのかないのか、私にはわからないけど、あの四国の事故で、死んでいたはずの生命が助かったときに、思ったんです。私の命を救ってくれた、運命みたいなものがあるにちがいないって。私は歌い手になるために生まれてきたんだ、だから神様が、生命を救ってくれたんだって」
ひばりの右の手首には、いまでもその時の傷跡がくっきりと残っている。」竹中労『完本 美空ひばり』ちくま文庫、2005年。pp.48-52.
このエピソードは、竹中労の思い入れもあるが、美空ひばりが父母の意志をこえて、プロの歌手になる覚悟を決めた体験として語られる。やはりただものではない天才少女だったのだろう。
「1948(昭和23)年五月一日、ひばりは、横浜国際劇場で、小唄勝太郎の前歌をうたった。それが、いわば職業歌手としての本格的なデビューということになる。
横浜国際劇場は、戦後になって桑島組という土建屋が建てた新興劇場だった。鉄筋コンクリート建て一回の身で2000名の収容能力である。当時の横浜では、超一流の劇場だった。1947年5月に開場して、第一回の公演はSKDのショー、幸四郎、海老蔵、三津五郎の三番叟でこけら落としをやった。それを皮切りに、主として実演を興行、横浜一の入りを誇った。歌舞伎、新派、エノケン、ロッパ、歌手も一流のタレントしか出演させなかった。
だから国際から出演の話があったとき、ひばりの母親が「いろいろ苦労ばかり多いので、もう芸能界をよそうと思っていました。そこへ国際からのお話で、せめて一ぺんは立ちたいと思っていた舞台に立てて、もうこれでやめても思い残すことはないと思いました」(「平凡」1949年3月号)といったのも当然だった。
福島通人(当時横浜国際劇場支配人)の話――
「ひばりちゃんの国際出演は、藤山一郎、笠置シヅ子、小唄勝太郎などと一緒でした。勝太郎さんが、自分の前座に、手を引いて出て来てくれる童謡の歌える子供がほしいという要求で、ひばりちゃんが出てきたわけです。私も相当興業界に顔があったから、東京のレコード会社などへたのめば、童謡歌手の一人や二人は連れてこれるのだが、せっかく横浜でやっているのだから地元の人間をと考えた。そしたら、劇場に出入りしている関という男が、それなら、うってつけの子供がいるといって連れてきたのがひばりちゃんでした。
リハーサルもなにもせず、ぶっつけで舞台に上げたら、いきなり大人の歌――笠置シヅ子の『セコハン娘』を唄いだしたのには驚きました。それがまた受けに受けて、しかも勝太郎さんがいい人で、別に文句もいわずニコニコして手を引かれて、袖から現れたのでホッとしたものです。その時のひばりちゃんのギャラは、一日300円から500円ぐらいでしたね。藤山、笠置クラスが楽団こみで五万円くらいの時代です」
「この興業がきっかけになって、ひばりちゃんをあずかることになりました。これは素質のある大変な子になると思ったので、すぐ横浜日劇歌劇団の専属みたいな形にして、めったに外へは出さなかったのです。特に東京へは、まともな舞台以外は出すまいと決心しました。専属の半年くらい、横浜国際では、少女歌劇の前座などに、ぽつぽつと使ってました。
そしてその年の暮れに、浅草国際でテイチク祭が開かれるのを知って、旧知の山崎プロデューサーに無理矢理たのんで、強引に飛び入りを承知させたのです。たまたま『星の流れに』の菊池章子が病欠してアナがあいたのも幸運でしたが、東京進出はちゃんとした舞台でなければいけないという願いが、まずかなえられたわけです。はたせるかな国際の出演では大人気で、続いてすぐ日劇の公演にも口がかかってきました」
小唄勝太郎の話――
「前唄に童謡歌手を出したらという案は、私がいいだしたのか福島さんがいいだしたのか、よく憶えていません。私はその時長い振袖の着物を着て出るので、手を引いて出てくれる女の子が欲しいと言ったのだと思います。そして福島さんが連れてきたのが、美空ひばりちゃんだったのです。無口で、おとなびた感じの娘さんでした。ところが歌いだしてみると、これが笠置さんや岡晴夫さんの真似をした歌で、すごくうまいんですよね。アッと驚きました。子供さんの前唄だから、童謡をうたうものとばかり思っていたので、ほんとにビックリしました」
「ええ、そのころは少女歌手なんていっても、ひばりちゃんだけだったんです。楽屋でも、あんな小さな子に流行歌なんか歌わせてと、眉をしかめる人もいました。でも、私はこう思ったんですよ。子供が大人の歌をうたって悪い理屈は、どこにもないんですよね。それに戦争が負けて、子どもが喜んで歌う歌なんか一つもなかったでしょう。キンコンカンっていう『鐘の鳴る丘』ね、あのくらいじゃなかったかしら。だからおやめなさい、趣味が悪いからっていう人もいましたけれど、私は、ずっとひばりちゃんに前唄をうたってもらうことにしたんです」
〽みなさんどなたも 私のことを セコハン娘と だれでもいいます
私のこのドレスも 着物も ハンドバッグも このハイヒールも
何一つ あれもこれも 私の姉さんの お古ばかり
おお だから私はセコハン娘 (『セコハン娘』結城雄二郎作詞 服部良一作曲)
この年四月八日からはじまった「東宝争議」は、八月一九日、アメリカ第一騎兵中隊の兵士と戦車で包囲され、おまけに空には監視のヘリコプター、軍用機が飛ぶというものものしさの中で、四カ月間すわりこんでいた砧スタジオから、争議団は実力で退去させられた。
東北地方では、冷害のために人身売買がさかんに行われ、若い娘たちの家出があいついだ。10月七日、昭電疑獄で芦田内閣総辞職、そのころ銀座街頭では「踊る宗教」が狂ったパレードをくりひろげていた。全学連が結成され(九月十八日)、東条英機以下七人の戦犯が絞首刑になり(十二月二三日)、海のむこうでは、12月十六日中国人民解放軍が北京を無血占領して社会主義革命を現実化していた。
動乱する世相を反映するように、笠置シヅ子のうたう「東京ブギ」の絶叫が、「セコハン娘」の投げやりな哀調が巷の空気をゆすっていた。庶民大衆は占領軍のセコハンの救援物資で、ほそぼそと生命をつないでいた。カストリ焼酎を飲んで、目がつぶれたり死んだりするものが多かった。そのころ新宿で復活したムーラン・ルージュで、楠トシエ、春日八郎が唄い、市村俊幸、由利徹、若水ヤエ子、左卜全などのコメディアンが活躍した。
『太陽を食べたネズミの話』(1947年3月)ではじまり、『国定忠治それまで物語』(1949年6月)で終わった戦後ムーランは、私の青春とともにあった。中江良夫の『にしん場』(1947年11月)、森繁久彌が登場したころから外語(*現・東京外大)の「怠学生」であった私はムーランに通いつめ、小柳ナナ子の肉体美や明日待子の美貌にうつつをぬかしていた。
ムーランの裏の尾津組のマーケットで、イカの塩辛を肴にカストリを飲んでいる森繫のすがたを、何度も見かけた。そのころから饒舌であった森繁は、虚実とりまぜて意表に出る話術で、人々を煙にまいていた。鼻をつくアセチレンガスの灯の下で、酔えば天鼓のごとく高らかに、またうらぶれて低く哀しくうたう森繁ぶしを、私は戦後の最もなつかしい思い出の一つとして胸の底にとどめている。」竹中労『完本 美空ひばり』ちくま文庫、2005年。pp.56-60.
「セコハン娘」がどういう歌か、ぼくはネットで聴くことができた。なるほど、コミカルソングではあるが、これを小学生が唄ったら、どんなに上手くても、教育的公序良俗を重んじる当時の良識派からは、なんと大人びた親の操り人形だと鼻白む人は多かっただろうと思う。そこをひばり母娘はまず、乗り超えなければならなかった。

B.半世紀逃亡した彼
1974~5年に連続企業爆破事件が起こり、指名手配されて49年間逃走していたとみられる桐島聡という人物が、鎌倉市の病院で末期がんのため入院して、本人だと明かし今日の朝、死亡したというニュースが流れた。新聞に、本人であれば彼は広島県出身で当年70歳。高校を出て東京の明治学院大学に入学とあった。え?ぼくよりも4年若いから、大学時代にすれ違っていた可能性はあまりないが、実は同じ頃同じ学部にいたやはり連続爆破犯として逮捕され死刑になった男がいたのは知っている。たぶん「東アジア反日武装戦線」を名乗る秘密グループとのかかわりがあの頃の大学のつながりで、あったのだろうと推測される。
「指名手配「桐島聡」名乗る男 「最期は本名で迎えたい」入院前 神奈川で生活か
1974年~75年に起きた連続企業爆破事件の一つに関与したとして、爆発物取締規則違反容疑で指名手配されていた過激派「東アジア反日武装戦線」のメンバー桐島聡容疑者(70)を名乗る男が入院先の神奈川県の病院で「最期は本名で迎えたい」と話していたことが、そうさかんけいしゃへの取材で分かった。男が入院前、同県の工務店に勤務していたことも判明。同県内で逃亡生活を送っていた可能性があり、警視庁公安部は詳しく調べるとともに、DNA鑑定などによる本人確認を急いでいる。
捜査関係者によると、男は入院前、少なくとも数年間、神奈川県内の工務店で働いていた。末期がんを患っており、今月、職場の同僚に付き添われて同県鎌倉市の病院を訪れた。入院時、運転免許証や健康保険証など身分を示すものは所持しておらず、当初は別の名前を口にしたが、「最期は本名で迎えたい」と話し、自身を桐島聡だと名乗ったという。
25日から公安部が事情聴取しているが重篤といい、本人と確認された場合でも任意で捜査を続けるとみられる。
男は桐島容疑者の家族の詳しい情報を話し、身長などの身体的特徴も一致している。公安部は、男が長年にわたり偽名を使って工務店で働いていたとみて、調べている。
東アジア反日武装戦線は、桐島容疑者が所属する「さそり」を含む「狼」「大地の牙」の3グループで構成。8人が死亡、約380人が重軽傷を負った74年8月の三菱重工ビル爆破など、企業を標的とする爆破事件を次々と起こした。
一連の事件では、桐島容疑者を除く9人が逮捕された。ただ、佐々木規夫(75)、大道寺あや子(75)両容疑者は逮捕後、日本赤軍のハイジャック事件などによる超法規的措置で釈放されたため、現在も逃亡している。
桐島容疑者は75年4月、東京・銀座は韓国産業経済研究所に手製爆弾を仕掛け、爆発させたとして、爆発物取締罰則違反容疑で同年5月に指名手配された。共犯者として国際手配された大道寺容疑者が逃亡中のため、時効が停止されている。
70年代から「長い闘い」公安OB衝撃
「死んでいると思っていた。一体どうやって生活していたのだろうか」。かつて桐島容疑者の行方を追った警視庁公安部OBの男性も既に70代。桐島容疑者を名乗る男が見つかったことに衝撃を隠せない様子で当時を振り返った。
1974年8月30日。東京・丸の内近くの勤務先で書類作業をしていると、突然耳をつんざく爆音が響いた。70年安保闘争が収束し、連合赤軍も壊滅するなど、過激派の活動もやや沈静化していた時期だった。三菱重工本社前に臨場すると「辺り一面血だらけだった。倒れている人や、片脚がない女性もいた」。
桐島容疑者がメンバーの東アジア反日武装戦線は、爆弾製造の方法などを記した「腹腹時計」を地下出版し、海外進出する企業を「侵略企業」と非難して爆弾闘争を主張。三菱重工を皮切りに、企業に次々と爆弾を仕掛けた。男性も極左暴力取締本部に取り立てられ、そこから同グループメンバーとの「長い闘い」が始まった。
80年代に入っても捜査は続いたが、桐島容疑者に近い人物から聞いた「あいつはもともと意識が低かった。今ごろは人民の海に紛れて普通に暮らしているだろう」との言葉が今も記憶の奥底に残っている。
手配写真では、長髪で笑顔を見せていた桐島容疑者。桐島容疑者を名乗る男の写真を見た現職捜査幹部は「面影はなかった」と明かす。その影を追い続けた公安部OBの男性は複雑な心境を吐露した。「逃走に一生をささげた人生を思うと、哀れみも覚える」」東京新聞2024年1月28日朝刊23面、社会欄。
半世紀という時間が経って、あの「過激派」が跳梁した時代のことは、今の人たちには想像もつかない異様さとしか思えないだろう。しかし、あの時代を大学生として生きていたぼくには、他人事として見過ごすことは難しい。
「ステージママ」なる言葉が、若い芸能人の卵を密着して売り出そうとする母親として知られるようになったのは、10歳の美空ひばりとその母・喜美枝さんのイメージが強く反映していた。なにしろ歌手はまだ小学生である。プロを目指すひばりは母親と一緒でなければなにもできない。戦後間もなくのまだテレビなどない時代、童謡歌手ではなく大人の歌を唄って巡業の旅をしなければ名も知られずお金も稼げない。加藤喜美枝さんは、東京山谷の育ちだが、夫の出征中も魚屋を支え子どもを育てるたくましさで、戦後すぐ娘が唄の才能をもつと信じて、この子を芸能界に売り出すことに情熱を燃やしたという。そういうことを考える親子は、たくさんいるだろうけれど、何もない焼け跡闇市の戦後に、本気で少女歌手でプロになれると思うのは、かなり現実離れしているだろう。第一、町の魚屋の子にはちゃんとした音楽教育を受けるチャンスなどない。
進駐軍の占領下にある横浜周辺は、米軍キャンプもあり歌手が唄う機会はあるが、アメリカ兵の求める音楽は当時のスウィング・ジャズである。やがてデビューしてからのひばりは、必要に迫られて英語でジャズも歌うようになるが、得意のレパートリーは日本の歌謡ヒット曲である。子どもが大人の歌を唄うのはまだ奇異の目で見られた。小学生にあんな歌を唄わせて、金を稼ごうなんてひどい親だと見る人もいたし、当の芸能界やレコード会社の幹部もそう考えた。
「そんなふうに、正規のルートで歌謡界に入ろうとしても、「いかがなものですかな?」と首を傾げられてしまうのだった。けっきょく、場末の劇場か田舎まわりの巡業で、職業歌手の前歌を歌うことだけしか、道はのこされていなかった。
〽星の流れに 身を占って
どこをねぐらの 今日の宿 (『星の流れに』清水みのる作詞 利根一郎作曲)
菊池章子の唄う『星の流れに』のデカダンスなメロディが、月収1800円ベースの生活苦の街に哀愁をかなでた1947(昭和22)年春、ひばりは、漫談の井口静波と俗曲の音丸夫妻の一座に加わって中国から四国への巡業に出発した。
そのころ、父親の増吉氏より母親の喜美枝さんのほうが、娘を歌手にすることに夢中になっていた。増吉氏にしてみれば、「美空楽団」の結成も一種の道楽だった。娘をプロの芸人にしようなどとは毛頭考えていなかった。だから、異常にハッスルしはじめた喜美枝さんと夫婦喧嘩になった。
「お前は和枝を河原コジキにするって、ずいぶん怒鳴られました。うちの人のガンコときたら、なみや、大ていじゃないんですからね。出てけバカヤローって、そのへんにあるものがとんでくる。ゲンコツが飛んでくる……」
だが喜美枝さんも負けず劣らず頑固だった。(この子は必ず日本一の歌手になる)という天の啓示のような想念に、母親はとり憑かれていた。それは信仰にも似た強さで喜美枝さんをとらえ、あの戦火の日々の闘魂をふるい立たせた。四国への旅と聞いて渋い顔をする増吉氏をやっとのことでくどき落として、喜美枝さんはひばりと母子二人、巡業に旅立っていった。
その巡業最中の四月二八日、四国の山の中で、ひばりにとって一生の運命を決定する事件がおこった。
……白い飛沫をあげて岩をかむ川の流れを、ひばりはバスの窓に頭をおしつけて、ぼんやり眺めていた。四国山脈をぬって走る山道だった。雨もよいの空は澱んでいた。さみしい風景だった。
ずっと立ちどおしで、足が痛くて、窓の外をみつめているうちに涙がこぼれてきた。子供心を、見知らぬ土地の孤独がしめつけた。そのとたんだった。からだが宙にさらわれ、天と地がぐるりと逆さになって、そのまま真っ暗な奈落に落ちていった。旧坂を下っていたバスがトラックと衝突したのである。
音丸の話――
「大杉という駅の近くにさしかかったとき、トンネルを出て、坂道を下っていったのですが、左手が崖になっていてその向こうに、駅が見えました。運転手がそちらの方をちょっとわき見したらしいのですね。目の前にいきなりトラックがあらわれて、あわててハンドルを切ったのですが、間に合わなくて、ぶつかってしまったのです。私たちのバスは、左手の崖に、横倒しになって落ちました」
「私は座席から床に投げ出されたのですが、不思議とケガをしませんでした。窓から外にはい出しました。見ると、和枝ちゃんが、血だらけになって倒れていました。バスの中から引き出して、近くの民家に運びこみました。息をしているかいないかという仮死状態でした。もう1人重傷だったのが女の車掌さんで、この人はバスの中から救い出した時は死んでいました。この車掌さんと和枝ちゃんと、二人を土間に寝かせて、むしろをかけようとしたのです。あ、ひどいことをするなと思ったとき、お母さんが、まだ死んでいない!と叫んで、和枝ちゃんのむしろをはねのけたのです。
お医者さんが来て人工呼吸をして、やがて息をふきかえしました。右手首のところを切り、胸や、頭を強くうっているようでした。押すとゴボッゴボッと音がしました。和枝ちゃんは、文字通り九死に一生を得て、二週間くらい高知の病院で治療してから横浜に帰っていきました」
「自己の起こる前、和枝ちゃんは一番うしろの座席に座っていて、窓に顔をおしつけて外の景色を眺めていました。そのうちに、涙をポロポロ流していたのです。どうしたのときいても、ウウンというだけで、黙ってまたポロポロ涙を流していました。どうしたのかわかりませんでしたが、和枝ちゃんて、そんな子供だったのです。おとなしくじっとしているのです。まるで、何かに耐えているような大人っぽい表情でいつも黙っているのです。あの時も何かを感じて涙を流していたのでしょうね」
横浜の家に帰って敷居をまたぐと、増吉氏が鬼のような顔をして待っていた。いきなり、喜美枝さんの横面をなぐりつけて、「もう金輪際、和枝には歌をうたわせないぞ」と怒鳴りつけた。
「ええ、そのときは私もあきらめてましたね。これ以上、うちの人に無理はいえないって。でもこういってみたんです。じゃあ、和枝の気持ちをきいてちょうだい。この子が納得したら、もうぷっつり芸事はやめさせます」
増吉氏が、歌手なんかやめて学校に行きなというと、ひばりは大声をあげて泣きだした。「いやだい、いやだい」いつまでも泣きやまない。とうとう根負けをした父親は「じゃ、勝手にしな」とさじを投げた。
ひばりの話――
「私の人生のテーマはそのとき決りました。歌手になれないなら、自殺しちゃおうって思ったんです。10歳でした。そんな小さな子供のくせに、そう思いました。神さまってものがあるのかないのか、私にはわからないけど、あの四国の事故で、死んでいたはずの生命が助かったときに、思ったんです。私の命を救ってくれた、運命みたいなものがあるにちがいないって。私は歌い手になるために生まれてきたんだ、だから神様が、生命を救ってくれたんだって」
ひばりの右の手首には、いまでもその時の傷跡がくっきりと残っている。」竹中労『完本 美空ひばり』ちくま文庫、2005年。pp.48-52.
このエピソードは、竹中労の思い入れもあるが、美空ひばりが父母の意志をこえて、プロの歌手になる覚悟を決めた体験として語られる。やはりただものではない天才少女だったのだろう。
「1948(昭和23)年五月一日、ひばりは、横浜国際劇場で、小唄勝太郎の前歌をうたった。それが、いわば職業歌手としての本格的なデビューということになる。
横浜国際劇場は、戦後になって桑島組という土建屋が建てた新興劇場だった。鉄筋コンクリート建て一回の身で2000名の収容能力である。当時の横浜では、超一流の劇場だった。1947年5月に開場して、第一回の公演はSKDのショー、幸四郎、海老蔵、三津五郎の三番叟でこけら落としをやった。それを皮切りに、主として実演を興行、横浜一の入りを誇った。歌舞伎、新派、エノケン、ロッパ、歌手も一流のタレントしか出演させなかった。
だから国際から出演の話があったとき、ひばりの母親が「いろいろ苦労ばかり多いので、もう芸能界をよそうと思っていました。そこへ国際からのお話で、せめて一ぺんは立ちたいと思っていた舞台に立てて、もうこれでやめても思い残すことはないと思いました」(「平凡」1949年3月号)といったのも当然だった。
福島通人(当時横浜国際劇場支配人)の話――
「ひばりちゃんの国際出演は、藤山一郎、笠置シヅ子、小唄勝太郎などと一緒でした。勝太郎さんが、自分の前座に、手を引いて出て来てくれる童謡の歌える子供がほしいという要求で、ひばりちゃんが出てきたわけです。私も相当興業界に顔があったから、東京のレコード会社などへたのめば、童謡歌手の一人や二人は連れてこれるのだが、せっかく横浜でやっているのだから地元の人間をと考えた。そしたら、劇場に出入りしている関という男が、それなら、うってつけの子供がいるといって連れてきたのがひばりちゃんでした。
リハーサルもなにもせず、ぶっつけで舞台に上げたら、いきなり大人の歌――笠置シヅ子の『セコハン娘』を唄いだしたのには驚きました。それがまた受けに受けて、しかも勝太郎さんがいい人で、別に文句もいわずニコニコして手を引かれて、袖から現れたのでホッとしたものです。その時のひばりちゃんのギャラは、一日300円から500円ぐらいでしたね。藤山、笠置クラスが楽団こみで五万円くらいの時代です」
「この興業がきっかけになって、ひばりちゃんをあずかることになりました。これは素質のある大変な子になると思ったので、すぐ横浜日劇歌劇団の専属みたいな形にして、めったに外へは出さなかったのです。特に東京へは、まともな舞台以外は出すまいと決心しました。専属の半年くらい、横浜国際では、少女歌劇の前座などに、ぽつぽつと使ってました。
そしてその年の暮れに、浅草国際でテイチク祭が開かれるのを知って、旧知の山崎プロデューサーに無理矢理たのんで、強引に飛び入りを承知させたのです。たまたま『星の流れに』の菊池章子が病欠してアナがあいたのも幸運でしたが、東京進出はちゃんとした舞台でなければいけないという願いが、まずかなえられたわけです。はたせるかな国際の出演では大人気で、続いてすぐ日劇の公演にも口がかかってきました」
小唄勝太郎の話――
「前唄に童謡歌手を出したらという案は、私がいいだしたのか福島さんがいいだしたのか、よく憶えていません。私はその時長い振袖の着物を着て出るので、手を引いて出てくれる女の子が欲しいと言ったのだと思います。そして福島さんが連れてきたのが、美空ひばりちゃんだったのです。無口で、おとなびた感じの娘さんでした。ところが歌いだしてみると、これが笠置さんや岡晴夫さんの真似をした歌で、すごくうまいんですよね。アッと驚きました。子供さんの前唄だから、童謡をうたうものとばかり思っていたので、ほんとにビックリしました」
「ええ、そのころは少女歌手なんていっても、ひばりちゃんだけだったんです。楽屋でも、あんな小さな子に流行歌なんか歌わせてと、眉をしかめる人もいました。でも、私はこう思ったんですよ。子供が大人の歌をうたって悪い理屈は、どこにもないんですよね。それに戦争が負けて、子どもが喜んで歌う歌なんか一つもなかったでしょう。キンコンカンっていう『鐘の鳴る丘』ね、あのくらいじゃなかったかしら。だからおやめなさい、趣味が悪いからっていう人もいましたけれど、私は、ずっとひばりちゃんに前唄をうたってもらうことにしたんです」
〽みなさんどなたも 私のことを セコハン娘と だれでもいいます
私のこのドレスも 着物も ハンドバッグも このハイヒールも
何一つ あれもこれも 私の姉さんの お古ばかり
おお だから私はセコハン娘 (『セコハン娘』結城雄二郎作詞 服部良一作曲)
この年四月八日からはじまった「東宝争議」は、八月一九日、アメリカ第一騎兵中隊の兵士と戦車で包囲され、おまけに空には監視のヘリコプター、軍用機が飛ぶというものものしさの中で、四カ月間すわりこんでいた砧スタジオから、争議団は実力で退去させられた。
東北地方では、冷害のために人身売買がさかんに行われ、若い娘たちの家出があいついだ。10月七日、昭電疑獄で芦田内閣総辞職、そのころ銀座街頭では「踊る宗教」が狂ったパレードをくりひろげていた。全学連が結成され(九月十八日)、東条英機以下七人の戦犯が絞首刑になり(十二月二三日)、海のむこうでは、12月十六日中国人民解放軍が北京を無血占領して社会主義革命を現実化していた。
動乱する世相を反映するように、笠置シヅ子のうたう「東京ブギ」の絶叫が、「セコハン娘」の投げやりな哀調が巷の空気をゆすっていた。庶民大衆は占領軍のセコハンの救援物資で、ほそぼそと生命をつないでいた。カストリ焼酎を飲んで、目がつぶれたり死んだりするものが多かった。そのころ新宿で復活したムーラン・ルージュで、楠トシエ、春日八郎が唄い、市村俊幸、由利徹、若水ヤエ子、左卜全などのコメディアンが活躍した。
『太陽を食べたネズミの話』(1947年3月)ではじまり、『国定忠治それまで物語』(1949年6月)で終わった戦後ムーランは、私の青春とともにあった。中江良夫の『にしん場』(1947年11月)、森繁久彌が登場したころから外語(*現・東京外大)の「怠学生」であった私はムーランに通いつめ、小柳ナナ子の肉体美や明日待子の美貌にうつつをぬかしていた。
ムーランの裏の尾津組のマーケットで、イカの塩辛を肴にカストリを飲んでいる森繫のすがたを、何度も見かけた。そのころから饒舌であった森繁は、虚実とりまぜて意表に出る話術で、人々を煙にまいていた。鼻をつくアセチレンガスの灯の下で、酔えば天鼓のごとく高らかに、またうらぶれて低く哀しくうたう森繁ぶしを、私は戦後の最もなつかしい思い出の一つとして胸の底にとどめている。」竹中労『完本 美空ひばり』ちくま文庫、2005年。pp.56-60.
「セコハン娘」がどういう歌か、ぼくはネットで聴くことができた。なるほど、コミカルソングではあるが、これを小学生が唄ったら、どんなに上手くても、教育的公序良俗を重んじる当時の良識派からは、なんと大人びた親の操り人形だと鼻白む人は多かっただろうと思う。そこをひばり母娘はまず、乗り超えなければならなかった。

B.半世紀逃亡した彼
1974~5年に連続企業爆破事件が起こり、指名手配されて49年間逃走していたとみられる桐島聡という人物が、鎌倉市の病院で末期がんのため入院して、本人だと明かし今日の朝、死亡したというニュースが流れた。新聞に、本人であれば彼は広島県出身で当年70歳。高校を出て東京の明治学院大学に入学とあった。え?ぼくよりも4年若いから、大学時代にすれ違っていた可能性はあまりないが、実は同じ頃同じ学部にいたやはり連続爆破犯として逮捕され死刑になった男がいたのは知っている。たぶん「東アジア反日武装戦線」を名乗る秘密グループとのかかわりがあの頃の大学のつながりで、あったのだろうと推測される。
「指名手配「桐島聡」名乗る男 「最期は本名で迎えたい」入院前 神奈川で生活か
1974年~75年に起きた連続企業爆破事件の一つに関与したとして、爆発物取締規則違反容疑で指名手配されていた過激派「東アジア反日武装戦線」のメンバー桐島聡容疑者(70)を名乗る男が入院先の神奈川県の病院で「最期は本名で迎えたい」と話していたことが、そうさかんけいしゃへの取材で分かった。男が入院前、同県の工務店に勤務していたことも判明。同県内で逃亡生活を送っていた可能性があり、警視庁公安部は詳しく調べるとともに、DNA鑑定などによる本人確認を急いでいる。
捜査関係者によると、男は入院前、少なくとも数年間、神奈川県内の工務店で働いていた。末期がんを患っており、今月、職場の同僚に付き添われて同県鎌倉市の病院を訪れた。入院時、運転免許証や健康保険証など身分を示すものは所持しておらず、当初は別の名前を口にしたが、「最期は本名で迎えたい」と話し、自身を桐島聡だと名乗ったという。
25日から公安部が事情聴取しているが重篤といい、本人と確認された場合でも任意で捜査を続けるとみられる。
男は桐島容疑者の家族の詳しい情報を話し、身長などの身体的特徴も一致している。公安部は、男が長年にわたり偽名を使って工務店で働いていたとみて、調べている。
東アジア反日武装戦線は、桐島容疑者が所属する「さそり」を含む「狼」「大地の牙」の3グループで構成。8人が死亡、約380人が重軽傷を負った74年8月の三菱重工ビル爆破など、企業を標的とする爆破事件を次々と起こした。
一連の事件では、桐島容疑者を除く9人が逮捕された。ただ、佐々木規夫(75)、大道寺あや子(75)両容疑者は逮捕後、日本赤軍のハイジャック事件などによる超法規的措置で釈放されたため、現在も逃亡している。
桐島容疑者は75年4月、東京・銀座は韓国産業経済研究所に手製爆弾を仕掛け、爆発させたとして、爆発物取締罰則違反容疑で同年5月に指名手配された。共犯者として国際手配された大道寺容疑者が逃亡中のため、時効が停止されている。
70年代から「長い闘い」公安OB衝撃
「死んでいると思っていた。一体どうやって生活していたのだろうか」。かつて桐島容疑者の行方を追った警視庁公安部OBの男性も既に70代。桐島容疑者を名乗る男が見つかったことに衝撃を隠せない様子で当時を振り返った。
1974年8月30日。東京・丸の内近くの勤務先で書類作業をしていると、突然耳をつんざく爆音が響いた。70年安保闘争が収束し、連合赤軍も壊滅するなど、過激派の活動もやや沈静化していた時期だった。三菱重工本社前に臨場すると「辺り一面血だらけだった。倒れている人や、片脚がない女性もいた」。
桐島容疑者がメンバーの東アジア反日武装戦線は、爆弾製造の方法などを記した「腹腹時計」を地下出版し、海外進出する企業を「侵略企業」と非難して爆弾闘争を主張。三菱重工を皮切りに、企業に次々と爆弾を仕掛けた。男性も極左暴力取締本部に取り立てられ、そこから同グループメンバーとの「長い闘い」が始まった。
80年代に入っても捜査は続いたが、桐島容疑者に近い人物から聞いた「あいつはもともと意識が低かった。今ごろは人民の海に紛れて普通に暮らしているだろう」との言葉が今も記憶の奥底に残っている。
手配写真では、長髪で笑顔を見せていた桐島容疑者。桐島容疑者を名乗る男の写真を見た現職捜査幹部は「面影はなかった」と明かす。その影を追い続けた公安部OBの男性は複雑な心境を吐露した。「逃走に一生をささげた人生を思うと、哀れみも覚える」」東京新聞2024年1月28日朝刊23面、社会欄。
半世紀という時間が経って、あの「過激派」が跳梁した時代のことは、今の人たちには想像もつかない異様さとしか思えないだろう。しかし、あの時代を大学生として生きていたぼくには、他人事として見過ごすことは難しい。