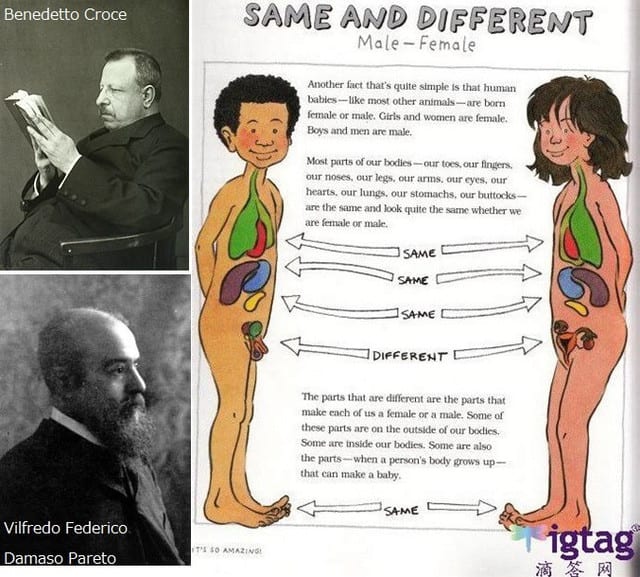A.イギリスの社会思想
戦前の日本の高等教育、つまり旧制高校や旧制大学の教育では、語学と言えば英独仏のどれかを学ぶもので、とくにデカンショと呼ばれた西洋哲学の原書を読めるようになることが、大学生の基礎的教養のように考えられていた(らしい)。実際どれほどの大学生が、カントやヘーゲルやデカルトやショーペンハウエルを原書で読んで理解できたのかは、怪しいかもしれないが、とにかく横文字を読めるのがステータスではあった。今の文科省みたいな、とにかく英語を自在に話せて外国人とサシで会話できるのが語学の価値で、学術的洋書を読むことなどできなくてもいい、という考えは、外国人と直接接する機会などなかった時代には現実的ではなかった。今でも大学で第二外国語として、ドイツ語やフランス語や、なかにはロシア語やスペイン語なども教えるクラスはあるが、これも実用的には英語に比べて格段に無用視されている。要するに、いまは読むことから話すことへ、語学の有用性が移行している。
同時に、グローバル世界の汎用言語として英語の使用頻度が圧倒的に高いという“常識”があって、だから英語だけは話せた方がいいという教育観になっている。でも、少なくとも学問の世界で、とくに社会科学の世界で、英会話が達者であることよりは、洋書が読めることの方がやはり絶対に重要だと思う。できれば英語だけでなく、フランス語かドイツ語が読めることは学問研究上、比較優位性があると思う。20世紀の半ばの時点では、重要な最新文献は翻訳もなく、原典を読めなければ先端の議論に参加できない。数式やデータで結果だけ理解できればよい理系の論文はともかく、社会科学や哲学は言語的読解が正確にできなければ、話にならない。
スチュアート・ヒューズの『大変貌』の主題は、ヨーロッパからアメリカに亡命した社会思想家の問題だから、ドイツ語圏やフランス語圏から英語圏への亡命者の言語の問題もかかわってくる。フランス人のアメリカ亡命者はドイツ語圏よりはるかに少なかった、というから、ドイツ人が英語圏に行ったらどうなるか、がひとつのテーマになるが、ここでは移民国家アメリカではなく、英語の祖国イギリス(イングランド)の哲学に外国人が影響を与えたか、という話である。
「19世紀末以来、イギリス思想の動きは、大陸での動きと局面がずれていた。イングランド人とスコットランド人は、自分たちで決めた特徴的な目的にあった概念だけを外国から借りてきて、独自のコースを歩んでいた。19世紀のはじめ、フランス大革命の反響は、ドイツやそれがもともと起った国にあらわれたほどには、啓蒙への広い疑問を惹き起さなかったので、また、ベンサムと二人のミルの伝統は1789年以前の精神世界から途切れることなく継続していたので、ジョン・スチュアート・ミル以降の数世代の知的闘いは、英仏海峡の向こうのものとは違った次元で起り、違った色調をもっていた。イギリスでは、自由主義と、平明で常識的な種類の実証主義とは、国内産の産物で、哲学的論究の第二の天性となっていた。この二つのものはともに、ジョン・ロックを正統の祖だとしていた。そして、実証主義的姿勢は、ダーウィンの時代の自然科学の勝利によって強化されていた。
この後者の態度の優位に対して、観念論的思想は、動揺し途切れがちな挑戦しかできなかった。厳しい甲冑に身を固めたドイツ観念論は、大陸での最盛期を半世紀も過ぎてからようやくイギリスの大学に到来した――そのとき、それはヘーゲル流の観念論であった。イギリスの観念論的思考様式の受容は、当時にあっても時代遅れのものであった。世紀の転換期に、すでに原型的な観念論と実証主義の双方を経験していた大陸の理論家たち――とくにデュルケームとウェーバー――が、この双方から学びとったものを総合して超えでるような新しい社会思想の準拠を明らかにしはじめていたときに、イギリスでは、F・H・ブラッドレーやバーナード・ポザンキットのような哲学者たちが、強情に抵抗する自国の人たちをヘーゲル哲学に導入しようとなお努力していたのである。
ヘーゲル観念論――あるいは絶対的観念論とも呼ばれる――は、「外国からの輸入品で……イギリスの風景では異国風のもの」とみられた。したがって、それが短期間力をもったのが、容易にしかも永久に力を失ったのも不思議はなかった。観念論的思考様式の退潮と、それに伴うイギリスのもっとも広く生き渡った20世紀思潮の明確化とは、二組の異なった著作家たちの手によって行われた。だが、この二組は、ともに足の地につかぬ抽象を嫌っただけでなく、さらに、ヘーゲル哲学への逸脱の時代をこえて本来的なイギリスの哲学的過去へと戻った点でも共通していた。
まず最初に現れたのは、経済のアルフレッド・マーシャルや社会学のグレアム・ウォ―ラスに典型的にみられるプラグマティクで唯名論的な社会科学であった。19世紀の普遍的理論追求の野望を棄て、マーシャルやウォーラスのような人びとは、個別的で特殊的なものに関心を向けた。かれらはまた、社会改革に深くかかわり、かれらの思想の実践的適用に力を入れていた。同時代の大陸の人びとよりも穏健な目標を追求したかれらは、1900年前後のドイツ人やフランス人、イタリア人がきわめて緊要な問題と考えていた認識論的問題にかかずらうことを拒んだ。イギリスの社会思想家たちは、思弁よりも測定を、認識理論よりも堅固な事実を好んだのである。かれらのもっとも影響力のある達成は、次の世代において、ジョン・メイナード・ケインズの新しい経済学とともに実現されることになった。
絶対的観念論を打破した第二の思想家の一群は、ケンブリッジの哲学者G・E・ムアとバートランド・ラッセルであった。世紀が転換して間もなく公刊された『倫理学原理』Principia Ethicaで、ムアは、「それ自体善なる」ものは「本質的にまったく独自」なものである――それは「現実についてのいかなる断定にも還元され」えない――と主張して、実証主義とヘーゲル哲学の教えの双方を論駁しようとした。この価値の領域と事実(ないし科学)の領域との分離は、これとほとんど同時に行われたマックス・ウェーバーの方法論的宣言と相通じるものであった。このイギリス人とドイツ人とは、二正面作戦を戦うという危険な立場を共にしていたのである。かれらは、一方で、読者に何の断りもなく科学的断言と倫理的断言の間を往復する安易な実証主義的研究に挑戦することが必要だと考えた。他方、かれらは、精神のある領域において、この二つの型の言表が堂々と綜合に達しうるというヘーゲル哲学の考え方を攻撃した。ムアのいうように、「真理を犠牲にして“統一”と“体系”を求めるのは」、「哲学の本務」ではないのであった。
ムアとウェーバーの努力の相似が、これまでほとんど注目されてこなかったのは不思議なことである。かれらの用語とかれらの論じた主題とがひじょうに異なったものであったので、かれらの根本的な知的一致が見過ごされたままになってきたのである。しかし、ふたりは、正しい問いかけ――すなわちまた、これまで哲学者たちが求めないできた問いかけ――を求めたのであり、かつて哲学者たちが問うていた問いの意味を暴露しようとした。ウェーバーの場合は、この手続きは、人間社会の探求のための予備学という形をとった。ムアとその同志たちの場合には、こういう端緒の前提の明確化が、まず最初になすべき主要な仕事になった。ムアのケンブリッジの同僚バートランド・ラッセルの初期の準数学的研究において、哲学は、言語の論理分析という狭い視野に還元され精緻化された。そして、これは、ラッセルのより厳密な継承者たちの研究に引き継がれた。ムアの遺産はもっと開かれたものであった。かれの簡明で直截な議論の仕方と「常識」の尊重とは、かれの影響を受けた学生たちの二世代に、まったく自由に自分たちに興味のあることがらを何でも探究させた。しかし、実際には、大ていのものは、安全で危なげのない論理学と認識論の境界内にとどまった。ムアの仕事に深く触発されたものたちのうちで、ケインズただひとりが第一級の社会思想家になった。
こうして、マーシャルとウォーラスを一つの知的努力のタイプとし、ムアとラッセルをもう一つのタイプにして、かれらは、ロック、ヒューム以来のイギリスの中心的伝統――経験的で唯名論的な――を賦活したのだが、イングランドとスコットランドの諸大学では、ウェーバーやデュルケームが創唱したような哲学的基礎に立つ社会科学は発展しなかった。ケインズは、そういう社会科学の定礎者の役割を演ずることができたはずだが、公務と技術的経済学にエネルギーを注ぐことの方を選んだ。結局、ケインズが友人として助け、財政的に援助までした一人の人物――ルートヴィヒ・ヴィトゲンシュタイン――が、時期的には遅れ、焦立たしい断片の形ではあったが、厳密な哲学的分析と社会の本質についての思弁とを結ぶ視点を、イギリスの学生たちに与えることになった。
ヴィトゲンシュタインは、政治的ないしは「人種的」迫害を逃れてきたものではなかった。ユダヤの出自ではあったが、かれは、その出自のために差別に苦しんだことはなかった。さらに、かれが最終的にイギリスに移住したのは、ドイツでのヒトラーの抬頭に四年先立っていた。しかし、かれがイギリス人の間で果した機能は、まさにアメリカ合衆国における中央ヨーロッパからの亡命者たちの仕事に対応するものであり――影響力という点ではそれに優ってさえいた。
イギリスの教育機関は、外国人に対してアメリカのそれより閉鎖的だった。イギリスの大学が受入れたのは、数の上ではるかに少なかったし、その大部分は文学ないし古典学の教科のもので、1930年代に大陸から亡命した社会科学者については、ほんの一握りのものしか吸収しなかった。それは単に教職のポジションが少かったからだけではなかった。それはまた、イギリスでは正式の大学院教育という考え方がやっと生まれたばかりであったからであり、大学に籍をもつ研究生の大部分は自然科学に特定されていたからであった。その上、社会学の分野は、混迷して沈滞していた。このようなあまり望みのない状況のなかでは、大部分の中央ヨーロッパの学者たちが大西洋を越える方をとったのも当然であった。そしてまた、イギリスに定住した大陸出身者のなかでもっとも影響力のあったそのひとが、純粋に正統的な哲学の分野で仕事をしたひとであり、しかも大学との結びつきが第一次世界大戦前に遡るひとであったのも、不思議ではない。」スチュアート・ヒューズ『大変貌 社会思想の大移動 1930-1965』荒川幾男・生松敬三訳、みすず書房、1978.pp.27-29.
ヒューズは、アメリカの思想史家として20世紀ヨーロッパを見ているので、どうしてもナチスに追われたユダヤ系亡命者のアメリカへの貢献、およびかれらの思想のアメリカでの発展というところに目が行く。そこで繰り返し出てくる名前が、ウェーバー、フロイト、そしてウィトゲンシュタインだが、この3人のうち亡命者といえるのは晩年のフロイトだけで、しかもフロイトもウィトゲンシュタインも移住したのは、アメリカではなくイギリスだったのだから、ヒューズの扱いは少々説明を工夫することになる。

B.誰のために働いているのか?
財務官僚は国家中枢の高級官僚中の官僚といわれている。この人たちは国民への奉仕者として大きな権限を与えられているが、それは時の首相と内閣が、国民から選ばれた国会で多数を占める与党の権力に基づき、政府が決めた方針や政策を忠実に実現することが仕事だからだ。この論理から、首相の意向に忠実に動くことは正当化される。でも、だからといって違法行為や国民に説明できない不正行為をやってよいはずはない。不正行為が発覚しその責任を問われて国会の証人喚問に呼ばれた財務官僚は、誰かの指示や意向を汲んで公文書の改竄をしたのではなく、自分のした不正行為の理由も経緯も説明を拒んだ。これは私は気が狂っていました、という意味か、それともどうしても隠したいことがある、と言っているとしか思えない。
「連立方程式:佐藤 優
二十七日、衆参両院の予算委員会で元財務相理財局長の佐川宣寿氏に対する証人喚問が行われた。森友学園への土地売却に関する公文書が改竄された経緯や自らの関与については、刑事訴追の恐れがあるという理由で証言拒否した。しかし、安倍昭恵首相夫人の関与については、全面的に否定した。佐川氏自身が本件に関する関与を、改竄された公文書を見たか否かという刑事訴追に関係するとは思われない事項に関して証言を拒否したうえで、改竄に関する昭恵氏の関与を否定するのは奇妙だ。なぜなら佐川氏自身が当該公文書を読んだことを含め、事案の全体像に通じていなくては昭恵氏の関与を否定できないからだ。
佐川氏は、首相官邸、財務省と自分を同時に守るという連立方程式をつくって尋問に臨んだ。その目的は、首相官邸と財務省を守れば、自分が刑事責任を追及されることを免れるという希望的観測に基づくものだ。佐川氏には、国民に対する奉仕者である国家公務員だったという意識が希薄だ。自分の生き残りしか考えていない。それだから、有権者による直接選挙によって選ばれた参議院議員、衆議院議員の前で真実を語ることに関心がなかったのだ。今回の証人喚問の結果、国民から超然として存在している元財務官僚の病理が可視化された。徹底的な治療が必要だ。(作家・元外務省主任分析官)」東京新聞2018年3月20日朝刊27面特報欄、本音のコラム。
自分のした行為に責任を取る、とはどういうことかを考えさせる記事もあった。
「成田闘争の象徴 撤去へ:成田空港(千葉県成田市など)の開港を4日後に控えた1978年3月26日、開港に反対する活動家たちが管制塔(高さ約64㍍)に侵入して機器を破壊する「管制塔占拠事件」が起き、開港は2カ月遅れた。あれから40年。成田国際空港会社(NAA)は「成田闘争の象徴」といえるこの建物を、2020年にも取り壊すことを決めた。
成田空港をめぐっては、建設が閣議決定された66年以降、地元農家らの反対運動が活動家を巻き込んで激化。警察官3人が死亡した東峰十字路事件など「成田闘争」が繰り広げられた。
78年3月、航空機への離着陸の指示などを担う管制塔の最上階の16階の管制室に活動家らが侵入。鉄パイプなどで機器を壊し、著類を窓から投げ捨てた。数時間後に逮捕されたが、開港は5月20日まで延期された。
93年2月に高さ約87㍍の新管制塔が北側に建てられた。事件が起きた建物は旧管制塔となり、地上の航空機の誘導などを担うランプコントロールタワーとして使われてきた。しかし、近年は老朽化が進み、雨漏りなど傷みが目立つ。NAAは2020年の運用開始を目指し、今年4月、南側に高さ約60㍍の新ランプコントロールタワーを着工する。運用開始後、旧管制塔を撤去する予定だ。
成田空港は現在、海外115都市、国内18都市を結ぶ。17年の旅客数は計468万人で、過去最多を更新。今月13日には。3本目の滑走路の新設や運用時間の延長に地元自治体などが合意した。
元活動家「管制官に謝りたい」
管制塔占拠事件の中心メンバー17人のうち、管制室まで入ったのは6人。その一人、中川憲一さん(70)=東京都=は当時、会社員だった。「怖い思いをさせて申し訳なかった。当時の管制官に謝りたい」。朝日新聞の取材にそう話した。
「特別な任務をやってくれないか」。数カ月前にそう言われた。任務で走れるようにたばこを断った。刑務所に入ると覚悟し、頭を丸刈りにした。管制室では「人を傷つけないように」と、窓から機器を投げずに書類をばらまいた。
出所後、しばらく日雇いで働き、再び会社員になった。定年まで勤めながら、空港反対運動に時々参加した。元活動家たちには国から1億300万円の損害賠償金を督促され、給与の差し押さえ命令が通知されるなどしたが、インターネットの支援サイトなどで約2千人が寄付してくれた。「心のこもったお金。感謝している」。この10年は、母親の介護で北陸と東京を往復しているという。
管制塔占拠事件を計画した和多田粂夫さん(77)=同=は「開港を延ばし、国に開港をあきらめさせようと思った。ぼくも福井県の農家の出身。農家を守りたいという思いもあった」と降り返る。
逮捕から11年半後に釈放され、出所後は会社勤めをして出版物発送会社の社長にも就いた。事件から40年。当時の反対派の農家の中には、子どもが空港で働いている人もいるという。「地元ではそうやって生きているのが現実」と受け止めている。
いまも反対運動を続けている人がおり、和多田さんは集会などに参加しているが、「もう僕らが外から何か言うものではない」と話す。山梨県にある畑に時々通い、野菜を育てている。(黒川和久)」朝日新聞2018年3月30日夕刊15面社会欄。
成田空港反対闘争は、60年代末から70年代半ばまで、いわゆる新左翼「過激派」が絡んださまざまな事件のなかで、若者中心の大学闘争や武力革命を叫んだ赤軍派事件など観念が先行した運動とは異なる、土地を奪われる農民の生活圏と国家が進める空港建設の対立というリアルな問題に、若者が実力で「支援する」ものだった。管制塔事件は、その象徴的な事件の一つだった。成田闘争の問題は発端で三里塚の農民を説得する努力を怠って、運輸省と政府が強引に強制収用などをすすめたことへの農民の反発に起因する。こじれ切った中で、多くの学生や若い社会人が運動に加わった。革命運動の一つとして党派的に関わった者も混じっていただろうが、多くは土地に生きる農民やその家族の心情に共感して反対運動に参加していたと思う。当時三里塚に行っていた友人を見ていて、運動の主体は農民であって学生はそれを応援しているのだ、という言い分に納得したと同時に、わくわくイヴェントに成田に行ってくるぜ、という軽薄な気分も感じた。闘争の行方を見兼ねた労働経済学者、隅谷三喜男先生たちが、政府と調停に立って反対派との和解をすすめ、計画を部分修正して空港がやっと開港した。
あのときの若者たちももはや70代!事件を知る人もみな老いた。成田空港は日本の玄関として賑わっている。しかし、管制塔を占拠破壊した行為は暴力的違法行為であるから、実行者は逮捕され刑務所に入って責任を取った。正義を信じて行った行為でも、人生にとっては重い責任である。国民の税金や資産を恣意的に動かした不正行為を、権力の意向で免れようとするのが高級官僚であるのなら、重い責任を取ってもらわねばならない。
戦前の日本の高等教育、つまり旧制高校や旧制大学の教育では、語学と言えば英独仏のどれかを学ぶもので、とくにデカンショと呼ばれた西洋哲学の原書を読めるようになることが、大学生の基礎的教養のように考えられていた(らしい)。実際どれほどの大学生が、カントやヘーゲルやデカルトやショーペンハウエルを原書で読んで理解できたのかは、怪しいかもしれないが、とにかく横文字を読めるのがステータスではあった。今の文科省みたいな、とにかく英語を自在に話せて外国人とサシで会話できるのが語学の価値で、学術的洋書を読むことなどできなくてもいい、という考えは、外国人と直接接する機会などなかった時代には現実的ではなかった。今でも大学で第二外国語として、ドイツ語やフランス語や、なかにはロシア語やスペイン語なども教えるクラスはあるが、これも実用的には英語に比べて格段に無用視されている。要するに、いまは読むことから話すことへ、語学の有用性が移行している。
同時に、グローバル世界の汎用言語として英語の使用頻度が圧倒的に高いという“常識”があって、だから英語だけは話せた方がいいという教育観になっている。でも、少なくとも学問の世界で、とくに社会科学の世界で、英会話が達者であることよりは、洋書が読めることの方がやはり絶対に重要だと思う。できれば英語だけでなく、フランス語かドイツ語が読めることは学問研究上、比較優位性があると思う。20世紀の半ばの時点では、重要な最新文献は翻訳もなく、原典を読めなければ先端の議論に参加できない。数式やデータで結果だけ理解できればよい理系の論文はともかく、社会科学や哲学は言語的読解が正確にできなければ、話にならない。
スチュアート・ヒューズの『大変貌』の主題は、ヨーロッパからアメリカに亡命した社会思想家の問題だから、ドイツ語圏やフランス語圏から英語圏への亡命者の言語の問題もかかわってくる。フランス人のアメリカ亡命者はドイツ語圏よりはるかに少なかった、というから、ドイツ人が英語圏に行ったらどうなるか、がひとつのテーマになるが、ここでは移民国家アメリカではなく、英語の祖国イギリス(イングランド)の哲学に外国人が影響を与えたか、という話である。
「19世紀末以来、イギリス思想の動きは、大陸での動きと局面がずれていた。イングランド人とスコットランド人は、自分たちで決めた特徴的な目的にあった概念だけを外国から借りてきて、独自のコースを歩んでいた。19世紀のはじめ、フランス大革命の反響は、ドイツやそれがもともと起った国にあらわれたほどには、啓蒙への広い疑問を惹き起さなかったので、また、ベンサムと二人のミルの伝統は1789年以前の精神世界から途切れることなく継続していたので、ジョン・スチュアート・ミル以降の数世代の知的闘いは、英仏海峡の向こうのものとは違った次元で起り、違った色調をもっていた。イギリスでは、自由主義と、平明で常識的な種類の実証主義とは、国内産の産物で、哲学的論究の第二の天性となっていた。この二つのものはともに、ジョン・ロックを正統の祖だとしていた。そして、実証主義的姿勢は、ダーウィンの時代の自然科学の勝利によって強化されていた。
この後者の態度の優位に対して、観念論的思想は、動揺し途切れがちな挑戦しかできなかった。厳しい甲冑に身を固めたドイツ観念論は、大陸での最盛期を半世紀も過ぎてからようやくイギリスの大学に到来した――そのとき、それはヘーゲル流の観念論であった。イギリスの観念論的思考様式の受容は、当時にあっても時代遅れのものであった。世紀の転換期に、すでに原型的な観念論と実証主義の双方を経験していた大陸の理論家たち――とくにデュルケームとウェーバー――が、この双方から学びとったものを総合して超えでるような新しい社会思想の準拠を明らかにしはじめていたときに、イギリスでは、F・H・ブラッドレーやバーナード・ポザンキットのような哲学者たちが、強情に抵抗する自国の人たちをヘーゲル哲学に導入しようとなお努力していたのである。
ヘーゲル観念論――あるいは絶対的観念論とも呼ばれる――は、「外国からの輸入品で……イギリスの風景では異国風のもの」とみられた。したがって、それが短期間力をもったのが、容易にしかも永久に力を失ったのも不思議はなかった。観念論的思考様式の退潮と、それに伴うイギリスのもっとも広く生き渡った20世紀思潮の明確化とは、二組の異なった著作家たちの手によって行われた。だが、この二組は、ともに足の地につかぬ抽象を嫌っただけでなく、さらに、ヘーゲル哲学への逸脱の時代をこえて本来的なイギリスの哲学的過去へと戻った点でも共通していた。
まず最初に現れたのは、経済のアルフレッド・マーシャルや社会学のグレアム・ウォ―ラスに典型的にみられるプラグマティクで唯名論的な社会科学であった。19世紀の普遍的理論追求の野望を棄て、マーシャルやウォーラスのような人びとは、個別的で特殊的なものに関心を向けた。かれらはまた、社会改革に深くかかわり、かれらの思想の実践的適用に力を入れていた。同時代の大陸の人びとよりも穏健な目標を追求したかれらは、1900年前後のドイツ人やフランス人、イタリア人がきわめて緊要な問題と考えていた認識論的問題にかかずらうことを拒んだ。イギリスの社会思想家たちは、思弁よりも測定を、認識理論よりも堅固な事実を好んだのである。かれらのもっとも影響力のある達成は、次の世代において、ジョン・メイナード・ケインズの新しい経済学とともに実現されることになった。
絶対的観念論を打破した第二の思想家の一群は、ケンブリッジの哲学者G・E・ムアとバートランド・ラッセルであった。世紀が転換して間もなく公刊された『倫理学原理』Principia Ethicaで、ムアは、「それ自体善なる」ものは「本質的にまったく独自」なものである――それは「現実についてのいかなる断定にも還元され」えない――と主張して、実証主義とヘーゲル哲学の教えの双方を論駁しようとした。この価値の領域と事実(ないし科学)の領域との分離は、これとほとんど同時に行われたマックス・ウェーバーの方法論的宣言と相通じるものであった。このイギリス人とドイツ人とは、二正面作戦を戦うという危険な立場を共にしていたのである。かれらは、一方で、読者に何の断りもなく科学的断言と倫理的断言の間を往復する安易な実証主義的研究に挑戦することが必要だと考えた。他方、かれらは、精神のある領域において、この二つの型の言表が堂々と綜合に達しうるというヘーゲル哲学の考え方を攻撃した。ムアのいうように、「真理を犠牲にして“統一”と“体系”を求めるのは」、「哲学の本務」ではないのであった。
ムアとウェーバーの努力の相似が、これまでほとんど注目されてこなかったのは不思議なことである。かれらの用語とかれらの論じた主題とがひじょうに異なったものであったので、かれらの根本的な知的一致が見過ごされたままになってきたのである。しかし、ふたりは、正しい問いかけ――すなわちまた、これまで哲学者たちが求めないできた問いかけ――を求めたのであり、かつて哲学者たちが問うていた問いの意味を暴露しようとした。ウェーバーの場合は、この手続きは、人間社会の探求のための予備学という形をとった。ムアとその同志たちの場合には、こういう端緒の前提の明確化が、まず最初になすべき主要な仕事になった。ムアのケンブリッジの同僚バートランド・ラッセルの初期の準数学的研究において、哲学は、言語の論理分析という狭い視野に還元され精緻化された。そして、これは、ラッセルのより厳密な継承者たちの研究に引き継がれた。ムアの遺産はもっと開かれたものであった。かれの簡明で直截な議論の仕方と「常識」の尊重とは、かれの影響を受けた学生たちの二世代に、まったく自由に自分たちに興味のあることがらを何でも探究させた。しかし、実際には、大ていのものは、安全で危なげのない論理学と認識論の境界内にとどまった。ムアの仕事に深く触発されたものたちのうちで、ケインズただひとりが第一級の社会思想家になった。
こうして、マーシャルとウォーラスを一つの知的努力のタイプとし、ムアとラッセルをもう一つのタイプにして、かれらは、ロック、ヒューム以来のイギリスの中心的伝統――経験的で唯名論的な――を賦活したのだが、イングランドとスコットランドの諸大学では、ウェーバーやデュルケームが創唱したような哲学的基礎に立つ社会科学は発展しなかった。ケインズは、そういう社会科学の定礎者の役割を演ずることができたはずだが、公務と技術的経済学にエネルギーを注ぐことの方を選んだ。結局、ケインズが友人として助け、財政的に援助までした一人の人物――ルートヴィヒ・ヴィトゲンシュタイン――が、時期的には遅れ、焦立たしい断片の形ではあったが、厳密な哲学的分析と社会の本質についての思弁とを結ぶ視点を、イギリスの学生たちに与えることになった。
ヴィトゲンシュタインは、政治的ないしは「人種的」迫害を逃れてきたものではなかった。ユダヤの出自ではあったが、かれは、その出自のために差別に苦しんだことはなかった。さらに、かれが最終的にイギリスに移住したのは、ドイツでのヒトラーの抬頭に四年先立っていた。しかし、かれがイギリス人の間で果した機能は、まさにアメリカ合衆国における中央ヨーロッパからの亡命者たちの仕事に対応するものであり――影響力という点ではそれに優ってさえいた。
イギリスの教育機関は、外国人に対してアメリカのそれより閉鎖的だった。イギリスの大学が受入れたのは、数の上ではるかに少なかったし、その大部分は文学ないし古典学の教科のもので、1930年代に大陸から亡命した社会科学者については、ほんの一握りのものしか吸収しなかった。それは単に教職のポジションが少かったからだけではなかった。それはまた、イギリスでは正式の大学院教育という考え方がやっと生まれたばかりであったからであり、大学に籍をもつ研究生の大部分は自然科学に特定されていたからであった。その上、社会学の分野は、混迷して沈滞していた。このようなあまり望みのない状況のなかでは、大部分の中央ヨーロッパの学者たちが大西洋を越える方をとったのも当然であった。そしてまた、イギリスに定住した大陸出身者のなかでもっとも影響力のあったそのひとが、純粋に正統的な哲学の分野で仕事をしたひとであり、しかも大学との結びつきが第一次世界大戦前に遡るひとであったのも、不思議ではない。」スチュアート・ヒューズ『大変貌 社会思想の大移動 1930-1965』荒川幾男・生松敬三訳、みすず書房、1978.pp.27-29.
ヒューズは、アメリカの思想史家として20世紀ヨーロッパを見ているので、どうしてもナチスに追われたユダヤ系亡命者のアメリカへの貢献、およびかれらの思想のアメリカでの発展というところに目が行く。そこで繰り返し出てくる名前が、ウェーバー、フロイト、そしてウィトゲンシュタインだが、この3人のうち亡命者といえるのは晩年のフロイトだけで、しかもフロイトもウィトゲンシュタインも移住したのは、アメリカではなくイギリスだったのだから、ヒューズの扱いは少々説明を工夫することになる。

B.誰のために働いているのか?
財務官僚は国家中枢の高級官僚中の官僚といわれている。この人たちは国民への奉仕者として大きな権限を与えられているが、それは時の首相と内閣が、国民から選ばれた国会で多数を占める与党の権力に基づき、政府が決めた方針や政策を忠実に実現することが仕事だからだ。この論理から、首相の意向に忠実に動くことは正当化される。でも、だからといって違法行為や国民に説明できない不正行為をやってよいはずはない。不正行為が発覚しその責任を問われて国会の証人喚問に呼ばれた財務官僚は、誰かの指示や意向を汲んで公文書の改竄をしたのではなく、自分のした不正行為の理由も経緯も説明を拒んだ。これは私は気が狂っていました、という意味か、それともどうしても隠したいことがある、と言っているとしか思えない。
「連立方程式:佐藤 優
二十七日、衆参両院の予算委員会で元財務相理財局長の佐川宣寿氏に対する証人喚問が行われた。森友学園への土地売却に関する公文書が改竄された経緯や自らの関与については、刑事訴追の恐れがあるという理由で証言拒否した。しかし、安倍昭恵首相夫人の関与については、全面的に否定した。佐川氏自身が本件に関する関与を、改竄された公文書を見たか否かという刑事訴追に関係するとは思われない事項に関して証言を拒否したうえで、改竄に関する昭恵氏の関与を否定するのは奇妙だ。なぜなら佐川氏自身が当該公文書を読んだことを含め、事案の全体像に通じていなくては昭恵氏の関与を否定できないからだ。
佐川氏は、首相官邸、財務省と自分を同時に守るという連立方程式をつくって尋問に臨んだ。その目的は、首相官邸と財務省を守れば、自分が刑事責任を追及されることを免れるという希望的観測に基づくものだ。佐川氏には、国民に対する奉仕者である国家公務員だったという意識が希薄だ。自分の生き残りしか考えていない。それだから、有権者による直接選挙によって選ばれた参議院議員、衆議院議員の前で真実を語ることに関心がなかったのだ。今回の証人喚問の結果、国民から超然として存在している元財務官僚の病理が可視化された。徹底的な治療が必要だ。(作家・元外務省主任分析官)」東京新聞2018年3月20日朝刊27面特報欄、本音のコラム。
自分のした行為に責任を取る、とはどういうことかを考えさせる記事もあった。
「成田闘争の象徴 撤去へ:成田空港(千葉県成田市など)の開港を4日後に控えた1978年3月26日、開港に反対する活動家たちが管制塔(高さ約64㍍)に侵入して機器を破壊する「管制塔占拠事件」が起き、開港は2カ月遅れた。あれから40年。成田国際空港会社(NAA)は「成田闘争の象徴」といえるこの建物を、2020年にも取り壊すことを決めた。
成田空港をめぐっては、建設が閣議決定された66年以降、地元農家らの反対運動が活動家を巻き込んで激化。警察官3人が死亡した東峰十字路事件など「成田闘争」が繰り広げられた。
78年3月、航空機への離着陸の指示などを担う管制塔の最上階の16階の管制室に活動家らが侵入。鉄パイプなどで機器を壊し、著類を窓から投げ捨てた。数時間後に逮捕されたが、開港は5月20日まで延期された。
93年2月に高さ約87㍍の新管制塔が北側に建てられた。事件が起きた建物は旧管制塔となり、地上の航空機の誘導などを担うランプコントロールタワーとして使われてきた。しかし、近年は老朽化が進み、雨漏りなど傷みが目立つ。NAAは2020年の運用開始を目指し、今年4月、南側に高さ約60㍍の新ランプコントロールタワーを着工する。運用開始後、旧管制塔を撤去する予定だ。
成田空港は現在、海外115都市、国内18都市を結ぶ。17年の旅客数は計468万人で、過去最多を更新。今月13日には。3本目の滑走路の新設や運用時間の延長に地元自治体などが合意した。
元活動家「管制官に謝りたい」
管制塔占拠事件の中心メンバー17人のうち、管制室まで入ったのは6人。その一人、中川憲一さん(70)=東京都=は当時、会社員だった。「怖い思いをさせて申し訳なかった。当時の管制官に謝りたい」。朝日新聞の取材にそう話した。
「特別な任務をやってくれないか」。数カ月前にそう言われた。任務で走れるようにたばこを断った。刑務所に入ると覚悟し、頭を丸刈りにした。管制室では「人を傷つけないように」と、窓から機器を投げずに書類をばらまいた。
出所後、しばらく日雇いで働き、再び会社員になった。定年まで勤めながら、空港反対運動に時々参加した。元活動家たちには国から1億300万円の損害賠償金を督促され、給与の差し押さえ命令が通知されるなどしたが、インターネットの支援サイトなどで約2千人が寄付してくれた。「心のこもったお金。感謝している」。この10年は、母親の介護で北陸と東京を往復しているという。
管制塔占拠事件を計画した和多田粂夫さん(77)=同=は「開港を延ばし、国に開港をあきらめさせようと思った。ぼくも福井県の農家の出身。農家を守りたいという思いもあった」と降り返る。
逮捕から11年半後に釈放され、出所後は会社勤めをして出版物発送会社の社長にも就いた。事件から40年。当時の反対派の農家の中には、子どもが空港で働いている人もいるという。「地元ではそうやって生きているのが現実」と受け止めている。
いまも反対運動を続けている人がおり、和多田さんは集会などに参加しているが、「もう僕らが外から何か言うものではない」と話す。山梨県にある畑に時々通い、野菜を育てている。(黒川和久)」朝日新聞2018年3月30日夕刊15面社会欄。
成田空港反対闘争は、60年代末から70年代半ばまで、いわゆる新左翼「過激派」が絡んださまざまな事件のなかで、若者中心の大学闘争や武力革命を叫んだ赤軍派事件など観念が先行した運動とは異なる、土地を奪われる農民の生活圏と国家が進める空港建設の対立というリアルな問題に、若者が実力で「支援する」ものだった。管制塔事件は、その象徴的な事件の一つだった。成田闘争の問題は発端で三里塚の農民を説得する努力を怠って、運輸省と政府が強引に強制収用などをすすめたことへの農民の反発に起因する。こじれ切った中で、多くの学生や若い社会人が運動に加わった。革命運動の一つとして党派的に関わった者も混じっていただろうが、多くは土地に生きる農民やその家族の心情に共感して反対運動に参加していたと思う。当時三里塚に行っていた友人を見ていて、運動の主体は農民であって学生はそれを応援しているのだ、という言い分に納得したと同時に、わくわくイヴェントに成田に行ってくるぜ、という軽薄な気分も感じた。闘争の行方を見兼ねた労働経済学者、隅谷三喜男先生たちが、政府と調停に立って反対派との和解をすすめ、計画を部分修正して空港がやっと開港した。
あのときの若者たちももはや70代!事件を知る人もみな老いた。成田空港は日本の玄関として賑わっている。しかし、管制塔を占拠破壊した行為は暴力的違法行為であるから、実行者は逮捕され刑務所に入って責任を取った。正義を信じて行った行為でも、人生にとっては重い責任である。国民の税金や資産を恣意的に動かした不正行為を、権力の意向で免れようとするのが高級官僚であるのなら、重い責任を取ってもらわねばならない。