A.熱帯魚の水を替えながら・・
あれはいつのことだったか?息子が小学生だった頃だから、15年は昔だろう。熱帯魚を飼うことにした。猫もいたので気が進まなかったが、息子が熱帯魚が欲しいというので水槽を買ってグッピーやらプラティやら、魚も買った。そのうち魚が繁殖して、水槽は2つになった。熱帯魚というのは、普通の水道の水を少し温めて適温にし、カリキを抜いて月に一回は水槽を掃除して、水替えをしなければならない。さらに、できれば水草が蔓延ったり汚れたりしないように月半ばに、水を3分の1ほど取り替えるのがベストとされている。毎月月末この作業に3~4時間はかかる。浄化ポンプやヒーターも2年ほどで痛んでくるので、いろいろメンテナンスが必要になる。この作業はもっぱらぼくの仕事である。
考えてみれば、この作業をぼくは15年も欠かさず続けているわけだ。1月以上海外に行っていた間は、やむなく家人に任せたが、手を抜くと魚が少し死んだ。魚は増えすぎて、もう10世代以上生存淘汰されているが、今もうじゃうじゃ群がって生息している。昨日も、水替えをしたのだが、寒くなってきたので水の温度調整に時間がかかる。これをしながらあるアイディアが湧き、いろいろ考えが巡った。
熱帯魚の棲む水は手を入れて冷たくもなく暖かくもない26℃くらい。水温計や体温計の示す温度は一定でも、人間の体感する温度はそうではない。真夏の炎暑にいて冷房のきいた室内に入った時は、26℃は涼しく感じ、逆に零下の寒風の野外から暖房の室内に入れば、26℃はかなり暖かい。水槽を洗いながら冷たい水に手を突っ込んでいると、26℃がどのくらいか感覚ではわからなくなる。人の生きている環境と、その環境で適温がどれほどと感じるかは、相対的なものだろう。
たとえば、冷帯の北海道で生まれ育った人は、雪や氷が当たり前の寒い環境に慣れているだろうから、逆に沖縄のような亜熱帯の熱さには弱いと思われる。その逆もあるとすれば、同じ出来事に対する体感は、慣れ親しんだ環境によって強弱があると考えてもよい。これを人の社会的生育に広げてみると、厳しい家庭環境に育った人と穏やかな環境に育った人とでは、同じ行為でも感じ方が違うと言えるかもしれない。応用問題として暴力とセクハラについて、考えてみた。
ぼくは親から手を挙げて叩かれたことがない。言葉で口汚く叱られた覚えもない。それを不思議だと思ってもいなかったので、親戚の家に行ったとき、その家の父親が子どもを怒鳴って頭を殴るのを見て驚いた。殴られた子も、反抗して親を足で蹴飛ばし罵っていたのだが、夕飯では一家仲よく談笑しているのでまた驚いた。暴力というのは日常化すると慣れるのか。それから高校時代にこんなこともあった。体育の剣道の授業のとき、さぼって遅れてきた同級生を教師は「そこに立て!」と言って竹刀で何度も叩いた。彼は床に倒れた。しかし、後で彼と話すと反省もしていなかったが教師を憎んでもいなかった。目の前で生起した暴力をぼくは怖れたが、考えてみると引っぱたかれたり怒鳴られたりというのは、肉体的には大した痛みではない。もっと甚大で致命的な暴力は別として、ぼくが感じたような恐怖は、多分に心理的なものだ。暴力にふだん親しんでいる子どもには、ぼくが感じたようには深刻に感じてはいない、かもしれない。
もうひとつ、セクハラという言葉はぼくの子どもの頃にはなかったが、今考えると普通の男たちが喋っていたこと、やっていたことはセクハラそのものだったと思う。女性に対する物言いに露骨にセクシャルな言辞を混ぜ、男同士では卑猥な冗談を言うのは日常的な風景だった。強姦を肯定するような「据え膳喰わぬは男の恥」という言葉が平然と語られた。しかしこれにも環境の差があって、セクハラ的なものへのタブーを元来もっていない人と、性的なもの一般をタブー視する人が男女双方にいたと思う。今から思えば奇妙なほど、清浄純潔主義と男根エロチシズムが併存していた。要するに、ある行為をタブーとみるか、問題ないとみるかは当人の育った環境で異なる、ということになる。
今の日本は、表面的には暴力もセクハラもタブーである。教師が生徒に暴力やセクハラをすれば、大問題になって批判を浴びる。暴力やセクハラを絶対に許さないと考える人々は、一切の暴力的思想・セクハラ的思考を否定するような教育を要求するだろう。でも、ぼくはちょっと違うことを考える。暴力やセクハラはもちろんよくないけれども、それをあまり気にしないような環境にいる人たちがたくさんいて、他方で暴力やセクハラにまったく縁のない無菌状態で育った人たちがいる。暴力やセクハラを根絶しようと考える人たちは、すごく無理なことをしようとしているのではないか、あるいは暴力やセクハラを日常化する環境に生きている人たちのことを理解していないのではないか、と思う。それはもちろん暴力やセクハラを認めようというのではない。ただ、学校教育のなかでいじめや体罰を根絶しようという思想には、不自然で神経質な無理があるのかもしれず、そういう厳格さは結局、環境の異なる生徒をさらに追い詰めるかもしれないと思う。糺すべきは環境の差異であって、個別行為の糾弾ではない。
とは言ってみたものの、これを福島の原発放射能の問題に応用したらどうなるだろう。

B.どこまで解っているのか?
「放射能汚染に慣れる」などということがあるのだろうか?でも、現に高濃度の汚染地域とされる場所に帰ろうとしている人たちがいる。自分の土地、建物、これまで築き上げてきた生活の一切を、原発事故で奪われている現実があり、それをできれば取り戻したいという願望は、まったくもって正当で自然なものである。そこで問題は、それは可能なのか?可能ならいつ帰還できるのか?そこが出発点であり終着点だろう。では、それを判断するのは誰なのか?
特定の問題について科学者、専門家と呼ばれる人たちがいかなる判断をしているかは、その分野について特別な知識などない素人が考えるよりずっと、正確で考え抜かれているはずだと普通は思われている。原発事故のような重大事故がもたらした問題について、これまで科学者・専門家が何をどう発言し行動したのかは、たいへん気になることである。原発事故から既に2年7か月。放射性物質がどこまでどのように飛散し、人間の生活にとってどこまで危険性があって、その処理に何がどこまで進んでいるのか?そうしたことはいうまでもなく実際の行動を決めるうえでたいへん重要である。しかし、報道等に目を凝らしてもよくわからない。実際に放射線植物生理学の研究者中西友子教授の書いた新刊を読んでみた。
「福島第一原発事故が引き起こした広範囲にわたる放射能汚染の実態を調べていくと、汚染の様子は時間とともに変化していくことがわかった。
事故で飛んできた放射性物質は、屋外にむき出しになっていたものに付着した。事故当時、畑ではほとんど作物が生育していなかった。空気中に小さく伸びていたのはムギ類とホウレンソウの葉くらいである。事故後、新しい葉が生えてきたものの、事故後に小さい葉に付着した放射性物質はその場からほとんど動かなかった。そのため、事故後に生えた新しい葉や茎中の放射性物質の量は、直接汚染された葉よりいちじるしく少なくなっている。
しかし当初、農作物の汚染が大きな問題となり、風評被害も加わって福島県の農業は大きな打撃を受けた。福島県は農業県である。2010年の農業産出額は全国第十一位であり、その中でもコメが40%弱と最大のシェアを占めている。またほかの農産物でも、モモが全国第二位、ナシやキュウリが全国第三位と、福島県の農作物は私たちの食を支えてきた。
〔中略〕
事故で放出された放射性セシウムの動きを振り返ってみよう。事故当初、一部の放射性物質は動いたものの、その後は次第に動かなくなった。土壌でも同様に、放射性物質は事故後からずっと、表面から数センチの厚さのところにとどまっている。すでに土にしっかり吸着した放射性物質は、そこに植えられた植物でも、まず吸い上げることはできない。
農地からだけでなく、汚染地帯の大部分を占める森林からも、放射性物質が動いて出てくることはほとんどないことがわかった。時間とともに放射性物質はより強固に、最初に付着した場所にとどまるようになった。そのほとんどが土壌である。木の葉や落ち葉に付着した放射性物質についても、植物が微生物などによって分解されるにつれて、その下にある土壌が放射性物質の付着する場所となった。
溜め池や沼などでは、池底の土壌に放射性物質が吸着している。土壌は、森林でも、農地や町の中でも依然としてその表面近くに放射性物質を強固に吸着させていて、そこから放射線を出している。だからこそ土壌が除染の一番の対象となったのである。しかし、土壌から放射性物質を分離するためには膨大なエネルギーと薬品が必要で、たとえ分離と除去に成功したとしても、その土壌はもう農地として使用できなくなってしまう。
土壌汚染での問題は、迅速な対応が求められたため、除染を行う側が提案する工学的除染法が、農業現場を守りつつ除染をしたいという農家側の求める方策とうまく合致しなかった事である。除染の技術開発者は、まず汚染土壌を集めてその土壌からどう放射性セシウムを分離するかに意識を集中させがちであり、工学的、科学的知識を駆使してセシウムを集めようとする。しかし農業の従事者は、生産の場である土壌を何とか守りたいという観点から除染を考えたのである。
土壌はその生成に非常に長い時間を要するだけでなく、地表わずか十数センチの限りある生産資源であり、農業を営む基盤でもある。食糧生産のための土壌がいったん破壊されると、それを回復するために百年単位の時間が必要となってくる。この土壌というものに対して、農家は何世紀にもわたって維持・管理に力を尽くしてきた。」中西友子『土壌汚染 フクシマの放射性物質のゆくえ』NHKブックス1208 ,2013. Pp.211-213.
確かに土壌を除染する必要性、除染の具体的方法とその効果、処理の結果福島の農業が再び再生できるか、という問題についてならデータを蓄積して中西さんたち専門家はかなり答えを出せるだろう。しかし、その前にもっと基本的な問い、いったい放射能汚染物質がどのように人体に影響を与えるのか、どこまで危険でどこからが安全なのか、これに科学者はちゃんと答えているのか。専門家・科学者といっても、これに応えるべき原子力の研究者はごく限られた人たちで、しかもそれは原発推進派と反原発派に二分され、推進派は電力会社と政府と結託しており、反原発派は完全に政策決定から排除されている。だからなおさら、放射能の安全について明確な基準・判断が求められているのだが、どうなのか?
「私たちは土壌が育んだ植物や動物を食べて生きている。つまり私たちが食べるものはすべて土壌から生まれてきたと言っても過言ではない。その土壌が放射能で汚染されてしまった。何とか再度、農業が可能な形にできないものか。土壌の汚染やそこに育つ作物・動物を詳細に調べていくことで、農業再生の糸口が見つかるかもしれない――私たちはそのような意識のもとに研究に取り組んできた。
しかし、福島の事故後、放射線の危険性、とくに人体への影響について議論が重ねられてきたが、いまだに専門家あるいは学会によって意見は異なっており、一致しない部分が多い。これは現代の科学の限界でもある。
たとえば放射線はなぜ危険なのかについて、その量と影響との関係、つまり、どのくらい放射線を浴びても大丈夫なのかという点一つをとってみても、はっきりとした科学的な答えはいまだに出ていないのである。それだけではない。測定を進めるうちに、今回の事故とは無関係な自然放射線、すなわちもともと自然に存在する放射線の影響に加え、1960年代を中心とする太平洋における核実験によって日本に降り注いできた放射性物質(フォールアウト)の放射能もあわせて考慮しなけれならないことがわかったのである。
かつての核実験によるフォールアウトの総量は、今回の福島の事故を凌駕するほどになっていたと推測されるが、その科学的影響はほとんど知られていない。自嘲的かもしれないが、放射能汚染に直面した私たちは、調査研究を進めるほど、放射線の人体への影響評価は非常に難しいということを認識させられ、いよいよ右往左往してしまうにすぎないのかもしれない。
放射能の人体への影響評価は一例にすぎないが、これ一つをとっても、放射能汚染の研究は個々の専門家だけではなく、あらゆる分野の研究者を総動員して対応していかなくてはならない問題であることがわかる。
2012年に内閣府原子力委員会の委員だった尾本彰氏によれば、同年のフランス原子力学会で、「原子力発電所がもたらした教訓」として、人と機械をつなぐ仕組みに留意すべきこと。次に、チェルノブイリ事故の教訓として、安全文化を創造すべきこと。そしてフクシマの場合は、危機管理や土壌汚染防止のために必要な、柔軟な方法を採り、責任ある利用を行うこと。
フクシマの例で言えば、危機管理については政治的かつ組織的な判断が必要だとしても、土壌汚染防止のために必要な方策を検討するためにも、どのように土壌が汚染されたかという科学的な検証が必要なのである。本書に紹介した研究はこうした目的のために行われた」中西友子『土壌汚染 フクシマの放射性物質のゆくえ』NHKブックス1208 ,2013. Pp.213-215..
おいおい、結局専門家・科学者にもよくわかってないわけ?「現代の科学の限界」などと言われると、ぼくたち素人はほとんど絶望するしかない。つまり、確実なことは現代の科学では実はかなりあいまいだってことになり、その場合は一番厳しい基準で対処しておくしかないと思うのだが、どうもそうなっていないらしい。社会科学者としては、そこはしょうがないとして、原発再稼働を目指している政府が国会で圧倒多数を取っている状況では、除染も帰還もたかが電力会社や時の与党の利害のためにあいまいな基準で決定されることの危険性の方が、放射能の危険性以上に危ないといわざるをえまい。
あれはいつのことだったか?息子が小学生だった頃だから、15年は昔だろう。熱帯魚を飼うことにした。猫もいたので気が進まなかったが、息子が熱帯魚が欲しいというので水槽を買ってグッピーやらプラティやら、魚も買った。そのうち魚が繁殖して、水槽は2つになった。熱帯魚というのは、普通の水道の水を少し温めて適温にし、カリキを抜いて月に一回は水槽を掃除して、水替えをしなければならない。さらに、できれば水草が蔓延ったり汚れたりしないように月半ばに、水を3分の1ほど取り替えるのがベストとされている。毎月月末この作業に3~4時間はかかる。浄化ポンプやヒーターも2年ほどで痛んでくるので、いろいろメンテナンスが必要になる。この作業はもっぱらぼくの仕事である。
考えてみれば、この作業をぼくは15年も欠かさず続けているわけだ。1月以上海外に行っていた間は、やむなく家人に任せたが、手を抜くと魚が少し死んだ。魚は増えすぎて、もう10世代以上生存淘汰されているが、今もうじゃうじゃ群がって生息している。昨日も、水替えをしたのだが、寒くなってきたので水の温度調整に時間がかかる。これをしながらあるアイディアが湧き、いろいろ考えが巡った。
熱帯魚の棲む水は手を入れて冷たくもなく暖かくもない26℃くらい。水温計や体温計の示す温度は一定でも、人間の体感する温度はそうではない。真夏の炎暑にいて冷房のきいた室内に入った時は、26℃は涼しく感じ、逆に零下の寒風の野外から暖房の室内に入れば、26℃はかなり暖かい。水槽を洗いながら冷たい水に手を突っ込んでいると、26℃がどのくらいか感覚ではわからなくなる。人の生きている環境と、その環境で適温がどれほどと感じるかは、相対的なものだろう。
たとえば、冷帯の北海道で生まれ育った人は、雪や氷が当たり前の寒い環境に慣れているだろうから、逆に沖縄のような亜熱帯の熱さには弱いと思われる。その逆もあるとすれば、同じ出来事に対する体感は、慣れ親しんだ環境によって強弱があると考えてもよい。これを人の社会的生育に広げてみると、厳しい家庭環境に育った人と穏やかな環境に育った人とでは、同じ行為でも感じ方が違うと言えるかもしれない。応用問題として暴力とセクハラについて、考えてみた。
ぼくは親から手を挙げて叩かれたことがない。言葉で口汚く叱られた覚えもない。それを不思議だと思ってもいなかったので、親戚の家に行ったとき、その家の父親が子どもを怒鳴って頭を殴るのを見て驚いた。殴られた子も、反抗して親を足で蹴飛ばし罵っていたのだが、夕飯では一家仲よく談笑しているのでまた驚いた。暴力というのは日常化すると慣れるのか。それから高校時代にこんなこともあった。体育の剣道の授業のとき、さぼって遅れてきた同級生を教師は「そこに立て!」と言って竹刀で何度も叩いた。彼は床に倒れた。しかし、後で彼と話すと反省もしていなかったが教師を憎んでもいなかった。目の前で生起した暴力をぼくは怖れたが、考えてみると引っぱたかれたり怒鳴られたりというのは、肉体的には大した痛みではない。もっと甚大で致命的な暴力は別として、ぼくが感じたような恐怖は、多分に心理的なものだ。暴力にふだん親しんでいる子どもには、ぼくが感じたようには深刻に感じてはいない、かもしれない。
もうひとつ、セクハラという言葉はぼくの子どもの頃にはなかったが、今考えると普通の男たちが喋っていたこと、やっていたことはセクハラそのものだったと思う。女性に対する物言いに露骨にセクシャルな言辞を混ぜ、男同士では卑猥な冗談を言うのは日常的な風景だった。強姦を肯定するような「据え膳喰わぬは男の恥」という言葉が平然と語られた。しかしこれにも環境の差があって、セクハラ的なものへのタブーを元来もっていない人と、性的なもの一般をタブー視する人が男女双方にいたと思う。今から思えば奇妙なほど、清浄純潔主義と男根エロチシズムが併存していた。要するに、ある行為をタブーとみるか、問題ないとみるかは当人の育った環境で異なる、ということになる。
今の日本は、表面的には暴力もセクハラもタブーである。教師が生徒に暴力やセクハラをすれば、大問題になって批判を浴びる。暴力やセクハラを絶対に許さないと考える人々は、一切の暴力的思想・セクハラ的思考を否定するような教育を要求するだろう。でも、ぼくはちょっと違うことを考える。暴力やセクハラはもちろんよくないけれども、それをあまり気にしないような環境にいる人たちがたくさんいて、他方で暴力やセクハラにまったく縁のない無菌状態で育った人たちがいる。暴力やセクハラを根絶しようと考える人たちは、すごく無理なことをしようとしているのではないか、あるいは暴力やセクハラを日常化する環境に生きている人たちのことを理解していないのではないか、と思う。それはもちろん暴力やセクハラを認めようというのではない。ただ、学校教育のなかでいじめや体罰を根絶しようという思想には、不自然で神経質な無理があるのかもしれず、そういう厳格さは結局、環境の異なる生徒をさらに追い詰めるかもしれないと思う。糺すべきは環境の差異であって、個別行為の糾弾ではない。
とは言ってみたものの、これを福島の原発放射能の問題に応用したらどうなるだろう。

B.どこまで解っているのか?
「放射能汚染に慣れる」などということがあるのだろうか?でも、現に高濃度の汚染地域とされる場所に帰ろうとしている人たちがいる。自分の土地、建物、これまで築き上げてきた生活の一切を、原発事故で奪われている現実があり、それをできれば取り戻したいという願望は、まったくもって正当で自然なものである。そこで問題は、それは可能なのか?可能ならいつ帰還できるのか?そこが出発点であり終着点だろう。では、それを判断するのは誰なのか?
特定の問題について科学者、専門家と呼ばれる人たちがいかなる判断をしているかは、その分野について特別な知識などない素人が考えるよりずっと、正確で考え抜かれているはずだと普通は思われている。原発事故のような重大事故がもたらした問題について、これまで科学者・専門家が何をどう発言し行動したのかは、たいへん気になることである。原発事故から既に2年7か月。放射性物質がどこまでどのように飛散し、人間の生活にとってどこまで危険性があって、その処理に何がどこまで進んでいるのか?そうしたことはいうまでもなく実際の行動を決めるうえでたいへん重要である。しかし、報道等に目を凝らしてもよくわからない。実際に放射線植物生理学の研究者中西友子教授の書いた新刊を読んでみた。
「福島第一原発事故が引き起こした広範囲にわたる放射能汚染の実態を調べていくと、汚染の様子は時間とともに変化していくことがわかった。
事故で飛んできた放射性物質は、屋外にむき出しになっていたものに付着した。事故当時、畑ではほとんど作物が生育していなかった。空気中に小さく伸びていたのはムギ類とホウレンソウの葉くらいである。事故後、新しい葉が生えてきたものの、事故後に小さい葉に付着した放射性物質はその場からほとんど動かなかった。そのため、事故後に生えた新しい葉や茎中の放射性物質の量は、直接汚染された葉よりいちじるしく少なくなっている。
しかし当初、農作物の汚染が大きな問題となり、風評被害も加わって福島県の農業は大きな打撃を受けた。福島県は農業県である。2010年の農業産出額は全国第十一位であり、その中でもコメが40%弱と最大のシェアを占めている。またほかの農産物でも、モモが全国第二位、ナシやキュウリが全国第三位と、福島県の農作物は私たちの食を支えてきた。
〔中略〕
事故で放出された放射性セシウムの動きを振り返ってみよう。事故当初、一部の放射性物質は動いたものの、その後は次第に動かなくなった。土壌でも同様に、放射性物質は事故後からずっと、表面から数センチの厚さのところにとどまっている。すでに土にしっかり吸着した放射性物質は、そこに植えられた植物でも、まず吸い上げることはできない。
農地からだけでなく、汚染地帯の大部分を占める森林からも、放射性物質が動いて出てくることはほとんどないことがわかった。時間とともに放射性物質はより強固に、最初に付着した場所にとどまるようになった。そのほとんどが土壌である。木の葉や落ち葉に付着した放射性物質についても、植物が微生物などによって分解されるにつれて、その下にある土壌が放射性物質の付着する場所となった。
溜め池や沼などでは、池底の土壌に放射性物質が吸着している。土壌は、森林でも、農地や町の中でも依然としてその表面近くに放射性物質を強固に吸着させていて、そこから放射線を出している。だからこそ土壌が除染の一番の対象となったのである。しかし、土壌から放射性物質を分離するためには膨大なエネルギーと薬品が必要で、たとえ分離と除去に成功したとしても、その土壌はもう農地として使用できなくなってしまう。
土壌汚染での問題は、迅速な対応が求められたため、除染を行う側が提案する工学的除染法が、農業現場を守りつつ除染をしたいという農家側の求める方策とうまく合致しなかった事である。除染の技術開発者は、まず汚染土壌を集めてその土壌からどう放射性セシウムを分離するかに意識を集中させがちであり、工学的、科学的知識を駆使してセシウムを集めようとする。しかし農業の従事者は、生産の場である土壌を何とか守りたいという観点から除染を考えたのである。
土壌はその生成に非常に長い時間を要するだけでなく、地表わずか十数センチの限りある生産資源であり、農業を営む基盤でもある。食糧生産のための土壌がいったん破壊されると、それを回復するために百年単位の時間が必要となってくる。この土壌というものに対して、農家は何世紀にもわたって維持・管理に力を尽くしてきた。」中西友子『土壌汚染 フクシマの放射性物質のゆくえ』NHKブックス1208 ,2013. Pp.211-213.
確かに土壌を除染する必要性、除染の具体的方法とその効果、処理の結果福島の農業が再び再生できるか、という問題についてならデータを蓄積して中西さんたち専門家はかなり答えを出せるだろう。しかし、その前にもっと基本的な問い、いったい放射能汚染物質がどのように人体に影響を与えるのか、どこまで危険でどこからが安全なのか、これに科学者はちゃんと答えているのか。専門家・科学者といっても、これに応えるべき原子力の研究者はごく限られた人たちで、しかもそれは原発推進派と反原発派に二分され、推進派は電力会社と政府と結託しており、反原発派は完全に政策決定から排除されている。だからなおさら、放射能の安全について明確な基準・判断が求められているのだが、どうなのか?
「私たちは土壌が育んだ植物や動物を食べて生きている。つまり私たちが食べるものはすべて土壌から生まれてきたと言っても過言ではない。その土壌が放射能で汚染されてしまった。何とか再度、農業が可能な形にできないものか。土壌の汚染やそこに育つ作物・動物を詳細に調べていくことで、農業再生の糸口が見つかるかもしれない――私たちはそのような意識のもとに研究に取り組んできた。
しかし、福島の事故後、放射線の危険性、とくに人体への影響について議論が重ねられてきたが、いまだに専門家あるいは学会によって意見は異なっており、一致しない部分が多い。これは現代の科学の限界でもある。
たとえば放射線はなぜ危険なのかについて、その量と影響との関係、つまり、どのくらい放射線を浴びても大丈夫なのかという点一つをとってみても、はっきりとした科学的な答えはいまだに出ていないのである。それだけではない。測定を進めるうちに、今回の事故とは無関係な自然放射線、すなわちもともと自然に存在する放射線の影響に加え、1960年代を中心とする太平洋における核実験によって日本に降り注いできた放射性物質(フォールアウト)の放射能もあわせて考慮しなけれならないことがわかったのである。
かつての核実験によるフォールアウトの総量は、今回の福島の事故を凌駕するほどになっていたと推測されるが、その科学的影響はほとんど知られていない。自嘲的かもしれないが、放射能汚染に直面した私たちは、調査研究を進めるほど、放射線の人体への影響評価は非常に難しいということを認識させられ、いよいよ右往左往してしまうにすぎないのかもしれない。
放射能の人体への影響評価は一例にすぎないが、これ一つをとっても、放射能汚染の研究は個々の専門家だけではなく、あらゆる分野の研究者を総動員して対応していかなくてはならない問題であることがわかる。
2012年に内閣府原子力委員会の委員だった尾本彰氏によれば、同年のフランス原子力学会で、「原子力発電所がもたらした教訓」として、人と機械をつなぐ仕組みに留意すべきこと。次に、チェルノブイリ事故の教訓として、安全文化を創造すべきこと。そしてフクシマの場合は、危機管理や土壌汚染防止のために必要な、柔軟な方法を採り、責任ある利用を行うこと。
フクシマの例で言えば、危機管理については政治的かつ組織的な判断が必要だとしても、土壌汚染防止のために必要な方策を検討するためにも、どのように土壌が汚染されたかという科学的な検証が必要なのである。本書に紹介した研究はこうした目的のために行われた」中西友子『土壌汚染 フクシマの放射性物質のゆくえ』NHKブックス1208 ,2013. Pp.213-215..
おいおい、結局専門家・科学者にもよくわかってないわけ?「現代の科学の限界」などと言われると、ぼくたち素人はほとんど絶望するしかない。つまり、確実なことは現代の科学では実はかなりあいまいだってことになり、その場合は一番厳しい基準で対処しておくしかないと思うのだが、どうもそうなっていないらしい。社会科学者としては、そこはしょうがないとして、原発再稼働を目指している政府が国会で圧倒多数を取っている状況では、除染も帰還もたかが電力会社や時の与党の利害のためにあいまいな基準で決定されることの危険性の方が、放射能の危険性以上に危ないといわざるをえまい。



















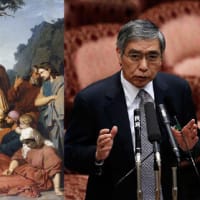






※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます