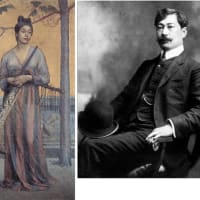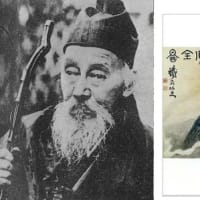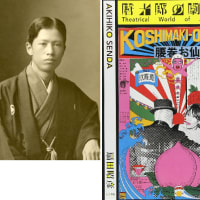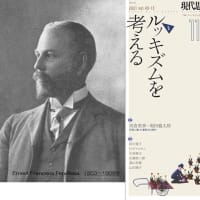A.画家と呼ぶ人だろうか?
明治から大正期まで文人画家として活躍した富岡 鉄斎(1837〈天保7〉年~1924〈大正13〉年)は、画家といってもこれまで見てきたような画家とは色合いが異なる。日本最後の文人と謳われる儒学者であり、教師でもあった。略歴を見ると、京都(三条通新町東)法衣商十一屋伝兵衛富岡維叙の次男として生まれる。猷輔を通称とし、のちに道昴・道節と称し、明治のはじめ頃、一時名を鉄斎としたが、しばらくのち百錬に改名。字を無倦、号を鉄斎。耳が少し不自由であったが、幼少の頃から勉学に励み、はじめ富岡家の家学である石門心学を、15歳頃から大国隆正に国学や勤王思想を、岩垣月洲らに漢学、陽明学、詩文などを学ぶ。維新後の30歳から40代半まで大和国石上神宮や和泉国大鳥神社の神官(宮司)を務めた。座右の銘である「万巻の書を読み、万里の道を往く」を実践し、日本各地を旅した。明治7年(1874年)には、松浦武四郎との交流から北海道を旅し、アイヌの風俗を題材にした代表作「旧蝦夷風俗図」を描いている。
明治14年(1881年)、兄伝兵衛の死に伴い京都薬屋町に転居し、終の住処とする。教育者としても活躍し、明治2年(1869年)、私塾立命館で教員になる。 明治26年(1893年)、京都市美術学校で教員に就任し、明治37年(1904年)まで修身を教える。明治42年(1909年)2月20日、吐血して胃潰瘍と診断される。胃潰瘍を病んだ後は食事にも工夫をこらし、それまでは鰻と蕎麦、小芋を好み、調理も辛みの煮付けを好んだとされるが、70歳以降は熱粥を常食とした。大正13年(1924年)大晦日、持病であった胆石症が悪化。京都の自宅にて没する。享年89。以上の事項はおもにWikipediaによる。
「鉄斎がこれほどまで旅行を好み、地誌の研究に惹かれた点について、多くの研究者はそれを彼の天性の成功によるものとしている。むろん、もともとそのような性向はあったではあろうが、私は、現実に鉄斎をこれほどまで熱心な行動へと駆り立てた重要なファクターとして、若い頃、久我家の春日潜庵について学んだ陽明学の影響があったことを見逃してはならないと考える。この潜庵春日讃岐守は、陽明学については当代一流の人物で、梁川星巌も佐久間象山に送った手紙のなかで「京師第一等の人物」と賞揚しており、西郷隆盛もその弟を入門させたほどの優れた学者であった。鉄斎の家は、代々石田梅厳の石門心学を家学としており、そのことが鉄斎に陽明学を受け入れ易というくさせた事情もあったろうが、いずれにしても、若い鉄斎に対する陽明学の影響は決定的なものがあった。
明治維新革命の精神的エネルギー源として、陽明学がどのような役割を果たしたかについては、今後いっそう精細に考察すべき問題であろうが、少なくとも、知行合一を説く陽明学の行動主義的教えが、幕末の勤王の志士たちの大きな精神的支えとなったことは疑いのないところであり、事実、春日潜庵の周囲には、薩摩や水戸の志士たちが多く集まっていた。若い鉄斎が、このような雰囲気のなかにあって影響を受けないはずがない。と言って鉄斎は決して偏狭な尊王攘夷論者であったわけではなく、後に見るように文久元年二十六歳の時には、世界の大勢を知るため、わざわざ長崎に出向いたりしているほどであるが、しかし彼は、もし幼少の頃に病んだ胎毒によって耳が不自由になったという不幸がなかったら、おそらく親しかった梅田雲浜や頼三樹三郎などと運命をともにしただろうと言われるほど、当時としては急進的な思想の持主であった。おそらく、陽明学によって養われたそのような行動への情熱が、後年の彼のあの休む間もない調査旅行となってあらわれたものであろう。それなればこそ、その旅行の最中でも、単に自分の学問的好奇心を満足させるだけではなく、つねに国家的方策を念頭に置いていたのである。そのことは、例えば、北海道旅行の際、千島の択捉に思いを馳せて、
北門鎖鑰近如何 独抱杞憂説向誰
欲試千洲開拓策 単身孤剣入蝦夷
と詠んでいることからも充分に想像がつく。大雅の実地踏査による「真景」を高く評価する彼の実証主義的精神も、またこの陽明学の思想と無縁ではない。
このような考え方からすれば、絵画表現において写生を重んじるのは当然のことである。鉄斎の作品は無論単に写実主義と言って片づけられるものではないが、その根底には実地調査にもとづくきわめて近代的な現実把握の精神があったのである。
このことは、現在残されている数少ない彼の画論からもうかがうことができる。例えば、鉄斎が書簡とともに門人に送ったという『南宗画論』のなかで、南派の人は古人の作品を研究すると同時に「其画ノ位置ハ、自己ノ胸中ヨリ組織スベシ。準而他人ノ図ヲ用フベカラズ。一木一石ヲ研究シ、真物ヲ参照シ、造化ヲ手ニ入ルベシ」と説いていることや、鉄斎が折に触れて語った言葉の断片からうかがわれるように、大雅、応挙をきわめて高く評価していたことからも明らかと言ってよいであろう。
興味深いのは、賦彩についての鉄斎の意見である。鉄斎が色彩画家として稀に見る豊かな才能の持ち主であることはすでに定評のあるところだが、『画林』第十号に発表された画論のなかで、色彩について彼は次のように述べている。
「太宰春台が紫芝園漫筆に曰く、画所以図物也。図物者貴肖。水墨不如丹青之拙。且彩色可以養目。故与水墨之工。不若丹青拙。と。春台は儒士にして、深く画事を知るの人に非ずと雖も、其論ずる所は則ち当れり。故に支那は勿論、我邦も上古の画を観るに、所謂画道六法中、応物写形の意にて、即ち写生也。其貴肖となれば、森羅万象其形容を彩色す。是其実物に肖似する所にして、古来人物を画くに皆容貌肉色等に深く意を用い、以て生存の如くなせしは則ち丹青の主意なり。然るに支那宋代に至り、其肖似に束縛せられ、神気活動を欠く所を生じ、写画貴形似を鄙とし、専ら活動を主とすれば、形似にのみ拘泥すべきに非ずとし、水墨画行わるに至る。是れ即ち物久しければ弊を生ずるにて、新奇を発揮するに非ずんば、技芸具妙処を尽すに至らず、是に於て我邦また水墨画の流行するに至り、古来の画法また衰退する支那と同じ。是よりして水墨画遊戯の逸興に趨り、瀟洒淡白の略画盛んになりて技芸一変し、肖重色法は益〻衰退す。蓋し古法の重色彩画容易の技術に非ず。故に竟に速成を喜び、簡略を主とし、遂に絵画の本色を喪うに至る也。円山応挙出るに及んで写生画を復古し、其画事の真趣を一変す。名手と謂うべし」(正宗得三郎著『鉄斎』平凡社 昭和三十六年刊より転載)
この画論における鉄斎の立場は、まことに明快そのものである。要するに、絵は眼に見えるものを写し出すのが本来の役割であるから「丹青の切なるもの」でも、ともかく色があるだけ水墨よりましだという太宰春台の考えをほとんど全画的に肯定しているからである。もちろん、鉄斎の画面そのものが、決して単に「応物写形」でないことは、幾重にも事実であるし、賦彩にしても、現実に見える色をそのまま再現しようとしていたわけではないことは、
「西洋画は絵具で描くが、日本画は墨と藍と代赭があれば、何でも描ける」
という鉄斎の言葉(正宗得三郎 前掲書)からも明らかである。しかしそれにもかかわらず、文人画といえばすぐ「気韻」とか「神韻」という言葉で造形的表現力の不備を誤魔化そうとする傾向がしばしば見られる時、敢えて写実に賭けようとする鉄斎の態度はきわめて健全なものであり、小気味よい爽やかな印象すら与えてくれるのである。
だがそれほどまで明快な、あまりにも単純すぎるほどの写実主義を主張する鉄斎がなぜあの「不尽山頂全図」のような、現実にそう見えることはあり得ない、つまりおよそ非写実的な、山容を描くのであろうか。ここでわれわれは、先ほどしばらく留保しておいた問題に立ち返って、明治三十一年、鉄斎が六十三歳の時に柴田治左衛門のために描いたあの六曲一双の「富士山図」屏風の左右半双をそれぞれ分析比較してみなければならない。
すでに述べたように、この右半双の全山遠望図は、左半双の山頂図は大雅の不二頂上図をその発想の出発点としている。しかしそれは、決してたまたま自分の尊敬するふたりの先輩画家の富士山図を借りて来たというだけのものではない。遠望図と頂上図とを左右に振り分けて、両方合わせて一双になるように組み合わせた全体構想には、鉄斎の明確な意図があったはずである。なぜなら、この両者は、題讃が右半双にしか書き込まれていないことからも明らかなように、ふたつ別々のものとして構想されたのではなく、最初からひと組のものとして考えられたことは疑いないからである。
その鉄斎の意図が那辺にあったかを解明してくれる鍵は、この「富士山図」屏風より二十二年遅れて、大正九年、つまり鉄斎の最晩年に描かれた紙本着色の「富士山図巻」にある。これは、その名の示す通り画巻形式のもので、巻頭に大きく「富士山全図」と篆書で書かれており、それに続いて、富士山全容の遠望図がひとつと、富士山頂図がふたつ描かれている。このふたつの富士山頂図のうち、最初のものは「不二山頂図縮写大雅堂原本」と書き込みがあるところから明らかなように、かつて鉄斎が模写したことのある大雅の山頂俯瞰地図であり、もうひとつが、大雅のその平面的な地図を斜上から見下ろしたようなかたちに立体化したものである。この全容遠望図と最後の立体的な山頂図がそのまま清荒神所蔵の「富士山図」屏風の右半双、左半双にそれぞれつながることは、一見して明らかである。事実、山頂図の部分の切り方や八葉嶽のたたずまい、また遠望図の斜めに白雲の懸かった様子や左手に宝永山の見える構図、さらには、その遠望図の右肩上に長文の題讃を書き込んだ全体のデザインにいたるまで、両者はそっくりそのままと言ってもよいほど酷似している。事実は、この両者のあいだに二十二年の歳月の隔たりがあるのであるが、一見したところ、同じ時に描かれたと言ってもよいほどである。(もっとも、当然のことながら、題讃の文章は異る。鉄斎の作品の場合、後に触れるようにこの題讃の文言がつねに重要な意味を持っているのだが、ここでは、あまりに繁雑になるので割愛する)
ところで、一巻の画巻のなかに、全容遠望図と頂上部分図とをいっしょに描き出したのはいったいどういう意味を持っているのだが、ここでは、あまりに繁雑になるので割愛する)
ところで、一巻の画巻のなかに、全容遠望図と頂上部分図とをいっしょに描き出したのはいったいどういう意味を持っているのだろうか。それは、画巻巻頭の題字を思い出してみれば、容易に想像がつく。その題字の文言は、単に「富士山図」というのではなく、「富士山全図」と書かれている。とすれば、遠望図と頂上図とを合わせたものが、富嶽の「全図」にほかならないということを意味するものであろう。つまり鉄斎にとっては、「富士山全図」とは、決して山頂から山麓までの「全容」を描き出したという意味ではなく、遠望図と頂上図とを合わせたものという意味なのである。
この場合、遠望図と頂上図とは、例えば広角レンズと望遠レンズとで撮影した全体図と部分図という関係ではない。すでに屏風絵の分析のところで述べたように、それは富士という自然に対する人間の対し方のふたつの異なったタイプを示す。すなわち、遠望図は「眺められた世界」、つまり知的認識者の自然把握であり、山頂図の方は「体験された世界」、つまり行動者の捉えた自然である。前者は「万巻の書を読む」鉄斎の見た富士であり、後者は「万里の路を行く」鉄斎が実際い肌で感じた富士だと言ってもよい。そして、視覚を通しての知的認識と、行動を通しての体験的把握とのこのいずれが欠けても、自然を完全な意味で捉えることはできない。富士は、遠くから仰ぎ見るのみでなく、自から実地にその山頂を踏破してはじめて、その「全貌」を人間の前に示してくれるのである。
すでに見たように、鉄斎があれほどまで大雅の富士に傾倒していたのも、おそらくは大雅がほとんど本能的にこのふたつの異なった自然把握を実践していたからに違いない。鉄斎がただ一度自ら富士に登ったのは、明治八年彼が四十歳の時のことであったが、後年、『賀史登岳』の中でその時の思い出を語るときにも、既に大雅が自分に先立って徹底的な「実地調査」を行ったことを、いささか口惜しげにつけ加えることを忘れなかった。すなわち、彼はこう語っている。
「……余は明治八年七月、甲州吉田口より登り、絶頂に一泊し、翌日駿河口へ降り、麓を巡覧し、不残見めぐり、又富士山眺望地彼是経歴せるも、大抵大雅皆既に遊歴せる所たり」(傍点高階)
つまり鉄斎にとっては、かつて大雅にとってそうであったように、実地に富士を訪れて「残らず見めぐ」らなければ、完全に富士を知ってとは言えなかったのである。
富士の遠望図と頂上図の持つこのような意味が明らかになれば、明治三十一年の屏風絵一双の意図も自ずからまた明らかであろう。それは右半双に遠望図、すなわち認識者の世界を、左半双に頂上図、すなわち行動者の世界を描いて、両者合わせて完全な富士の姿を示そうとしたものである。したがってこの両者は、等しく富士を対象としながら、まったく異なったアプローチの方法を示している。両者が、その構成のみならず、表現法や筆使いにいたるまで、まったく対照的な性格を見せているのも、当然のことなのである。
事実、右半双の遠望図においては、知的認識の世界にふさわしく、すべてが落ち着いた平静な表現であるのに対し、左半双の頂上図では、逆に行動的世界を暗示するように、すべてが激しくダイナミックな表現になっている。遠望図では、雲もあるかなきかの風に静かに棚引き、富士は永遠の不動性を備えて無言のまま佇立しているのに反し、山頂図では、雲も荒海の坂巻く大浪のようにうねり、岩塊は画面から飛び出さんばかりの勢いでせめぎ合っている。当然、遠望図は平面的で艶麗な装飾性を見せ、山頂図は立体的でダイナミックな生命感を感じさせる。その筆の勢いは、自ずから「鉄斎外史」と書かれた署名にまで及び、遠望図の署名が折り目正しい楷書体であるのに対し、山頂図の署名は畢生激しい行書体で書かれている。そしてこの山頂図が、一見およそ実際にあり得ないように思われる不自然な相貌を見せているのも、それがどこか架空の空中の一点から「眺められた」ものではなく、この山頂を自からの足で「残らず見めぐ」った鉄斎の体験の総和にほかならない以上、当然のことなのである。この山頂図が、「不尽山頂図」ではなくて、「不尽頂全図」である所以も、おそらくそこにある。それは、もし写実主義という言葉で呼ぶなら、きわめて徹底した写実主義と言うべきであろう。しかも、そのように全山くまなく踏破して獲得された体験的世界と、遠くから眺められた視覚的世界とを合わせてはじめて完全な富士の姿を捉えることができるというのは、さらに徹底した写実主義と言わなければならない。
しかしながら、知的認識と行動的認識とを統一したこのような世界を支持する言葉としては、写実主義という呼称は、あまりにも西欧の伝統的世界と馴れ合い過ぎている。鉄斎のこの富岳図の背後にあるのは、西欧流の写実精神ではなく、やはり知行合一の思想であろう。鉄斎のみならず、幕末から明治にかけての革新的な若者たちに大きな影響を与えた陽明学は、鉄斎のこの「富士山図」屏風一双のなかに、そのもっとも見事な造形化を持つことができたのである。」高階秀爾『日本近代美術史論』講談社文庫、1980年、pp.302-311.
富士山を描くのに、遠くから眺めるだけでなく実際に登って火口まで体感し、その全体像を描き、さらに文章を添える。これは画家というよりは、知行合一の思想家の仕事で、まさに最後の文人だな。

B.反省…
このブログの記述について、グーグルと朝日新聞などの管理者から警告を戴いた。新聞記事や画像を無断でここに引用・掲載したことで、著作権法への抵触が疑われるため、閲覧停止の措置をとったとのこと。なるほど、記事や写真などをそのまま全文引用している箇所がある。どこからの引用か、出所出典は文章については必ずページまで示したつもりだが、画損はネットで採集してオリジナルは示していない(示せない)。これは確かに、著作権に抵触するといわれれば、その通りであり、閲覧停止となっても仕方がない。したがって、今後はできるかぎり全文引用は避け、画像についても作成者撮影者等の情報を添え、それがないものは避けるようにしたい。
というわけで、以下は東京新聞掲載のコラムだが、愛読しているので、短いもので読者に拡散したい内容であるのと、コメントをつけることでお許しいただきたい。
「形式化した3分 斎藤美奈子
伊藤信太郎環境相と水俣病被害者団体との懇談会(1日)で環境省側がマイクを切った件。
ネット上のニュース動画で一部始終を見てみると、やっぱりひどいと思わざるを得ない。3分を過ぎるや否や「お時間でございます」「お話をおまとめください」と繰り返す司会者(環境省の担当室長)。「聞いてやれ絵や大臣」などの声を無視したうえ、会の最後に国会答弁よろしくペーパーを読むだけの大臣。
8日、大臣と室長は再び水俣を訪れて謝罪したものの、年に一度のこの懇談会が形式化していたことがうかがえる。
そもそもこの件は、水俣病がいまだ解決に至っていないことが背景にある。水俣病未認定患者をめぐる裁判は各地で判断が分かれている。大阪地裁は原告全員を水俣病と認定。熊本地裁は提訴時期が遅いとして全員請求棄却、新潟地裁(新潟水俣病)は6割を認定、4割の請求は退けた。
だが国に水俣病特措法の見直しや政治判断で早期解決を図る気はないらしく、特措法が定める健康調査すらまだ実施されていない。こうした不誠実な対応の延長線上で起きたマイクオフ事件。それは「あなたの話は聞きません」という態度の表明にほかならず、だからみんな怒ったのだ。
環境相の信頼は謝罪だけでは回復できまい。政府や国会も巻き込んで今こそ救済に乗り出すべきだろう。(文芸評論家)」東京新聞2024年5月15日朝刊21面、特報欄「本音のコラム」
環境庁(現環境省)ができたのは、公害問題が大きく注目された高度経済成長の最盛期で、とくに水俣病が公害病として認定されたことが影響していたと思う。公害企業の責任が厳しく問われ、政府もこれを認め対策を講じることになった。タカ派で知られる石原慎太郎も環境相になると、水俣病患者に頭を下げて謝罪したニュースがあったことを記憶する。それが今、このマイクオフ事件に現れた政府の冷たい態度は、その背景に生活保護切り捨てとも通じる弱者への冷笑的視線を感じる。どうしてこうなってしまったのか?自民党長期政権がいかに社会を壊したか、弱肉強食を肯定する思想の蔓延を感じる。
明治から大正期まで文人画家として活躍した富岡 鉄斎(1837〈天保7〉年~1924〈大正13〉年)は、画家といってもこれまで見てきたような画家とは色合いが異なる。日本最後の文人と謳われる儒学者であり、教師でもあった。略歴を見ると、京都(三条通新町東)法衣商十一屋伝兵衛富岡維叙の次男として生まれる。猷輔を通称とし、のちに道昴・道節と称し、明治のはじめ頃、一時名を鉄斎としたが、しばらくのち百錬に改名。字を無倦、号を鉄斎。耳が少し不自由であったが、幼少の頃から勉学に励み、はじめ富岡家の家学である石門心学を、15歳頃から大国隆正に国学や勤王思想を、岩垣月洲らに漢学、陽明学、詩文などを学ぶ。維新後の30歳から40代半まで大和国石上神宮や和泉国大鳥神社の神官(宮司)を務めた。座右の銘である「万巻の書を読み、万里の道を往く」を実践し、日本各地を旅した。明治7年(1874年)には、松浦武四郎との交流から北海道を旅し、アイヌの風俗を題材にした代表作「旧蝦夷風俗図」を描いている。
明治14年(1881年)、兄伝兵衛の死に伴い京都薬屋町に転居し、終の住処とする。教育者としても活躍し、明治2年(1869年)、私塾立命館で教員になる。 明治26年(1893年)、京都市美術学校で教員に就任し、明治37年(1904年)まで修身を教える。明治42年(1909年)2月20日、吐血して胃潰瘍と診断される。胃潰瘍を病んだ後は食事にも工夫をこらし、それまでは鰻と蕎麦、小芋を好み、調理も辛みの煮付けを好んだとされるが、70歳以降は熱粥を常食とした。大正13年(1924年)大晦日、持病であった胆石症が悪化。京都の自宅にて没する。享年89。以上の事項はおもにWikipediaによる。
「鉄斎がこれほどまで旅行を好み、地誌の研究に惹かれた点について、多くの研究者はそれを彼の天性の成功によるものとしている。むろん、もともとそのような性向はあったではあろうが、私は、現実に鉄斎をこれほどまで熱心な行動へと駆り立てた重要なファクターとして、若い頃、久我家の春日潜庵について学んだ陽明学の影響があったことを見逃してはならないと考える。この潜庵春日讃岐守は、陽明学については当代一流の人物で、梁川星巌も佐久間象山に送った手紙のなかで「京師第一等の人物」と賞揚しており、西郷隆盛もその弟を入門させたほどの優れた学者であった。鉄斎の家は、代々石田梅厳の石門心学を家学としており、そのことが鉄斎に陽明学を受け入れ易というくさせた事情もあったろうが、いずれにしても、若い鉄斎に対する陽明学の影響は決定的なものがあった。
明治維新革命の精神的エネルギー源として、陽明学がどのような役割を果たしたかについては、今後いっそう精細に考察すべき問題であろうが、少なくとも、知行合一を説く陽明学の行動主義的教えが、幕末の勤王の志士たちの大きな精神的支えとなったことは疑いのないところであり、事実、春日潜庵の周囲には、薩摩や水戸の志士たちが多く集まっていた。若い鉄斎が、このような雰囲気のなかにあって影響を受けないはずがない。と言って鉄斎は決して偏狭な尊王攘夷論者であったわけではなく、後に見るように文久元年二十六歳の時には、世界の大勢を知るため、わざわざ長崎に出向いたりしているほどであるが、しかし彼は、もし幼少の頃に病んだ胎毒によって耳が不自由になったという不幸がなかったら、おそらく親しかった梅田雲浜や頼三樹三郎などと運命をともにしただろうと言われるほど、当時としては急進的な思想の持主であった。おそらく、陽明学によって養われたそのような行動への情熱が、後年の彼のあの休む間もない調査旅行となってあらわれたものであろう。それなればこそ、その旅行の最中でも、単に自分の学問的好奇心を満足させるだけではなく、つねに国家的方策を念頭に置いていたのである。そのことは、例えば、北海道旅行の際、千島の択捉に思いを馳せて、
北門鎖鑰近如何 独抱杞憂説向誰
欲試千洲開拓策 単身孤剣入蝦夷
と詠んでいることからも充分に想像がつく。大雅の実地踏査による「真景」を高く評価する彼の実証主義的精神も、またこの陽明学の思想と無縁ではない。
このような考え方からすれば、絵画表現において写生を重んじるのは当然のことである。鉄斎の作品は無論単に写実主義と言って片づけられるものではないが、その根底には実地調査にもとづくきわめて近代的な現実把握の精神があったのである。
このことは、現在残されている数少ない彼の画論からもうかがうことができる。例えば、鉄斎が書簡とともに門人に送ったという『南宗画論』のなかで、南派の人は古人の作品を研究すると同時に「其画ノ位置ハ、自己ノ胸中ヨリ組織スベシ。準而他人ノ図ヲ用フベカラズ。一木一石ヲ研究シ、真物ヲ参照シ、造化ヲ手ニ入ルベシ」と説いていることや、鉄斎が折に触れて語った言葉の断片からうかがわれるように、大雅、応挙をきわめて高く評価していたことからも明らかと言ってよいであろう。
興味深いのは、賦彩についての鉄斎の意見である。鉄斎が色彩画家として稀に見る豊かな才能の持ち主であることはすでに定評のあるところだが、『画林』第十号に発表された画論のなかで、色彩について彼は次のように述べている。
「太宰春台が紫芝園漫筆に曰く、画所以図物也。図物者貴肖。水墨不如丹青之拙。且彩色可以養目。故与水墨之工。不若丹青拙。と。春台は儒士にして、深く画事を知るの人に非ずと雖も、其論ずる所は則ち当れり。故に支那は勿論、我邦も上古の画を観るに、所謂画道六法中、応物写形の意にて、即ち写生也。其貴肖となれば、森羅万象其形容を彩色す。是其実物に肖似する所にして、古来人物を画くに皆容貌肉色等に深く意を用い、以て生存の如くなせしは則ち丹青の主意なり。然るに支那宋代に至り、其肖似に束縛せられ、神気活動を欠く所を生じ、写画貴形似を鄙とし、専ら活動を主とすれば、形似にのみ拘泥すべきに非ずとし、水墨画行わるに至る。是れ即ち物久しければ弊を生ずるにて、新奇を発揮するに非ずんば、技芸具妙処を尽すに至らず、是に於て我邦また水墨画の流行するに至り、古来の画法また衰退する支那と同じ。是よりして水墨画遊戯の逸興に趨り、瀟洒淡白の略画盛んになりて技芸一変し、肖重色法は益〻衰退す。蓋し古法の重色彩画容易の技術に非ず。故に竟に速成を喜び、簡略を主とし、遂に絵画の本色を喪うに至る也。円山応挙出るに及んで写生画を復古し、其画事の真趣を一変す。名手と謂うべし」(正宗得三郎著『鉄斎』平凡社 昭和三十六年刊より転載)
この画論における鉄斎の立場は、まことに明快そのものである。要するに、絵は眼に見えるものを写し出すのが本来の役割であるから「丹青の切なるもの」でも、ともかく色があるだけ水墨よりましだという太宰春台の考えをほとんど全画的に肯定しているからである。もちろん、鉄斎の画面そのものが、決して単に「応物写形」でないことは、幾重にも事実であるし、賦彩にしても、現実に見える色をそのまま再現しようとしていたわけではないことは、
「西洋画は絵具で描くが、日本画は墨と藍と代赭があれば、何でも描ける」
という鉄斎の言葉(正宗得三郎 前掲書)からも明らかである。しかしそれにもかかわらず、文人画といえばすぐ「気韻」とか「神韻」という言葉で造形的表現力の不備を誤魔化そうとする傾向がしばしば見られる時、敢えて写実に賭けようとする鉄斎の態度はきわめて健全なものであり、小気味よい爽やかな印象すら与えてくれるのである。
だがそれほどまで明快な、あまりにも単純すぎるほどの写実主義を主張する鉄斎がなぜあの「不尽山頂全図」のような、現実にそう見えることはあり得ない、つまりおよそ非写実的な、山容を描くのであろうか。ここでわれわれは、先ほどしばらく留保しておいた問題に立ち返って、明治三十一年、鉄斎が六十三歳の時に柴田治左衛門のために描いたあの六曲一双の「富士山図」屏風の左右半双をそれぞれ分析比較してみなければならない。
すでに述べたように、この右半双の全山遠望図は、左半双の山頂図は大雅の不二頂上図をその発想の出発点としている。しかしそれは、決してたまたま自分の尊敬するふたりの先輩画家の富士山図を借りて来たというだけのものではない。遠望図と頂上図とを左右に振り分けて、両方合わせて一双になるように組み合わせた全体構想には、鉄斎の明確な意図があったはずである。なぜなら、この両者は、題讃が右半双にしか書き込まれていないことからも明らかなように、ふたつ別々のものとして構想されたのではなく、最初からひと組のものとして考えられたことは疑いないからである。
その鉄斎の意図が那辺にあったかを解明してくれる鍵は、この「富士山図」屏風より二十二年遅れて、大正九年、つまり鉄斎の最晩年に描かれた紙本着色の「富士山図巻」にある。これは、その名の示す通り画巻形式のもので、巻頭に大きく「富士山全図」と篆書で書かれており、それに続いて、富士山全容の遠望図がひとつと、富士山頂図がふたつ描かれている。このふたつの富士山頂図のうち、最初のものは「不二山頂図縮写大雅堂原本」と書き込みがあるところから明らかなように、かつて鉄斎が模写したことのある大雅の山頂俯瞰地図であり、もうひとつが、大雅のその平面的な地図を斜上から見下ろしたようなかたちに立体化したものである。この全容遠望図と最後の立体的な山頂図がそのまま清荒神所蔵の「富士山図」屏風の右半双、左半双にそれぞれつながることは、一見して明らかである。事実、山頂図の部分の切り方や八葉嶽のたたずまい、また遠望図の斜めに白雲の懸かった様子や左手に宝永山の見える構図、さらには、その遠望図の右肩上に長文の題讃を書き込んだ全体のデザインにいたるまで、両者はそっくりそのままと言ってもよいほど酷似している。事実は、この両者のあいだに二十二年の歳月の隔たりがあるのであるが、一見したところ、同じ時に描かれたと言ってもよいほどである。(もっとも、当然のことながら、題讃の文章は異る。鉄斎の作品の場合、後に触れるようにこの題讃の文言がつねに重要な意味を持っているのだが、ここでは、あまりに繁雑になるので割愛する)
ところで、一巻の画巻のなかに、全容遠望図と頂上部分図とをいっしょに描き出したのはいったいどういう意味を持っているのだが、ここでは、あまりに繁雑になるので割愛する)
ところで、一巻の画巻のなかに、全容遠望図と頂上部分図とをいっしょに描き出したのはいったいどういう意味を持っているのだろうか。それは、画巻巻頭の題字を思い出してみれば、容易に想像がつく。その題字の文言は、単に「富士山図」というのではなく、「富士山全図」と書かれている。とすれば、遠望図と頂上図とを合わせたものが、富嶽の「全図」にほかならないということを意味するものであろう。つまり鉄斎にとっては、「富士山全図」とは、決して山頂から山麓までの「全容」を描き出したという意味ではなく、遠望図と頂上図とを合わせたものという意味なのである。
この場合、遠望図と頂上図とは、例えば広角レンズと望遠レンズとで撮影した全体図と部分図という関係ではない。すでに屏風絵の分析のところで述べたように、それは富士という自然に対する人間の対し方のふたつの異なったタイプを示す。すなわち、遠望図は「眺められた世界」、つまり知的認識者の自然把握であり、山頂図の方は「体験された世界」、つまり行動者の捉えた自然である。前者は「万巻の書を読む」鉄斎の見た富士であり、後者は「万里の路を行く」鉄斎が実際い肌で感じた富士だと言ってもよい。そして、視覚を通しての知的認識と、行動を通しての体験的把握とのこのいずれが欠けても、自然を完全な意味で捉えることはできない。富士は、遠くから仰ぎ見るのみでなく、自から実地にその山頂を踏破してはじめて、その「全貌」を人間の前に示してくれるのである。
すでに見たように、鉄斎があれほどまで大雅の富士に傾倒していたのも、おそらくは大雅がほとんど本能的にこのふたつの異なった自然把握を実践していたからに違いない。鉄斎がただ一度自ら富士に登ったのは、明治八年彼が四十歳の時のことであったが、後年、『賀史登岳』の中でその時の思い出を語るときにも、既に大雅が自分に先立って徹底的な「実地調査」を行ったことを、いささか口惜しげにつけ加えることを忘れなかった。すなわち、彼はこう語っている。
「……余は明治八年七月、甲州吉田口より登り、絶頂に一泊し、翌日駿河口へ降り、麓を巡覧し、不残見めぐり、又富士山眺望地彼是経歴せるも、大抵大雅皆既に遊歴せる所たり」(傍点高階)
つまり鉄斎にとっては、かつて大雅にとってそうであったように、実地に富士を訪れて「残らず見めぐ」らなければ、完全に富士を知ってとは言えなかったのである。
富士の遠望図と頂上図の持つこのような意味が明らかになれば、明治三十一年の屏風絵一双の意図も自ずからまた明らかであろう。それは右半双に遠望図、すなわち認識者の世界を、左半双に頂上図、すなわち行動者の世界を描いて、両者合わせて完全な富士の姿を示そうとしたものである。したがってこの両者は、等しく富士を対象としながら、まったく異なったアプローチの方法を示している。両者が、その構成のみならず、表現法や筆使いにいたるまで、まったく対照的な性格を見せているのも、当然のことなのである。
事実、右半双の遠望図においては、知的認識の世界にふさわしく、すべてが落ち着いた平静な表現であるのに対し、左半双の頂上図では、逆に行動的世界を暗示するように、すべてが激しくダイナミックな表現になっている。遠望図では、雲もあるかなきかの風に静かに棚引き、富士は永遠の不動性を備えて無言のまま佇立しているのに反し、山頂図では、雲も荒海の坂巻く大浪のようにうねり、岩塊は画面から飛び出さんばかりの勢いでせめぎ合っている。当然、遠望図は平面的で艶麗な装飾性を見せ、山頂図は立体的でダイナミックな生命感を感じさせる。その筆の勢いは、自ずから「鉄斎外史」と書かれた署名にまで及び、遠望図の署名が折り目正しい楷書体であるのに対し、山頂図の署名は畢生激しい行書体で書かれている。そしてこの山頂図が、一見およそ実際にあり得ないように思われる不自然な相貌を見せているのも、それがどこか架空の空中の一点から「眺められた」ものではなく、この山頂を自からの足で「残らず見めぐ」った鉄斎の体験の総和にほかならない以上、当然のことなのである。この山頂図が、「不尽山頂図」ではなくて、「不尽頂全図」である所以も、おそらくそこにある。それは、もし写実主義という言葉で呼ぶなら、きわめて徹底した写実主義と言うべきであろう。しかも、そのように全山くまなく踏破して獲得された体験的世界と、遠くから眺められた視覚的世界とを合わせてはじめて完全な富士の姿を捉えることができるというのは、さらに徹底した写実主義と言わなければならない。
しかしながら、知的認識と行動的認識とを統一したこのような世界を支持する言葉としては、写実主義という呼称は、あまりにも西欧の伝統的世界と馴れ合い過ぎている。鉄斎のこの富岳図の背後にあるのは、西欧流の写実精神ではなく、やはり知行合一の思想であろう。鉄斎のみならず、幕末から明治にかけての革新的な若者たちに大きな影響を与えた陽明学は、鉄斎のこの「富士山図」屏風一双のなかに、そのもっとも見事な造形化を持つことができたのである。」高階秀爾『日本近代美術史論』講談社文庫、1980年、pp.302-311.
富士山を描くのに、遠くから眺めるだけでなく実際に登って火口まで体感し、その全体像を描き、さらに文章を添える。これは画家というよりは、知行合一の思想家の仕事で、まさに最後の文人だな。

B.反省…
このブログの記述について、グーグルと朝日新聞などの管理者から警告を戴いた。新聞記事や画像を無断でここに引用・掲載したことで、著作権法への抵触が疑われるため、閲覧停止の措置をとったとのこと。なるほど、記事や写真などをそのまま全文引用している箇所がある。どこからの引用か、出所出典は文章については必ずページまで示したつもりだが、画損はネットで採集してオリジナルは示していない(示せない)。これは確かに、著作権に抵触するといわれれば、その通りであり、閲覧停止となっても仕方がない。したがって、今後はできるかぎり全文引用は避け、画像についても作成者撮影者等の情報を添え、それがないものは避けるようにしたい。
というわけで、以下は東京新聞掲載のコラムだが、愛読しているので、短いもので読者に拡散したい内容であるのと、コメントをつけることでお許しいただきたい。
「形式化した3分 斎藤美奈子
伊藤信太郎環境相と水俣病被害者団体との懇談会(1日)で環境省側がマイクを切った件。
ネット上のニュース動画で一部始終を見てみると、やっぱりひどいと思わざるを得ない。3分を過ぎるや否や「お時間でございます」「お話をおまとめください」と繰り返す司会者(環境省の担当室長)。「聞いてやれ絵や大臣」などの声を無視したうえ、会の最後に国会答弁よろしくペーパーを読むだけの大臣。
8日、大臣と室長は再び水俣を訪れて謝罪したものの、年に一度のこの懇談会が形式化していたことがうかがえる。
そもそもこの件は、水俣病がいまだ解決に至っていないことが背景にある。水俣病未認定患者をめぐる裁判は各地で判断が分かれている。大阪地裁は原告全員を水俣病と認定。熊本地裁は提訴時期が遅いとして全員請求棄却、新潟地裁(新潟水俣病)は6割を認定、4割の請求は退けた。
だが国に水俣病特措法の見直しや政治判断で早期解決を図る気はないらしく、特措法が定める健康調査すらまだ実施されていない。こうした不誠実な対応の延長線上で起きたマイクオフ事件。それは「あなたの話は聞きません」という態度の表明にほかならず、だからみんな怒ったのだ。
環境相の信頼は謝罪だけでは回復できまい。政府や国会も巻き込んで今こそ救済に乗り出すべきだろう。(文芸評論家)」東京新聞2024年5月15日朝刊21面、特報欄「本音のコラム」
環境庁(現環境省)ができたのは、公害問題が大きく注目された高度経済成長の最盛期で、とくに水俣病が公害病として認定されたことが影響していたと思う。公害企業の責任が厳しく問われ、政府もこれを認め対策を講じることになった。タカ派で知られる石原慎太郎も環境相になると、水俣病患者に頭を下げて謝罪したニュースがあったことを記憶する。それが今、このマイクオフ事件に現れた政府の冷たい態度は、その背景に生活保護切り捨てとも通じる弱者への冷笑的視線を感じる。どうしてこうなってしまったのか?自民党長期政権がいかに社会を壊したか、弱肉強食を肯定する思想の蔓延を感じる。