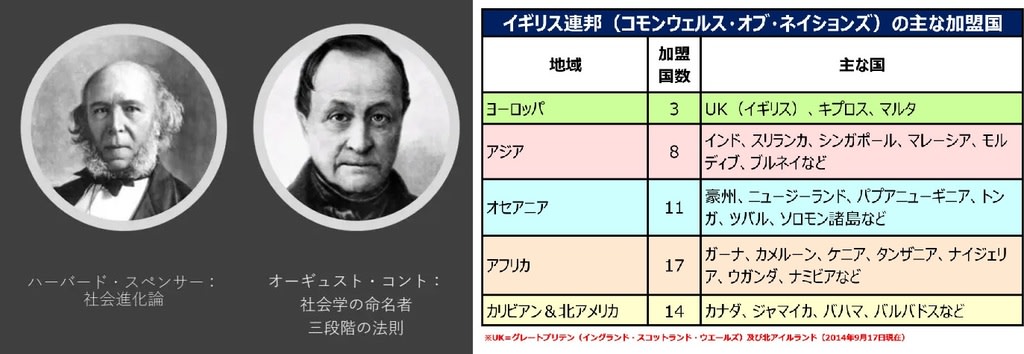A.「現代小説作法」を読む
戦後まもなく、「野火」「俘虜記」などを発表した小説家大岡昇平は、1958年1月から翌59年12月まで雑誌『文学界』に「現代小説作法」という文章を連載し、1962年8月に単行本となって文芸春秋社から刊行された。その後も、著者は版が改まるたびに改訂をしたという。1998年79歳で亡くなるまで、この小説論には手を加えて、小説家がみずからの作品についてではなく、近代の小説というものを本格的にその技法と過去の名作の読み込みについてやさしい語り口で説いた著作として、半世紀経ったいまも読むに値するものだと思う。もともと、スタンダールの研究家であり、太平洋の戦争に30過ぎで徴兵され、フィリピン・レイテ島で日本軍兵士として戦い、捕虜となった経験を小説にするという特異な経歴をもつ大岡が、こうした文学論を書いたのは、この人が戦後日本文学でしかるべき地位を占め、書くべきものをいちおう書いてしまったあとで次に向かう助走ということもあっただろうが、それ以上に西洋起源の近代小説という形式が、20世紀後半の現代社会には、そぐわない時代とのずれを意識していたからだと思える。それは日本の文壇というような狭い世界の話題ではなく、世界の文学の新しい潮流を元に遡って考えていたことからくるように思う。
「話のうまさというものは、話し手の声音や表情と結びついています。印刷された文字を通しても、われわれはそれを感じます。これは小説にあっては、むしろ場違いといえるかもしれませんが、純粋な散文というものは、純粋な水がないように、この世にはないものらしい。
メリメ、モーパッサンの短編を読むと、美しく着飾った貴婦人の前で、細いがよく通る声で語るサロンの洒落者の様子が目に見えるような気がしますし、西鶴の短編を読めば、湯吞をささげて喉をうるおす今日の落語家の身ぶりのようなものを感じます。
デイケンズやデフォーがうまい語り手である例は前章で示しましたが、彼らは相次いで起こる事件や息つく暇もない我々の側の緊張を、先刻承知という顔付で、かえって落着払い、あれやこれやの尾鰭をつけて、いつ果てるともしれない長話に、自ら陶酔している作者の内心が読み取れます。
小説は今日散文の代表、つまりもっとも客観的なものみたいにいわれていますが、何度も書いたように、ほんとうは語り手は聞き手を予想しなければ成り立たないので、大変人間臭く、幻想を許容するジャンルなのです。
話である以上、聞き手にとって、興味あるものでなければならない。われわれに涙をしぼらせる悲しい話、げらげら笑わせる面白い話でなくても、遠い異国の物珍しい話、あるいは伝説、怪異譚を伝えるのも、古くから小説の目的の一つでした。紀行文的要素、ドキュメンタリー的要素は最初から小説に付随していたので、現代の主人公が観光的名所ですれ違ったり、新聞記事にちょっと味をつけただけのルポルタージュ風の小説が行われるのも理由なしとしないのです。
ストオリーが小説の根底でありながら、現代ではなんとなく、下等な、いわば小説の恥部のように感じられるに到ったのは、前世紀のフロベールや、エリオット、メレディスに代表されるリアリズムの小説美学のためです。
夏目漱石はがんらい「坊っちゃん」に見られるようにすぐれた話し手なのですが、ヴィクトリア朝の小説美学にとらわれて、だんだん重苦しい小説を書くようになりました。漱石の偏見がどういうものであったかは、デフォーを論じた「文学評論」のうちにも、うかがわれます。「文学評論」は十八世紀のイギリス文学を論じたもので、日本の外国文学研究の中で、唯一といってもいいくらい、材料をよくこなした論文ですが、デフォーは始終下等な雑駁なジャーナリストとして扱われている。そこに時代の流行、日本流の文人気質を示しています。」大岡昇平『現代小説作法』ちくま学芸文庫、2014年、pp.52-54.(原著は1962年文藝春秋新社から刊行され、その後なんどか改訂されている)
この本の第一章「小説に作法があるかという問題」で、これがたんなる小説を書く作法、技術の指導書ではないし、そんなものを過信するのはまちがいだと述べ、第二章「小説はどう書きだすべきか」で、小説の第一の条件は主題、読者が面白く新鮮だと感じる主題が何であるか、作者自身がそれを明確に把握することが重要だと指摘する。あとは小説はいかに書かれてきたか、を古今の作品に即して分析的に述べていくという形をとる。
「プロットは普通「筋」と訳され、ストオリーと混同されがちですが、実ははっきりした区別があります。
Plotは英語で、フランス語ならアントリーグintrigue、「計略」「陰謀」が第一義で、「校長排斥のプロットがあった」という風に使われます。従って「筋立」とか「仕組」と訳す方が適切です。
ストオリーは時間の順序に従って、興味ある事件を物語るけれど、プロットは物語る順序を、予め「仕組む」ことを意味します。重大な事件は物語の始まる前に起こっていて、あるいは最後の章で判明する場合もあります。出来事のすべてを物語るわけではなく、結末に予定されている事件に、関連のあるものだけを書く。最後の章に到って、それらの「伏線」が一つの結末に向かって統一されているのを知って、読者は一種の満足感を味わいます。
「王が死に、それから王妃が死んだ」と書けばストオリーだが、「王が死に、悲しみのあまり王妃が死んだ」あるいは「王妃が死んだ。そのわけは誰も知らなかったが、王の崩御を悲しんだためであることが分かった」と書けばプロットだ、と「インドへの道」の作者フォースターが書いています。(「小説の諸相」田中西二郎訳、新潮文庫)
結局は物語る技術の一種ですが、これが前世紀以来重視されるようになったのは、教育が普及して読者が進歩したからです。読者は書かれた事実を理解する能力を有し、結末もある程度予測できますから、「それからどうなったの」というような、子どもらしい好奇心を持ち続けるとはかぎりません。プロットは教養ある読者を満足させる手段ということが出来ます。
近頃誰それは、「すぐれたストオリー・テラーだ」といわれることがありますが、実際はプロットの立て方のうまいことを意味する場合が多いのです。新派や歌舞伎で「趣向」といわれたものに当るので、自然主義以来、趣向は実感の伴わないものとして、排斥されていました。
小説家が小説に取り掛かる前に、プロットを考えておく方がいいといわれるようになったのは、読者がそういう実感尊重や写実的短編に飽き、筋のある長編小説を求めるようになった昭和中期以後です。しかし実際は作家がこの問題をどんな風に処理していたかは、次の川端康成の証言にあらわれています。
「実際創作に当ってゐる人の体験を聞くと、日本の作家にはあまり筋(プロット)を考へず、書き出しに色々と苦心をし、あとはその場その場で最も妥当と思はれる方向に小説を運んでゆくといふ人がかなりゐるやうである。また最初から作品の筋を全部考へておいて、それに従って整然と書き進めるといふ方法による作家もある。これは両方ともプロットが有るのであって、前者はとかくプロットがないといふやうに考へられがちであるけれども、これは間違ひである。主題がはっきりときまって作者の肚が出来上ってゐれば、プロットは自らきまってゆくことが多い」(「小説の研究」角川文庫)
これは川端氏の体験に基づいた言葉であるだけに貴重です。事実今日でも新聞雑誌の零細小説は、たいていその場その場の即興で運ばれ、結末で辻褄を合わせるという風に書かれることが多いので、厳密な意味でプロットを立てて書いた作家は、藤村、荷風、潤一郎ぐらいなものかも知れません。
彼らの作品がいつまでも読むにたえる理由の一つはここにありますが、しかし川端氏の方法も大変実際的です。あまりきっちり計算しない方が、人物が生きて来るということもあるのでいちがいには言えません。それはだんだん考えて行くつもりですが、ここに一つ、どうしてもプロットを決めておかないと、始められない種類の小説があります。推理小説です。
推理小説は前世紀では卑俗な小説と考えられて、文学史にも記載されないのが例でしたが、現代のように流行して来ると、ただ読者の好奇心だけを満足させる、時間つぶしのジャンルとして、軽蔑してスませることは出来まいと思われます。
イギリスでグリーンのようなカトリックを標榜する作家、ルイスのような知的な詩人が推理小説を書いているというようなことは、例外と考えてもよいくらいまれですが、一般に現代小説の全部が推理小説に近づいているのが事実です。推理小説の方でも、犯人や被害者の社会的境遇をバルザックの手法で書き、被害者の心理を「意識の流れ」のような前衛的な手法で描くようになっています。
犯罪は平和時にあっては、最も刺激的な事件であり、「赤と黒」や「罪と罰」も結局は一つの犯罪をめぐる物語です。ただこれらの傑作では、犯人は初めから主人公とわかっていて、犯罪を犯すに至る経路、あるいは犯行後の心理が主題となっているのに反し、推理小説は原則として、誰が犯人であるかはわからず、図の明晰な探偵がそれを探り出す興味が中心になっています。
作者は犯人が誰であるか、最初から知っているし、犯行の細部もあらかじめ考えてある。それを徐々に読者にわからせて行く、あるいはわざと読者を迷わすような被疑者を出したり引っ込めたりしながら、最後の意外な解決によって、一挙に読者の好奇心と期待に満足を与える仕組になっています。
こういう小説はあらかじめプロットが出来なくては、一行と言えども書き下ろすわけにはいかないのは明瞭です。推理小説は1841年のポーの「モルグ街の殺人」が最初といわれ、比較的新しいジャンルですが、近代社会は都会への人口の集中、悪漢共の増加につれて、犯罪の手口も複雑になり、従って警察の捜査方法も進歩したから、推理小説の材料はだんだん豊富になった。
昔の山賊や海賊はアウト・ロウで、巣窟も人相もわかっている。それを討伐する兵力が、権力の側にあるかどうかという問題でしたが、現代では市民のほとんど全部が、犯人になる機会を持っています。毒薬は薬局で手に入るようになったから、婦人もたやすく人が殺せるようになった。
「誰が殺したか」推測困難な業になったので、シャーロック・ホームズ以来おびただしい数の「謎解き」が考案されたのも当然ですが、一方読者の方も進歩して、建てつけの悪いプロットでは、すぐ見抜かれてしまいます。犯人が誰かが先にわかってしまっては、推理小説の興味はゼロでしょう。
新聞雑誌の書評でも、推理小説の筋は知らせないのが例であり、読者も最後の頁は、まるでこわいもののように大事にしています。本を手に取った時、そこが開いてしまったら、あわてて目をつぶるぐらいの用心をします。およそ一冊の「本」がこれほど大事にされるのは、聖書や仏典以来、例がないのではないかと思われます。小説がこれほど技巧を要求されたことはありません。
無論こういうプロットの勝利は、作中人物の性格の歪曲や、実感の犠牲なしにはすまされないので、推理小説はもともと現実を遊離した頭脳の戯れなのですが、この高度の技術性は他の文学にも影響を与えています。
シャーロック・ホームズのベーカー街の応接室は、様々の依頼人が悩みをたずさえておとずれる場所であり、初対面の人として、ホームズの炯眼の前に、その階級、気質、経歴の徴候を露出するので、「見知らぬ人」の外面描写として、すぐれた例を残しました。今日の目から見ればホームズの探偵術は幼稚なものですが、こういう細部がよく出来ているので、いつまでも読まれるのです。」大岡昇平『現代小説作法』ちくま学芸文庫、2014年、pp.59-64.
以上は第五章「ストオリーについて」と第六章「プロットについて」の一部だが、小説というものを書くにあたって作者がなにを考えるのかを、実作者ならではの実際的な問題を、広く深く考察するというもので、いまもなお本質的な議論につながると思う。推理小説のつくり方は今も不動だが、大衆向け小説のなかにミステリーがこれほど大量にもてはやされ書かれるに至ることを、高度経済成長期のはじめに見通していた大岡は、やがて自身で「事件」などの推理小説も書いた。

B.戦争の転機になるか?
ロシアの侵攻に始まり半年を過ぎたウクライナの戦争が、ここに来て東部戦線でのヘルソン州などの奪還に成功し、一方でロシア軍の占領地域での住民投票実施という新たな局面が起っている。ロシア軍の疲弊を補おうとプーチンは、予備役の大量徴兵を打ち出してロシア国民から反発を受ける状況も報じられている。これをどう見るか、この先がどうなるか、まだ予断は許さないが、冬を控えいくつか予測は出てきた。
「ウクライナの戦況とロシアの危機 :内田 樹 神戸女学院大学名誉教授・凱風館館長
ウクライナの戦況が大きく変動した。東部戦線においての長期にわたる戦線膠着の後、ウクライナ軍が失地回復を果たしたのである。
ウクライナ軍にはタイムリミットがあった。冬が来る前に攻勢に出るということである。冬を迎えると、ロシアの天然ガスに依存している西欧諸国ではエネルギー不足から国民の間で厭戦気分が亢進する可能性が高い。自分たち自身の生活の不便に苦しむ市民たちの間から「先の見えない長期戦になったらウクライナのことは見限ろう」という冷ややかな世論が高まり、欧米諸国のウクライナ支援の足並みが乱れることをプーチンは予測していたと思う。しかし、寒くなる前に電撃的な反攻が成功してしまった。この反攻で「戦争はどちらもが決定的な勝利を収めることができぬまま、いつまでもだらだら続くだろう」という予測は修正を余儀なくされた。予想より早く決着がつくかもしれない。
今回のウクライナの反攻はロシア軍の練度が低く、士気が低下していることを明らかにした。ロシア軍の兵器や弾薬が大量に鹵獲されたという報道がなされているが、それが事実ならロシアの兵士たちがウクライナ軍の侵攻に虚を衝かれて戦線を維持できなかったことを意味している。「生き残れるものは生き延びよ」というのは船が沈没する時や軍隊で前線が崩れて指揮系統が機能しなくなった時に船長や指揮官が発令する言葉である。この後、どうすればいいかについては誰も指示をしない。あとは自分の才覚で生き延びてくれということである。短期間にこれほどの広域にわたってウクライナ軍が国土を奪還できたということはロシア軍の相当部分が「生き延びるために算を乱して敗走した」ことを意味している。欧米の報道は軍事支援の効果を重視しているが、私は「ロシア軍の士気の低さ」の方がむしろ気になった。
ただ、この知らせに、ウクライナを支援している欧米諸国は安堵と同時に不安をも感じてもいるはずである。アメリカは自国からはるかかなたで行われている戦争のせいでロシアの国際社会における地位が低下し、国力がじわじわと削り取られてゆく現状を好ましいものと見なしている。もちろんロシアが主権国家の領土を武力で併合することは許されないことだが、ウクライナが完全勝利するというシナリオもまた欧米にとっては決して歓迎すべきものではない。それがロシア国内に(プーチンの退陣を含む)劇的な政局の変動をもたらすリスクがあるからである。
プーチンがグリップできなくなったロシアがどういう混乱を来し、国際社会に対してどういうふるまいをするか、確実な予測をできる人間はどこにもいない。私たちは、旧ソ連末期のロシアの混乱を記憶している。ふたたびクーデターやデモが繰り返され、統治機構が麻痺し、新しい「オリガルヒ」たちが登場して国有財産の私物化を図り、武器が「死の商人」に売り飛ばされ、自由を求める市民が国から逃れ出る…何よりも大量の核兵器を有した国のカオス化は世界にとって恐怖以外の何ものでもないのである。
すでに各国の情報機関はロシアの政治混乱がもたらすリスクについてのリストを気欝な顔で作成し始めていると思う。」東京新聞2022年9月25日朝刊5面、時代を読む欄。
追い詰められたプーチンが、核兵器のボタンを押すのではないかというのが、世界の最大の恐怖であることは、誰もが思うことだ。