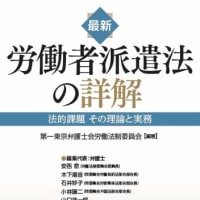Q14使用者と社員が合意することにより,以下のような定めをすることはできますか?
① 1日の所定労働時間を12時間として,基本給を1日12時間×所定労働日数勤務したことに対する対価とすること
② 週40時間,1日8時間を超えて労働した場合でも残業代を支給しないとすること
③ 残業代込みで月給30万円とすること
④ 一定額の残業手当を支給するとすること
①についてですが,労基法32条2項は,「使用者は,1週間の各日については,労働者に,休憩時間を除き1日について8時間を超えて,労働させてはならない。」と定め,労基法13条は,「この法律で定める基準に達しない労働条件を定める労働契約は,その部分については無効とする。その場合において,無効となった部分は,この法律で定める基準による。」と規定しています。
労基法の強行的直律的効力(労基法13条)により,労働契約の1日の所定労働時間が12時間という部分は無効となり,所定労働時間は労基法32条2項が上限とする8時間となると考えられます。
したがって,①1日の所定労働時間を12時間として,基本給を1日12時間×所定労働日数勤務したことに対する対価とすることはできないことになります。
なお,8時間を超える労働時間の割増賃金の支払が基本給の支払によってなされていると評価できるとの反論も理屈では考えられなくはありませんが,所定労働時間分の賃金と時間外労働分の割増賃金に当たる部分を明確に区分して合意していない以上,基本給の支払はあくまでも所定労働時間の労働に対する対価であると判断されるリスクが高いものと思われます。
その結果,使用者は1日8時間を超える部分の労働時間について想定外の割増賃金の支払を労基法37条により強制されるのみならず,通常賃金・割増賃金の時間単価についても,使用者が想定していたものよりも高額となってしまうことになりますので,所定労働時間は1日8時間以内で合意した上で,割増賃金については基本給とは明確に分けて支払うようにしておくべきと考えます。
使用者が,社員との間で,週40時間,1日8時間を超えて労働した場合であっても残業代を支払わない旨の合意をしていたとしても,労基法の強行的直律的効力(労基法13条)により当該合意は無効となり,法定時間外労働時間に対応した労基法37条所定の割増賃金(及び通常の賃金)の支払義務を負うことになります。
したがって,②のように,週40時間,1日8時間を超えて労働した場合でも残業代を支給しないとすることはできず,残業代を支払わない合意があるから支払わなくても大丈夫だと思って残業代を支払わないでいると,残業代を支払わないことにいったんは納得していた社員が,解雇されたことなどを契機に気が変わって残業代を請求してきたような場合には,使用者は未払となっていた残業代を支払わなければならないことになります。
年俸制を採った場合であっても,使用者は残業代の支払義務を免れませんから,ご注意下さい。
中小企業の中には,それなりに高額の基本給・手当・賞与を社員に支給し,昇給までさせているにもかかわらず,残業代は全く支給しない会社が散見されます。
社員の努力に対しては,月給や賞与の金額で応えているのだから,それで十分と,経営者が考えているからだと思われます。
しかし,基本給の金額が上がれば割増賃金の単価が上がることになり,かえって,高額の割増賃金の請求を受けるリスクが高くなりますし,賞与の支給は割増賃金の支払の代わりにはなりません。
高額の基本給・手当・賞与は,社員にとって望ましいことなのかもしれませんが,使用者としては,まずは法律を守る必要があります。
労基法37条の定める以上の割合による割増賃金の支払をした上で,さらに高額の賞与の支給を行うのであればいいのですが,法律を守らずに,残業代の支払を怠った状態で,高額の賞与等を支給するのは本末転倒です。
支払う順番を間違えたばかりに,高額の割増賃金請求を受けることのないよう,十分に注意して下さい。
中小零細企業などでは,③のように,残業代込みで月給30万円などと口約束して,社員を雇っている事例が散見されますが,このような賃金の定め方は,トラブルが多く,訴訟になったら負ける可能性が極めて高いやり方です。
労働契約書,労働条件通知書,給与明細書などで残業代相当額が明示されていないと,通常の賃金にあたる部分と残業代にあたる部分を判別することができないため,残業代が全く支払われておらず,30万円全額が残業代算定の基礎となる賃金額であると認定されるのが通常です。
残業代込みで月30万円と約束しており,それで文句が全く出ていないのだから,そのような訴訟が提起されるわけはない,少なくともうちは大丈夫,と思い込んでいる経営者もいるかもしれませんが,甘い考えと言わざるを得ません。
現実には,退職を契機に,未払残業代を請求するたくさんの労働審判,訴訟が提起されており,残業代の請求に必要な情報は,インターネットをちょっと検索してみれば,簡単に見つかります。
また,訴訟になれば,労働者側は必ず,「月給30万円に残業代が含まれているなんて話は聞いたことがない。」と主張するに決まっており,そうなってから使用者側が後悔しても後の祭りです。
現時点で在籍している社員から文句が出ていないのは,社長の機嫌を損ねて職場に居づらくなるのが嫌だからに過ぎず,退職させられるような事態が生じた場合は,躊躇なく,会社に対して未払残業代の請求をするようになります。
残業代の請求を受けてから,「文句があるんだったら,最初から言ってくれればよかったのに。」と嘆く社長さんが大勢いるのは残念なことです。
本来であれば,全ての会社が,すぐにでも制度変更して,通常の賃金にあたる部分と残業代にあたる部分を区別できるような形で賃金を支払うようにすればいいのですが,一度,痛い目にあってからでないと,なかなか,対策が採られないというのが実情です。
そういった無防備な会社をターゲットにした残業代請求が,ビジネスモデルとして確立しつつある印象ですので,ご注意下さい。
④のような一定額の残業手当を支給するとすること(残業代定額制)についてですが,所定労働時間分の賃金と時間外労働分の割増賃金に当たる部分を明確に区分して合意し,かつ,労基法所定の計算方法による額がその額を上回る場合には,その差額を当該賃金の支払期に支払うことを合意しているのであれば,有効と考えられています。
残業手当の金額が不足している場合は,使用者は不足額について支払義務を負うことになりますので,残業手当の金額が低すぎることがないよう注意する必要があります。
例えば,基本給21万円,時間外勤務手当1万円では,ちょっと残業しただけで,時間外勤務手当が不足することになってしまいます。
とはいえ,初めから極端な長時間労働を予定して,基本給と比較して高額の定額残業代を支払うことにしておかなければならないようでは,労働安全衛生上の問題が生じかねないのではないかとの懸念が生じますし,労働者のモチベーションを下がって優秀な人材を確保する障害になりかねませんので,その金額は,1月あたり45時間分程度までにとどめておくべきなのではないかと考えています。
例えば,基本給14万円,時間外勤務手当8万円といった極端な比率に設定することは,やめるべきでしょう。
少なくとも,私は,そのような比率で賃金設定のなされている会社で働きたくはありません。
これでは,長時間労働を当然に予定していることを,宣言しているようなものです。
また,一か月あたりの平均所定労働時間が160時間の会社でこのような賃金額を定めた場合,基本給14万円÷160時間=875円/時となってしまい,下手するとパート・アルバイトよりも低い時間単価となってしまいます。
ボーナスを考慮すれば,パート・アルバイトよりも賃金が高くなる可能性はありますが,これでは,働く意欲が削がれ,常に転職先を探しながら仕事をするということになりかねません。
なお,残業代定額制を採用する場合は,営業手当等の名目で一定額を支給するよりも,「時間外勤務手当」等,それが残業手当であることが給与明細書の記載から直ちに分かるよう記載しておくと,労使紛争となるリスクが減少する印象です。
なぜなら,弁護士等が労働者から相談を受け,割増賃金が不払となっているかどうかを検討する際,給与明細書の記載を参考にすることが多いからです。
給与明細の時間外勤務手当欄に記載されている金額については残業手当の趣旨で支給していることが明らかですが,営業手当等の欄に記載されている金額についてはその文言から直ちに判断することができないため,残業手当の趣旨ではないという前提で労働審判を申し立てられることになりやすく,労使紛争を十分に予防できないことになってしまいます。
また,入社以来,給与明細書の時間外勤務手当欄に十分な金額の時間外勤務手当が記載されて支給されているのであれば,そもそも,労働者は残業代については不満に思いませんから,残業代だけのために弁護士等に相談することはないという面もあります。
労働審判等の対応が会社にとって大きな負担となることは明らかなのですから,訴訟で勝てばいいというものではなく,労使紛争が生じないようにするための方法を考えていくことが重要です。
弁護士 藤田 進太郎
① 1日の所定労働時間を12時間として,基本給を1日12時間×所定労働日数勤務したことに対する対価とすること
② 週40時間,1日8時間を超えて労働した場合でも残業代を支給しないとすること
③ 残業代込みで月給30万円とすること
④ 一定額の残業手当を支給するとすること
①についてですが,労基法32条2項は,「使用者は,1週間の各日については,労働者に,休憩時間を除き1日について8時間を超えて,労働させてはならない。」と定め,労基法13条は,「この法律で定める基準に達しない労働条件を定める労働契約は,その部分については無効とする。その場合において,無効となった部分は,この法律で定める基準による。」と規定しています。
労基法の強行的直律的効力(労基法13条)により,労働契約の1日の所定労働時間が12時間という部分は無効となり,所定労働時間は労基法32条2項が上限とする8時間となると考えられます。
したがって,①1日の所定労働時間を12時間として,基本給を1日12時間×所定労働日数勤務したことに対する対価とすることはできないことになります。
なお,8時間を超える労働時間の割増賃金の支払が基本給の支払によってなされていると評価できるとの反論も理屈では考えられなくはありませんが,所定労働時間分の賃金と時間外労働分の割増賃金に当たる部分を明確に区分して合意していない以上,基本給の支払はあくまでも所定労働時間の労働に対する対価であると判断されるリスクが高いものと思われます。
その結果,使用者は1日8時間を超える部分の労働時間について想定外の割増賃金の支払を労基法37条により強制されるのみならず,通常賃金・割増賃金の時間単価についても,使用者が想定していたものよりも高額となってしまうことになりますので,所定労働時間は1日8時間以内で合意した上で,割増賃金については基本給とは明確に分けて支払うようにしておくべきと考えます。
使用者が,社員との間で,週40時間,1日8時間を超えて労働した場合であっても残業代を支払わない旨の合意をしていたとしても,労基法の強行的直律的効力(労基法13条)により当該合意は無効となり,法定時間外労働時間に対応した労基法37条所定の割増賃金(及び通常の賃金)の支払義務を負うことになります。
したがって,②のように,週40時間,1日8時間を超えて労働した場合でも残業代を支給しないとすることはできず,残業代を支払わない合意があるから支払わなくても大丈夫だと思って残業代を支払わないでいると,残業代を支払わないことにいったんは納得していた社員が,解雇されたことなどを契機に気が変わって残業代を請求してきたような場合には,使用者は未払となっていた残業代を支払わなければならないことになります。
年俸制を採った場合であっても,使用者は残業代の支払義務を免れませんから,ご注意下さい。
中小企業の中には,それなりに高額の基本給・手当・賞与を社員に支給し,昇給までさせているにもかかわらず,残業代は全く支給しない会社が散見されます。
社員の努力に対しては,月給や賞与の金額で応えているのだから,それで十分と,経営者が考えているからだと思われます。
しかし,基本給の金額が上がれば割増賃金の単価が上がることになり,かえって,高額の割増賃金の請求を受けるリスクが高くなりますし,賞与の支給は割増賃金の支払の代わりにはなりません。
高額の基本給・手当・賞与は,社員にとって望ましいことなのかもしれませんが,使用者としては,まずは法律を守る必要があります。
労基法37条の定める以上の割合による割増賃金の支払をした上で,さらに高額の賞与の支給を行うのであればいいのですが,法律を守らずに,残業代の支払を怠った状態で,高額の賞与等を支給するのは本末転倒です。
支払う順番を間違えたばかりに,高額の割増賃金請求を受けることのないよう,十分に注意して下さい。
中小零細企業などでは,③のように,残業代込みで月給30万円などと口約束して,社員を雇っている事例が散見されますが,このような賃金の定め方は,トラブルが多く,訴訟になったら負ける可能性が極めて高いやり方です。
労働契約書,労働条件通知書,給与明細書などで残業代相当額が明示されていないと,通常の賃金にあたる部分と残業代にあたる部分を判別することができないため,残業代が全く支払われておらず,30万円全額が残業代算定の基礎となる賃金額であると認定されるのが通常です。
残業代込みで月30万円と約束しており,それで文句が全く出ていないのだから,そのような訴訟が提起されるわけはない,少なくともうちは大丈夫,と思い込んでいる経営者もいるかもしれませんが,甘い考えと言わざるを得ません。
現実には,退職を契機に,未払残業代を請求するたくさんの労働審判,訴訟が提起されており,残業代の請求に必要な情報は,インターネットをちょっと検索してみれば,簡単に見つかります。
また,訴訟になれば,労働者側は必ず,「月給30万円に残業代が含まれているなんて話は聞いたことがない。」と主張するに決まっており,そうなってから使用者側が後悔しても後の祭りです。
現時点で在籍している社員から文句が出ていないのは,社長の機嫌を損ねて職場に居づらくなるのが嫌だからに過ぎず,退職させられるような事態が生じた場合は,躊躇なく,会社に対して未払残業代の請求をするようになります。
残業代の請求を受けてから,「文句があるんだったら,最初から言ってくれればよかったのに。」と嘆く社長さんが大勢いるのは残念なことです。
本来であれば,全ての会社が,すぐにでも制度変更して,通常の賃金にあたる部分と残業代にあたる部分を区別できるような形で賃金を支払うようにすればいいのですが,一度,痛い目にあってからでないと,なかなか,対策が採られないというのが実情です。
そういった無防備な会社をターゲットにした残業代請求が,ビジネスモデルとして確立しつつある印象ですので,ご注意下さい。
④のような一定額の残業手当を支給するとすること(残業代定額制)についてですが,所定労働時間分の賃金と時間外労働分の割増賃金に当たる部分を明確に区分して合意し,かつ,労基法所定の計算方法による額がその額を上回る場合には,その差額を当該賃金の支払期に支払うことを合意しているのであれば,有効と考えられています。
残業手当の金額が不足している場合は,使用者は不足額について支払義務を負うことになりますので,残業手当の金額が低すぎることがないよう注意する必要があります。
例えば,基本給21万円,時間外勤務手当1万円では,ちょっと残業しただけで,時間外勤務手当が不足することになってしまいます。
とはいえ,初めから極端な長時間労働を予定して,基本給と比較して高額の定額残業代を支払うことにしておかなければならないようでは,労働安全衛生上の問題が生じかねないのではないかとの懸念が生じますし,労働者のモチベーションを下がって優秀な人材を確保する障害になりかねませんので,その金額は,1月あたり45時間分程度までにとどめておくべきなのではないかと考えています。
例えば,基本給14万円,時間外勤務手当8万円といった極端な比率に設定することは,やめるべきでしょう。
少なくとも,私は,そのような比率で賃金設定のなされている会社で働きたくはありません。
これでは,長時間労働を当然に予定していることを,宣言しているようなものです。
また,一か月あたりの平均所定労働時間が160時間の会社でこのような賃金額を定めた場合,基本給14万円÷160時間=875円/時となってしまい,下手するとパート・アルバイトよりも低い時間単価となってしまいます。
ボーナスを考慮すれば,パート・アルバイトよりも賃金が高くなる可能性はありますが,これでは,働く意欲が削がれ,常に転職先を探しながら仕事をするということになりかねません。
なお,残業代定額制を採用する場合は,営業手当等の名目で一定額を支給するよりも,「時間外勤務手当」等,それが残業手当であることが給与明細書の記載から直ちに分かるよう記載しておくと,労使紛争となるリスクが減少する印象です。
なぜなら,弁護士等が労働者から相談を受け,割増賃金が不払となっているかどうかを検討する際,給与明細書の記載を参考にすることが多いからです。
給与明細の時間外勤務手当欄に記載されている金額については残業手当の趣旨で支給していることが明らかですが,営業手当等の欄に記載されている金額についてはその文言から直ちに判断することができないため,残業手当の趣旨ではないという前提で労働審判を申し立てられることになりやすく,労使紛争を十分に予防できないことになってしまいます。
また,入社以来,給与明細書の時間外勤務手当欄に十分な金額の時間外勤務手当が記載されて支給されているのであれば,そもそも,労働者は残業代については不満に思いませんから,残業代だけのために弁護士等に相談することはないという面もあります。
労働審判等の対応が会社にとって大きな負担となることは明らかなのですから,訴訟で勝てばいいというものではなく,労使紛争が生じないようにするための方法を考えていくことが重要です。
弁護士 藤田 進太郎