



昨日のこと、裏山に登る石段の手すりで探していたクヌギエダイガタマバチをついに見つけた。
(たまたま撮ったものを調べているうちに、それだと判ったのだが。)
5mm強でタマバチの中では大きいという。
前翅の裾には水玉模様のような独特の斑紋がある。
3年越しで見たいものが見れたことになる。
このタマバチの話は2012年09月17日(記事にリンク)に近くの公園で見つけたイガフシから始まる。

このクヌギエダイガフシを作った寄主が今回見つけたタマバチだったのだ。
この翌年の2013年09月30日(記事にリンク)にはクヌギエダイガフシの中から幼虫を発見している。

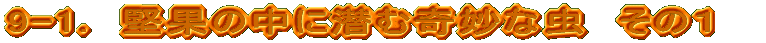 様にクヌギエダイガフシの中の様子が写真入りで詳しく書かれている。
様にクヌギエダイガフシの中の様子が写真入りで詳しく書かれている。
この虫瘤を枝から1つだけ取り外して解体してみると、中央に虫室があり、その中に1匹のクヌギエダイガタマバチの幼虫が暮らしていました(図9-1-10参照)。
虫室の一端は枝と繋がっているので、この幼虫は枝から何がしかの栄養分を吸収して成長すると考えられます。
そして、この中で成虫になるまで過ごして、羽化と同時に孔を開けて虫室の外に出てきます。
(記事にリンク)
田中川の生き物調査隊 様でもこのタマバチを取り上げでおられる。




























