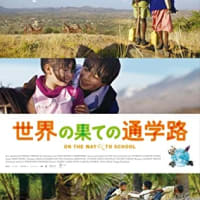私は「特別支援教育」に反対です。
「選択」すればいい、というのでもありません。
特別支援教育は、子どもの成長と差別や隔離の問題について、あまりに無神経で無関心すぎます。
特別支援教育では、分けられる子どもの痛みや思いに関心が寄せられることはありません。
特別支援教育は相変わらず「遅れを招く環境」であり、「悪性の社会心理」に覆われています。
しかし、「遅れを招く環境」も「悪性の社会心理」も、とても見えにくいものにされています。
そこには一定の順序を以て進行する枠組みがあり、この順序が実に政治的に巧妙なのです。
私は、子どもが親と離れたくない、兄弟家族と離れたくない、友だちと離れたくない、という思いは、子どもの安全と安心と自由(その子らしさ)を守るために不可欠な基本的な権利だと考えています。
その「思い」こそは、無条件で保障されなければなりません。
「良い子でいたら」とか、「課題をクリアしたら」、その他「肌の色」や「目の色」、「生まれた国」や、「障害の有無」という条件があってはいけません。
子どもが子どもである、ことでのみ、子どもの思いは大事にされるべきです。
それを、奪うことは、「いじめ」だと私は思ってきました。
中井久夫の「いじめの政治学」を読んで以来、その思いは確かなものになりました。
中井さんは、いじめの過程を、「孤立化」「無力化」「透明化」の三段階に分けて説明しています。
以下は、「いじめの政治学」のワニなつ翻訳版です。
◆
まず、「孤立化」について。
普通学級という場所では、孤立していない子どもは、時たまいじめに会うかもしれないが、持続的にいじめの標的にはならない。また、立ち直る機会がある。
立ち直る機会を与えず、分ける対象にするためには、孤立させる必要がある。
時たまいじめにあうような子どもを、「いじめられるのはかわいそうだから、分けた方がいい」と思われるようにするために、いくつかの手順、作戦が必要であり、まずは「孤立化作戦」が展開される。
作戦の一つは、標的化である。
誰かがマークされたということを周知させる。
そうするとそうでない者がほっとする。
そうして「分けられる子」から距離を置く。
(就学時健康診断が標的化の役割を果たしているのは確かなことだ。)
ついで、分けられる子どもがいかに分けられるに値するかというPR作戦が始まる。
仔細な身体的特徴や癖からはじまって、何ということはない行動やちょっとしたことが問題になる。
45分座っていられるか。ひらがなが読めるか。授業についていけるか。
分からない授業をただ我慢して聞いているだけじゃかわいそう。
これは周囲の差別意識に訴える力がある。
このPR作戦は、教師にも向けられる。
「そういえば、あの子にはそんなところがあるよなあ」という何気ない一言、かすかなうなずき、黙って聞いていることさえも、分ける側には千万の味方を得た思いを与え、傍観者には傍観の許しを与える。
それだけではない。PR作戦は、子どもにも自分は分けられても仕方がないという気持ちを次第にしみ通らせる。
分けられる子どもは子どもなりに、どうして自分が分けられるのか、理不尽な事態に自分なりの説明を与えようと必死になっている。
PR作戦は、やがて、子どもの心に、自分が分けられても仕方のない、だめな子、誰にも好かれない、みんなといる資格のない、ひとりぼっちの存在であると思いこませていく。
その思い込みは、実際に、子どもをそういう見かけに仕立てていくばかりでなく、分ける側と傍観者とを勇気づける。
担任はまた、家庭への連絡帳にあなたのお子さんの困った点として、まさにPR作戦の内容どおりを書くかもしれない。これは、子どもを家庭からも孤立させる。
分けられる子どもは、絶えず気を配っていなければならない。
周囲にも、自分の仕草や話し方、振る舞いにもである。
子どもは緊張から解放されることがなく、周囲に対してもゆとりのある対応ができなくなっていく。
そうした緊張は周囲にも察知され、「こんなにも無理をさせるのはかわいそう」と言われ、
「もう少し、ゆったりした環境、この子のニーズに合った教育が望ましい」につながる。
結局、分けられる子どもの思いに寄りそい、分けられる恐さ、ひとりぼっちになる恐怖に寄りそってくれる人などいない、ということを示し、彼がいつどこにいても孤立無援であることを実感させる作戦が、「孤立化作戦」である。
過去に、いったいどれほどの子どもたちが「孤立化」され、普通学級から分けられてきたか。
◇
以下、
「無力化」について
「透明化」について
最新の画像もっと見る
最近の「分けられること」カテゴリーもっと見る
最近の記事
カテゴリー
- ようこそ就園・就学相談会へ(521)
- 就学相談・いろはカルタ(60)
- 手をかすように知恵をかすこと(29)
- 0点でも高校へ(405)
- 手をかりるように知恵をかりること(60)
- 8才の子ども(165)
- 普通学級の介助の専門性(54)
- 医療的ケアと普通学級(94)
- ホームN通信(105)
- 石川憲彦(36)
- 特別支援教育からの転校・転籍(48)
- 分けられること(69)
- ふつう学級の良さは学校を終えてからの方がよくわかる(14)
- 膨大な量の観察学習(32)
- ≪通級≫を考えるために(15)
- 誰かのまなざしを通して人をみること(134)
- この子がさびしくないように(87)
- こだわりの溶ける時間(58)
- 『みつこさんの右手』と三つの守り(21)
- やっちゃんがいく&Naoちゃん+なっち(50)
- 感情の流れをともに生きる(15)
- 自分を支える自分(15)
- こどものことば・こどものこえ・こどものうちゅう(19)
- 受けとめられ体験について(29)
- 関係の自立(28)
- 星になったhide(25)
- トム・キッドウッド(8)
- Halの冒険(56)
- 金曜日は「ものがたり」♪(15)
- 定員内入学拒否という差別(99)
- Niiといっしょ(23)
- フルインクル(45)
- 無条件の肯定的態度と相互性・応答性のある暮らし(26)
- ワニペディア(14)
- 新しい能力(28)
- みっけ(6)
- ワニなつ(351)
- 本のノート(59)
バックナンバー
人気記事