先日、民友新聞に「草刈りは慎重に 生態系へ配慮を」を投稿し、絶滅が心配されるヒメシロチョウの保護について問題を提起した。
その後、関係行政と善後策を検討し、未だ除草の済まない土手の一部にヒメシロチョウの食草ツルフジバカマの群落を残してもらった。


穏やかな秋の日に、ロープで囲われ刈り残されたツルフジバカマを見に行くと、無事終令にまで育ったヒメシロチョウの幼虫がいくつも見つかった。
やがて蛹になり、長い冬を越して春一番で舞い立つヒメシロチョウを想像した。
何頭もの貴重なヒメシロチョウのいのちが救われ、嬉しかった。


会津地方ではヒメシロチョウは年3回の発生だが、その1回でもいのちのつながりが絶たれたら絶滅してしまう。
ヒメシロチョウの生息は局地的であり、食草の分布が重要だ。
これからは、草刈りのあり方と共に土手一帯に食草を移植することも一策だと思う。
近い将来の絶滅を防ぐ為にも、こうした実践が急務と思う。











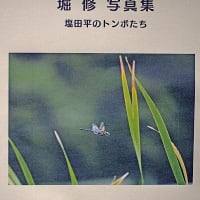








先生の問題提起が実を結んだのですね
素晴らしい!
官と民が協力しあってより良い環境が
保たれればと思っています
ヒメシロチョウにとっては、刈らずにおくだけではいろいろ支障がありそうです。研究考察中です。
秋も深まり、紅葉を楽しみながらゆっくり温泉に浸かりたい心境ですが、なかなか実現できないでいます。
減っているように感じます。
会津地方では何とか増えてくれると嬉しい
です。
食草の関連、あまり飛ばないチョウなので、生息は局地的です。
草原性のチョウで、草刈りもある程度必要で、むずかしいところがあります。