
朝から曇り空、夕方孫たちが帰宅する頃から雨となった。
降り出す前にウスバシロチョウの楽園に、[赤いカメラ]を探しに行った。
最もタンポポが多い、きのう探した西側を竹の棒を握って重点的に探した。
やはり朝のうちはタンポポに止まり蜜を吸う個体が多かった。約1時間半、大分伸びてきたフキの間に顔を出すタンポポを見ながらさがした。
今日も見つからなかった。



長原の山林へ立ち寄った。入ったことのない道を川沿いに進むとかなり奥の方まで田んぼがあった。上の方は水が入っていたが田植えはまだだった。
咲き出したウツギの花の周囲をチョウが舞っていた。ゴマダラチョウか?いや時期が早すぎる・・・と眺めていたら、なんとアサギマダラだった。







夏から秋に会津若松市内でもたまに見かけることはあったが、今年は大分早い飛来だと思った。
8月には裏磐梯デコ平に群生するヨツバヒヨドリを求めて多数飛来し、現地で観察会も行われている。最近はマーキング調査が盛んだ。
このチョウ、春は南方より北上、秋には気温の低下と共に日本から南方へ長距離を移動することが判明している。
でもその目的は不明で、生態については謎が多いチョウだ。
 フジ
フジ  ミズキ
ミズキ
 ヤブデマリ
ヤブデマリ ウツギ
ウツギ
アサギマダラの幼虫の越冬北限は食草のキジョラン(ガガイモ科)とほぼ一致し、会津では幼虫越冬が出来ない。
思わぬところで、思わぬチョウに出会った。











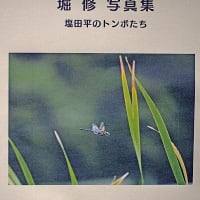








アサギマダラ撮影の報が載っておりました。
北青木の古川氏とありました。
また一箕町でも別の男性が発見したと
これは先生のことでしょう。
怪我などなさらないよう気を付けて
観察なさってください。
美しい写真をありがとうございました。
少々疲れ気味ですが、里山巡りで毎日発見があります。
ビールがおいしい季節になりましたね。
ふわふわ舞うアサギマダラはなんとも美しいチョウです。
移動が大きく全国どこでも見られるようですが、秋になぜ2000キロも南下するのか?よく分かっていないようです。越冬のためでもなく、産卵のためでもなく・・・。
毎年繰り返しですが、飽きずに里山を巡って写真を撮り歩いています。
おそらく会津でも今の時季に見られる新鮮な個体は現地で蛹越冬した羽化個体と思われます。
しかし、決定的な証拠が見つからず想像の域を出ませんが・・・何とか確信を掴みたいと思っています。
当地では今がオオルリシジミの最盛期です。
6月1日に北御牧のオオルリシジミ親子観察会があり、私も説明スタッフの一人として会場に行きます。
厳寒の信州で越冬できれば会津でも出来るでしょう。
オオルリシジミは皆さんの努力で安泰ですね。
かつて会津にも記録があり、上野の科学博物館の標本は会津坂下の産と聞いています。クララはたくさんありますが、DNAレベルで考えると移住は出来ないでしょう。
親子観察会い~ですね。こうして子どもたちに、身近に当たり前に地域の自然保護思想が生まれると思います。