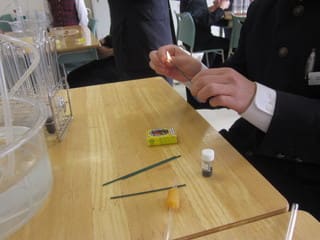11月9日(水)
午前10時30分頃、学校のガラス窓に激突した鳥を用務員の方が保護してくれました。
空を見ると、カラスが飛んでいます。
どうやら、カラスに襲われて逃げてきたようです。
その鳥は、内田先生のところへ届けられました。
内田先生は、段ボール箱に止まり棒を入れて、すぐに巣箱を作りました。
段ボール箱のに中には、携帯用カイロを入れます。
保護した鳥は、温かくしないといけないからです。
段ボール箱の中に入れる理由は、鳥を落ち着かせるためです。
内田先生は鳥かごも用意しています。
しかし、鳥かごでは、暴れたときに針金が翼に引っかかったりします。
また、暗いところでは、鳥は大人しく、無駄な体力を使わせなくて済むので、
段ボール箱がよいそうです。
次に、エサを用意します。
エサは、いつも学校の近くにある早川鳥獣店に買いに行きます。
早川鳥獣店で、ミルワームと練り餌を頂きました。
早川さんは、内田先生がいつも野鳥を助けるので、名古屋経済大学高蔵中学校高等学校を応援してくれています。
生き物が大好きでこの商売を始めたので、自然に応援する気持ちになるそうです。
内田先生が帰ろうとしたら、奥から男の人がやってきて、親しく話をしてきたそうです。
その方は、早川さんから高蔵高校の話を聞いていて、是非内田先生に会ってみたかったそうです。
また、NHKのアナウンサーの叔父に当たるそうで、内田先生の話を放送してもらったらどうかと言って来たそうです。
最近元気の無くなるニュースが多い中で、心温まる出来事は是非紹介して欲しいとの事でした。
内田先生は、鳥のことが心配なので、とりあえず断わて、すぐに学校へ戻ってエサをあげました。
6時間目が終った頃、鳥の様子を見に来た内田先生が、鳥の異変に気づきました。
息が荒くなり、左目の上が大きく膨らんでいて、食べた物をはき出していたそうです。
こうなっては、助かる可能性はほとんどありません。
急遽、ブドウ糖溶液を直接胃の中に入れました。
しかし、元気になる様子もありません。
左目の上が腫れているということは、内出血をしているということです。
諦めて、手の中で温めてあげました。
すると、「ピー」と声を出して、その後は静かに息を引き取りました。
その経過の一部を写真で紹介します。

元気が無くなってしまった鳥です。

左目が腫れているのがわかります。
これで助からないと実感したそうです。

からだが固くなりました。

鶯色をしていてとても可愛い鳥でした。

みんなで埋めました。
しっかりとみんなで祈りました。
出来ることは、全て行いましたが、後悔は尽きません。
次はしっかりと助けたいと思います。
午前10時30分頃、学校のガラス窓に激突した鳥を用務員の方が保護してくれました。
空を見ると、カラスが飛んでいます。
どうやら、カラスに襲われて逃げてきたようです。
その鳥は、内田先生のところへ届けられました。
内田先生は、段ボール箱に止まり棒を入れて、すぐに巣箱を作りました。
段ボール箱のに中には、携帯用カイロを入れます。
保護した鳥は、温かくしないといけないからです。
段ボール箱の中に入れる理由は、鳥を落ち着かせるためです。
内田先生は鳥かごも用意しています。
しかし、鳥かごでは、暴れたときに針金が翼に引っかかったりします。
また、暗いところでは、鳥は大人しく、無駄な体力を使わせなくて済むので、
段ボール箱がよいそうです。
次に、エサを用意します。
エサは、いつも学校の近くにある早川鳥獣店に買いに行きます。
早川鳥獣店で、ミルワームと練り餌を頂きました。
早川さんは、内田先生がいつも野鳥を助けるので、名古屋経済大学高蔵中学校高等学校を応援してくれています。
生き物が大好きでこの商売を始めたので、自然に応援する気持ちになるそうです。
内田先生が帰ろうとしたら、奥から男の人がやってきて、親しく話をしてきたそうです。
その方は、早川さんから高蔵高校の話を聞いていて、是非内田先生に会ってみたかったそうです。
また、NHKのアナウンサーの叔父に当たるそうで、内田先生の話を放送してもらったらどうかと言って来たそうです。
最近元気の無くなるニュースが多い中で、心温まる出来事は是非紹介して欲しいとの事でした。
内田先生は、鳥のことが心配なので、とりあえず断わて、すぐに学校へ戻ってエサをあげました。
6時間目が終った頃、鳥の様子を見に来た内田先生が、鳥の異変に気づきました。
息が荒くなり、左目の上が大きく膨らんでいて、食べた物をはき出していたそうです。
こうなっては、助かる可能性はほとんどありません。
急遽、ブドウ糖溶液を直接胃の中に入れました。
しかし、元気になる様子もありません。
左目の上が腫れているということは、内出血をしているということです。
諦めて、手の中で温めてあげました。
すると、「ピー」と声を出して、その後は静かに息を引き取りました。
その経過の一部を写真で紹介します。

元気が無くなってしまった鳥です。

左目が腫れているのがわかります。
これで助からないと実感したそうです。

からだが固くなりました。

鶯色をしていてとても可愛い鳥でした。

みんなで埋めました。
しっかりとみんなで祈りました。
出来ることは、全て行いましたが、後悔は尽きません。
次はしっかりと助けたいと思います。