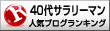日本語の「土産」は、英語ではsouvenirと訳されます。
ところが、この二つの言葉は随分と意味合いが違うようです。
日本語の「土産」は辞書を引いてみると、
① 旅先で求め帰り人に贈る、その土地の産物。
② 人の家を訪問する時に持って行く贈物。 (広辞苑)
となっています。
状況の違いはあれ、いずれにしても「人に贈る品物」という意味です。
語源は諸説ありますが、神社が参拝者に配る「宮笥」というものが起源という説や、よく見て調べて人に差し上げるという意味の「見上(みあげ)」が語源という説などがあります。
一方、英語のsouvenirは、18世紀に英語に入ってきた言葉で、「心に浮かぶ、思い出す」という意味のラテン語が語源です。ここからも分かるように、souvenirは、旅の思い出を心に留めておくためのもので、主に「自分のために」買い求める記念品といった意味の言葉です。
英語では、人に贈る物は、旅先で買ったものかどうかを問わず、giftやpresentといった言葉を使います。
こうした言葉の意味の違いの裏には、両国の「土産文化」の違いがあるようです。
日本人は、旅に出ると必ずと言ってよいほど他人に土産を買って帰ります。
家族に、友人に、恋人に、会社の同僚に…。
海外では、日本人がどっさりと土産物を買い込んで、重くなったスーツケースを転がして帰ってくるといった場面がよく見られます。
西洋では、旅に出たからといって会社の同僚にまで土産物を買って帰るという習慣はあまりないと言います。
日本での英会話講師になるために海外で研修を受ける外国人が、「日本ではお土産を忘れないように」と指導されているという話も聞きます。
日本には、独特の土産文化が発達していて、それを表す言葉が「土産」というわけです。
時代をさかのぼってみると、江戸時代の経済発展を背景にした特産品の発達が大きな契機となっているようです。
各藩の奨励で作られた各地方ならではの食材・工芸品などが特産品として発達し、江戸後期に旅ブームが起こると旅人たちがこぞってその特産品を手に入れて帰るようになりました。
明治以降、鉄道が発達すると旅にかかる時間が短くなり、食べ物も土産として買い求められるようになり、やがて饅頭や煎餅など土産物としてオリジナルに開発された商品も出回るようになりました。
また、日本独特の「村社会意識」も土産物文化を特徴づけていると言われています。
村・藩、あるいは会社など組織への帰属意識が強く、平等を重要視するため、味が平均的で誰の口にもあい、大きさも形もそろった「○○饅頭」のような土産商品が売れるというわけです。
暮らしの中の小さな事柄であっても、長い歴史の中で日本独特の習慣が育ってくると、他国の言葉では言い表しにくい文化となるのですね。
ところが、この二つの言葉は随分と意味合いが違うようです。
日本語の「土産」は辞書を引いてみると、
① 旅先で求め帰り人に贈る、その土地の産物。
② 人の家を訪問する時に持って行く贈物。 (広辞苑)
となっています。
状況の違いはあれ、いずれにしても「人に贈る品物」という意味です。
語源は諸説ありますが、神社が参拝者に配る「宮笥」というものが起源という説や、よく見て調べて人に差し上げるという意味の「見上(みあげ)」が語源という説などがあります。
一方、英語のsouvenirは、18世紀に英語に入ってきた言葉で、「心に浮かぶ、思い出す」という意味のラテン語が語源です。ここからも分かるように、souvenirは、旅の思い出を心に留めておくためのもので、主に「自分のために」買い求める記念品といった意味の言葉です。
英語では、人に贈る物は、旅先で買ったものかどうかを問わず、giftやpresentといった言葉を使います。
こうした言葉の意味の違いの裏には、両国の「土産文化」の違いがあるようです。
日本人は、旅に出ると必ずと言ってよいほど他人に土産を買って帰ります。
家族に、友人に、恋人に、会社の同僚に…。
海外では、日本人がどっさりと土産物を買い込んで、重くなったスーツケースを転がして帰ってくるといった場面がよく見られます。
西洋では、旅に出たからといって会社の同僚にまで土産物を買って帰るという習慣はあまりないと言います。
日本での英会話講師になるために海外で研修を受ける外国人が、「日本ではお土産を忘れないように」と指導されているという話も聞きます。
日本には、独特の土産文化が発達していて、それを表す言葉が「土産」というわけです。
時代をさかのぼってみると、江戸時代の経済発展を背景にした特産品の発達が大きな契機となっているようです。
各藩の奨励で作られた各地方ならではの食材・工芸品などが特産品として発達し、江戸後期に旅ブームが起こると旅人たちがこぞってその特産品を手に入れて帰るようになりました。
明治以降、鉄道が発達すると旅にかかる時間が短くなり、食べ物も土産として買い求められるようになり、やがて饅頭や煎餅など土産物としてオリジナルに開発された商品も出回るようになりました。
また、日本独特の「村社会意識」も土産物文化を特徴づけていると言われています。
村・藩、あるいは会社など組織への帰属意識が強く、平等を重要視するため、味が平均的で誰の口にもあい、大きさも形もそろった「○○饅頭」のような土産商品が売れるというわけです。
暮らしの中の小さな事柄であっても、長い歴史の中で日本独特の習慣が育ってくると、他国の言葉では言い表しにくい文化となるのですね。