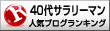チェコではたいがいのことは英語で通じるものですから、観光ではチェコ語を覚える必要がほとんどありませんでした。
それでも、何日か滞在すると、嫌でも覚えてしまう単語はあります。
旅先で覚える単語といえば、まず第一に飲食のこと。
今回、チェコ滞在中に覚えた単語といえば、何といってもpivoです。
ビールのことです。
チェコは一人当たりのビール消費量が世界一のビール大国。
そんな国に行ってビールを飲まないなんてあり得ない!
というわけで毎日ビールを頼んでいる間に、メニューを見ながら覚えてしまった単語です。
しかしメニューを見ながら、ちょっと不思議に感じました。
同じアルファベットを使い、同じ意味を表しているのに、BeerとPivo、つづりも音もまったく共通点がありません。
英語とドイツ語などはよく似ているのですが…。
「ビール」に限らず、チェコ語の文章を見ていると、英語やドイツ語に似た単語がまったく出てきません。
想像すらつきません。
チェコ語は、スラブ語派に属する言語。
英語やドイツ語は、ゲルマン語派に属する言語。
だから、同じアルファベットを使っていても、語彙に関係性がまったくといってよいほどないのです。
語派が異なっていても、例えばロマンス語派のイタリア語やフランス語と、英語との間には関連のある語彙が多くあります。
歴史的経緯で、ロマンス語派のフランスやイタリアと、ゲルマン語派のドイツ・イギリスなどの交流が盛んだったからです。
それにしても、同じ文字を使いながら、並び方の違いだけでこのような様々な語派や言語が存在するという現象は、日本人から見ると、ある意味で不思議に思えます。
漢字はともかく、ひらがなやカタカナは、日本語以外の言語では使いません。
文字そのものが日本語でしか使われていないわけです。
しかし、チェコ語や英語、ドイツ語を使う人たちにとっては、同じアルファベットという文字を使いながら、並び方が違うだけで別の言語になってしまいます。
日本語で想像すると、例えば
「ならサナニね、てなナサニぬにこつ、なにぷ」
と書かれる別の国の言葉が存在するようなものです。
日本語は、言語学では「孤立語」といわれます。
世界の多くの言語の話者にとって、「ならサナニね、てなナサニ…」は、当たり前の現象であり、その経験を持たない日本人の方が珍しいケースなのです。
チェコで、まったく意味の分からないアルファベットのメニューを眺めながら、ふと、日本語がいかに珍しい言葉だったのかを、あらためて実感しました。
それでも、何日か滞在すると、嫌でも覚えてしまう単語はあります。
旅先で覚える単語といえば、まず第一に飲食のこと。
今回、チェコ滞在中に覚えた単語といえば、何といってもpivoです。
ビールのことです。
チェコは一人当たりのビール消費量が世界一のビール大国。
そんな国に行ってビールを飲まないなんてあり得ない!
というわけで毎日ビールを頼んでいる間に、メニューを見ながら覚えてしまった単語です。
しかしメニューを見ながら、ちょっと不思議に感じました。
同じアルファベットを使い、同じ意味を表しているのに、BeerとPivo、つづりも音もまったく共通点がありません。
英語とドイツ語などはよく似ているのですが…。
「ビール」に限らず、チェコ語の文章を見ていると、英語やドイツ語に似た単語がまったく出てきません。
想像すらつきません。
チェコ語は、スラブ語派に属する言語。
英語やドイツ語は、ゲルマン語派に属する言語。
だから、同じアルファベットを使っていても、語彙に関係性がまったくといってよいほどないのです。
語派が異なっていても、例えばロマンス語派のイタリア語やフランス語と、英語との間には関連のある語彙が多くあります。
歴史的経緯で、ロマンス語派のフランスやイタリアと、ゲルマン語派のドイツ・イギリスなどの交流が盛んだったからです。
それにしても、同じ文字を使いながら、並び方の違いだけでこのような様々な語派や言語が存在するという現象は、日本人から見ると、ある意味で不思議に思えます。
漢字はともかく、ひらがなやカタカナは、日本語以外の言語では使いません。
文字そのものが日本語でしか使われていないわけです。
しかし、チェコ語や英語、ドイツ語を使う人たちにとっては、同じアルファベットという文字を使いながら、並び方が違うだけで別の言語になってしまいます。
日本語で想像すると、例えば
「ならサナニね、てなナサニぬにこつ、なにぷ」
と書かれる別の国の言葉が存在するようなものです。
日本語は、言語学では「孤立語」といわれます。
世界の多くの言語の話者にとって、「ならサナニね、てなナサニ…」は、当たり前の現象であり、その経験を持たない日本人の方が珍しいケースなのです。
チェコで、まったく意味の分からないアルファベットのメニューを眺めながら、ふと、日本語がいかに珍しい言葉だったのかを、あらためて実感しました。