『あなたの知らない愛知県の歴史』(洋泉社)山本 博文 著 の中から、気になるいくつかを紹介します。
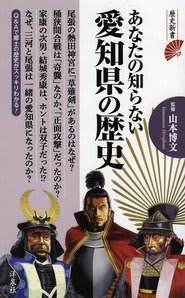
Q46 清洲から名古屋への遷府、「清洲越し」はなぜ行われた?
山本氏は、「清須という町ごと名古屋へ移動させる一大事業」「人口6万という日本有数の城下町だった清須は、文字通り跡形もなくなった」とし、一緒に移った商工業者は「御扶助之町人」として、名古屋の発展を支えたとしています。
まさにその通りです。
移転の理由としては、清須は低地で、水攻めには耐えられないので、山下氏勝による建議で高台へ移すこと、豊臣系の大名に命じて、財力を弱めることなどが書かれています
これらもその通りでしょう。
ここからは、書かれていないことを補足します。
「御扶助之町人」として、清須から移った人には誰がいるか?
伊藤蘭丸祐広のいえは、清須越しして、本町に「いとう呉服店」を開きました。これが現在の「松坂屋」の前身であり、東海銀行、今の東京三菱UFA銀行にもつながっています。現在の「竹中工務店」も、竹中藤兵衛正高が清須越しして名古屋で創業したのが始まりです。
跡形もなくなったとされた清須は、その後は、美濃路の宿場町として復活し、枇杷島に青果市場も開設され勢いを取り戻しています。
家康に建議した山下氏勝とは?
実は、初代藩主・義直の傅役(もりやく)です。なぜなら、義直の母は、氏勝の義姉なのです。
こうして、慶長17年には熱田台地の北西の端に天守が完成。
その南に町人町が広がり、それを武家地と社寺地で取り囲む構成になっていました。防衛拠点のまちづくりです。
碁盤割に区画された町人町への引越しは、本町のひとは、本町へと同じ名の町へ引っ越しています。町人の共同体は保存されたのです。現在も受け継がれている町名も多くあります。
慶長19年7月に名古屋城一帯が完成すると、その3ヶ月後に大阪冬の陣が始まり、徳川による幕藩体制が固まるのです。
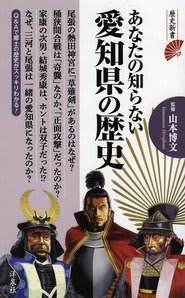
Q46 清洲から名古屋への遷府、「清洲越し」はなぜ行われた?
山本氏は、「清須という町ごと名古屋へ移動させる一大事業」「人口6万という日本有数の城下町だった清須は、文字通り跡形もなくなった」とし、一緒に移った商工業者は「御扶助之町人」として、名古屋の発展を支えたとしています。
まさにその通りです。
移転の理由としては、清須は低地で、水攻めには耐えられないので、山下氏勝による建議で高台へ移すこと、豊臣系の大名に命じて、財力を弱めることなどが書かれています
これらもその通りでしょう。
ここからは、書かれていないことを補足します。
「御扶助之町人」として、清須から移った人には誰がいるか?
伊藤蘭丸祐広のいえは、清須越しして、本町に「いとう呉服店」を開きました。これが現在の「松坂屋」の前身であり、東海銀行、今の東京三菱UFA銀行にもつながっています。現在の「竹中工務店」も、竹中藤兵衛正高が清須越しして名古屋で創業したのが始まりです。
跡形もなくなったとされた清須は、その後は、美濃路の宿場町として復活し、枇杷島に青果市場も開設され勢いを取り戻しています。
家康に建議した山下氏勝とは?
実は、初代藩主・義直の傅役(もりやく)です。なぜなら、義直の母は、氏勝の義姉なのです。
こうして、慶長17年には熱田台地の北西の端に天守が完成。
その南に町人町が広がり、それを武家地と社寺地で取り囲む構成になっていました。防衛拠点のまちづくりです。
碁盤割に区画された町人町への引越しは、本町のひとは、本町へと同じ名の町へ引っ越しています。町人の共同体は保存されたのです。現在も受け継がれている町名も多くあります。
慶長19年7月に名古屋城一帯が完成すると、その3ヶ月後に大阪冬の陣が始まり、徳川による幕藩体制が固まるのです。









