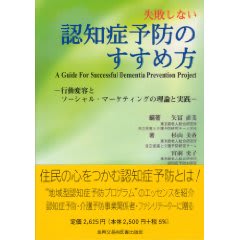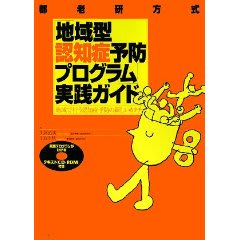先日、認知症予防を目的とした料理と旅行のプログラムの第2回目がありました。
概要は前の日記を参照してください。
http://blog.goo.ne.jp/silbo/e/b69e31ff43151951f8514f8f2038d8ff
http://blog.goo.ne.jp/silbo/e/b69e31ff43151951f8514f8f2038d8ff
今回は8名中5名の方の参加がありました。
隣市の桑名市の神社仏閣を歩いて2~3巡ってはどうかという概案ができました。
詳細はこれから詰めていきます。
旅行プログラムは私と年配のHさんとコンビを組んで担当することになりました、と書きました。
それで、「船頭多くして船山へ上る Too many cooks spoil the broth.」になってはいけないので、Hさんに進行を委ねることにしました。
今回も進行で話すのは主にHさんで、私は一歩引いて喋ることは少なかったです。
普段、チームで行動することは少ないので、まだぎこちない部分もありますが、自分なりにできることをやっていこうと思います。
グループに参加させてもらって痛感したのは、自分が如何に狭い世界に生きているか、狭い見識で物事を見ているか、ただ単に壊れた井戸の中で自分だけで楽しんでいるだけなのか、管窺蠡測、夏虫疑氷であるか。。(´_`)
先入観を捨てて、頭を柔軟にし、物事を見る、考えることの重要性を改めて再認識させられました。。
海亀になって大海を知るのは無理ですけど、せめて、井戸から顔を出して、もしくは少しづつでも井戸から広い世間に出ていけるようにしたいです。。(´_`)
概要は前の日記を参照してください。
http://blog.goo.ne.jp/silbo/e/b69e31ff43151951f8514f8f2038d8ff
http://blog.goo.ne.jp/silbo/e/b69e31ff43151951f8514f8f2038d8ff
今回は8名中5名の方の参加がありました。
隣市の桑名市の神社仏閣を歩いて2~3巡ってはどうかという概案ができました。
詳細はこれから詰めていきます。
旅行プログラムは私と年配のHさんとコンビを組んで担当することになりました、と書きました。
それで、「船頭多くして船山へ上る Too many cooks spoil the broth.」になってはいけないので、Hさんに進行を委ねることにしました。
今回も進行で話すのは主にHさんで、私は一歩引いて喋ることは少なかったです。
普段、チームで行動することは少ないので、まだぎこちない部分もありますが、自分なりにできることをやっていこうと思います。
グループに参加させてもらって痛感したのは、自分が如何に狭い世界に生きているか、狭い見識で物事を見ているか、ただ単に壊れた井戸の中で自分だけで楽しんでいるだけなのか、管窺蠡測、夏虫疑氷であるか。。(´_`)
先入観を捨てて、頭を柔軟にし、物事を見る、考えることの重要性を改めて再認識させられました。。
海亀になって大海を知るのは無理ですけど、せめて、井戸から顔を出して、もしくは少しづつでも井戸から広い世間に出ていけるようにしたいです。。(´_`)