詩集を出版することにはそれなりの決断がいる。自分の作品をなぜ詩集という形にしたいのか、自分のどの作品を集めれば望む詩集となるのか、などといった本質的なことがもちろんある。それに加えて実際的な事柄もある。
我が国で詩集を出したいと思ったら、(ごく一部の人を除いては)自分で出版費用を負担することになるのが現状だ。 詩集の判型、製本方法、発行部数、などにもよるが、かなりのまとまった経費を覚悟することになる。
最近は電子出版という形態がある。これはインターネット上にある詩集を、料金を支払って自分のコンピューターにダウンロードするというものである。音楽をituneなどでダウンロードするのと同じやり方である。
電子書籍を読むツールとして、汎用コンピューター以外にもiPad、キンデルなどの様々なタブレットも充実してきている。一般の電子書籍の流通が盛んとなってきており、詩集出版に関してもそれが主流となる時代が来るのかもしれない。
電子書籍のメリットとしては、タブレットを利用して読む場合の携帯性がまずあげられる。それ以外にも、データベース機能の利便性もあげられる。研究目的で書籍を資料として扱う場合には、これは紙媒体の書籍とは全く比較にならないほどの利便性がある。
科学的な研究においてはそれまでの論文の解析、比較検討など応用範囲は広い。文学の世界でもそれは当てはまる。たとえば、西脇順三郎の全作品を電子書籍の形で蓄えておけば、発表年代順に作品を検討することも可能であるし、「女神」という言葉が使われている作品を検索するといったことも容易にできる。また、接続詞の使われ方を分析する、などということもできる。
土曜美術社出版販売では、すでに中上哲夫、中井ひさ子、中村不二夫、一色真理などの詩集を電子書籍として販売している。制作費については調べていないが、紙媒体の詩集出版に比べればかなりの低経費だろうと思われる。
しかし、 詩集に限っていえば、やはり印刷された紙媒体の方がよいという感情はあるだろう。資料として読むのではなく、作品そのものとして読む場合はなおさらだ。
その紙媒体の詩集だが、経費削減のためには、装丁、製本の簡素化を工夫することができる。また出版形式の工夫としてはオンデマンド出版がある。この形式での出版はこれまでも皆無ではなく、いくつかの案内を見たことがある。しかしその取り扱い部数はごく限られたものではなかっただろうか。
従来のやり方で多くの紙媒体の詩集を出版していた思潮社が、最近オンデマンドの詩集出版をはじめた。その第一弾として発行された詩集の案内葉書が、阿部嘉昭、高塚謙太郎の連名で届いた。その文面を一部転載する。
ネット注文のみで書店に並ぶことはありませんが、注文に応じて製本する形式なので、自己負担額も通常の七分の一程度と画期的に廉価で、今後の詩集出版のひとつの指針になると期待しています。
著者自身で注文することもできるのですが、それで皆様に贈呈してしまうと、従来までの互酬的な詩集贈呈のかたちとおなじになってしまいます。ぜひともみなさまには、お手数ながらアマゾンにて著者名を検索いただき、ご注文いただければと存じます。
たいへん不躾なご案内と恐縮しておりますが、オンデマンド・メリットを確保することで今後の詩集流通を変化させたいわたしどもの趣旨をご理解いただき、ご注文のお手間をとっていただければ幸いです。
その直裁的な態度に感心した。二人の作品を読んでみたいという思いもあったので、早速ネット上で注文してみた。届いた詩集は、私が勝手に想像していたオンデマンド出版の体裁をはるかに超えた美しい装丁、製本のものだった。このレベルであれば、充分に詩集を所有しているという満足感を満たすことができると個人的には思えた。
さて、電子出版にせよ、オンデマンド出版にせよ、このような新しい形式での出版形式に伴って大きく変化するかも知れないことは、詩の世界での献本の慣習だろう。
紙媒体で詩集を出版した場合には、現在の我が国では自費出版であることとも関係して、そのほとんどを献本という形で作者が(あるいはその依頼を受けた出版社が)読んでほしい人に送付する。作者が一面識のない相手に送ることもあり、送られた者には未知の人の詩集に接する機会が生じるということもあった。
これに反して、電子出版、オンデマンド出版の場合は、原則的にはこの献本はなくなる。いずれの場合も詩集を読みたい側がネット上で注文をして料金を支払う。
そのため、紙媒体の詩集がほしい読者がオンデマンド出版の詩集を注文購入するのは、あらかじめ作者を知っていて、実物を手に取らなくても料金を払ってでも入手したいと思った詩集、と言うことになる。
詩集という形あるものが作られたからには、そこには作者と読者が存在するわけだが、これまでの詩集の読者は作者から送られてきた詩集を読むという受け身の存在であることが多かった。
今後こういった新しい出版形式の普及に関するポイントとしては、自分で料金を支払って詩集を購入して読む者がどれぐらいいるか、あるいは、料金を支払って読んでもらえる詩を書く作者がどれぐらいいるか、ということになる。
また、読む側からすれば、送られてきた詩集によって見知らぬ新しい作者、そしてその作品と出会うということも、実質的にはなくなることになる。これも献本の慣習がなくなった場合の変化になるだろう。
我が国で詩集を出したいと思ったら、(ごく一部の人を除いては)自分で出版費用を負担することになるのが現状だ。 詩集の判型、製本方法、発行部数、などにもよるが、かなりのまとまった経費を覚悟することになる。
最近は電子出版という形態がある。これはインターネット上にある詩集を、料金を支払って自分のコンピューターにダウンロードするというものである。音楽をituneなどでダウンロードするのと同じやり方である。
電子書籍を読むツールとして、汎用コンピューター以外にもiPad、キンデルなどの様々なタブレットも充実してきている。一般の電子書籍の流通が盛んとなってきており、詩集出版に関してもそれが主流となる時代が来るのかもしれない。
電子書籍のメリットとしては、タブレットを利用して読む場合の携帯性がまずあげられる。それ以外にも、データベース機能の利便性もあげられる。研究目的で書籍を資料として扱う場合には、これは紙媒体の書籍とは全く比較にならないほどの利便性がある。
科学的な研究においてはそれまでの論文の解析、比較検討など応用範囲は広い。文学の世界でもそれは当てはまる。たとえば、西脇順三郎の全作品を電子書籍の形で蓄えておけば、発表年代順に作品を検討することも可能であるし、「女神」という言葉が使われている作品を検索するといったことも容易にできる。また、接続詞の使われ方を分析する、などということもできる。
土曜美術社出版販売では、すでに中上哲夫、中井ひさ子、中村不二夫、一色真理などの詩集を電子書籍として販売している。制作費については調べていないが、紙媒体の詩集出版に比べればかなりの低経費だろうと思われる。
しかし、 詩集に限っていえば、やはり印刷された紙媒体の方がよいという感情はあるだろう。資料として読むのではなく、作品そのものとして読む場合はなおさらだ。
その紙媒体の詩集だが、経費削減のためには、装丁、製本の簡素化を工夫することができる。また出版形式の工夫としてはオンデマンド出版がある。この形式での出版はこれまでも皆無ではなく、いくつかの案内を見たことがある。しかしその取り扱い部数はごく限られたものではなかっただろうか。
従来のやり方で多くの紙媒体の詩集を出版していた思潮社が、最近オンデマンドの詩集出版をはじめた。その第一弾として発行された詩集の案内葉書が、阿部嘉昭、高塚謙太郎の連名で届いた。その文面を一部転載する。
ネット注文のみで書店に並ぶことはありませんが、注文に応じて製本する形式なので、自己負担額も通常の七分の一程度と画期的に廉価で、今後の詩集出版のひとつの指針になると期待しています。
著者自身で注文することもできるのですが、それで皆様に贈呈してしまうと、従来までの互酬的な詩集贈呈のかたちとおなじになってしまいます。ぜひともみなさまには、お手数ながらアマゾンにて著者名を検索いただき、ご注文いただければと存じます。
たいへん不躾なご案内と恐縮しておりますが、オンデマンド・メリットを確保することで今後の詩集流通を変化させたいわたしどもの趣旨をご理解いただき、ご注文のお手間をとっていただければ幸いです。
その直裁的な態度に感心した。二人の作品を読んでみたいという思いもあったので、早速ネット上で注文してみた。届いた詩集は、私が勝手に想像していたオンデマンド出版の体裁をはるかに超えた美しい装丁、製本のものだった。このレベルであれば、充分に詩集を所有しているという満足感を満たすことができると個人的には思えた。
さて、電子出版にせよ、オンデマンド出版にせよ、このような新しい形式での出版形式に伴って大きく変化するかも知れないことは、詩の世界での献本の慣習だろう。
紙媒体で詩集を出版した場合には、現在の我が国では自費出版であることとも関係して、そのほとんどを献本という形で作者が(あるいはその依頼を受けた出版社が)読んでほしい人に送付する。作者が一面識のない相手に送ることもあり、送られた者には未知の人の詩集に接する機会が生じるということもあった。
これに反して、電子出版、オンデマンド出版の場合は、原則的にはこの献本はなくなる。いずれの場合も詩集を読みたい側がネット上で注文をして料金を支払う。
そのため、紙媒体の詩集がほしい読者がオンデマンド出版の詩集を注文購入するのは、あらかじめ作者を知っていて、実物を手に取らなくても料金を払ってでも入手したいと思った詩集、と言うことになる。
詩集という形あるものが作られたからには、そこには作者と読者が存在するわけだが、これまでの詩集の読者は作者から送られてきた詩集を読むという受け身の存在であることが多かった。
今後こういった新しい出版形式の普及に関するポイントとしては、自分で料金を支払って詩集を購入して読む者がどれぐらいいるか、あるいは、料金を支払って読んでもらえる詩を書く作者がどれぐらいいるか、ということになる。
また、読む側からすれば、送られてきた詩集によって見知らぬ新しい作者、そしてその作品と出会うということも、実質的にはなくなることになる。これも献本の慣習がなくなった場合の変化になるだろう。











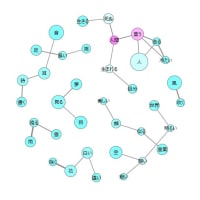


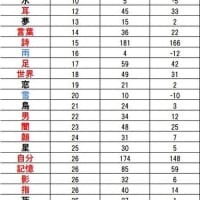
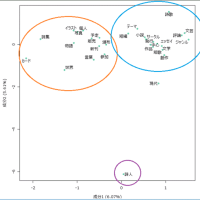
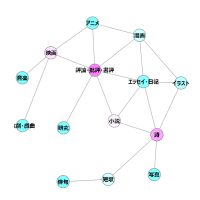
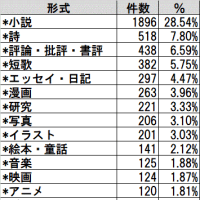
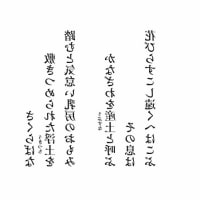
※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます