高校の古文などで枕草子に『鶏鳴狗盗』の故事が登場するが、その主人公が孟嘗君である。鶏鳴狗盗という単語からでも想像できるようにどうも堅気の人間ではない雰囲気だ。孟嘗君に関しては、戦国策をはじめとして史記などに数々の逸話が載っているが、どれもこれもヤクザの大親分の貫禄だ。司馬遷は史記の巻75に孟嘗君の伝を書いたが、その末尾に「孟嘗君が任侠を好んだのでヤクザ者が6万戸も住みついた。それで、そのあたり一帯(薛)は今でも乱暴者が多い」と非難めいた口調で締めくくっている。
中国の史書などを読むと、中国では伝統的に必ずしも官吏が good guy でヤクザ者が bad guy とは言えないようだ。水滸伝のように、逆に、官吏が bad guy でお尋ね者が good guy であるケースも少なくはない。そもそも、動乱や革命が頻発した中国では、道徳的な意味での good や bad は全く意味を持たない。一般的には易姓革命と称して、徳の優った者が徳の劣った者になり代わって天下を治めるともっともらしい論理を立てるが、何の事はない単に最終的に勝った者が good guy と自称しているだけの話しだ。勝てば、過去の全ての悪が帳消しとなる。現代風に言えば、Winner-Take-All ということだ。 この意味から言えば、孟嘗君が集めたヤクザ者も漢楚の戦乱が決着して、世の中が落ち着いてしまったから使い道がなくなっただけの話しで、戦乱時には王侯たちから頼りにされる一団であったはずだ。
さて、孟嘗君にはたくさんのブレーンがいたが、とりわけ馮驩(ふうかん)の智慧のキレは比類がない。孟嘗君が主君である斉王に嫌われ、宰相を罷免された時、3000人もいた食客たちはさあーっといなくなってしまった。しかし、暫くして宰相に復位すると大勢の食客たちがまたすりよってきた。あまりにも日和見的な食客たちの行動に孟嘗君が馮驩に「こいつらが、のこのこと顔をだしたらその面(ツラ)に唾をかけてやろう!」と怒ったが、馮驩はそれを咎めて「貴卿は何も分かっていないお方だなあ!」と言って次のように諭した。
+++++++++++++++++++++++++++
生者が死ぬのは必定で、物にも必然の定めがあります。富貴な者にはすり寄ってくる者が多く、貧賤なものには誰も近寄りません。これは物の道理というものです。貴卿は人々が朝に市場に出かける様子をみたことがありませんか?朝には肩をそびやかし、市門に争って入って行きますが、夕方になって市門が閉まるころには、朝に市場に来た者もさっさと通りすぎていきます。別に朝が好きで、夕方が嫌いだという訳ではありません。市場にはなにも欲しい物がないからです。この度、貴卿が宰相を罷免されて、賓客が去って行ったからと言って彼らを恨んで、今後、一切賓客を抱えないというバカなまねはしないでください。何事もなかったように、いままで通りに賓客をもてなすことです。
「生者必有死,物之必至也;富貴多士,貧賤寡友,事之固然也。君独不見夫趣市朝者乎?明旦,側肩争門而入;日暮之後,過市朝者掉臂而不顧。非好朝而悪暮,所期物忘其中。今君失位,賓客皆去,不足以怨士而徒絶賓客之路。願君遇客如故。」
+++++++++++++++++++++++++++
馮驩の忠告はいかにも二枚舌が常習の中国らしい。腹の底は煮えくりかえっていても、そのようなそぶりは見せず、感情を押し殺し、利用出来る者はとことん利用尽くせば、その方が得だということだ。孟嘗君もさすが大親分、素直に従った。
しかし、大抵の日本人は、どうもこのような伝統中国の価値観にはついていけないものを感じるだろう。日本人の考えの根底には、人との付き合いには『信頼』を基盤(ベース)とすべし、というような不文律があるようだ。信頼もしていない人間を単に自分の利益のためだけにしゃぶり尽くすというのは、どうも気がひける、と感じるのではないだろうか?
一般的には、このエピソードで馮驩は孟嘗君に『寛容の徳』を教えたと説くのだろうが、それは孟嘗君が表面的ではなく、本心から納得した場合のことだ。だが、孟嘗君の過去の行動や性格からはそういったことは期待できないことが分かる。ただ、孟嘗君はさておき、この部分を読む我々にとって「人の上に立つものの心構えとは」という点で教えてくれるものを持っている。これが私の考える、中国史書の読み方、である。

【出典】亞醜杞婦卣
ただ、『地大物博』を誇る中国のことだから、探せば、我々日本人のように考える人もいる。
前漢の時代、清廉で公平な政治をする翟方進という人がいた。父を早くに亡くし苦学したが、最終的には丞相(総理大臣)の位にまで登った。その父というのも、また骨のある人であった。漢の武帝の時代(BC130年ごろ)に廷尉(法務大臣)にまでなった翟公だが、この人の考えは馮驩とは異なる。
+++++++++++++++++++++++++++
さて、下邽出身の翟公が廷尉(総理大臣)になったので、家中が賓客で充満した。しかし、失脚すると途端にだれも来なくなったので、雀たちが大威張りで門のあたりに群がった。その後、また廷尉に復位すると賓客たちがやって来た。そこで、翟公は門に次のような文句を大書した。
一死一生,乃知交情; 生きる死ぬの瀬戸際になると、人の本当の友情が分かる。
一貧一富,乃知交態; 金持ちになったり貧乏になると、人の本当の思惑が分かる。
一貴一賤,交情乃見. 高位に就いたり失脚すると、人の本当の思いが見えてくる。
下邽翟公為廷尉,賓客亦填門,及廃,門外可設爵羅.後復為廷尉,客欲往,翟公大署其門曰:「一死一生,乃知交情;一貧一富,乃知交態;一貴一賤,交情乃見.」
+++++++++++++++++++++++++++
『一貴一賤,交情乃見』(一貴一賤、交情すなわち見(あら)わる)とは、失脚したからと言ってさっさと去ってしまうような薄情なヤツには用が無いと言ったのだ。現在中国で行われている習近平の汚職摘発では、この翟公の文句をほろ苦くかみしめている役人が多々いることだろう、と想像される。
ところで、ここに『門外可設雀羅』(門外に雀羅を設くべし)の文句がでてくるが、ここから諺ができた。日本語では『門前雀羅』と言うが、現代中国語では『門可羅雀』と言う。日中の文字の使い方で差がみられる。日本語では『雀羅』という句をオリジナル通り使っているが、現代中国では『羅雀』とひっくり返して、『雀を羅(あみと)る』と『羅』を動詞に用いる。私の勝手な想像だが、昔は雀を食糧としていたので多分、『雀羅』(じゃくら)という雀取り専門の網があったのだろう。しかし、雀をあまり食べなくなったので、雀を捕まえるのに一般的な網を使うようになった。それで、今のような表現に変わったのではないだろうか?
中国の史書などを読むと、中国では伝統的に必ずしも官吏が good guy でヤクザ者が bad guy とは言えないようだ。水滸伝のように、逆に、官吏が bad guy でお尋ね者が good guy であるケースも少なくはない。そもそも、動乱や革命が頻発した中国では、道徳的な意味での good や bad は全く意味を持たない。一般的には易姓革命と称して、徳の優った者が徳の劣った者になり代わって天下を治めるともっともらしい論理を立てるが、何の事はない単に最終的に勝った者が good guy と自称しているだけの話しだ。勝てば、過去の全ての悪が帳消しとなる。現代風に言えば、Winner-Take-All ということだ。 この意味から言えば、孟嘗君が集めたヤクザ者も漢楚の戦乱が決着して、世の中が落ち着いてしまったから使い道がなくなっただけの話しで、戦乱時には王侯たちから頼りにされる一団であったはずだ。
さて、孟嘗君にはたくさんのブレーンがいたが、とりわけ馮驩(ふうかん)の智慧のキレは比類がない。孟嘗君が主君である斉王に嫌われ、宰相を罷免された時、3000人もいた食客たちはさあーっといなくなってしまった。しかし、暫くして宰相に復位すると大勢の食客たちがまたすりよってきた。あまりにも日和見的な食客たちの行動に孟嘗君が馮驩に「こいつらが、のこのこと顔をだしたらその面(ツラ)に唾をかけてやろう!」と怒ったが、馮驩はそれを咎めて「貴卿は何も分かっていないお方だなあ!」と言って次のように諭した。
+++++++++++++++++++++++++++
生者が死ぬのは必定で、物にも必然の定めがあります。富貴な者にはすり寄ってくる者が多く、貧賤なものには誰も近寄りません。これは物の道理というものです。貴卿は人々が朝に市場に出かける様子をみたことがありませんか?朝には肩をそびやかし、市門に争って入って行きますが、夕方になって市門が閉まるころには、朝に市場に来た者もさっさと通りすぎていきます。別に朝が好きで、夕方が嫌いだという訳ではありません。市場にはなにも欲しい物がないからです。この度、貴卿が宰相を罷免されて、賓客が去って行ったからと言って彼らを恨んで、今後、一切賓客を抱えないというバカなまねはしないでください。何事もなかったように、いままで通りに賓客をもてなすことです。
「生者必有死,物之必至也;富貴多士,貧賤寡友,事之固然也。君独不見夫趣市朝者乎?明旦,側肩争門而入;日暮之後,過市朝者掉臂而不顧。非好朝而悪暮,所期物忘其中。今君失位,賓客皆去,不足以怨士而徒絶賓客之路。願君遇客如故。」
+++++++++++++++++++++++++++
馮驩の忠告はいかにも二枚舌が常習の中国らしい。腹の底は煮えくりかえっていても、そのようなそぶりは見せず、感情を押し殺し、利用出来る者はとことん利用尽くせば、その方が得だということだ。孟嘗君もさすが大親分、素直に従った。
しかし、大抵の日本人は、どうもこのような伝統中国の価値観にはついていけないものを感じるだろう。日本人の考えの根底には、人との付き合いには『信頼』を基盤(ベース)とすべし、というような不文律があるようだ。信頼もしていない人間を単に自分の利益のためだけにしゃぶり尽くすというのは、どうも気がひける、と感じるのではないだろうか?
一般的には、このエピソードで馮驩は孟嘗君に『寛容の徳』を教えたと説くのだろうが、それは孟嘗君が表面的ではなく、本心から納得した場合のことだ。だが、孟嘗君の過去の行動や性格からはそういったことは期待できないことが分かる。ただ、孟嘗君はさておき、この部分を読む我々にとって「人の上に立つものの心構えとは」という点で教えてくれるものを持っている。これが私の考える、中国史書の読み方、である。

【出典】亞醜杞婦卣
ただ、『地大物博』を誇る中国のことだから、探せば、我々日本人のように考える人もいる。
前漢の時代、清廉で公平な政治をする翟方進という人がいた。父を早くに亡くし苦学したが、最終的には丞相(総理大臣)の位にまで登った。その父というのも、また骨のある人であった。漢の武帝の時代(BC130年ごろ)に廷尉(法務大臣)にまでなった翟公だが、この人の考えは馮驩とは異なる。
+++++++++++++++++++++++++++
さて、下邽出身の翟公が廷尉(総理大臣)になったので、家中が賓客で充満した。しかし、失脚すると途端にだれも来なくなったので、雀たちが大威張りで門のあたりに群がった。その後、また廷尉に復位すると賓客たちがやって来た。そこで、翟公は門に次のような文句を大書した。
一死一生,乃知交情; 生きる死ぬの瀬戸際になると、人の本当の友情が分かる。
一貧一富,乃知交態; 金持ちになったり貧乏になると、人の本当の思惑が分かる。
一貴一賤,交情乃見. 高位に就いたり失脚すると、人の本当の思いが見えてくる。
下邽翟公為廷尉,賓客亦填門,及廃,門外可設爵羅.後復為廷尉,客欲往,翟公大署其門曰:「一死一生,乃知交情;一貧一富,乃知交態;一貴一賤,交情乃見.」
+++++++++++++++++++++++++++
『一貴一賤,交情乃見』(一貴一賤、交情すなわち見(あら)わる)とは、失脚したからと言ってさっさと去ってしまうような薄情なヤツには用が無いと言ったのだ。現在中国で行われている習近平の汚職摘発では、この翟公の文句をほろ苦くかみしめている役人が多々いることだろう、と想像される。
ところで、ここに『門外可設雀羅』(門外に雀羅を設くべし)の文句がでてくるが、ここから諺ができた。日本語では『門前雀羅』と言うが、現代中国語では『門可羅雀』と言う。日中の文字の使い方で差がみられる。日本語では『雀羅』という句をオリジナル通り使っているが、現代中国では『羅雀』とひっくり返して、『雀を羅(あみと)る』と『羅』を動詞に用いる。私の勝手な想像だが、昔は雀を食糧としていたので多分、『雀羅』(じゃくら)という雀取り専門の網があったのだろう。しかし、雀をあまり食べなくなったので、雀を捕まえるのに一般的な網を使うようになった。それで、今のような表現に変わったのではないだろうか?


















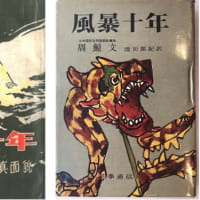








※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます