現在私たちが使っている漢字の熟語のほとんどは、中国からの輸入ですが、明治以降に日本で作られた熟語で逆に中国に輸出されているものもかなりあります。社会、新聞、人民、共和国など。一方、はるばるインドから中国を経由して入ってきた単語もいくつかあります。閼伽(あか)、荼毘(だび)、旦那(だんな)のような仏教用語です。この閼伽という単語ですが、学生の頃しばらくの間日本の古典文学に浸ってたころ『閼伽棚』という単語の注釈に『閼伽とはサンスクリットのアカという単語からの音訳であり、これはラテン語の aqua (水)と同根語である』と言う解説があったのを最近『サンスクリット語入門』を読んでいて、確認しました。
私は中学の時から英語は好きでしたし、他の言語に対する関心はあったものの『英語もできないのに、他の言語なんて無理だ』と思いこんでいました。しかし、高校1年の時、私のクラスメートが『ぼくの塾の先生は英語・ドイツ語・フランス語の3ヶ国語ができる』と自慢していたのです。私はその時、初めて人間(あるいは日本人でも)というのは、単に1つの外国語(英語)だけでなく、複数の語学をマスターすることができるのだ、と感銘を受けました。まさにこのときの一言が天啓となり、polyglotの道を歩みだしたのでした
大学の時に読んだ何かの本に英語の辞書を買うときは必ず語源が詳しく説明しているものを買いなさい、ということが書いてありました。その忠告通り語源の詳しく載っている辞書を買ってみたものの、ラテン語まではある程度分かっても語源がギリシャ語まで遡ると、まったく感じがつかめませんでした。今、ギリシャ語とラテン語がある程度分かるようになって振り返ると、やはり、ギリシャ語を真剣に勉強しないと英単語でもギリシャ語起源のものは本来的な意味が理解できない、とわかりました。つまり、一つの言語の体系全体が分からないと、一つ一つの単語の本当の意味が分からないのは当然なのです。
このように語源自体には興味は持っていましたが、私がギリシャ語やラテン語を始めたのは、語源を知りたいというような言語学的興味よりも、学生の時(20~25歳にかけて)に非常に感銘を受けたプラトン、プルターク、セネカ、マルクス・アウレリウス、キケロなどのギリシャ語・ラテン語の原文を読んでみたい、という単純な願望がはるかに強かったのです。学生時に読んだSchopenhauerやMontaigneがいづれもこれらの人たちを自在に引用しているのがそもそもこれらの古代の哲人に興味を持つ発端でした。
ドイツ語を勉強していた時は、その語彙体系の構築美に感銘を受けていたものでした。それで、今だに、言語そのものとして見た場合、ドイツ語のほうが英語より優れていると思っています。(後述の高津晴春繁氏もそう言っています。)
幸運にもドイツに一年留学できたのと、学生の時に数年ドイツ語漬けになっていたおかげで、読む分には、ドイツ語は英語とほぼ同程度に困らないのが、今もって私の人生における一つの大きな収穫であったと感じています。
ドイツ語ができたおかげで、ギリシャ語・ラテン語を学んでいて、特にギリシャ語を理解するのに非常に役に立っています。つまり、格変化、接続法の用法、分離動詞・非分離動詞の意味の違い、前置詞の格支配、冠飾句の用法、などはドイツ語の知識が応用できて、よく理解できます。またギリシャ語はドイツ語以上に語彙構築が体系だっていて、非常に合理的である、と感じます。ただ、動詞の不規則変化はそれこそ、はちゃめちゃなですが。
ここで、我流の古典語の学習方法の概略を説明しますと:
1.まずかなり薄めの文法書を買う。
2.基本単語2000語~3000語を自分でMDやiPodに録音して、それを常に聞いて音で覚える。
3.数週間目から(単語、文法とも)うろ覚えでもとにかく、本物の本を読む。(英語では、Loeb Classical Libraryが充実してます。ドイツ語はレクラムでギリシャ語・ラテン語とドイツ語の対訳本が八重洲ブックセンターに置いてあります。)
4.ギリシャ語・ラテン語とも変化形から原型を見つけるのに苦労するので、コンピュータソフトを購入するかWebからダウンロードする。
ギリシャ語 --Tuft大学のPerseusのWindows用のCDを買う。$150程度。
ラテン語 --http://www.erols.com/whitaker/words.htmからword.exe をダウンロードする。無料。
5.あとはとにかく自分のすきなものを読む。純語学的なことより原文で読むということが肝要。分からないところはどんどんとばす。読書量が大体5000ページを超えるころになると文章の骨格が感覚的につかめるものです。
英語を勉強しているときにはあまり感じませんでしたが、ドイツ語を勉強している時に、岩波全書の『英語発達史』(中島文雄・著)をよみ、「古英語がドイツ語の知識でかなりの部分分かる」、と言う点に興味をそそられました。また、ギリシャ語・ラテン語を勉強していると、人間の思考回路(どのような順序で、しゃべりたい事柄が心に浮かんでくるか)や言語構造を自分なりに考えるきっかけになりました。つまり、ギリシャ語・ラテン語の単語の並べ方は日本語とほとんど一緒にすることが可能なのです!
この辺りのはなしは、岩波文庫の高津春繁氏の『比較言語学入門』に詳しく載っています。高津氏は、ギリシャ語が専門ですが、それでもサンスクリットの方がギリシャ語より完璧だと述べています。私も早速、サンスクリット語入門を読んでみましたが、その理屈はあまり分かりませんでした。ただ、ギリシャ語・ラテン語の知識があると、サンスクリット語の文法、単語がある程度わかるのは確かだという事は実体験として分かった次第です。
私は中学の時から英語は好きでしたし、他の言語に対する関心はあったものの『英語もできないのに、他の言語なんて無理だ』と思いこんでいました。しかし、高校1年の時、私のクラスメートが『ぼくの塾の先生は英語・ドイツ語・フランス語の3ヶ国語ができる』と自慢していたのです。私はその時、初めて人間(あるいは日本人でも)というのは、単に1つの外国語(英語)だけでなく、複数の語学をマスターすることができるのだ、と感銘を受けました。まさにこのときの一言が天啓となり、polyglotの道を歩みだしたのでした
大学の時に読んだ何かの本に英語の辞書を買うときは必ず語源が詳しく説明しているものを買いなさい、ということが書いてありました。その忠告通り語源の詳しく載っている辞書を買ってみたものの、ラテン語まではある程度分かっても語源がギリシャ語まで遡ると、まったく感じがつかめませんでした。今、ギリシャ語とラテン語がある程度分かるようになって振り返ると、やはり、ギリシャ語を真剣に勉強しないと英単語でもギリシャ語起源のものは本来的な意味が理解できない、とわかりました。つまり、一つの言語の体系全体が分からないと、一つ一つの単語の本当の意味が分からないのは当然なのです。
このように語源自体には興味は持っていましたが、私がギリシャ語やラテン語を始めたのは、語源を知りたいというような言語学的興味よりも、学生の時(20~25歳にかけて)に非常に感銘を受けたプラトン、プルターク、セネカ、マルクス・アウレリウス、キケロなどのギリシャ語・ラテン語の原文を読んでみたい、という単純な願望がはるかに強かったのです。学生時に読んだSchopenhauerやMontaigneがいづれもこれらの人たちを自在に引用しているのがそもそもこれらの古代の哲人に興味を持つ発端でした。
ドイツ語を勉強していた時は、その語彙体系の構築美に感銘を受けていたものでした。それで、今だに、言語そのものとして見た場合、ドイツ語のほうが英語より優れていると思っています。(後述の高津晴春繁氏もそう言っています。)
幸運にもドイツに一年留学できたのと、学生の時に数年ドイツ語漬けになっていたおかげで、読む分には、ドイツ語は英語とほぼ同程度に困らないのが、今もって私の人生における一つの大きな収穫であったと感じています。
ドイツ語ができたおかげで、ギリシャ語・ラテン語を学んでいて、特にギリシャ語を理解するのに非常に役に立っています。つまり、格変化、接続法の用法、分離動詞・非分離動詞の意味の違い、前置詞の格支配、冠飾句の用法、などはドイツ語の知識が応用できて、よく理解できます。またギリシャ語はドイツ語以上に語彙構築が体系だっていて、非常に合理的である、と感じます。ただ、動詞の不規則変化はそれこそ、はちゃめちゃなですが。
ここで、我流の古典語の学習方法の概略を説明しますと:
1.まずかなり薄めの文法書を買う。
2.基本単語2000語~3000語を自分でMDやiPodに録音して、それを常に聞いて音で覚える。
3.数週間目から(単語、文法とも)うろ覚えでもとにかく、本物の本を読む。(英語では、Loeb Classical Libraryが充実してます。ドイツ語はレクラムでギリシャ語・ラテン語とドイツ語の対訳本が八重洲ブックセンターに置いてあります。)
4.ギリシャ語・ラテン語とも変化形から原型を見つけるのに苦労するので、コンピュータソフトを購入するかWebからダウンロードする。
ギリシャ語 --Tuft大学のPerseusのWindows用のCDを買う。$150程度。
ラテン語 --http://www.erols.com/whitaker/words.htmからword.exe をダウンロードする。無料。
5.あとはとにかく自分のすきなものを読む。純語学的なことより原文で読むということが肝要。分からないところはどんどんとばす。読書量が大体5000ページを超えるころになると文章の骨格が感覚的につかめるものです。
英語を勉強しているときにはあまり感じませんでしたが、ドイツ語を勉強している時に、岩波全書の『英語発達史』(中島文雄・著)をよみ、「古英語がドイツ語の知識でかなりの部分分かる」、と言う点に興味をそそられました。また、ギリシャ語・ラテン語を勉強していると、人間の思考回路(どのような順序で、しゃべりたい事柄が心に浮かんでくるか)や言語構造を自分なりに考えるきっかけになりました。つまり、ギリシャ語・ラテン語の単語の並べ方は日本語とほとんど一緒にすることが可能なのです!
この辺りのはなしは、岩波文庫の高津春繁氏の『比較言語学入門』に詳しく載っています。高津氏は、ギリシャ語が専門ですが、それでもサンスクリットの方がギリシャ語より完璧だと述べています。私も早速、サンスクリット語入門を読んでみましたが、その理屈はあまり分かりませんでした。ただ、ギリシャ語・ラテン語の知識があると、サンスクリット語の文法、単語がある程度わかるのは確かだという事は実体験として分かった次第です。


















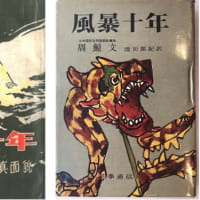








ところで、僕も閼伽の語源はラテン語の aqua (水)であるとの説を高校時代に知って最近までそう思ってきました。
ところが異説があるのでちょっと紹介します。
中島利夫(注1)という研究者が唱えている事柄です。
『「閼伽」の語源はサンスクリット語で「価値ある」を意味する「arghya」であり,「aqua」に対応するサンスクリット語は「水」を意味する「ap」である。この両者に関連性がないことは,オックスフォード羅語辞典・モニエル梵英辞典等を対照してみれば明らかである』
詳細は下記サイトにて。
http://d.hatena.ne.jp/hakuriku/20030422#20030422f1
そして、日本人学生が閼伽の語源=ラテン語の aqua説をなんとなく信じてしまう傾向をつくりだしたのは、岩田一男『英単語記憶術』が火元だったようである、と論じています。
ちなみに僕は昔、『英単語記憶術』を読んでいました。
注1:「通俗語源説と『閼伽』の問題点」『奈良大学紀要』第5号,pp264-266,S51・12・21,奈良大学
http://d.hatena.ne.jp/hakuriku/20030422#20030422f1
その内容を私の持っている辞書や参考書で確認しました。
まず、インドヨーロッパ語族の金字塔と言われているJulius Pokornyの
Indogermanisches etymologisches Woerterbuch
で確認しました。
http://en.wikipedia.org/wiki/Indogermanisches_etymologisches_W%C3%B6rterbuch
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%8D%B0%E6%AC%A7%E8%AA%9E%E6%BA%90%E8%BE%9E%E5%85%B8
この本のP.51には、サンスクリット語では ap が水の事であることが書かれています。しかしこれ以上にラテン語との関連は触れられていません。ついでに言いますと、P.23には、ラテン語の aqua は aquilus(暗い、dunkel)や aquila(鷲、Adler、元来は黒い色をした鳥)と関連がある語である旨の記述があります。つまり、ローマ人にとって、水の色は黒であり、日本人が考える『みずいろ』のような明るい・華やかな色ではなかったようです。
またもう一冊の本、Georg Curtiusの Grundzuege der Griechischen Etymologie は19世紀末の出版(私の持っているのは1879年の第5版)ですので、いろいろと間違いが多いとの批判がある本ですがのぞいてみました。
http://en.wikipedia.org/wiki/Georg_Curtius
http://de.wikisource.org/wiki/ADB:Curtius,_Georg
この本のP.469にはおおよそ次のようなことが書いてあります。『従来ほとんど推測の域を出ていなかった仮説、 k の音から p の音への移行が本当に存在していたという証拠がここに見られる』として、例にラテン語の aqua と サンスクリット語の ap (複数: apas )が挙げられています。同時にドイツ語とラテン語では k の音である一方でギリシャ語は p の音(potamos)であることが記されています。
まったく『俗説は耳に快きも、真理を遠ざく』ですね。反省しきりです。
実は大乗密教に伝わる真言(混交サンスクリット語)をかじっています。
サンスクリット語では、動詞の語根「クシュ」に、私を表す語尾「ミ」がついて、「私はクシャミをする」を「クシャウミ」といいます。
動詞に主格をあわらす語尾がさかさまについて文章となります。
『さかさになってオレ、クシャウミ』笑)なんて語呂あわせで覚えていましたが。。
日本語と意味も発音も似ていますが、本来なんの関係もありません。でも、こういうのは面白いので、どうでもいいことながら記憶してしまいます。不思議ですね。
サンスクリットでは、マーターは「お母さん」という意味。このへんは、どうしてもmother(英),mutter(独)と印欧語としての繋がりがあるように思えますが、詳しいところは??です。
たぶん、異なった言語の間には、いろいろと偶然の一致や、珍奇な符号がたくさんあるのでしょう。こうしたことに出くわすのも、ひとつの語学の楽しみですね。
京都では翌日、大覚寺(大覚寺派真言宗)へ行ってイラン地方から習合して仏教にこっそりはいったMithraという神様のことを真言に照らして調べてました。とても得るものがありました。