かなり以前の話になるが、ドイツ文学者の中野孝次氏の『清貧の思想』がベストセラーとなった。暫く経ってこの本を読んでみたが、無暗と日本(や東洋)の清貧思想に感激していたような記憶がある。清貧というのは西洋ではアッシジの聖フランチェスコ位しか見当たらない、というような書き振りだった。この見解は、あきらかにソクラテスを始めとして、エピクロスやディオゲネスなどのギリシャ・ローマの清貧哲学者達を看過している。前評判が高い本だっただけに、いやしくもヨーロッパの神髄を理解していてしかるべきドイツ文学者の中野氏のこの浅薄な知識に軽い失望を覚え、それ以降中野氏の本を手にとることはなかった。
ところが、2003年ごろ本屋で『ローマの哲人 セネカの言葉』というタイトルの本が目に飛び込んできた。ドイツ留学以降、私はセネカにぞっこんほれこんでいたので、手に取って見た所、著者があの中野氏であった。すぐに『清貧の思想』の著者だと分かり、本棚に戻そうとしたが、「まあ、ちょっとぐらいは中を見てもいいか」と思い、ぱらぱらと読んでみた。
中野氏は東大の文学部・独文科を卒業したので、ドイツ語は堪能であるが、ラテン語は本人の弁だと、全くダメとのことだ。それで、このセネカの本は、ドイツ語のレクラム文庫からの訳だというが、それはまさしく私がドイツ留学時に購入したものだった。中野氏も書いていた(と思うが?)ように、レクラムのドイツ語はまるでセネカがドイツ語ネイティブであるような流麗な文章である。その上、セネカの芸術的ともいえる雄弁術(Rhetoric)でぐいぐいと読み手に迫ってくる、非常に高揚感を催す本だ。
セネカはすでに何度となくレクラムで読んでいたので、中野氏の本は私には新鮮味が全く感じられなかったので、買わずにそのまま本棚に戻した。それから再度、中野氏がセネカの翻訳本を出したのを知ったが、「また、あの類か」と、ちょっと覗き見ただけで、あまり気に留めずにいた。
その後長らく、中野氏のセネカに関する本のことは忘れていたが、数年前、ギリシャ・ローマの古典について調べる必要があって久々に中野氏のことを思い出した。それで図書館から借りてチェックしたが、そこには中野氏が2冊目の本を出版した直後にガンだと判明したと書いてあった。Webで調べると、中野氏はガンが見つかって数ヶ月も経たない内に逝去されたとのことであった。数ヶ月の苦しいガン治療では、セネカの『ルキリウス書簡集』の言葉が励みになったという。ドイツ文学者でありながら、最後はローマ人・セネカが心の支えとなったのだった。

【出典】Le buste dit de Sénèque chez Ivoire-Lyon
さて、改めて中野氏の2冊目の本『セネカ 現代人への手紙』を読んでみたところ、次のような一節に出会った。(同書P.11-12、一部省略)
================
…練達の筆というしかないみごとな論の運びようではないか。
そしてこれもセネカの文章をきわだたせる特徴の一つなのだが、論を展開するところどころ、ちょうど曲がり角に当たるようなところに、セネカは必ずおそろしく切れ味のいい、一度聞いたら忘れられぬ、堅固に構築された格言、ないし箴言を要石(かなめいし)として据えておくのだ。ここで言えば、たとえば、
― どこにでもいることは、どこにもいないということだ。
Everywhere means nowhere. いたるところに顔出しする者は、どこにも存在したことのない者だ、という。
(中略)
こうした片言隻句に名文句をはさむ術では、どんな著者もセネカに及ばない。わたしはこういう切れ味のいい名句に触れるたびに、これを簡潔なラテン語で読んだらどうだろうと想像し、若い時にラテン語を学んでおかなかったことをわが悔みとする。
================
引用した中野氏の文にある Everywhere means nowhere. は英語の Loeb Classical Libraryの文章である。当然のことながら、中野氏は Reclamのドイツ文も読んでいるのだが、読者の便を図って英語の訳文を挙げたのだろうが、以下に原文、ドイツ語訳、フランス語訳も並べて示そう。
【ラテン語】Nusquam est, qui ubique est.
【和訳】どこにでもいることは、どこにもいないということだ。
【私訳】どこにでも出掛けて行く人は、落ち着く場所がどこにもない。
【英訳】Everywhere means nowhere.
【独訳】Nirgends ist, wer überall ist.
【仏訳】C’est n’être nulle part que d’être partout.
この警句の意味するところは、「物理的に移動する」という意味ではなく、いろいろな本をちょこちょこと走り読みせず、いくつかの価値ある本をしっかりと読め、ということである。そこから自らの人生観を形成せよということだ。
さて、これらを文を見比べてみると、ドイツ語の訳が一番ラテン語の原文に近いことが分かる。ただ、それはラテン語の構文がある程度分かって初めていえることで、上で告白しているように中野氏は自分にその力がないことを大いに悔やんでいた。
中野氏はセネカと波長がドンピシャ合ったようで、この本・『セネカ 現代人への手紙』の端々からセネカに対する強烈な恋慕の情が立ち昇ってくる。私の勝手な推量では、もし天が中野氏にもう数年でも時間を与えたなら、中野氏はきっと80歳からでもラテン語を習い始め、切れ味のいい名句をラテン語で味わうという幸福な時間を持ったに違いない。死んでしまった人のことは、今更言っても詮無いことだがまだ生きている若い人は、中野氏と同じ切ない思いしないように願う次第だ。
【参照ブログ】
沂風詠録:(第37回目)『セネカの本: De Vita Beata』
ところが、2003年ごろ本屋で『ローマの哲人 セネカの言葉』というタイトルの本が目に飛び込んできた。ドイツ留学以降、私はセネカにぞっこんほれこんでいたので、手に取って見た所、著者があの中野氏であった。すぐに『清貧の思想』の著者だと分かり、本棚に戻そうとしたが、「まあ、ちょっとぐらいは中を見てもいいか」と思い、ぱらぱらと読んでみた。
中野氏は東大の文学部・独文科を卒業したので、ドイツ語は堪能であるが、ラテン語は本人の弁だと、全くダメとのことだ。それで、このセネカの本は、ドイツ語のレクラム文庫からの訳だというが、それはまさしく私がドイツ留学時に購入したものだった。中野氏も書いていた(と思うが?)ように、レクラムのドイツ語はまるでセネカがドイツ語ネイティブであるような流麗な文章である。その上、セネカの芸術的ともいえる雄弁術(Rhetoric)でぐいぐいと読み手に迫ってくる、非常に高揚感を催す本だ。
セネカはすでに何度となくレクラムで読んでいたので、中野氏の本は私には新鮮味が全く感じられなかったので、買わずにそのまま本棚に戻した。それから再度、中野氏がセネカの翻訳本を出したのを知ったが、「また、あの類か」と、ちょっと覗き見ただけで、あまり気に留めずにいた。
その後長らく、中野氏のセネカに関する本のことは忘れていたが、数年前、ギリシャ・ローマの古典について調べる必要があって久々に中野氏のことを思い出した。それで図書館から借りてチェックしたが、そこには中野氏が2冊目の本を出版した直後にガンだと判明したと書いてあった。Webで調べると、中野氏はガンが見つかって数ヶ月も経たない内に逝去されたとのことであった。数ヶ月の苦しいガン治療では、セネカの『ルキリウス書簡集』の言葉が励みになったという。ドイツ文学者でありながら、最後はローマ人・セネカが心の支えとなったのだった。

【出典】Le buste dit de Sénèque chez Ivoire-Lyon
さて、改めて中野氏の2冊目の本『セネカ 現代人への手紙』を読んでみたところ、次のような一節に出会った。(同書P.11-12、一部省略)
================
…練達の筆というしかないみごとな論の運びようではないか。
そしてこれもセネカの文章をきわだたせる特徴の一つなのだが、論を展開するところどころ、ちょうど曲がり角に当たるようなところに、セネカは必ずおそろしく切れ味のいい、一度聞いたら忘れられぬ、堅固に構築された格言、ないし箴言を要石(かなめいし)として据えておくのだ。ここで言えば、たとえば、
― どこにでもいることは、どこにもいないということだ。
Everywhere means nowhere. いたるところに顔出しする者は、どこにも存在したことのない者だ、という。
(中略)
こうした片言隻句に名文句をはさむ術では、どんな著者もセネカに及ばない。わたしはこういう切れ味のいい名句に触れるたびに、これを簡潔なラテン語で読んだらどうだろうと想像し、若い時にラテン語を学んでおかなかったことをわが悔みとする。
================
引用した中野氏の文にある Everywhere means nowhere. は英語の Loeb Classical Libraryの文章である。当然のことながら、中野氏は Reclamのドイツ文も読んでいるのだが、読者の便を図って英語の訳文を挙げたのだろうが、以下に原文、ドイツ語訳、フランス語訳も並べて示そう。
【ラテン語】Nusquam est, qui ubique est.
【和訳】どこにでもいることは、どこにもいないということだ。
【私訳】どこにでも出掛けて行く人は、落ち着く場所がどこにもない。
【英訳】Everywhere means nowhere.
【独訳】Nirgends ist, wer überall ist.
【仏訳】C’est n’être nulle part que d’être partout.
この警句の意味するところは、「物理的に移動する」という意味ではなく、いろいろな本をちょこちょこと走り読みせず、いくつかの価値ある本をしっかりと読め、ということである。そこから自らの人生観を形成せよということだ。
さて、これらを文を見比べてみると、ドイツ語の訳が一番ラテン語の原文に近いことが分かる。ただ、それはラテン語の構文がある程度分かって初めていえることで、上で告白しているように中野氏は自分にその力がないことを大いに悔やんでいた。
中野氏はセネカと波長がドンピシャ合ったようで、この本・『セネカ 現代人への手紙』の端々からセネカに対する強烈な恋慕の情が立ち昇ってくる。私の勝手な推量では、もし天が中野氏にもう数年でも時間を与えたなら、中野氏はきっと80歳からでもラテン語を習い始め、切れ味のいい名句をラテン語で味わうという幸福な時間を持ったに違いない。死んでしまった人のことは、今更言っても詮無いことだがまだ生きている若い人は、中野氏と同じ切ない思いしないように願う次第だ。
【参照ブログ】
沂風詠録:(第37回目)『セネカの本: De Vita Beata』

















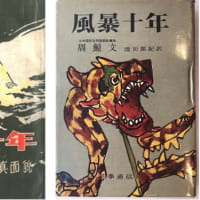









※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます