恵比寿の街を歩いていたら、
偶然「道しるべ」に出くわしました。

都内に残る道しるべとしては、
この他に三軒茶屋や参宮橋のものを見たことがありますが、
いずれも野ざらし。
このように祠状になっているのは初めてです。
説明板によると江戸中期に建てられたものだそうで、
勿論まわりを囲む風よけは、当時からのものではないけど、
その風化具合や道しるべの石との同化具合から、
あたかも江戸からこの姿だったような錯覚を覚えます。

中央には「南無阿弥陀仏」、
石の右面には「ゆうてんじ道」、
左面には「不動尊道」と彫られています。
解説板によると、
台座には「道中講」と彫られているそうです。
「富士講」や「庚申講」と同様、
道に関しても「講」があったんですね。

道しるべの向かって左側に、
半レリーフの、これまた年季の入った彫像があります。
その姿形から、よく庚申塚でみかける猿の形をしていますが、
説明板はなにも触れていないのでわかりません。
もし庚申塚だとすれば道中と庚申の、
講のコラボということになるんでしょうか。
この時は時間がなく、サラッと撮影しただけでしたが
次回訪れたら、この彫り物をもう少し調べてみようと想います。
※郷土史とかみればあっさり出てるかな。。。

偶然「道しるべ」に出くわしました。

都内に残る道しるべとしては、
この他に三軒茶屋や参宮橋のものを見たことがありますが、
いずれも野ざらし。
このように祠状になっているのは初めてです。
説明板によると江戸中期に建てられたものだそうで、
勿論まわりを囲む風よけは、当時からのものではないけど、
その風化具合や道しるべの石との同化具合から、
あたかも江戸からこの姿だったような錯覚を覚えます。

中央には「南無阿弥陀仏」、
石の右面には「ゆうてんじ道」、
左面には「不動尊道」と彫られています。
解説板によると、
台座には「道中講」と彫られているそうです。
「富士講」や「庚申講」と同様、
道に関しても「講」があったんですね。

道しるべの向かって左側に、
半レリーフの、これまた年季の入った彫像があります。
その姿形から、よく庚申塚でみかける猿の形をしていますが、
説明板はなにも触れていないのでわかりません。
もし庚申塚だとすれば道中と庚申の、
講のコラボということになるんでしょうか。
この時は時間がなく、サラッと撮影しただけでしたが
次回訪れたら、この彫り物をもう少し調べてみようと想います。
※郷土史とかみればあっさり出てるかな。。。














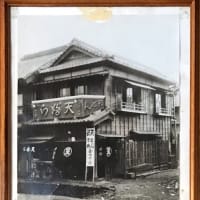




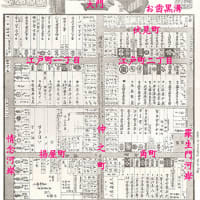
※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます