南の地域ではすでに梅雨入りしたと報じられていますが、関東のこのごろは、
たまに晴れもありますが不安定な日々が続いています。 昨日には、生協から届いた
山椒の実100gを佃煮にしました。 部屋中に山椒の香りが漂い、初夏の気分を
味わっています。
今月も早く終わり、不思議な日本語の回りとなりました。例によって、当意即妙
・・順不同で並べてみました。 言葉を繰って行くと、どんどんと派生して脇枝に
入って、その意味などが膨らんできて面白いですが長くなるのでそれらは割愛・・。
(それでも長くなってしまいました。)
では・・・。
・進物 最近では言葉を検索すると、「AIによる概要」として、真っ先に内容が
示されてきます。これによれば、「進物」とは、目上の人や、お世話になっている人
に差し上げる品物、贈り物のことを指します。 一般的に、贈答品や、お歳暮、
お中元などの際に使われる言葉です・・とあります。
進と物で、差し上げる品が「物」であるとしても、「進」がどうして、このような
意味を持つのでしょうか?
そのようなことをいちいち、詮索することはないのでは? とも思いますが、
ここでは少し立ち止まって、その謂れみたいなところを探ってみたいと思いました。
進物の語源・・で再び検索をしてみますと、AIの概要には、「進」は、「進む」や
「差し上げる」「たてまつる」という意味を持つ漢字です・・とあります。
「神に進む」や「献上する」というように、何かを捧げたり、前に進ませたりする
行為を表わすのだそうです。 「物」は、「もの」という意味の漢字で、具体的な
物事を指します。 字源は「牛」と「犂(スキ)」を組み合わせたもので、農具と
して牛を使い土を耕す様子を表しているとされます。‥このような解説がありま
した。
 (おいしいご進物より)
(おいしいご進物より)
もう少し・・。 「進」を漢字ペディアでみますと、①すすむ。すすめる。前へ
出る。「進行」「進出」「発進」 ②のぼる。上の段階へあがる。「進学」「昇進」
③よくなる。向上する。「進化」「進展」 ④さし出す。さしあげる。「進言」「進呈」
「寄進」 とあります。
確かに、「進」の漢字には、進学、発進、進化、進言・・などありますね。
ちょっとくどかったかしら?
・自分 辞書には、1、その人自身。2.《代名詞的に》わたくし。とあります。
「自」は”おのずから"や”みずから”の意味がありますから、自分自身を指している‥
ことは理解できます。 そもそも、「自」という漢字の語源は、鼻の形からできた
象形文字とありました。 鼻を指して「じぶん」ということから、「じぶん」の意味に
使われるようになった。
では「分」は、どのような意味があるのか? 「分相応」などに使われている”分”
には、
①区別をつける。わける。わかれる。㋐間をあける。離す。ばらばらになる。
「分割・分散・等分・細分・四分五裂」 ㋑えだわかれ。支流。「分家・分派・
分教場」 ②全体の中の、他と区別された一部。「余った分は貯蔵する」「部分・
半分・領分・夜分」。構成する中身。「成分・水分・養分」 ③(天から)わけ与え
られたもの。 ㋐もちまえの性質。「天分・性分しょうぶん・気分」 ㋑義務。責任。
「分を尽くす」「本分・職分」
とありますから、この③の意味ですね。つまり、天から分け与えられたもの・・
ですね。
 (いらすとくんより)
(いらすとくんより)
自分のことを、昔流に言えば、わし:年配者が使う、やや古い言い方です。 拙者:
武士などが使う、謙譲の表現です。 我輩:若い男性が使う、丁寧な表現です。
某(それがし)::謙譲の表現で、自分の名前を言わない場合に使います。 小生:
男性が、目上の人に使う謙譲の表現です。 手前:江戸時代以降、特に男性が使う、
へりくだった表現です。
関西地方では、あなたのことを「自分」と言ったりしていました。
・血潮 goo辞書には、1 潮のようにほとばしり出る血。「—に染まる」2
体内を潮のように流れる血。激しい情熱や感情。「熱き青春の—」 とあり「血」との
違いは、「血」は血そのものを指すのに対し、「血潮」は、流れる血や注ぎ出される
血を意味する‥と解説されています。分かり切ったことでも、説明するとなると
難しいもんですね。
で、なぜ「潮」なんでしょうか? 血潮の語源というところには次のように
記述されています。
「脊椎動物が海から陸へ上陸するとき、彼らは古代の海の水を『いのちの水』として
持って上がったのだ。」 と述べています。動物の血液は、『その命の水』からできた
ものです。故に、「血潮(血汐)」とは、そのような意味を如実に表現したもの
だったのです。 また、平安時代中期に編纂された「和名類聚抄」には、海水が
結晶化した塩も、海水の満ち引きの現象をさす「潮」も区別なく、どちらも
「しお、うしお」と書かれていたそうです。
「潮」は「しお」、あるいは「うしお」と読みます。「汐」は「せき」と読みます。
ついでに、「潮」は、海水の満ち引きや、水の流れ、時の流れなどを指し、具体的
には、朝の干満を指しており、「汐」は、夕方の干満を指すことが多いとあります。
『若鷲の歌』(作詞:西条八十、作曲:古関裕而)の歌いだしに・・♬若い血潮の
予科練の七つボタンは 桜に錨・・また、『手のひらを太陽に』(作詞:やなせた
かし、作曲:いずみたく)では、♬手のひらを太陽に透かして見れば、真っ赤に
輝く僕の血潮・・が浮かびますね。
・床屋 江戸時代に、男の髪を結う髪結い職が、床の間のある店(床店)で
仕事をしていたことから「床の間のある店」という意味から「床屋」と呼ばれる
ようになった。現代の理容店、理髪店ですね。
床屋の由来は、2つあり、一つは古く鎌倉時代に、藤原采女亮政之という人が、
下関で髪結い業を営んでいた際、店に床の間が設えられていたことから「床の間の
ある店」として「床屋」と呼ばれた説。 も一つは、江戸時代、髪結いが床店
(商売をするだけで人の住まない店舗)で髪結い床として仕事をしていたことから
との説があるとあります。
ここで、藤原の采女亮政之(ふじわらのうねめのすけまさゆき)について、全国
理容生活衛生同業組合連合会のページに詳しく述べられていますので、一部を
抜粋しました。
『采女亮は、鎌倉時代京都で生まれますが、父親と共に下関に下り、そこで武士を
客として月代そり、髪結い業を始めた。采女亮は父親が亡くなると鎌倉に移ります
が、采女亮が下関で髪結いの仕事をはじめたのが床屋の始まりとされている。
その店には床の間が設えられ、そこには亀山天皇を祀る祭壇と藤原家の掛け軸が
あったことから、「床の間のある店」→「床場」→「床屋」と呼ぶようになったと
言われています。 采女亮は1335年(建武2年)に亡くなりますが、昭和のはじめ頃
まで全国の理美容業者はその命日17日を毎月の休みとした。』
また、髪結い職のことを「一銭職」とも呼ばれるそうですが、江戸時代に
『一銭職分由緒書』という書が残されているそうです。これには、理美容業の
祖といわれる藤原采女亮政之が鎌倉時代に髪結職(一銭職)をはじめた経緯から、
戦国時代になって采女亮から17代目の北小路藤七郎が武田軍から敗走する徳川
家康が天竜川を渡る手助けをし、褒美として銀銭一銭を賜り一銭職と呼ばれる
ようになった経緯が記されているそうです。亀山天皇時代の出来事から、徳川
家康を助け、また徳川吉宗や大岡越前も登場する、奇想天外な書だとあります。
平成7年(1995年)に、亀山八幡宮の正面大鳥居右側に「床屋発祥の地」記念碑
が下関理容美容専修学校理事長によって建てられたとあります。
こちらはお墓です。采女亮の墓(長野県善光寺)
 (ウイキペディアより)
(ウイキペディアより)
・面白半分 goo辞書に、興味本位の気持ちがあって、真剣さに欠けている
こと。また、そのさま。とあります。 ここで気になるのが「半分」の意味なん
ですね。 半分とは、数量的に50%ということですが、面白半分や冗談半分の半分は、
必ずしも50%と言っているわけではないでしょう。
「面白半分に○○に応募した」などは、ある程度真剣に応募しているが、やや照れ
隠し的にぼかしている・・と思われるので、真剣みが強い。しかし、「面白半分に
いたずらした」や「面白半分にからかった」などは、面白さが強く、罪悪感は
それほどでもないかもしれません。
「冗談半分」にしても、冗談めかして言った本気の話もありますよね。言い訳や、
言いにくいことを冗談に包み隠して言う場合などがそうですね。 このように
「半分」の意味はそのような雰囲気を前面に押し立てて、真剣みや罪悪感、本気度
などを和らげていると思われます。で、その程度はそれぞれの言葉や状況によって
変わってくる・・。
「面白い」の語源は、もともと「顔が白くなるほど、表情が明るくなる」という
意味からのようで、また、目の前の風景が明るく、美しく見えるというイメージも
含まれていると考えられているようです。
面は「顔」を指し、白は「明るくなる」ことを意味し、そこから転じて、楽しい、
心地よいなどの感情を表現するようになったとあります.

作家、吉行淳之介のアイデアから、大光社が雑誌『面白半分』の出版を企画した
そうですが、大光社が閉鎖されたため、別に株式会社面白半分を設立し「面白くて
タメにならない雑誌」を1971年12月に刊行。 編集長は吉行の後、野坂昭如、開高健、
五木寛之、藤本義一、金子光晴、井上ひさし、遠藤周作、田辺聖子、筒井康隆、
半村良、田村隆一等が交代で務めたとあります。
 (雑誌日本の古本屋より)
(雑誌日本の古本屋より)
お疲れさまでした・・。
Le temps des fleurs










 (ウイキペディアより)
(ウイキペディアより)


 (教育業界ニュースより)
(教育業界ニュースより)



 (共同通信より)
(共同通信より)

 (読売オンラインより)
(読売オンラインより) (会報より)
(会報より) (会報より)
(会報より)









 (キープデザインより)
(キープデザインより) (イラストくんより)
(イラストくんより)
 (京都新聞より)
(京都新聞より)
 (そうだ京都、行こうより)
(そうだ京都、行こうより)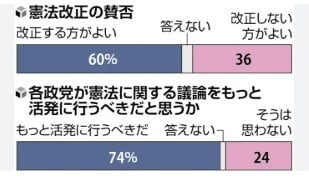 (読売新聞オンラインより)
(読売新聞オンラインより)


 (ac-illust.comより)
(ac-illust.comより) (いらすとやより)
(いらすとやより) (noteより)
(noteより) (LINE NEWSより)
(LINE NEWSより)








