夜ヒット名シーンシリーズ、今回はYMO(イエロー・マジック・オーケストラ)の「ライディーン」「テクノポリス」(1980年6月2日放送)を取り上げます。
YMOは、1978年、元「はっぴいえんど」の細野晴臣、元「サディスティック・ミカバンド」の高橋幸宏、そして主にスタジオミュージシャンとして山下達郎らの楽曲製作に参加していた坂本龍一の3人によって結成された音楽グループです。
何と言っても彼らの最大の特徴は、何もかもが当時の日本の音楽産業からすれば「斬新」そのものであったこと。
サウンド面では、いまさら詳しく言及するまでも「テクノサウンド」と称される、コンピューター・シンセサイザー等の新進気鋭の技術をフル活用した、かつてないサウンドを世に知らしめたこと。そして、プロモーション面では、ワールドツアーを実施したり、アメリカの市場に向けてアルバム製作を行うなど、日本だけにとどまらず常に海外に目を向けた活動を展開したこと。また、当時の日本の若年層では長髪が主流であった中で、彼らの短髪カットも「テクノカット」としてブームとなるなど、存在そのものが「新たな時代の象徴」ともいえるものでした。
日本での活動が本格化したのは、1979年11月の国内でのファースト・シングル「テクノポリス」の発表から。翌1980年に入り、初の国内ツアーを実施し、「テクノポリス」に続くセカンドシングルにしてYMO最大の代表作ともいえる「ライディーン」が発表され、日本でのYMO人気は不動のものとなります。
そして、この年の6月、待望の夜ヒット初出演。この際、彼らは通常の第6スタジオからではなく、他のスタジオからのライブという形で上記の「テクノポリス」「ライディーン」を続けて演奏しました。
彼らの斬新な世界観に呼応するかのごとく、夜ヒットスタッフ陣も、モノクロ調をベースとした反転技術を使ったり、演奏者の姿を万華鏡のように多重に映し出したり、海の映像との合成を行ったりするなど、当時の生放送の放送技術レベルでは限界と考えられる斬新な映像効果を多用し、彼らの演奏に華を添えました。その様子は「異次元の世界」といった雰囲気すらありました。
1980年代の夜ヒットは、新進気鋭のアーティストを続々登場させて、いい意味で番組のそれまでのカラーを「破壊」する実験的な演出を多用することで、他の競合音楽番組との差別化を図っていったわけですが、その端緒はやはりこのYMOの初出演シーンであろうと思います。まさに「夜ヒットに変革が起きた瞬間」それこそがこのYMOの一場面であったと言っても過言ではないでしょう。古くからの番組フリークには大きな衝撃を以って迎えられ、他方、それまで「古臭さのある番組」と感じ、番組を敬遠していた視聴者をふり向かせた、そういう意味でもこのYMOのシーンは夜ヒットという番組史を通じても重要なターニングポイントと見るべきかもしれません。
つい最近、某所で改めてこのときのシーンのフルバージョンを拝見しましたが、とても26年も前のシーンとは思えないほどに色あせぬ「斬新」さがありました。むしろ、却って今のJ-POPのヒット曲のほうが「古臭く」感じてしまう。それぐらいに楽曲・演出、すべてを通じてとてつもない迫力を感じます。26年前の映像を今見てこう思うんですから、当時リアルタイムで見ていた方々はそれ以上にこの夜ヒットのシーンに「衝撃」を覚えるのも必然だろうなあ・・・という気がします。
ちなみに、YMOはこれから3年後の1983年に「君に、胸キュン。」「過激な淑女」「以心電信」とそれまでの曲調とはまた異なるポピュラー志向のロック路線を展開し、新たな世界観を開拓するかに見えたのもつかの間、この年の末を以って惜しまれつつ「散開」。実質的な活動期間はわずか5年という短さでしたが、その5年間の中で、日本の音楽シーンに「テクノ」という新ジャンルを築き上げ、シンセサイザー・コンピューター技術が楽曲製作の場面で必須の存在となるなど、日本の音楽シーンの発展を一気に加速させたという点で、YMOが日本の音楽界に残した功績はこれからも久しく語り継がれて行くことだろうと思います。
同時に細野・坂本・高橋の3氏が「散開」後に築き上げた各自の独自の世界観をもう一度結集させて、元気のない昨今の日本の音楽界に「刺激」を与えてほしいと思ったりもします。最近、ビールのCMで久々にこの3氏が再会を果たしましたが、これが本格的な「再生」に繋がってほしいと思っているファンの方も少なくないはず。今一度、成熟した「ライディーン」「テクノポリス」を聞いて見たい、そう願わずにはいられません。
(※動画リンクは下記ロゴ画像に貼ってあります。)
YMOは、1978年、元「はっぴいえんど」の細野晴臣、元「サディスティック・ミカバンド」の高橋幸宏、そして主にスタジオミュージシャンとして山下達郎らの楽曲製作に参加していた坂本龍一の3人によって結成された音楽グループです。
何と言っても彼らの最大の特徴は、何もかもが当時の日本の音楽産業からすれば「斬新」そのものであったこと。
サウンド面では、いまさら詳しく言及するまでも「テクノサウンド」と称される、コンピューター・シンセサイザー等の新進気鋭の技術をフル活用した、かつてないサウンドを世に知らしめたこと。そして、プロモーション面では、ワールドツアーを実施したり、アメリカの市場に向けてアルバム製作を行うなど、日本だけにとどまらず常に海外に目を向けた活動を展開したこと。また、当時の日本の若年層では長髪が主流であった中で、彼らの短髪カットも「テクノカット」としてブームとなるなど、存在そのものが「新たな時代の象徴」ともいえるものでした。
日本での活動が本格化したのは、1979年11月の国内でのファースト・シングル「テクノポリス」の発表から。翌1980年に入り、初の国内ツアーを実施し、「テクノポリス」に続くセカンドシングルにしてYMO最大の代表作ともいえる「ライディーン」が発表され、日本でのYMO人気は不動のものとなります。
そして、この年の6月、待望の夜ヒット初出演。この際、彼らは通常の第6スタジオからではなく、他のスタジオからのライブという形で上記の「テクノポリス」「ライディーン」を続けて演奏しました。
彼らの斬新な世界観に呼応するかのごとく、夜ヒットスタッフ陣も、モノクロ調をベースとした反転技術を使ったり、演奏者の姿を万華鏡のように多重に映し出したり、海の映像との合成を行ったりするなど、当時の生放送の放送技術レベルでは限界と考えられる斬新な映像効果を多用し、彼らの演奏に華を添えました。その様子は「異次元の世界」といった雰囲気すらありました。
1980年代の夜ヒットは、新進気鋭のアーティストを続々登場させて、いい意味で番組のそれまでのカラーを「破壊」する実験的な演出を多用することで、他の競合音楽番組との差別化を図っていったわけですが、その端緒はやはりこのYMOの初出演シーンであろうと思います。まさに「夜ヒットに変革が起きた瞬間」それこそがこのYMOの一場面であったと言っても過言ではないでしょう。古くからの番組フリークには大きな衝撃を以って迎えられ、他方、それまで「古臭さのある番組」と感じ、番組を敬遠していた視聴者をふり向かせた、そういう意味でもこのYMOのシーンは夜ヒットという番組史を通じても重要なターニングポイントと見るべきかもしれません。
つい最近、某所で改めてこのときのシーンのフルバージョンを拝見しましたが、とても26年も前のシーンとは思えないほどに色あせぬ「斬新」さがありました。むしろ、却って今のJ-POPのヒット曲のほうが「古臭く」感じてしまう。それぐらいに楽曲・演出、すべてを通じてとてつもない迫力を感じます。26年前の映像を今見てこう思うんですから、当時リアルタイムで見ていた方々はそれ以上にこの夜ヒットのシーンに「衝撃」を覚えるのも必然だろうなあ・・・という気がします。
ちなみに、YMOはこれから3年後の1983年に「君に、胸キュン。」「過激な淑女」「以心電信」とそれまでの曲調とはまた異なるポピュラー志向のロック路線を展開し、新たな世界観を開拓するかに見えたのもつかの間、この年の末を以って惜しまれつつ「散開」。実質的な活動期間はわずか5年という短さでしたが、その5年間の中で、日本の音楽シーンに「テクノ」という新ジャンルを築き上げ、シンセサイザー・コンピューター技術が楽曲製作の場面で必須の存在となるなど、日本の音楽シーンの発展を一気に加速させたという点で、YMOが日本の音楽界に残した功績はこれからも久しく語り継がれて行くことだろうと思います。
同時に細野・坂本・高橋の3氏が「散開」後に築き上げた各自の独自の世界観をもう一度結集させて、元気のない昨今の日本の音楽界に「刺激」を与えてほしいと思ったりもします。最近、ビールのCMで久々にこの3氏が再会を果たしましたが、これが本格的な「再生」に繋がってほしいと思っているファンの方も少なくないはず。今一度、成熟した「ライディーン」「テクノポリス」を聞いて見たい、そう願わずにはいられません。
(※動画リンクは下記ロゴ画像に貼ってあります。)










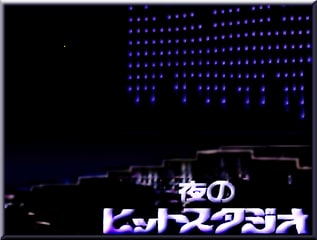

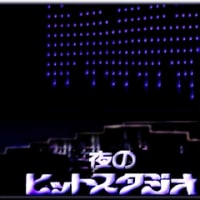
当時のYMOは、イエローマジックオーケストラでして、本当に魔術にかかったかの様な音楽スタイルでした。
とにかく衝撃的で、理屈ぬきに好きになった記憶があります。
当時の「ライディーン」、今でも聴くことが多いです。
YMO台頭前は、ニューミュージック・フォークの台頭という新しい波はあったものの、総じて言えば、「歌謡曲
」の大きな牙城を完全に切り崩すまでには至らなかった。
いわゆる「演歌」の曲調と「四畳半フォーク」の曲調はさほど距離感があるという感じもなかったですしね・・・。
ところがYMOの「テクノサウンド」が持て囃されるや否や、他のアーティストも彼らのいわゆる「打ち込み演奏」の技術を参考にしたり、シンセサイザーを積極的に演奏・楽曲製作時に用いるようになるなどして、音のクオリティーが相対的に高まり、結果として、歌謡曲が、本格的に様々なジャンルへと細分化されるに至った、という感があります。1980年代のヒット曲と一まとめにしても、1980年にヒットした歌と、1989年にヒットした歌では、質感的に大きな違いがあるように感じるのは、YMOが知らしめた「新たな音楽製作スタイル」がその10年間の間で浸透し、そして一般化したことの何よりの表れ、という気がします。
もう一ついえることは歌詞のない「インストロメンタル」のみの作品でも興行的に成功を収める先例を築いた、というのもまた大きなところでしょうかね。歌詞ありの作品の場合には、当然に歌詞を通じて悪くいえば「容易に」作品の世界観を聞く側に訴えることができるわけですが、インストのみの場合は歌詞がない分、聞く側へのアピールの面がどうしても弱くなる。しかし、YMOの「テクノポリス」「ライディーン」はむしろ「歌詞をつける事で音楽の世界観が悪い方向に破壊されてしまう」という稀有な作品。そういった意味でも、日本のこれまでの歌謡曲の固定概念を彼らは打破したと言いうると思います。