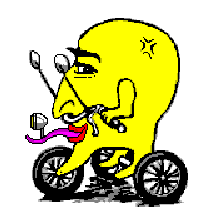「皇室の名宝―日本美の華 1期:永徳、若冲から大観、松園まで」 @東京国立博物館
朝いちで入場して、若冲部屋に向かうと、すでに大混雑。逆に昼過ぎのほうがゆったりしていた。伊藤若冲の動植綵絵三十幅がぐるりと、ひと部屋に展示されている。こりゃすごい。宮内庁三の丸尚蔵館は全部展示するほど広くないので、まとめて見られるいい機会だ。好きなのは、巨匠対決にも出ていた《雪中遊禽図》によく似た《雪中鴛鴦図》の「ボク平気カモ」 それから、真っ赤なもみじの枝にちっこい鳥が二羽止まっている《紅葉小禽図》 自宅の庭にニワトリを飼っていた若冲だけあって、ニワトリの絵が多い。それもまた繊細な筆遣いがすごいんだけど、リアルなニワトリはリアルにキモイんだなぁ。
わりと大きめな、並河靖之の《七宝四季花鳥図花瓶》があった。きめ細かくてすばらしい。
鏑木清方の《散春》という屏風も印象的。右隻には皇居の草の上で和やかに語らう女学生、その先に黒い自動車。左隻には水上生活をする母と子の姿、その小舟の浮かぶ遠景におぼろに浮かぶ鉄筋の清洲橋。鏑木清方の屏風絵にそんなモノがあることがちょっと不思議な感じ。
ミュージアムショップに尾形光琳が描いた百人一首というものが売っていた。値段は273,000円。なんじゃそりゃ。
朝いちで入場して、若冲部屋に向かうと、すでに大混雑。逆に昼過ぎのほうがゆったりしていた。伊藤若冲の動植綵絵三十幅がぐるりと、ひと部屋に展示されている。こりゃすごい。宮内庁三の丸尚蔵館は全部展示するほど広くないので、まとめて見られるいい機会だ。好きなのは、巨匠対決にも出ていた《雪中遊禽図》によく似た《雪中鴛鴦図》の「ボク平気カモ」 それから、真っ赤なもみじの枝にちっこい鳥が二羽止まっている《紅葉小禽図》 自宅の庭にニワトリを飼っていた若冲だけあって、ニワトリの絵が多い。それもまた繊細な筆遣いがすごいんだけど、リアルなニワトリはリアルにキモイんだなぁ。
わりと大きめな、並河靖之の《七宝四季花鳥図花瓶》があった。きめ細かくてすばらしい。
鏑木清方の《散春》という屏風も印象的。右隻には皇居の草の上で和やかに語らう女学生、その先に黒い自動車。左隻には水上生活をする母と子の姿、その小舟の浮かぶ遠景におぼろに浮かぶ鉄筋の清洲橋。鏑木清方の屏風絵にそんなモノがあることがちょっと不思議な感じ。
ミュージアムショップに尾形光琳が描いた百人一首というものが売っていた。値段は273,000円。なんじゃそりゃ。