
土佐のくじらです。
参議院選挙も、早くも終盤となって参りました。
高知選挙区で出馬中の、橋詰毅(つよし)氏の応援を、拙ブログでは今取り組んでおりますが、
橋詰氏から伺っているビジョンの全てを、ブログ記事でご紹介するのは難しいかも知れません。
それくらい橋詰氏の語るビジョンは多く、そして内容が濃いのです。
私の筆力が、どこまで通用するか、私自身全く自信はございません。
前回記事はそう言った意味で、とても長い文章となってしまいましたが、
期間限定でございますので、詰め詰めパッケージ記事となっていることをご了承ください。(笑)
四国縦断貫通トンネルの話を橋詰氏から伺ったときから、私は、
「なぜ今まで、そういう発想に至らなかったのだろうか。」と思いました。
橋詰氏の構想は、聞いた最初は、「この人は、何て大きなことを言う人なんだ。」と思ってしまうのですが、
その効果を聞くと、
「今後それなしでは道は開けない。」と思ってしまうものばかりです。(笑)
江戸時代初期に造られた、野中兼山の残した土佐の公共インフラは、当時としては破格の大規模工事ばかりです。
兼山と同時代の人たちの多くは、「こんな大きなもの、必要なかろうが!」と思っただろうと思います。
しかしそれは、土佐藩200以上の富の蓄積・・・いや現代でも、高知の一次産業の基盤となっております。
先見の明を持つ者は、常に同時代の誤解と、隣り合わせの人生です。
野中の公共工事は、領民が毎日使えるという特徴があります。
そして全てが、とにかく丈夫なのですね。
橋詰氏説では、それらは国防的意味合いもあった・・・ということなので、
生活インフラにしては超頑丈で、大規模すぎるのもそういうことでしょうし、
国防インフラを、生活インフラとして使っていた・・・と考えるなら、
野中兼山という方の、発想力のすごさ、大胆さを再認識するところです。
国防インフラは通常、利益のリターンがありませんが、野中兼山という方は、国防インフラで利益を上げる・・・ということを発想できる政治家だったということになります。
私は歴史好きですが、そういう発想の政治家を、野中以外では存じないです。
さて、高知県民は、四国縦断貫通トンネルを欲するべきです。
それは高知県に、物流の劇的変化をもたらし、高知-新居浜が同一経済圏となります。
それが意味するものは、安定的な消費地人口が約2倍になりますから、高知の美味しい魚や、レベルの極めて高い農作物の売り上げも、一時的でない大幅上昇が見込めます。
そして重要なのは、大規模災害時の救援路を兼ねているからです。
災害有事に際して、余りにも心もとない現状であることは、前回記事で述べたとおりです。
効果は、それだけに留まりません。
橋詰氏は津波対策用防波堤に一つに、たくさんの機能を盛り込んだように、トンネルにも多くの効用を構築しているのですね。
高知-新居浜の間には、盆地も存在します。
有名な早明浦(さめうら)ダムを有する、高知嶺北(れいほく)地域です。
四国縦断貫通トンネルは、ここが中継地点となります。
高知ー嶺北地域は、直線距離で言えば、十数㎞に過ぎません。
しかし今、高知からこの嶺北地域に向かうには、一旦東に20kmほど大きく迂回し、
山すそを北上して、大豊町というところを経由し、そこからまた、西に20km進まなくてはいけません。
高知県民にとって、嶺北の地は、物理的にも精神的にも遠い地域なのです。
ところがこの、四国縦断貫通トンネルができれば、この土佐の寒村地域は、
高知市周辺地域と、愛媛県側の新居浜周辺地域、両都市の通勤通学圏内に、楽々と入ってしまうのですね。
さすれば遠く、慢性的な人口減と、超高齢化に長年悩み続けた寒村は、一気に新興住宅街へと変貌するわけです。
新興住宅街ができれば、当然住宅需要が高まります。
そうすれば当然、この地域で培ってきた山林が生きてきます。
林業の復活です。
しかも一時的な林業復興事業ではなく、継続的かつ永続的な発展が見込まれるのです。
この四国縦断貫通トンネルにアクセスする道路を、横に広げていけば、四国の山々の寒村群の繁栄エリアがドンドン広がる訳ですから。
政治的にこの寒村群に、企業を誘致したりする試みは、今までも行われています。
しかし橋詰氏のお話を聞いていて、「そういう試みは、荒地に苗を植えるようなものだな。」と、私は感じた次第です。
米を収穫したければ、土地をビチャビチャにしなければなりません。
ビチャビチャにするためには、たくさんの水が必要です。
そうして、用水路が必要となり、用水路に大量の水を、安定的に流すにはその上流に堰(せき=ダム)が必要です。
山間部を発展させるには、つまり米の取れる地域にするには、そこに大都市に繋がる便利な道を通せば良い。
道が用水路、大都市が堰・・・。
これもまた橋詰氏独特の、野中兼山的発想なのではないでしょうか?
しかし問題があります。
それは、高低差のある急な勾配のトンネルは危険です。
高知市と山間部の嶺北地域には、それなりに高低差があると思ったのです。
私はそれを、橋詰氏に質問しました。
橋詰氏曰く。
「くじらさん。高知-新居浜直通トンネルと、高低差を考慮した地域間トンネル、そんなの、色々なレパートリーのトンネルを、たくさん造ればいいじゃないですかぁ。(笑)」
そうでした。
橋詰流錬金術・・・いや、橋詰氏の所属する、幸福実現党の考えなのかも知れませんから、
アベノミクスにちなんで、コウフクノミクス・・・とでも言う方が、正しいかも知れませんね。
彼らの、大事な事業に関する予算の考え方なら、税金の枠にとらわれず、投資と資産運用を中心としますから、
需要があればいくらでも、造ろうと思えば造れるのでした。(笑)
投資というものは、信用さえあれば、事業規模に合わせて資金は集まるものだからです。
ともあれ、橋詰氏の構想力は、トンネル一つで、崩壊と存続の危機に瀕する、土佐の寒村群を、繁栄モードに変えてしまいます。
皆さん、このような政治的構想を、高知県でお聞きになったことがありますか?
橋詰氏は、友人ならずとも応援しなければならない、大政治家候補なのです。
橋詰毅(つよし)氏は、野中兼山の再来と呼ぶに相応しい人物なのです。
(続く)













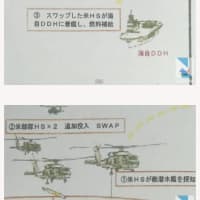






※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます