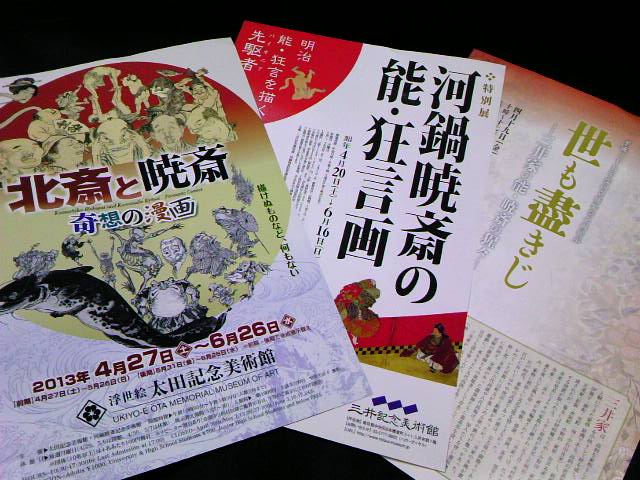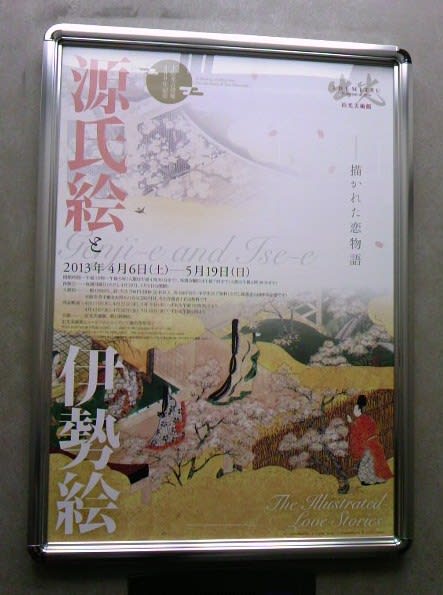板橋区立美術館の毎年夏のお楽しみ、イタリア・ボローニャ国際絵本原画展♪
今年で33回目を迎え昨日が最終日であった。

入選作家77名の作品が展示されていたが、そのうち15名は日本人。
それらのどの作品も独創性がある素晴らしいものばかりで日本のレベルの高さに感動した♪♪♪
小輪瀬護安さんの「除雪車」CG
刀根里衣さんの「かえるのぴっぽ」アクリル
酒井冬子さんのアップリケとフランス刺繍の「カメレオン」も面白い作品だった。
今年はブックフェアの50周年にあたるそうで、
「ボローニャ発世界へ - 絵本作家たちの挑戦」の特別展示もあって
世界に羽ばたいた日本の作家たちの作品も紹介されており、
その中のお一人の三浦太郎さんが来館されておられサインを頂戴することができた。
夢があって愛らしいけどデザイン性に優れていてとてもおしゃれな作品たちに魅了された♪♪♪